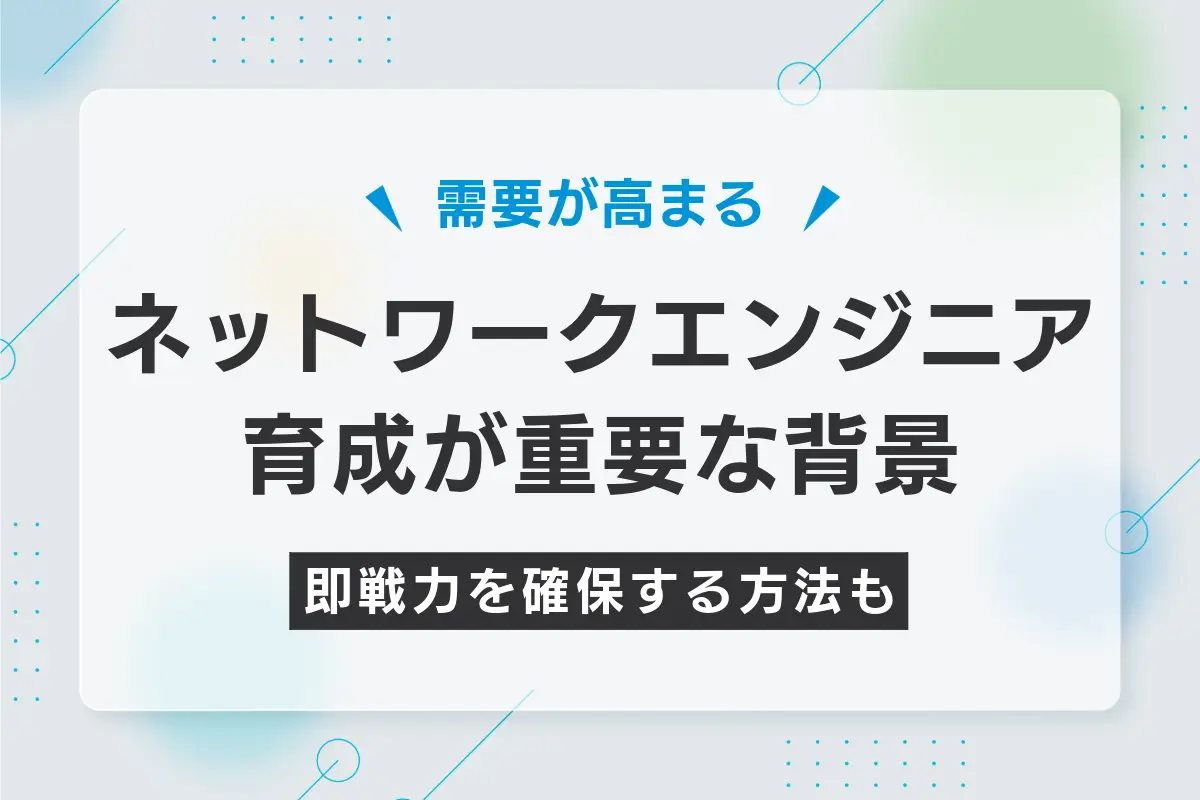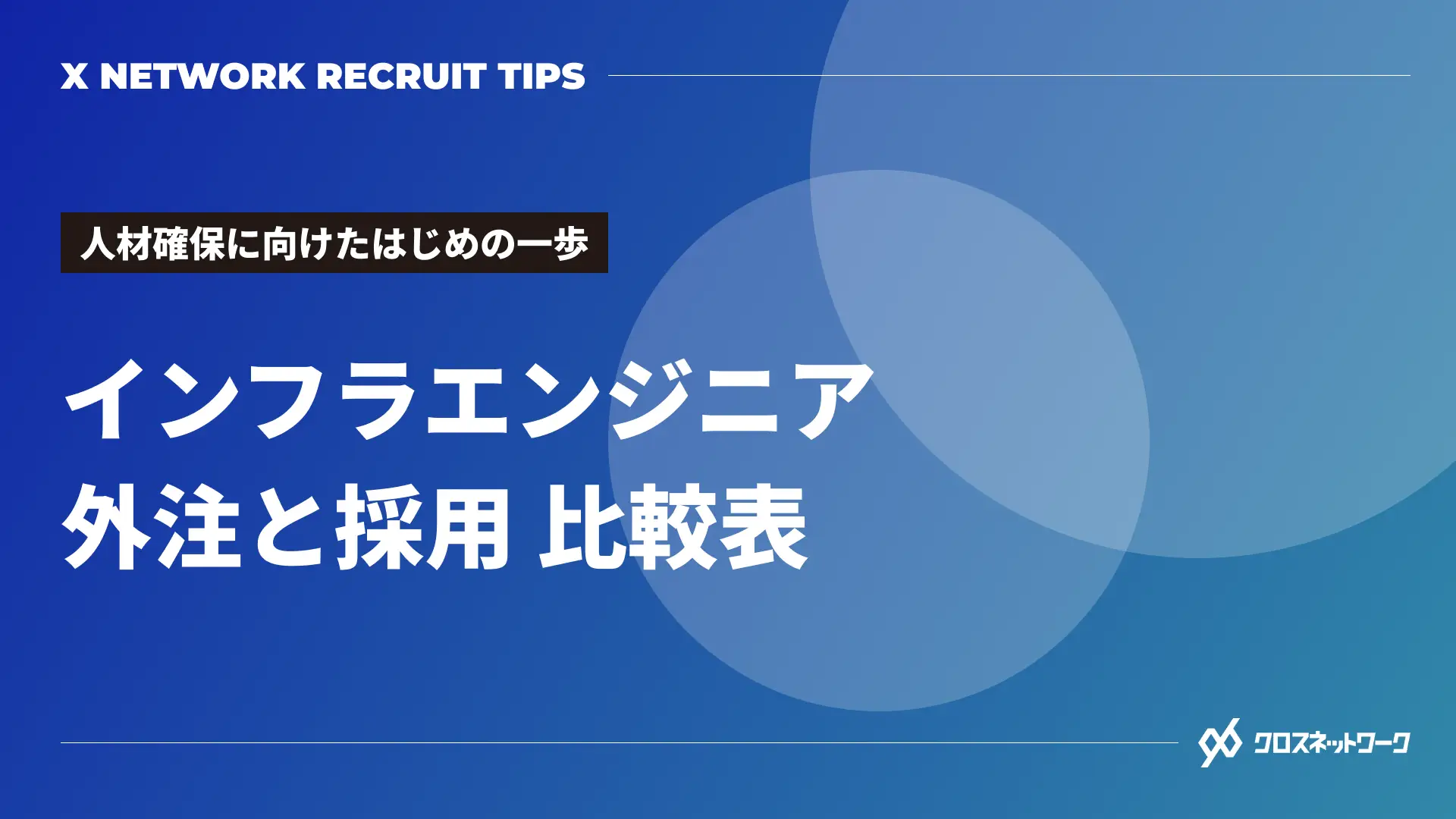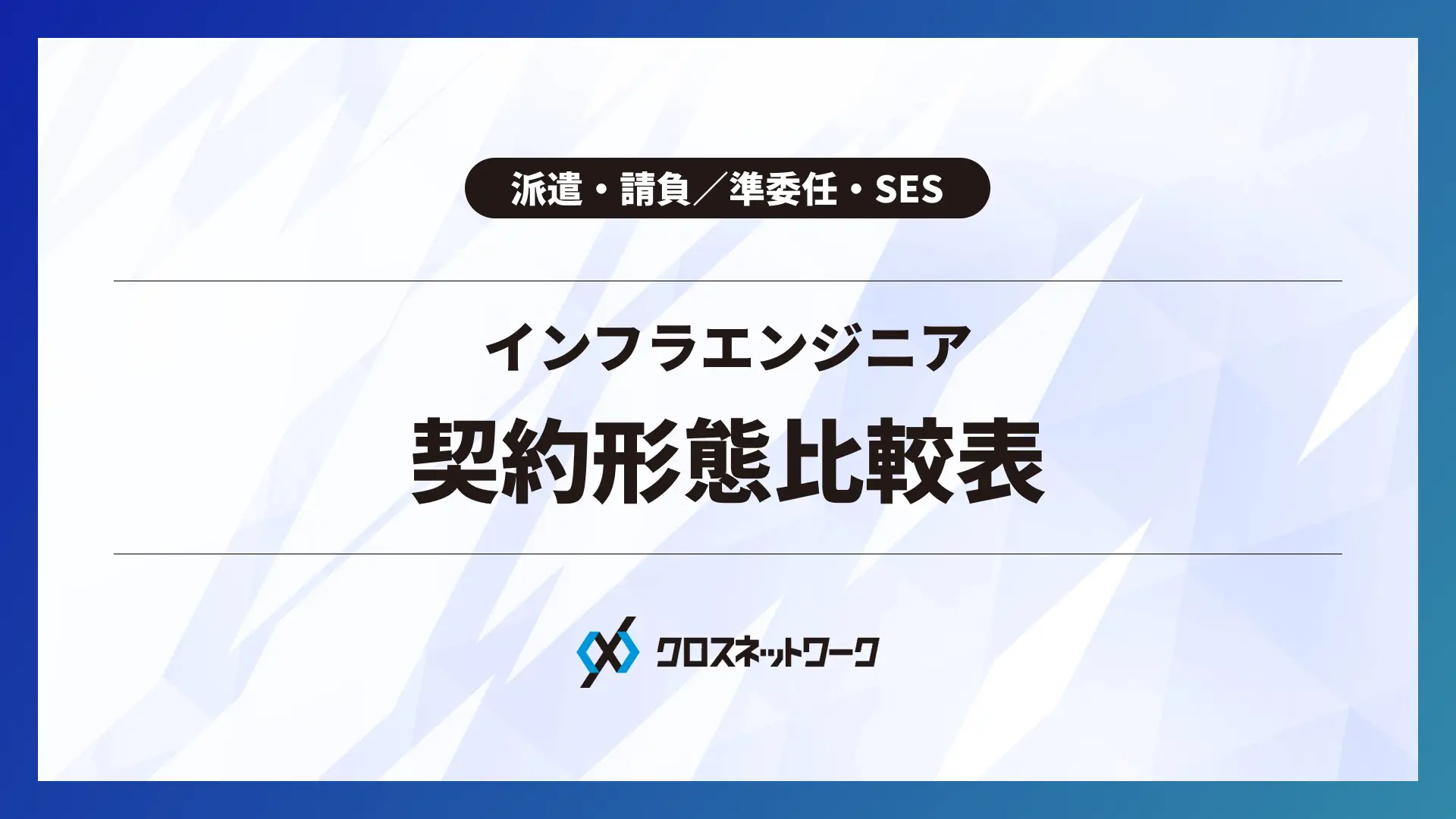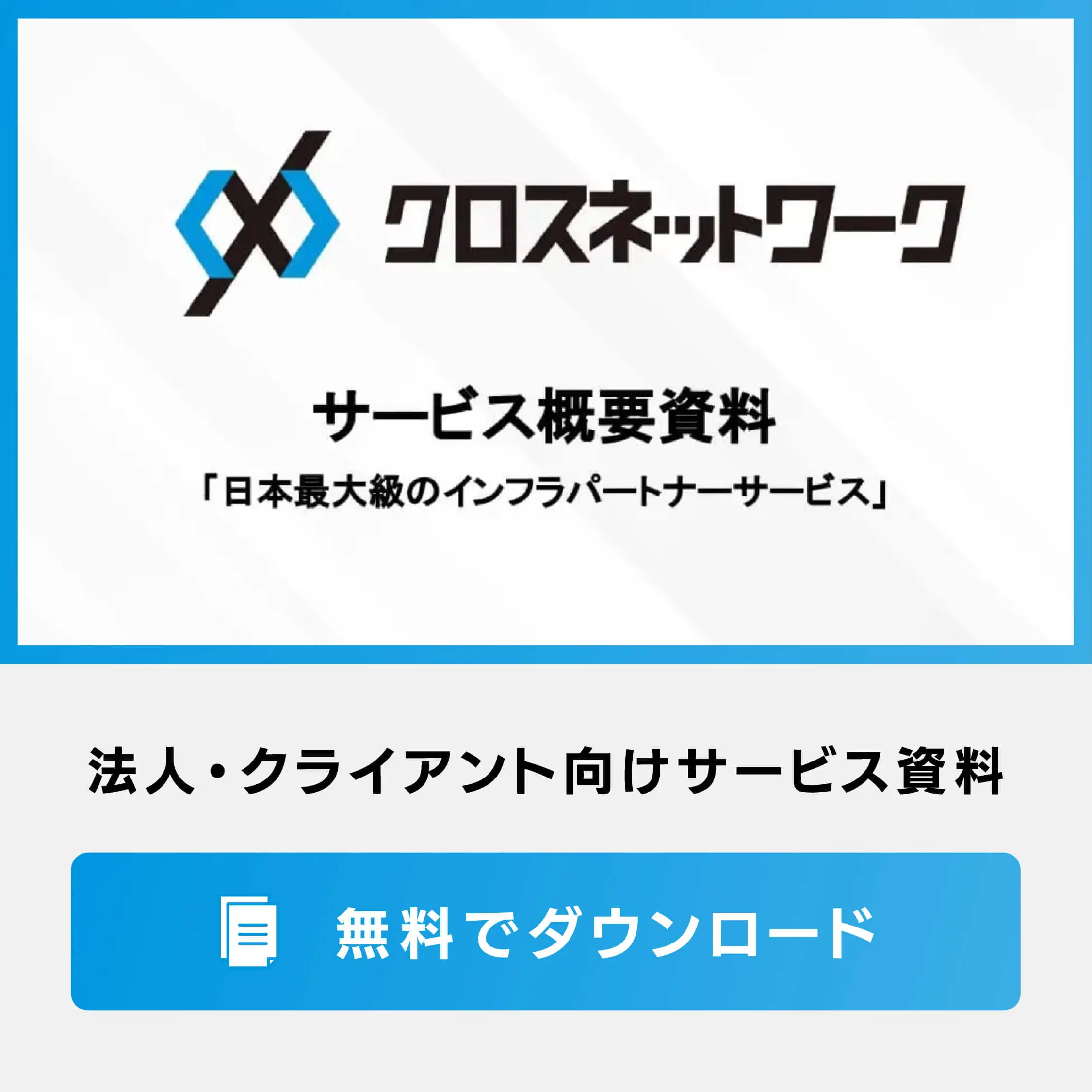クラウドの普及やITインフラの老朽化により、ネットワークの刷新に迫られている企業も多いのではないでしょうか?上層部からも、次世代を担えるネットワークエンジニアを育成するよう圧力をかけられているIT担当者は少なくありません。
しかし、具体的な育成方法や教育プログラムの作り方がわからず困っている方も多いです。そこで本記事は、以下の内容について解説します。
ネットワークエンジニアの育成が重要な背景
自社でネットワークエンジニアを育成するメリット
ネットワークエンジニアの育成を成功させるポイント
即戦力のネットワークエンジニアを確保する方法
本記事を最後まで読めば、即戦力となるネットワークエンジニアを計画的に育成できるでしょう。その結果、プロジェクトが成功して会社からの評価も高まり、より上位のポジションでの活躍機会を得られるようになるはずです。ぜひ参考にしてください。
ネットワークエンジニアの育成が重要な背景
ネットワークエンジニアの育成が重要な理由は以下のとおりです。
ネットワークの需要が急増しているため
オンプレミスからハイブリッド環境への移行が進んでいるため
サイバーセキュリティの強化が必要なため
ネットワークの需要が急増しているため
ネットワークの需要は増加の一途をたどっており、この傾向は今後も加速すると予測されています。通信市場の調査とコンサルティングを専門とするTeleGeographyによると、国際帯域需要(国と国を繋ぐ通信回線の通信容量)は2020年~2024年の間で3倍に達し、年間の平均成長率も30%前後と発表しました。
これは、最新技術の登場による通信容量の増大が影響しているものと推測されます。たとえばIoT(※)機器の普及一つ取っても、管理すべきデバイス数が爆発的に増加しています。最新のオフィスビルであれば、従来のIT端末だけでなく、空調システム、照明、カメラなど、数百から数千のデバイスがネットワークに接続されているケースは珍しくありません。
さらに5G通信サービスの本格展開により、これまでとは比較にならない高速・大容量通信への対応が求められるようになりました。また、リモートワークの定着もおおきな要因で、従業員の自宅からも安全に社内システムにアクセスできる環境を構築する必要が生じています。
このように、最新技術の登場やワークスタイルの変化でデータ通信量も急激に増加しており、従来の設計思想では対応しきれないケースが増えているのです。
(※)IoT(Internet of Things):家電製品や自動車などさまざまモノをネットワークにつなげること
関連記事:ネットワークエンジニアの人材不足が与える影響と解消手段を解説
オンプレミスからハイブリッド環境への移行が進んでいるため
単純なオンプレミス(※)環境だけでネットワークを運用している企業は多くなく、クラウドとの組み合わせがメインになっています。クラウドファーストが主流となり、オンプレミスとクラウドを適材適所で使い分ける複雑なネットワーク構成が必要になりました。
このハイブリッド環境では、社内のサーバールームにあるシステムと、AWSやAzureなどのクラウド上のシステムを安全かつ効率的に接続する技術が不可欠です。そのため、マルチクラウド環境では、それぞれ異なる仕様のクラウドを一元的に管理する高度なスキルが求められます。
(※)オンプレミス:自社が所有・管理するITリソースを自前で設置・運用すること
関連記事:ITインフラのクラウド化とは?導入のメリット・移行手順などを解説
サイバーセキュリティの強化が必要なため
サイバー攻撃による被害額は年々増加しており、日本国内でも、インターネットバンキングの不正送金やランサムウェア(※1)などで数十億円規模の被害に遭った企業もいます。厄介なことに攻撃手法も高度化・巧妙化しており、従来のファイアウォールやウイルス対策ソフトだけでは防ぎきれない脅威が増えています。
そのため、ゼロトラストモデル(※2)の導入が、多くの企業で検討されるようになりました。また、セキュリティインシデントが発生したときの迅速な対応力も重要で、24時間365日の監視体制を支える人材育成が急務となっているのです。
(※1)ランサムウェア:システム上のデータにロックをかけ、その解除と引き換えに身代金を要求するソフトウェア
(※2)ゼロトラストモデル:信頼できるラインという考えを取り除き、すべての通信を常に検証・監視すること
関連記事:ITインフラにおけるセキュリティとは?重要性と企業の被害事例・対策も解説
ネットワークエンジニアを育成するメリット
ネットワークエンジニアの育成に投資すれば、短期的なコストを上回る長期的なリターンをもたらすでしょう。ネットワークエンジニアを育成する主なメリットは以下のとおりです。
プロジェクトの成功率向上を期待できる
自社全体の技術力向上を図れる
エンジニアのモチベーションを維持できる
将来の技術リーダー候補を確保できる
プロジェクトの成功率向上を期待できる
プロジェクトの失敗原因の多くは技術力不足に起因しており、エンジニアの育成はプロジェクト成功への最も確実な投資といえます。技術力の高いエンジニアが設計に関わることで、後工程での手戻りや設計変更が大幅に削減され、プロジェクトの品質が向上するでしょう。
予期せぬ問題が発生したときでも、幅広い知識を持つエンジニアなら代替案を素早く提示できるはずです。また顧客からの技術的な要求に対しても、単に「できる・できない」ではなく、「こういう方法なら実現可能です」といった建設的な提案ができるようになるのです。
自社全体の技術力向上を図れる
1人の優秀なエンジニアを育成することで、その知識とスキルが組織全体に波及し、全体の技術レベルが底上げされます。育成されたエンジニアが日常的にナレッジシェアを行うことで、他のメンバーも自然とスキルアップするからです。
技術標準化も進みやすくなり、属人化していた作業が誰でもできるようになることで、作業効率が向上し品質も安定します。新技術への対応力も組織的に向上し、SD-WANのような新しい技術も、チーム全体で素早く習得できるようになるでしょう。
エンジニアのモチベーションを維持できる
エンジニアが業務に対し高い意欲を維持できるのも、育成のメリットです。
たとえば、資格取得支援や研修参加など技術習得の機会を提供することで、エンジニアは自分の成長を実感でき、仕事への満足度が向上するでしょう。専門性が向上すると、より難易度の高いプロジェクトにも参加できるようになります。
新しい技術にチャレンジする機会も増え、ルーティンワークから脱却して、創造的で挑戦的な業務に携われるようになります。給与面でも、スキルアップに応じた評価制度を整備することで、努力が報われる環境を作ることができるのです。
関連記事:ITインフラ業務におすすめの資格11選!取得へのロードマップ・仕事内容・即戦力の採用方法も紹介
将来の技術リーダー候補を確保できる
エンジニアを育成すれば、5年後、10年後の組織の技術的な中核を担う人材に成長します。次世代のプロジェクトリーダーやマネージャー候補を計画的に育成することで、組織の持続的な成長が可能になるでしょう。
技術的な判断力を持つ人材は、単に技術を知っているだけでなく、ビジネス視点でも適切な判断ができるようになり、経営層との橋渡し役としても活躍できます。組織の技術戦略を立案・実行できる人材も育ち「5年後のネットワークインフラはこうあるべき」という長期的なビジョンを描ける人材が生まれます。
ネットワークエンジニアの育成が進まない背景
前章のようなメリットがあるにも関わらず、実際には多くの企業でネットワークエンジニア育成が思うように進んでいないのが現実です。育成担当者が感じている「なぜうまくいかないのか」という疑問に、具体的な原因と解決の糸口をお伝えします。
エンジニアのスキルレベルに差がある
時間と予算に余裕がない
若手のモチベーションが低い
教育体制が整っていない
エンジニアのスキルレベルに差がある
部下のスキルレベルがバラバラな状態では、効果的な育成プログラムを組むことが困難になります。新人エンジニアはネットワークの基礎知識から学ぶ必要がある一方で、経験者は最新技術の習得を求めており、この幅広いスキルレンジに対応するのは容易ではありません。
個別対応しようとすると、マネージャーの負担が増大し、結果的に育成効率が大幅に低下してしまいます。統一的な評価基準や育成カリキュラムがないため、何をどこまで教えればよいのか曖昧になりがちなのです。
関連記事:【一覧表】インフラエンジニアに求めるスキル15選!資格も紹介
時間と予算に余裕がない
育成が進まない原因の一つとして「いますぐ成果を出さなければならない」というプレッシャーが挙げられます。プロジェクトの納期が迫る中で、じっくりと部下を育成する時間を確保することは現実的に困難です。
研修費用や外部講師を招く予算も限られており、費用対効果が見えにくい人材育成より目の前の案件を優先せざるを得ない現場も少なくありません。日常業務に追われる中でエンジニア自身も学習時間を確保できず「勉強したいけど時間がない」という状況になっているのです。
若手のモチベーションが低い
「頑張って勉強しても、その先に何があるのかわからない」といった不安から、学習意欲が湧かないエンジニアが増えています。
技術習得の成果が見えにくい環境では「資格を取っても給料が上がらない」「新しい技術を学んでも使う機会がない」などの不満が蓄積します。日々の業務で達成感を得られる機会も少なく、上司からの評価も不十分だと「自分の成長が認められていない」と感じるエンジニアも出てくるでしょう。
教育体制が整っていない
育成が現場任せになっており、体系的な教育プログラムがない企業も存在します。「見て覚えろ」という昔ながらの方法では、最新技術の習得スピードに追いつけず、若手の成長が遅れてしまいます。
指導できる上級エンジニアも不足しており、教える側も手探り状態の企業も多いです。育成ノウハウの蓄積と共有体制も欠如しているため、せっかくの成功事例が組織内で生かされない企業は珍しくありません。
ネットワークエンジニアの育成を成功させるポイント
育成を成功させるには、個人の努力に頼らない組織的なアプローチが必要です。ネットワークエンジニアの育成を成功させるポイントは以下のとおりです。
具体的で測定可能な育成目標を設定する
体系的な学習プログラムを構築する
実践的な経験機会を積極的に提供する
継続的な学習をサポートする環境を整備する
具体的で測定可能な育成目標を設定する
育成が成功している企業の共通点は「3か月後にはこのスキルを身につける」といった具体的な目標設定にあります。単に「ネットワークに詳しくなる」ではなく「VLANの設計ができる」「BGPの基本設定ができる」など、測定可能な目標を設定することが重要です。
具体的には、スキルマップを作成し各エンジニアの現在地と目標地点を可視化しましょう。進捗管理が容易になるだけでなく、定期的な評価とフィードバックで「できるようになったこと」と「まだ足りないこと」を明確にすることができます。
体系的な学習プログラムを構築する
場当たり的な研修ではなく、基礎から応用まで段階的に学べるカリキュラムの設計が不可欠です。「第1段階:ネットワーク基礎」「第2段階:スイッチ・ルータ設定」「第3段階:クラウドネットワーク」といった段階的な構成にします。
理論学習と実践演習のバランスも重要で、座学で学んだことをすぐに実機やシミュレータで試せる環境を整えることが効果的です。最新技術トレンドも取り入れ、SD-WANやゼロトラストなど、今後必要になる技術も継続的にカリキュラムに反映していきます。
実践的な経験機会を積極的に提供する
実際のプロジェクトで経験を積ませることも効果的な育成方法です。OJTの機会を意図的に創出し、先輩エンジニアの仕事を見学させたり、簡単な作業から徐々に任せていきます。
チャレンジングな業務への積極的なアサインも重要で「少し背伸びすれば届く」レベルの仕事を与えることで成長を促進します。失敗を許容する環境づくりも不可欠で「失敗から学ぶ」文化を醸成し、トラブル対応も貴重な学習機会として活用しましょう。
継続的な学習をサポートする環境を整備する
一時的な研修だけでなく、日常的に学習できる環境を整備することが持続的な成長の鍵となります。社内勉強会や技術共有会を定期的に開催し、エンジニア同士が学び合う文化を作ることで、組織全体のレベルアップを図ります。
外部研修への参加や資格取得も積極的に支援し、CCNAやAWS認定資格の受験料補助や合格報奨金制度を設けるのも効果的。技術書籍の購入補助やオンライン学習ツールのライセンス提供など、自己学習をサポートする制度も充実させます。
なお、外部研修の代わりにフリーランスエンジニアを活用するのも一つの手です。プロジェクトの隙間時間に勉強会を主催してもらったり、新任エンジニアの技術指導を任せたりするのも良いでしょう。
学習時間確保のための業務調整も重要で「金曜日の午後は自己学習時間」といったルールを設けることも大切です。このような継続的なサポート体制により、エンジニアは常に最新技術をキャッチアップでき、組織の技術力も維持・向上するでしょう。
ネットワークエンジニアを育成するステップ
ネットワークエンジニアを育成する具体的なステップは以下のとおりです。
- 育成目的を明らかにする
- 必要な人材像を定義する
- キャリアパスを策定する
- 育成プランを作成する
- 実務でスキルアップを図る
- 振り返りの場を設ける
1. 育成目的を明らかにする
育成の失敗の多くは「なぜ育成するのか」という目的が曖昧なまま始めてしまうことに原因があります。組織の事業戦略と技術戦略の整合性を確認することから始め、「3年後にクラウドサービスの売上を2倍にする」といった事業目標に対して、どんな技術力が必要かを明確にしましょう。
現在の技術力と目指すべき技術力のギャップ分析も重要で、「いまのチームはオンプレミスには強いがクラウドは弱い」といった現状を正確に把握します。育成によって解決すべき課題も明確にし「プロジェクトの遅延を30%削減する」「トラブル対応時間を半分にする」など、具体的な改善目標を設定します。
2. 必要な人材像を定義する
「優秀なネットワークエンジニア」という漠然とした目標ではなく、具体的なスキル要件を明文化することが育成の鍵です。専門スキルだけでなく、ビジネススキル(顧客対応力、提案力)やヒューマンスキル(コミュニケーション力、リーダーシップ)の要件も定義します。
レベル別の人材要件も設定し「レベル1:基本的な設定ができる」「レベル2:設計ができる」「レベル3:アーキテクチャを決定できる」といった段階を設けます。将来の技術トレンドも考慮し、「5年後にはAIを活用したネットワーク自動化が主流になる」といった予測を踏まえた人材像を定義しましょう。
3. キャリアパスを策定する
必要な人材像が固まったら、若手エンジニアに明確なキャリアパスを提示しましょう。たとえば専門性を追求するルートでは「ネットワークスペシャリスト」「セキュリティアーキテクト」など、その分野を極める道筋を設計します。
マネジメント職への昇進ルートも整備し「チームリーダー→課長→部長」といった管理職への道も明確に示します。他領域への展開可能性も検討し、「ネットワークエンジニアからクラウドアーキテクトへ」といったキャリアチェンジの選択肢を用意することも重要です。
また、各段階での必要スキルと経験を明確にし、「チームリーダーになるには、3つ以上のプロジェクトでリード経験が必要」といった具体的な条件を設定します。このようなキャリアパスの明示によりエンジニアは将来への希望を持ち、主体的に努力するはずです。
4. 育成プランを作成する
個人の特性と組織のニーズを両立させた、オーダーメイドの育成計画を立てましょう。個人別の育成計画書を作成し、現在のスキルレベル、強み・弱み、本人の希望を踏まえた具体的な成長プランを策定します。
短期(3か月)・中期(1年)・長期(3年)の目標を設定し、「3か月後にCCNA取得、1年後にAWS認定取得、3年後にプロジェクトリーダー」といった段階的な計画を立てます。必要なリソースの確保も重要で、研修費用、学習時間、メンターの割り当てなど、計画実行に必要な要素を事前に準備しましょう。
また進捗管理とマイルストーンの設定を行うことで「毎月第一金曜日に進捗確認」「四半期ごとに計画見直し」といった管理サイクルを確立できます。このような綿密な計画により、場当たり的な育成から脱却し、着実な成長を実現できるようになります。
5. 実務でスキルアップを図る
座学だけでは実力は身につかず、実際のプロジェクトで手を動かすことが最も効果的な学習方法です。計画的なプロジェクトアサインにより、簡単な作業から徐々に難易度を上げていき、無理なく経験を積み重ねられるようにしましょう。
段階的な責任範囲の拡大も重要で、最初は先輩のサポート役から始め、徐々に一部分を任せ、最終的には全体を任せる流れを作ります。上級者からの指導とフィードバックも欠かせません。作業後には必ず振り返りを行い、「なぜこの設計にしたのか」という思考プロセスも共有します。
このような実践的な経験の積み重ねにより、自信を持って業務に取り組めるエンジニアが育っていきます。
6. 振り返りの場を設ける
育成は「やりっぱなし」では効果が半減し、定期的な振り返りによって初めて本当の成長を実現できます。定期的な1on1ミーティングを実施し、月に1回は30分程度の時間を確保して、進捗確認と悩み相談の場を設けましょう。
四半期ごとの成果レビューでは、設定した目標に対する達成度を確認し、うまくいった点と改善が必要な点を明確にします。育成プロセス自体の改善も重要で「この研修は効果的だった」「この進め方は負担が大きすぎた」といったフィードバックを次期計画に反映します。
ネットワークエンジニアを育成する余裕のない企業が人材を確保する方法
ここまでネットワークエンジニアの育成方法を解説してきました。しかし育成の余裕がなくすぐにでも即戦力が欲しい企業もいるでしょう。ここでは即戦力のネットワークエンジニアを確保する方法を紹介します。
ネットワークエンジニアを確保する方法 | メリット | デメリット |
開発会社に委託 |
|
|
即戦力を中途採用 |
|
|
フリーランスの活用 |
|
|
開発会社に委託する
短期的に高度な技術力が必要な場合、開発会社への委託が迅速な解決策となります。専門性の高いチームを即座に活用でき「来月からクラウド移行プロジェクトを開始したい」といった急な要求に対応できることもあります。
プロジェクト規模に応じた柔軟なリソース調整も可能で、繁忙期には10名体制、通常期には3名体制といった調整が容易です。最新技術への対応力と豊富な経験により、自社では対応困難な高度な要求にも確実に応えてもらえるでしょう。これにより、社内の研修費用や採用活動にかかる時間と費用も節約できるでしょう。
ただし、委託費用が高額になる可能性があり、長期的には自社で育成するよりもコストがかかることがあります。また、社内にノウハウが蓄積されないという課題もあり、プロジェクト終了後に同様の案件が発生した場合も再度委託が必要になるでしょう。
このように、長期的な依存関係による自立性の低下も懸念され、技術的な判断を外部に頼り続けることで、組織の技術力が向上しないリスクもあります。
即戦力を中途採用する
経験豊富な人材による即戦力としての貢献はおおきく、入社初日から短期間でプロジェクトの戦力となります。
他社のノウハウや技術を取り入れることができ、「前職ではこういう方法で解決していた」といった新しい視点をもたらしてくれます。社内の技術レベル向上と既存メンバーへの刺激にもなり、中途採用者から学ぼうとする姿勢が組織全体に広がるでしょう。
しかし、優秀な人材の獲得競争は激しく、とくにネットワークエンジニアは需要が高いため、採用が困難な状況が続いています。高額な給与水準による人件費の増加も避けられず、既存社員との給与バランスを考慮する必要も出てきます。
また、企業文化への適応に時間がかかる場合もあり、技術力は高くても組織になじめずに退職してしまうリスクにも注意が必要です。
関連記事:インフラエンジニアは正社員採用するべき?メリットと採用のポイントなどを解説
フリーランスを活用する
フリーランスの活用は、必要なときに必要なスキルを柔軟に調達できる、コストパフォーマンスの高い選択肢です。プロジェクト期間に応じた柔軟な契約形態が可能で、3か月の短期プロジェクトから1年以上の長期案件まで、ニーズにあわせて契約できます。
正社員雇用に比べても採用手続きが簡素で、面接から稼働開始まで1週間程度で完了することも珍しくありません。たとえば弊社のインフラエンジニア専門エージェント「クロスネットワーク」では最短3営業日でアサインが可能です。また、複数の企業で経験を積んだフリーランスならではの幅広い知見も活用できるでしょう。
一方で、チームワークや組織文化への適応が課題となることがあり、「個人プレーが多い」「報連相が不十分」といった問題が生じることもあります。また案件の待遇によってモチベーションに差が出ることもあり、興味のある仕事には積極的でも、そうでない仕事には消極的になる人材もいます。
自社にフィットした人材を探すためにも、専門エージェントへ相談してみましょう。
関連記事:インフラエンジニア案件をフリーランスに業務委託する方法とメリットを解説
即戦力を採用する、フリーランスを活用する場合のどちらにおいても、異なるメリット・デメリットがあります。最適な方法を見極め、自社の業務改善などにつなげましょう。
以下の資料では、インフラエンジニアの採用と外注について、メリット・デメリットなどを解説しています。インフラエンジニアを求めている企業担当者は、ぜひダウンロードしてみてください。
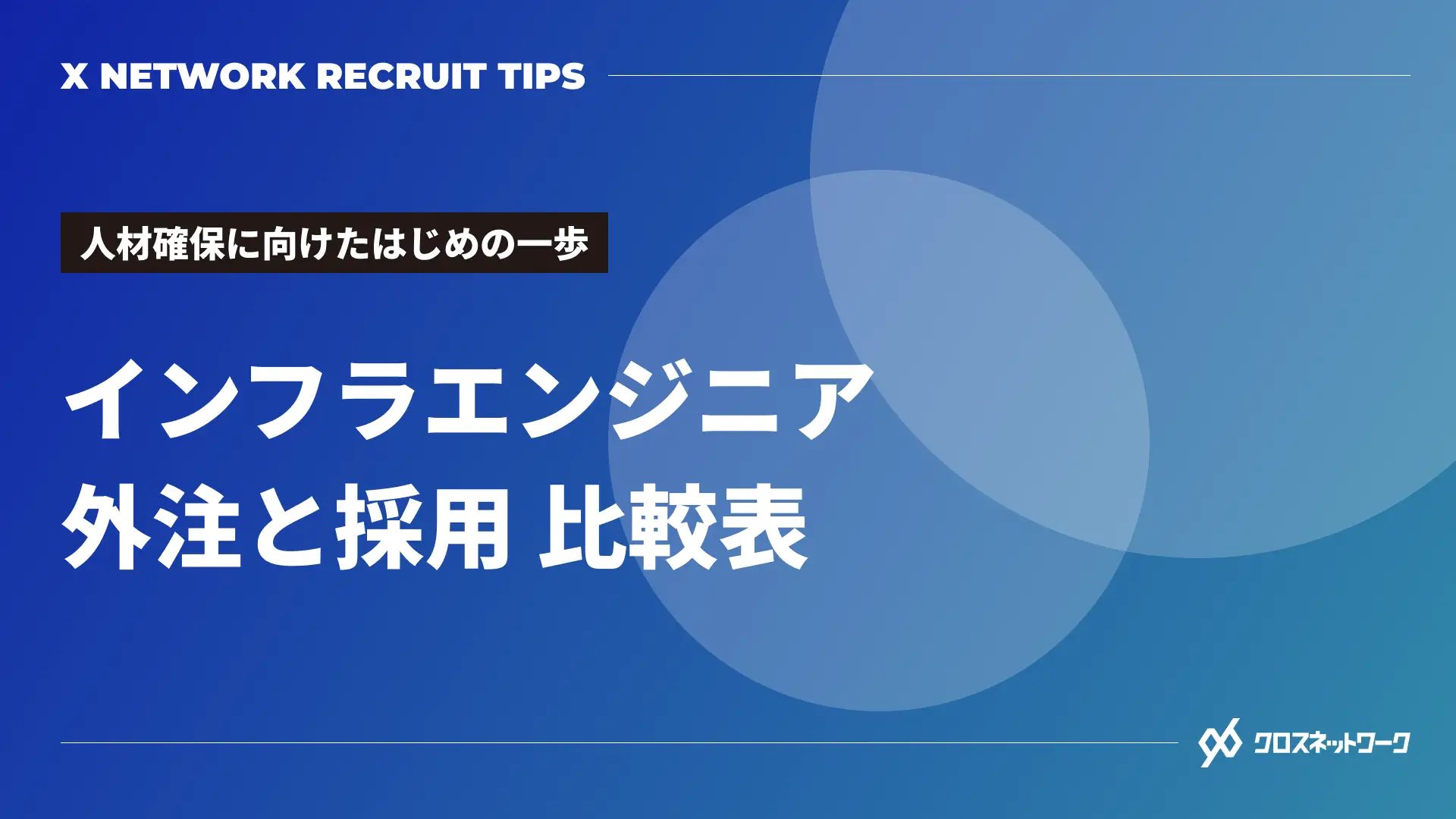
即戦力のネットワークエンジニアをお探しならクロスネットワークにご相談ください
本記事では、ネットワークエンジニアの育成が重要な背景と育成を成功させるポイントなどについて解説しました。
近年はクラウドの普及やDX化の流れで、求められるネットワーク技術の要件が多様化しています。限られた時間と予算の中で複雑なネットワーク技術に対応できる人材を育成するためには、育成目的と人材要件を明確にして、教育体制を整備する必要があります。外部研修も活用するなどして、現在保有しているリソースを最大限活用しましょう。
一方で「育成に注力する余裕がない」「予算をかけずに即戦力を確保したい」という企業も多いはずです。
経験豊富なネットワークエンジニアを確保するなら、ぜひクロスネットワークにご相談ください。クロスネットワークはインフラエンジニア専門のエージェントサービスで、通過率5%と厳しい審査に合格した人材のみ在籍しています。ネットワークの設計・構築やクラウド運用などの多様なジャンルに長けたエンジニアを、クライアントの要望にあわせてスムーズにマッチングします。
採用後のやりとりもサポートしますので、トラブルを回避できるのもメリット。さらに、登録しているインフラエンジニアと合意があれば、正社員登用もできます。
エージェントに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週3日程度の依頼も可能なので、自社の必要リソースにあわせて柔軟に外注できます。
こちらよりサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力のインフラエンジニアをお探しの方は【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

新卒で大手インフラ企業に入社。約12年間、工場の設備保守や運用計画の策定に従事。 ライター業ではインフラ構築やセキュリティ、Webシステムなどのジャンルを作成。「圧倒的な初心者目線」を信条に執筆しています。