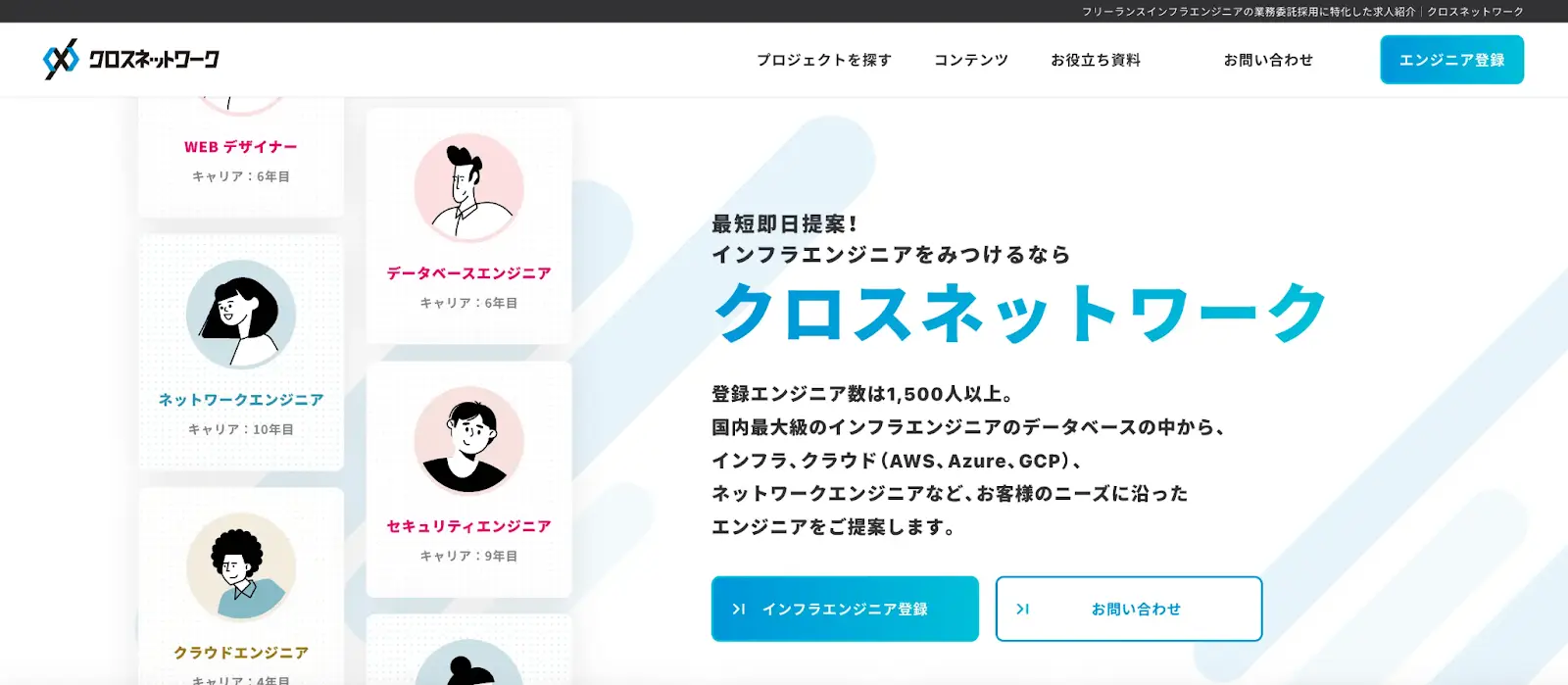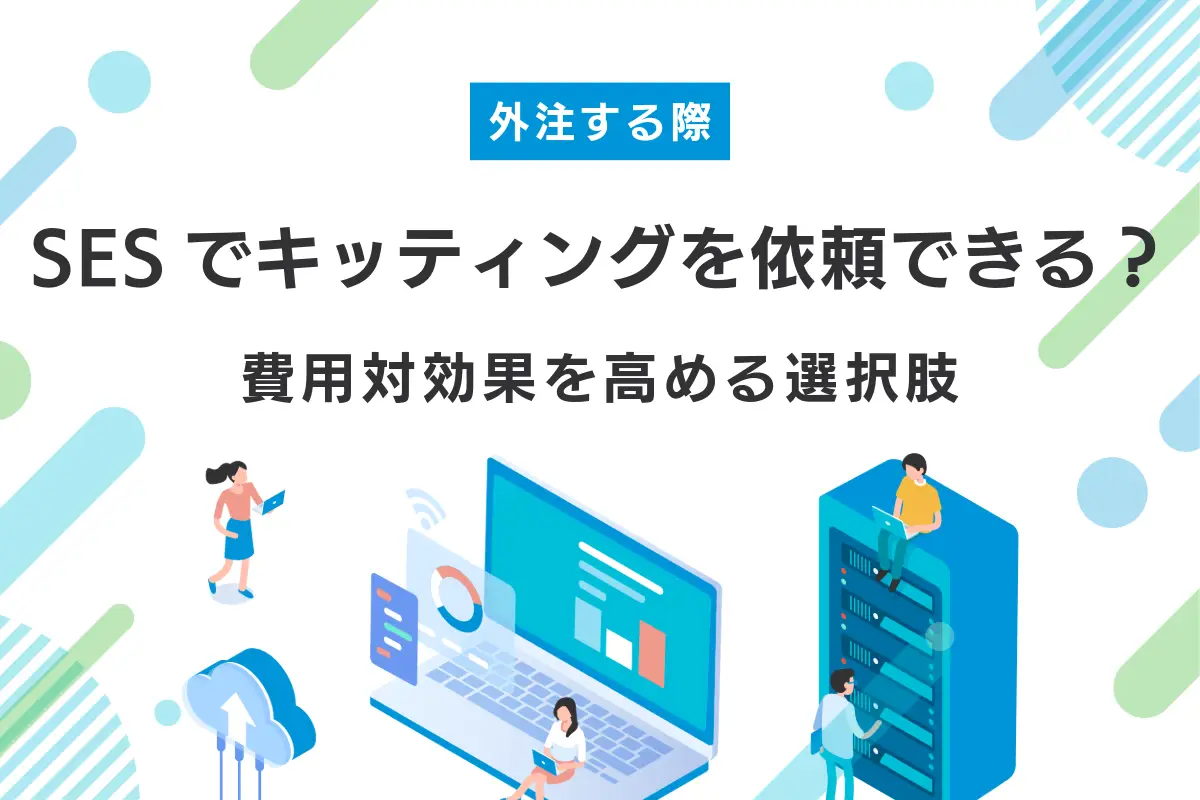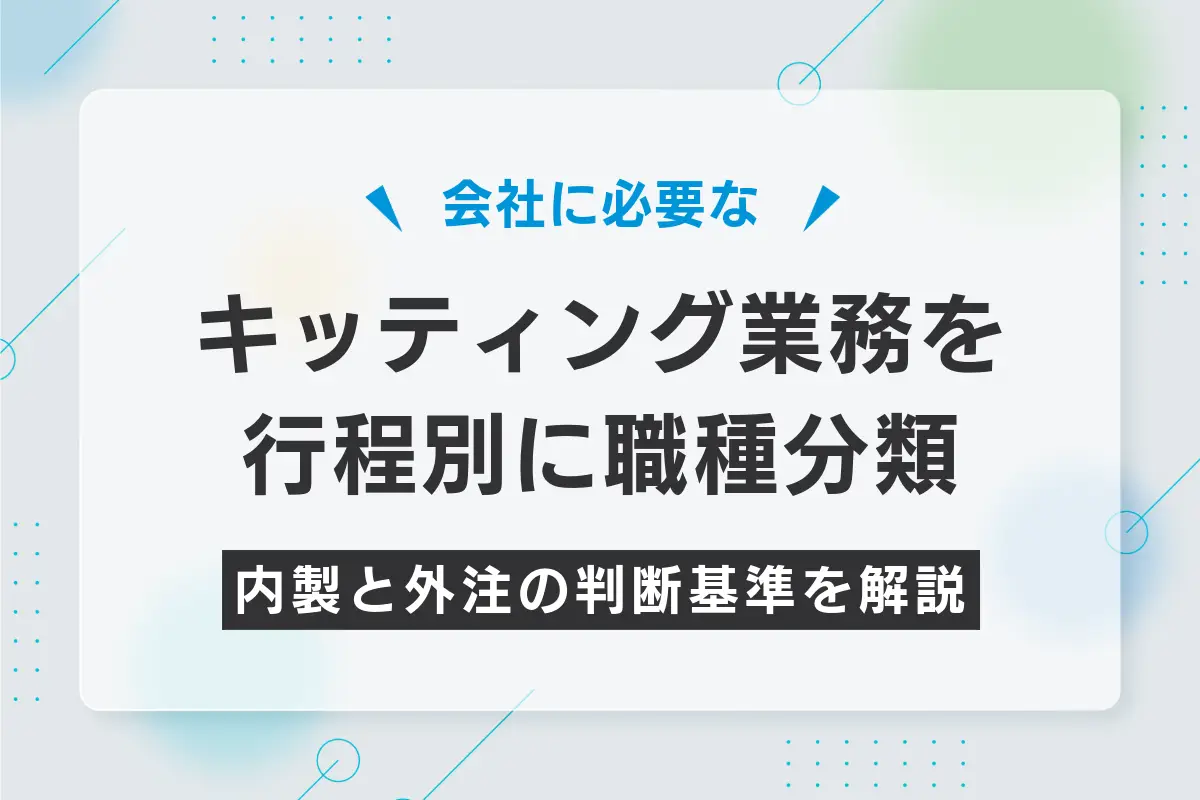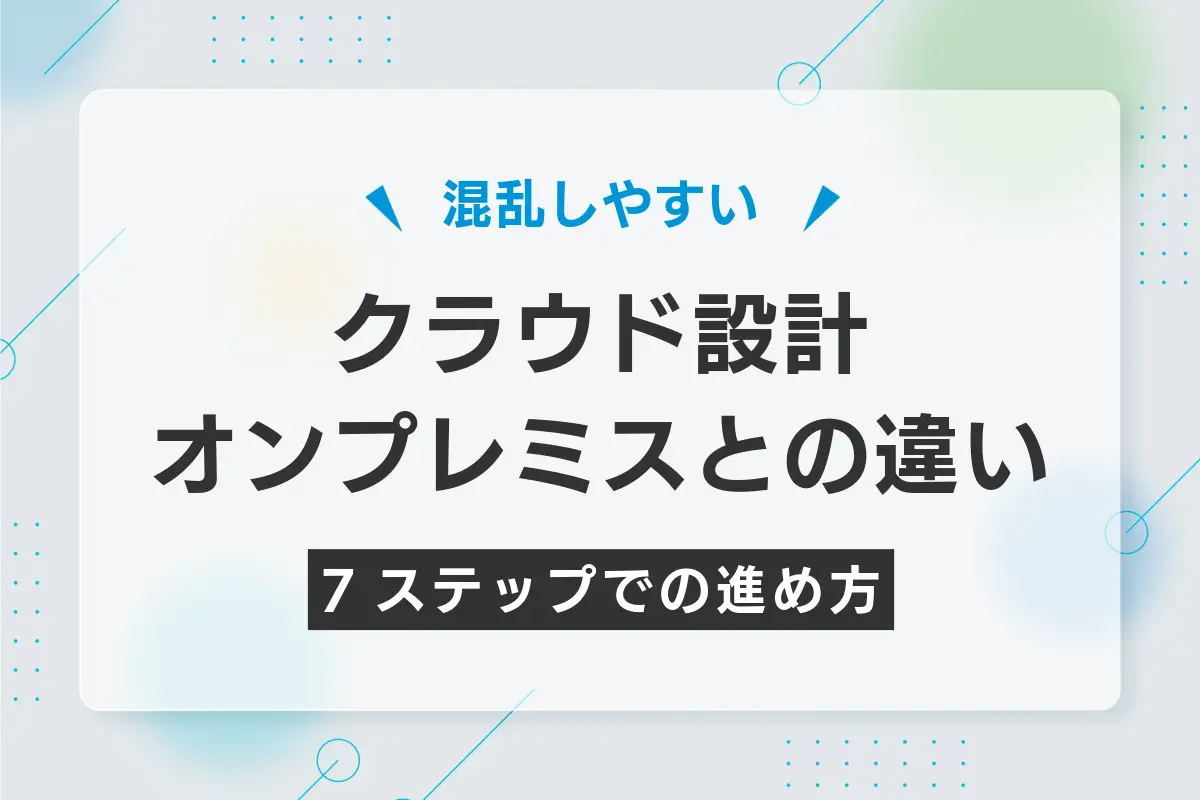
ITインフラの生産性向上、コスト削減においてクラウドが注目されています。自社にリソースをもたず運用管理の負担が少ないことから、経営層からもクラウド移行の指示が出ている企業も多いでしょう。
一方で「クラウドの知識がないから構築方法がわからない」「すぐにクラウドへ移行すべきなのか疑問」と思うIT担当者もいるはずです。闇雲にクラウドへ移行して、予算と時間を浪費するのは避けたいもの。
そこで本記事では以下の内容について解説します。
- ITインフラをクラウド化するメリット
- クラウドへ移行する手順
- 移行するときの注意点
本記事を最後まで読めば、計画的かつ安全にクラウドへ移行する方法を理解できるでしょう。運用コストの削減とシステム安定性の向上を図りたい中小企業の経営者は、参考にしてください。
ITインフラのクラウド移行とは?
ITインフラのクラウド移行とは、自社で管理しているオンプレミスシステムを、インターネット上のクラウド環境へ移すプロセスのことです。
これまで多くの企業では、自社の建物内や外部のデータセンターにサーバーやネットワーク機器を設置し、IT部門が24時間365日の運用・保守を担ってきました。しかし、近年は老朽化したハードウェアの更新コストの高騰、リモートワーク対応の必要性、人材不足などの課題から、クラウド移行を検討する企業が増加しています。
多くの企業のクラウド移行では、限られた予算内での実現、社内のクラウド知識不足、既存システムとの互換性などの課題があります。このような課題からどのようにして企業のITインフラを最適化するかが、クラウド移行における重要なポイントと言えるでしょう。
クラウドインフラの種類
クラウドインフラには、以下の3つの種類があります。
- パブリッククラウド
- プライベートクラウド
- ハイブリッドクラウド
それぞれ特徴や適用場面が異なるため、自社の要件にあわせて最適な選択肢を見つけることが重要です。
パブリッククラウド
パブリッククラウドとは、クラウド事業者が所有・運用するサーバーやネットワークのリソースを、多数の利用者が共有しながらも、論理的に分離された形で利用できるクラウドサービスのことです。利用者はインターネット経由のほか、専用線やVPNなどの閉域接続を通じてクラウド環境にアクセスすることも可能です。主要なサービスの特徴は以下のとおりです。
- AWS:豊富なサービス群とエコシステム、高い拡張性と信頼性
- Azure:Microsoft製品との高い親和性と企業向け統合サービス
- GCP:データ分析と機械学習に強み、Googleの強力なインフラ基盤
クラウドサービス選定基準として、既存システムとの親和性、必要な機能、コスト要件を総合的に判断することが重要です。また、複数のクラウドサービスを組み合わせてリスク分散を図る手法もあります。
関連記事:インフラエンジニアが扱うAWSの仕事内容とは?代表的なサービスも紹介
プライベートクラウド
プライベートクラウドとは、自社専用に構築されたクラウド環境のことです。
プライベートクラウドが適している企業は、機密情報を扱う金融機関や医療機関、特殊な要件があるシステムを運用する企業などです。セキュリティ要件やコンプライアンス要件の厳しい業界では、プライベートクラウドが重要な役割を果たすでしょう。
ハイブリッドクラウド
ハイブリッドクラウドとは、クラウドサービス(パブリッククラウドやプライベートクラウド)とオンプレミスを組み合わせたシステム環境のことです。おおきな特徴は、システムの柔軟性とセキュリティの両方を確保できること。
たとえば、高いセキュリティが求められるシステムではオンプレミスで実装し、需要に応じてリソースの調整が必要な場合はクラウド対応する、といったことが可能です。また、ピーク時と平常時でオンプレミスとクラウドを使い分けることで、変動費の管理も容易になるでしょう。
災害やトラブル発生時のリカバリー、バックアップも強化されるので、事業の継続性も向上します。
クラウドサービスの提供モデル
クラウドサービスには、提供される範囲によって大きく3つのモデルがあります。
- IaaS
- PaaS
- SaaS
それぞれの特徴と適用場面を理解することで、自社に最適なサービスを選択できるようになるでしょう。
IaaS
IaaS(Infrastructure as a Service)は、サーバー、ストレージ、ネットワークといったITインフラの基盤部分のみを提供するクラウドサービスです。主要なIaaSサービスの特徴は以下のとおりです。
- Amazon EC2:AWSはクラウド市場で世界最大のシェアを誇り、EC2では豊富なインスタンスタイプ(※)が選択可能
- Azure Virtual Machines:Microsoft製品との親和性が高く、企業環境に適している
- Google Compute Engine:Googleの強力なネットワークインフラを活用できる
IaaSは、既存システムをそのままクラウドに移行したい場合や、システム構成を自由にカスタマイズしたい場合に向いています。
(※)インスタスタイプ:仮想サーバーのスペックを表す区分のこと
PaaS
PaaS(Platform as a Service)は、アプリケーション開発に必要なOS、ミドルウェア、データベースなどをセットで提供するサービスです。主要なPaaSサービスの特徴を以下にまとめました。
- AWS Elastic Beanstalk:多様なプログラミング言語に対応し、簡単なデプロイが可能
- Azure App Service:Visual StudioやGitHubとの連携が優れている
- Google App Engine:自動スケーリング機能が強力で、トラフィック変動に柔軟対応
PaaSのメリットは、開発環境と実行環境の違いによるトラブルを減らせること。そのため、開発からリリースまでの期間を大幅に短縮できます。
SaaS
SaaS(Software as a Service)は、完成されたソフトウェアアプリケーションをインターネット経由で提供するサービスです。主要なSaaSの活用事例は以下のとおりです。
- Microsoft 365:文書作成、メール、オンライン会議を統合的に提供
- Google Workspace:リアルタイム共同編集機能に優れたオフィススイート
- Salesforce:顧客管理から営業支援まで包括的に対応
同じクラウドサービスでも、SaaSは標準的な業務フローで運用できる分野に適したモデルです。経理や人事など多くの企業で共通する業務の効率化に向いているでしょう。
ITインフラにおけるクラウドとオンプレミスの違い
ITインフラにおいてクラウドとオンプレミスのどちらを選ぶかは重要な判断です。クラウドとオンプレミスには、以下のように運用方法からコスト構造までさまざまな違いがあります。
項目 | オンプレミス | クラウド |
運用モデル |
|
|
コスト構造 |
|
|
拡張性 |
|
|
セキュリティモデル |
|
|
可用性 |
|
|
オンプレミスの特徴
オンプレミスの特徴は、自社が所有・管理するITリソースを自前で設置・運用していることです。
ハードウェアの調達(購入またはリース)に多くの手間とお金がかかるうえに、日々のメンテナンスも発生します。将来性を見越して拡張性を担保するとなると、余裕をもって設計しなければなりません。
また、ITインフラ構築やセキュリティ対策などにおいて専門の人材を確保することも必要です。
クラウドの特徴
クラウドはネットワーク経由でクラウド事業者のサービスを使うため、リソースを保有する必要がありません。その分、導入費用と環境構築の負担を減らせる点が魅力です。
もし、リソースが急遽必要になったときには、管理画面から自由にリソースを調整することができます。また、セキュリティ対策や構築面ではクラウドの標準機能を利用できるため、必ずしも高度な専門スキルを必要としないのもポイントです。
ITインフラをクラウドに移行するメリット
クラウド移行には数多くのメリットがありますが、とくに注目すべきは以下の3つです。
- 初期コストを削減できる
- 柔軟にリソースを拡張できる
- 運用の負担を軽減できる
初期コストを削減できる
クラウド移行の最大のメリットは初期導入コストを大幅に削減できることです。
オンプレミスでシステムを構築する場合、サーバーやネットワーク機器の購入・リース費用、データセンターへの設置費用などで数百万円から数千万円の初期投資が必要になります。
一方、クラウドサービスでは初期費用をほぼゼロに抑えることができ、必要なサービスを選んですぐに利用開始できます。たとえば、Amazon EC2やAzure Virtual Machinesなどのサービスでは、アカウント作成から数分でサーバーを起動できるため、スピーディーなシステム構築が可能です。
これにより、とくにスタートアップや中小企業にとっては、資金調達の負担を軽減しながら本格的なITインフラを活用できるようになります。
柔軟にリソースを拡張できる
クラウドの真価は必要に応じてリソースを柔軟に拡張・縮小できる点にあります。
クラウドでは、数分から数時間でCPUやメモリ、ストレージを追加でき、不要になったら即座に削除することも可能です。自動スケーリング機能を設定すれば、アクセス数の増減に応じて自動的にリソースを調整してくれるため、管理者の負担も軽減されます。
この柔軟性により、急成長する企業や季節変動のあるビジネスでも、無駄なコストをかけずに最適なITインフラを維持できるのです。
運用の負担を軽減できる
運用管理の負担を軽減できることもクラウド移行のメリットです。物理インフラの運用管理をクラウド事業者が担当するため、自社の担当者は本来の業務であるアプリケーション開発や改善に集中しやすくなるからです。
障害発生時の対応も、ハードウェア関連の問題はクラウド事業者が復旧してくれるため、従来に比べて緊急対応の頻度は大幅に減少します。ただし、復旧後のシステム確認やアプリケーション層の障害対応は引き続き自社の管理が必要となります。これにより、IT部門の負担を軽減しつつ、より戦略的な業務に人材を集中させることができます。
運用管理の負担軽減について詳しく知りたい方は以下の記事もおすすめです。
関連記事:ITインフラの運用自動化とは?重要性とメリット成功事例も紹介
ITインフラをクラウドに移行するデメリット
クラウド移行にはメリットがある一方で、事前に把握しておくべきデメリットも存在します。
- ランニングコストが増加するリスクがある
- カスタマイズ性に制限がある
- セキュリティに配慮しなければいけない
ランニングコストが増加するリスクがある
従量課金制のクラウドサービスでは、使用量に応じて料金が変動します。そのため、利用状況をしっかり管理しないと想定以上のコストが発生するかもしれません。
とくにPaaSやIaaSサービスでは、事業の拡大や人員の増加に伴ってトラフィックが増大し、予測コストを大幅に上回ることもあります。また、複数のクラウドサービスを併用するマルチクラウド化により、トータルコストが予算を超過してしまうリスクも考えられるでしょう。
このような状況を避けるためには、定期的なコスト監視とリソースの最適化が欠かせません。
カスタマイズ性に制限がある
クラウドサービスは、サービス提供事業者が用意した機能や構成に一定の制約があるため、オンプレミス環境と比べて細かなカスタマイズが難しい場合があります。また、これまで自社で利用していたシステムがクラウドサービスに対応していない場合、継続して利用することができなくなる可能性があります。
クラウド移行を検討する場合には、現在利用しているシステムのうち、継続利用できる機能とそうでない機能を整理しておくことが重要です。
セキュリティに配慮しなければいけない
クラウドサービスはインターネット経由で利用されるケースが多いため、外部からの不正アクセスやサイバー攻撃のリスクを十分に考慮する必要があります。もちろん、クラウド事業者側で高度なセキュリティ対策を行っていますが、標準のセキュリティ機能だけを過信し、利用者側の適切な設定や運用を怠ると、思わぬセキュリティリスクを招く可能性があります。
そのため、ユーザー側で実施すべきセキュリティ対策を正しく理解しなければいけません。たとえば、データの暗号化、アクセス権限の管理、ネットワークアクセス制御、多要素認証の導入などは、利用者側で実装・管理する必要があります。
さらに、どこまでの業務をクラウドで行うか、どの程度の重要データを取り扱うかといったシステム要件定義も、セキュリティリスクを考慮して検討する必要があります。
適切なセキュリティ対策を実施することで、クラウド環境でも安全にシステムを運用できるでしょう。
関連記事:ITインフラにおけるセキュリティとは?重要性と企業の被害事例・対策も解説
ITインフラをクラウドに移行する6ステップ
クラウド移行は各工程で発生し得る技術的・業務的な課題を事前に整理し、段階的に進めることが成功の鍵となります。ここでは、代表的な移行ステップを解説していきます。
- ステップ1:現状分析と移行対象システムの選定
- ステップ2:クラウドサービスの選定
- ステップ3:クラウド環境のセットアップ
- ステップ4:データ移行の実行
- ステップ5:アプリケーション移行とテスト検証
- ステップ6:本番環境への切り替えとモニタリング体制の構築
ステップ1:現状分析と移行対象システムの選定
まずは現在運用しているすべてのシステムをリストアップし、それぞれの稼働状況や依存関係を整理しましょう。
重要なのは、システムごとのビジネス影響度とクラウド移行の難易度を評価することです。たとえば、顧客データベースのように機密性が高く業務への影響がおおきいシステムと、社内の勤怠管理システムのように影響範囲が限定的なシステムでは、移行の優先順位が変わってきます。
影響度が低く移行しやすいシステムから段階的に進めることで、リスクを最小限に抑えながらクラウド環境を構築できるでしょう。
ステップ2:クラウドサービスの選定
クラウドサービスの選定は単なる機能比較だけでなく、自社の現状システムとの相性を重視することが重要です。
AWS、Azure、GCPといった3大クラウドサービスにはそれぞれ特徴があり、既存システムとの親和性や移行のしやすさが異なります。たとえば、マイクロソフト製品を多用している企業ならAzure、オープンソース技術を積極活用している企業ならAWSやGCPが適している傾向にあります。
移行するときには、自社システムの要件に応じて使い分けましょう。
ステップ3:クラウド環境のセットアップ
クラウド環境のセットアップはのちの運用コストと安定性に直結するため、慎重に設計する必要があります。
この段階で重要なのは、将来の拡張性を考慮した設計にすることです。特に、将来的なシステム拡張や組織成長を見据えたネットワークアドレス設計、権限管理、アカウント構成など論理的な柔軟性を確保することがポイントです。
ステップ4:データ移行の実行
データ移行は最もリスクが高く、慎重な計画と実行が求められるステップです。大容量データの移行では、ネットワーク帯域の制限や転送時間を考慮し、段階的な移行スケジュールを立てることが重要です。
万が一の障害に備えて、オンプレミス環境のデータは移行完了後も一定期間保持しましょう。移行が失敗したときに備えて、切り戻し可能な状態を維持しておくとより安全です。
ステップ5:アプリケーション移行とテスト検証
アプリケーション移行では動作検証とパフォーマンステストを段階的に実施し、本番環境と同等の条件で確認することが重要です。クラウド環境では、オンプレミスとは異なるパフォーマンス特性を示すことがあるため、十分な負荷テストと非機能要件の検証(スケーリング挙動、フェイルオーバー確認など)を行う必要があります。
また受け入れテストでは、実際の業務フローに沿って検証し、現場の担当者に操作感や応答速度について確認してもらうことが大切です。この段階で発見された課題は、本番切り替え前に必ず解決しておきましょう。
ステップ6:本番環境への切り替えとモニタリング体制の構築
本番切り替えは計画的な段階移行により、ビジネスへの影響を最小限に抑えることが可能です。まず、影響範囲の小さなシステムから順次切り替えを行い、問題がないことを確認してから次のシステムに進みます。
切り替え当日は、関係者全員が参加する作業体制を構築し、問題発生時の連絡手順と切り戻し手順を明確にしておくことが重要です。移行完了後はモニタリングツールを導入し、システムパフォーマンスやコスト使用量を継続的に監視する体制を整えておきましょう。
ITインフラをクラウドに移行するときの注意点
クラウド移行を成功させるためには、事前に把握しておくべき重要な注意点があります。
- レガシーシステムとの互換性を検証する
- 移行中にサービスへの影響がないか洗い出す
- データ保全のアプローチ方法を検討する
- ベンダーロックインの回避策を立てる
これらのポイントを理解し、適切な対策を講じることで、移行プロジェクトのリスクを大幅に軽減できます。
レガシーシステムとの互換性を検証する
レガシーシステムの互換性問題は、クラウド移行プロジェクトが失敗する原因の一つです。
現行システムのOS・ミドルウェアのバージョンを調査して、クラウド環境でサポートされているかチェックしましょう。データベース移行時の文字コードや機能互換性の事前チェックも大切な項目です。
また、互換性テストのための検証環境構築と実施手順も確立しましょう。互換性問題が発生した場合の代替手段やワークアラウンドの準備をしておくことも重要です。
ITインフラ全般の整備方法について詳しく知りたい方は、下の記事も参考にすると良いでしょう。
関連記事:ITインフラの整備とは?重要な理由と具体的な手順・成功事例・注意点も解説
移行中にサービスへの影響がないか洗い出す
業務影響を最小化するためには、移行時間帯と移行順序の計画が重要です。
システム切り替え時のダウンタイム見積もりと許容範囲の設定を明確にしておきましょう。移行作業は基本的に業務時間外や休日に実施しますが、24時間稼働が必要なシステムでは特別な配慮が必要です。
万が一予定時間内に移行が完了しない場合のために、切り戻しの判断基準と実施手順を明確にしておくことも重要です。
データ保全のアプローチ方法を検討する
大容量データの効率的な転送方法と、整合性チェック手順の確立が重要です。具体的には、以下の点を明らかにすることが重要です。
- データ暗号化要件の明確化
- 暗号化・検証手順の移行プロセスへの組み込み
- 機密データの取り扱いルール
データの破損・紛失は、企業の競争力、信頼性を下げる要因になりかねません。ルールと手順を決めてデータの保護に取り組みましょう。
ベンダーロックインの回避策を立てる
ベンダー固有機能への過度な依存を避けるために、代替手段を確保することも検討しましょう。具体的には、特定のPaaS機能を避けてコンテナ環境を利用する、OSSベースのミドルウェアを選択するといった方法があります。
また、マルチクラウドによりリスクを分散することで、ベンダーの価格変更や仕様変更に柔軟に対応しやすくなり、一定の交渉余地を確保できる可能性があります。
ITインフラのクラウド移行にフリーランスエンジニアを活用するメリット
クラウド移行プロジェクトは技術的な専門性と豊富な経験が求められる重要な取り組みです。そんなときに頼りになるのがフリーランスエンジニアの存在です。
ここでは、クラウド移行においてフリーランスエンジニアを活用するメリットを解説していきます。
- 即戦力として活用できる
- 人件費を適正化できる
- 社外の知見を得られる
即戦力として活用できる
フリーランスエンジニアは専門スキルを活かした即戦力として、クラウド移行プロジェクトを迅速かつ的確に進めるうえで貴重な存在です。すでに多様な企業でクラウド移行の実務経験を積んでいることが多く、プロジェクトに参画後すぐに高いパフォーマンスを発揮してくれます。
正社員の場合は入社後の研修や業務慣れに時間がかかりますが、フリーランスエンジニアなら契約後すぐに実務に取り掛かれるため、プロジェクトの納期が迫っている状況でも安心です。
人件費を適正化できる
フリーランスエンジニアの活用により、正社員採用と比較してコストを適正化しやすくなります。正社員を採用する場合、基本給に加えて社会保険料の企業負担、福利厚生費、退職金積立など、実際の給与以外にも多くの間接費用が発生します。
一方、フリーランスエンジニアに支払う費用は報酬と業務に伴う諸経費のみです。また、契約期間が終了すれば人員の調整も柔軟に行えるため、人件費を最適化しやすくなるでしょう。。
関連記事:インフラエンジニアの報酬単価と相場はいくら?外注するメリットも解説
社外の知見を得られる
フリーランスエンジニアは、多様な企業での経験で得た豊富な知見を提供してくれます。社内のエンジニアだけでは気づかない課題や、他社で成功した移行手法、最新の技術トレンドなど、外部の視点からアドバイスを受けられるはずです。
とくに同業他社での移行経験があるフリーランスエンジニアは貴重です。業界特有の課題や規制要件についても深い理解をもっているため、より実践的な提案をしてくれるでしょう。
ITインフラのクラウドに強いフリーランスエンジニアをお探しの方はクロスネットワークがおすすめ
今回は、ITインフラをクラウド化するメリットと移行手順、導入するときの注意点などについて解説しました。
中小企業のITインフラを刷新するうえで、クラウドは効果的な手段の一つです。初期コストの削減や管理負担の軽減などさまざまなメリットがあるため、収益力の強化を期待できるでしょう。
一方で、正しい手順を踏まないと予想外の障害やコスト増大に直面するかもしれません。本記事を参考に、スムーズなクラウド移行へのヒントをつかみましょう。
また「クラウドに移行したいけれど人材がいない」「エンジニアを養成する余裕がない」という企業も多いかと思います。
優秀なインフラエンジニアにクラウド移行を任せたい方は、ぜひクロスネットワークにご相談ください。クロスネットワークはインフラエンジニア専門のエージェントサービスで、通過率5%と厳しい審査に合格した人材のみ在籍しています。幅広い業界でクラウドの経験を積んだインフラエンジニアを、クライアントの要望にあわせてスムーズにマッチングします。
採用後のやりとりもサポートしますので、トラブルを回避できるのもメリット。さらに、登録しているインフラエンジニアと合意があれば、正社員登用もできます。
エージェントに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週3日程度の依頼も可能なので、自社の必要リソースにあわせて柔軟に外注できます。
こちらよりサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力のインフラエンジニアをお探しの方は【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

新卒で大手インフラ企業に入社。約12年間、工場の設備保守や運用計画の策定に従事。 ライター業ではインフラ構築やセキュリティ、Webシステムなどのジャンルを作成。「圧倒的な初心者目線」を信条に執筆しています。