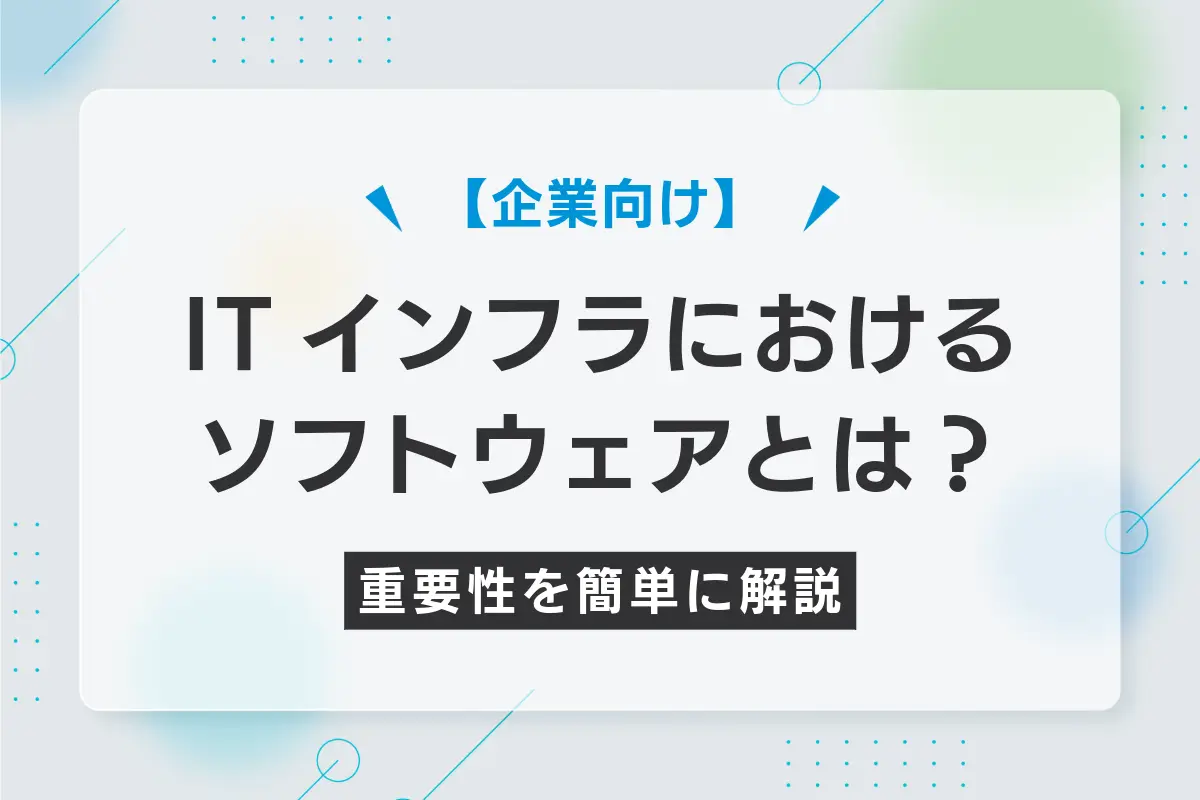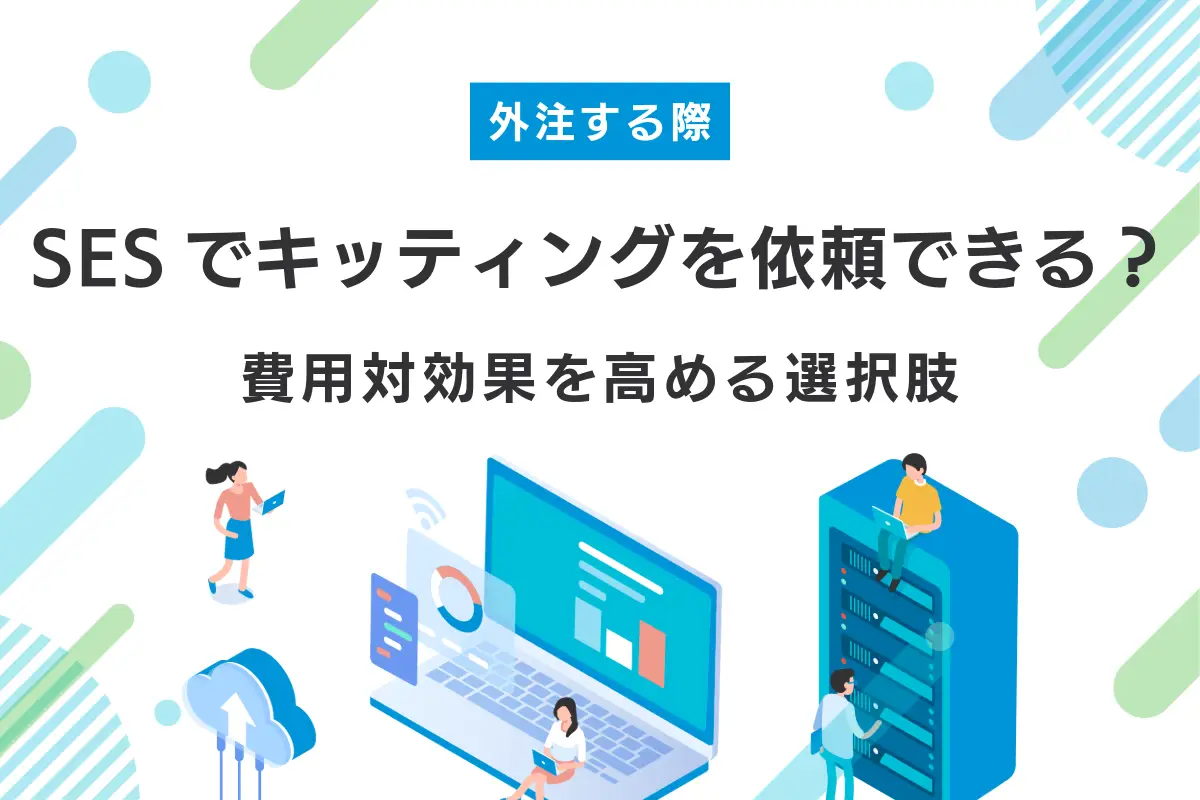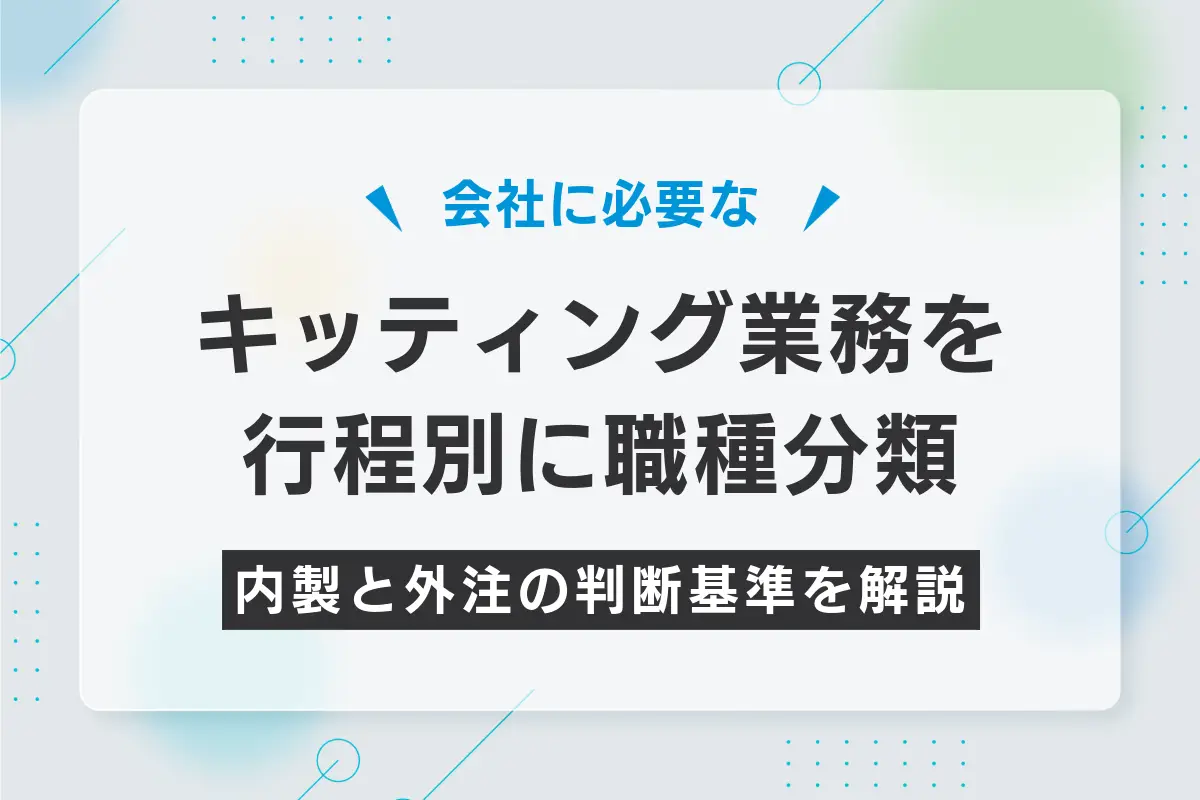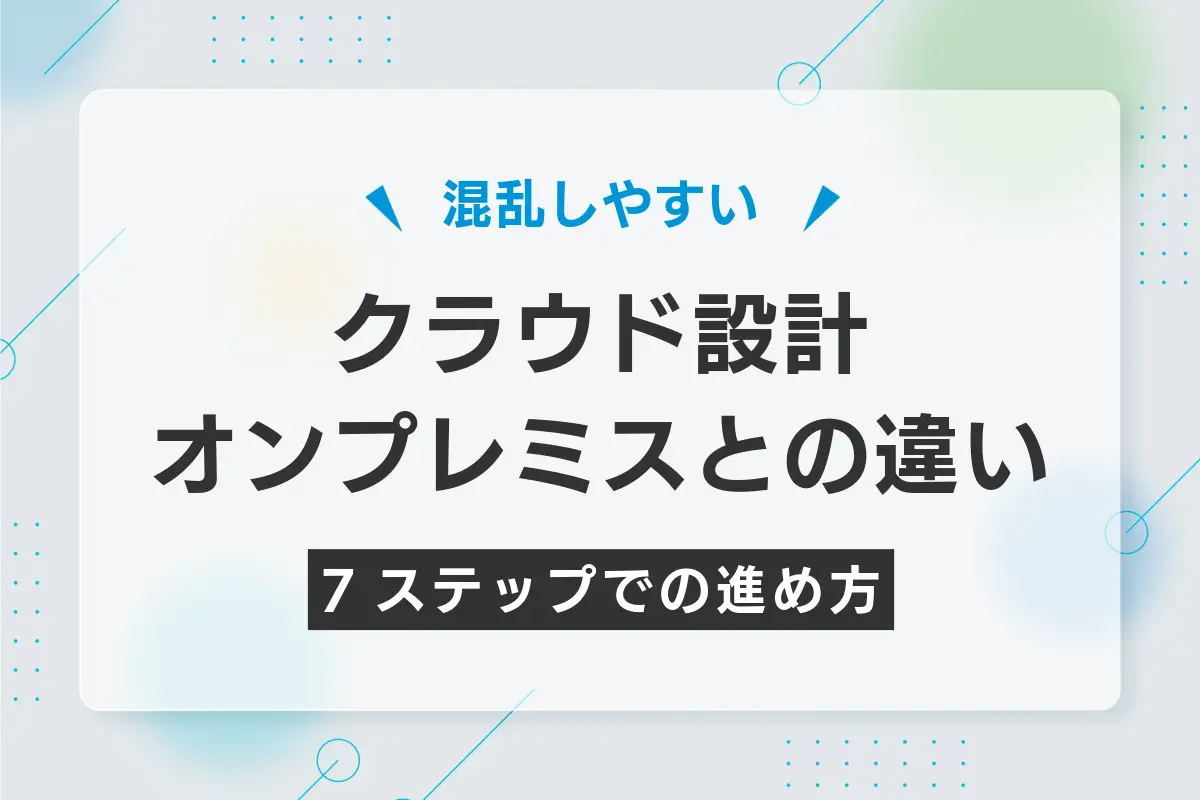
ITインフラの品質を高めるうえで、ソフトウェアは大切な要素です。自社でもITインフラを刷新するために、ソフトウェアの見直しを検討している企業は多いかと思います。
一方で「ITインフラの知識があまりない」「専門人材が不足している」と悩む中小企業の経営者も多いでしょう。そこで本記事では以下の内容について解説します。
ITインフラにおけるソフトウェアの重要性
ITインフラで利用される主なソフトウェア
ITインフラを構築する流れ
ITインフラへの整備、人材確保にお悩みの中小企業の経営者はぜひ参考にしてください。
ITインフラとは?経営者が知っておくべき基本概念
ITインフラとは、企業の情報資産を支える基盤のことです。具体的にはサーバーやPC、ネットワーク機器といったハードウェアと、それらを制御する基本ソフトウェアで構成されています。
ITインフラはビジネスの土台として機能し、業務システムやアプリケーションを安定して動作させる役割を持っています。建物にたとえると、ITインフラは基礎や骨組みの部分にあたり、その上に顧客管理システムや会計ソフトなどの業務アプリケーションが構築される形です。
ITインフラとソフトウェアの関係性
ITインフラはハードウェアとそれらを動かすソフトウェア(OS・ミドルウェア・仮想化ソフトなど)で構成されています。両者の適切なバランスが重要で、ここが崩れるとコスト増や性能低下を招いてしまいます。
たとえば、CPUの性能やストレージの容量を挙げてもOSのバージョンが古いと十分にITインフラのパフォーマンスを引き出せなくなります。一方でOSや仮想化ソフトが最新で、サーバーの処理能力が低いとソフトウェアの動作が不安定になるでしょう。
つまりITインフラの要件を満たすためには、ソフトウェアとハードウェアの要件を精査することが重要です。
ITインフラのソフトウェア整備が重要な理由
ITインフラのソフトウェア整備とは、企業の情報システムを支える基盤技術を適切に設計、構築、運用することを指します。
デジタル化が進む現代において、適切なITインフラとソフトウェアの整備は競争力の源泉です。とくに中小企業では限られたリソースを最大限に活用するための重要な経営戦略となります。
ITインフラのソフトウェア整備が重要な理由は、主に以下の3つに分類されます。
安定稼働の確保
運用効率の向上と人手依存の軽減
セキュリティと事業継続性の強化
安定稼働の確保
ITインフラのソフトウェアは、システムが止まらず安定して動き続けるために不可欠です。システムが稼働する土台が整っていないと、障害・停止・データ消失のリスクが高まります。
たとえば、OSの障害で仮想マシン上の顧客データや取引履歴が消失すると、経営そのものに支障が出ます。また監視ソフトウェアがないと障害の兆候を見逃し「突然システムが止まって受注ができない」「製造ラインが止まる」といった事態も想定されるでしょう。
ITインフラにおけるソフトウェアの安定性は、企業経営における重要な基盤と言えます。
運用効率の向上と人手依存の軽減
ITインフラを運用・管理するソフトウェアを整備することで人的ミスの防止、作業標準化、属人化の解消にもつながり、運用コスト全体を抑制できます。また、手作業で行っていたサーバー設定や定期メンテナンスを自動化することで、IT担当者の作業負荷を大幅に軽減することも可能です。
結果として、限られたIT人材をより戦略的な業務に集中させることができるでしょう。とくに中小企業にとって、少ない人員で効率的にシステムを運用できる環境は価値があります。
セキュリティと事業継続性の強化
ITインフラを運用・管理するソフトウェア整備は、サイバー攻撃や障害発生時のリスクを低減するうえでも重要です。
とくに、近年増加するサイバー攻撃や自然災害による被害から企業を守るためには、多層防御の考え方に基づいたセキュリティ対策が重要です。具体的には外部からの侵入防止、内部での異常検知、データのバックアップという複数の観点でソフトウェアを整備します。
適切なバックアップ体制が整っていれば迅速な復旧が可能になり、事業への影響を最小限に抑えられます。
ITインフラで利用される主なソフトウェア
ITインフラ上で動作するソフトウェアは、企業の業務を支えるアプリケーションが安定して稼働するための基盤機能を提供します。中小企業では、初期コストと運用負荷を考慮したソフトウェア選択が重要になってきます。
ITインフラを構成するソフトウェア
ITインフラを構成するソフトウェアとは、会社のコンピューターシステムの「土台」となる部分で、企業のシステムが安定稼働できるよう性能を左右しています。
近年はクラウド技術の浸透により、オンプレミスとクラウド双方の環境に対応したソフトウェアが求められています。それに伴い、仮想化技術やコンテナ技術の活用も進んでいるため、柔軟な構成が可能です。
ITインフラを構成するソフトウェアを以下にまとめました。
OS:Windows Server、Linuxなど
仮想化ソフトウェア:VMware ESXi、Hyper-Vなど
ミドルウェア:Apache、Tomcat、PostgreSQLなど
これらのソフトウェアを適切に組み合わせることで、経営に必要なアプリケーションを安定的に動かすことができるようになります。
ITインフラを運用・管理するソフトウェア
ITインフラの運用・管理ソフトウェアは、システムの健康状態を見守り、トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。主なソフトウェアとその特徴、製品の例を以下にまとめました。
ソフトウェアの種類 | 概要・特徴 | 主な製品 |
監視ソフト | サーバーの稼働状況やネットワークの通信状態をリアルタイムで監視 | |
バックアップソフト | 大切なデータを定期的に複製保存し、万が一のシステム障害やサイバー攻撃に備える | |
セキュリティソフト | 外部からの不正アクセスやウイルス感染を防ぎ、会社の機密情報や顧客情報を保護 | |
構成管理・自動化ソフト | 複数のサーバーの設定を一括管理したり定型的な作業を自動化 | |
ログ管理・分析ソフト | システムの動作履歴を記録・分析し、異常やパターンを把握 |
これらの運用・管理ソフトウェアを導入することで、専門のエンジニアがいない中小企業でも安定したITインフラ運用を期待できるでしょう。
ITインフラでソフトウェアを導入するときの注意点
ITインフラでソフトウェアを導入するときの注意点は、主に以下のとおりです。
既存システムへの影響を考慮する
セキュリティ対策を怠らない
外部委託と内製化のバランスを考慮する
トラブル発生時の対策を検討する
既存システムへの影響を考慮する
ソフトウェアを導入するときには、既存のシステムとの相性や全体の安定性への影響を確認する必要があります。具体的には、以下のポイントに注意しましょう。
既存の基幹システムとの連携がスムーズにいくかの事前検証
ソフトウェア間のバージョン互換性の確認
システムの冗長構成(同じ機能を持つ装置を複数用意)の検討
フェイルオーバー対応(障害時に自動的に予備系統に切り替わる仕組み)の実装
ソフトウェア導入前には必ず検証環境でテストを行い、本番環境への影響を最小限に抑える計画を立てることが重要です。
セキュリティ対策を怠らない
多くの中小企業はセキュリティ対策が十分でないケースが多く、悪意ある第三者の標的にされる傾向にあります。とくにITインフラに新たなソフトウェアを導入する場合、既存のセキュリティ体制が脆弱なままでは、システム全体のリスクを高めてしまうため注意が必要です。
セキュリティ対策の基本は多層防御です。これは一つの防御策が破られても、別の防御層でカバーするという発想で、具体的には以下のような対策が必要です。
ファイアウォールによる不正アクセスの遮断
全端末へのアンチウイルスソフトの導入と定期的な更新
重要システムへの厳格なアクセス制御(ID・パスワード管理)
ソフトウェア導入後を含めた定期的なセキュリティパッチの適用
また、どのような対策をしても100%安全ということはありません。そのため、万が一の障害やサイバー攻撃に備え、定期的なバックアップとリストア(復元)手順も確立しておきましょう。
さらに重要なのは、セキュリティポリシーの策定と従業員への教育です。セキュリティ対策は技術だけでなく「人」も弱点になりがちです。セキュリティリテラシーは人によって差があるため、定期的に社内研修を実施しましょう。
関連記事:ITインフラにおけるセキュリティとは?重要性と企業の被害事例・対策も解説
外部委託と内製化のバランスを考慮する
ITインフラにソフトウェアを導入するときには、外部の専門家の知見を活用しながらも、長期的には自社の運用自走力を高めることが大切です。多くの中小企業では、ソフトウェア導入の要件定義・設計・構築は外部ベンダーやSIer(システムインテグレーター)に依頼し、導入後の日常的な運用・監視・障害対応は自社内で対応するというバランスが効果的です。
外部委託と内製化の比較表
フェーズ | 外部委託 | 内製化 |
要件定義・設計 | ◎ | △ |
構築 | ◎ | ○ |
運用・保守 | ○ | ◎ |
外部委託のメリットは専門的な知識やスキルを持った人材をすぐに活用できる点です。一方でコストがかかることや、依存度が高まりすぎると自社での判断や運用が難しくなり、柔軟な対応ができなくなるリスクもあります。
内製化のメリットは、自社のビジネスに最適化した運用ができることや、長期的にはコスト削減につながる可能性がある点です。しかし、社内にIT人材を確保・育成する必要があり、すぐには成果が出ないこともあります。
重要なのは、導入後の日々の運用作業が増えすぎない設計になっているかを事前に確認することです。機能は充実していても、管理が複雑すぎると本来の業務に支障をきたすでしょう。
また、委託先との契約では、知識移転(ナレッジトランスファー)の項目を含めることで、将来的な内製化への道筋をつけておくことも重要です。
トラブル発生時の対策を検討する
どれほど高品質なソフトウェアを導入しても、トラブルを完全に避けるのは難しいのが現状です。重要なのは、トラブルが起きたときに迅速に復旧する手段を確保することです。
具体的には、バックアップとリカバリ計画を立てて、システム障害の影響を最小限に抑えるます。主なポイントを以下にまとめました。
バックアップの頻度(重要データは日次、その他は週次など)
バックアップの保管場所(オンサイトとオフサイトの両方が理想的)
リストア手順の文書化と定期的な訓練
リカバリ目標時間(RTO)の設定
とくにクラウド基盤上にソフトウェアを導入する場合、クラウド事業者の障害もリスクとして想定しておきましょう。2022年にはAWSの大規模障害で多くの企業が影響を受けました。このような事態に備えて、最低限の業務を継続できる代替手段(重要データのローカル保存や紙ベースの業務フローなど)を確保しておくことが重要です。
関連記事:インフラエンジニアの育成方法を解説!おすすめの研修や資格なども紹介
ITインフラを構築する流れ6ステップ
ここまで、ITインフラにおけるソフトウェアの役割や選定時のポイントを解説してきましたが、実際の構築ではソフトウェアだけでなく、ハードウェアや設計、運用体制まで含めた全体的な視点が求められます。そこで改めて、ITインフラを効果的に構築するための全体像を6つのステップに分けてご紹介します。
- 現状分析と課題の明確化
- 要件定義
- 設計
- 構築
- 導入・移行と運用テスト
- 社内教育と運用体制の確立
1. 現状分析と課題の明確化
現状分析は、 ITインフラ構築プロジェクトの成否を決める重要なステップです。
現在のインフラ構成と運用状況を詳細に可視化し、パフォーマンスのボトルネックや非効率な部分を特定します。経営課題とインフラ要件の関連付けを行い、投資対効果の高い領域を見極めることで、限られた予算を最大限に活用できるでしょう。社内の各部門からの運用上の要望や課題もヒアリングし、優先順位をつけることも重要です。
また、競合他社や業界のベストプラクティスとの比較分析を行うことも効果的です。短期的な課題と中長期的な課題に分けて整理することで、戦略的な投資判断も可能になるでしょう。
2. 要件定義
要件定義とは現状の課題を踏まえて「何を作るのか」「どのような機能が必要か」「どのような性能が求められるか」といった要求事項を明確にする工程です。具体的には、インフラに求める機能要件と非機能要件(性能、セキュリティ、可用性など)を明確に定義し、現場の実際の業務フローとの適合性を確認します。
また、全体スケジュールを策定するときに無理のない現実的な計画を立てることも重要です。投資予算の配分と投資回収計画を策定し、リスク分析と対応策を検討しましょう。
データ移行計画の策定と検証も大切で、とくに重要なマスターデータの整備については慎重な準備が必要です。
3. 設計
設計段階では、要件定義で決めた内容を具体的な技術仕様に落とし込んでいきます。
システム全体のアーキテクチャ設計から始まり、ネットワーク構成、サーバー構成、セキュリティ設計まで詳細に検討します。将来の拡張性や保守性を考慮した設計を行うことで、運用コストを抑制できるでしょう。
技術選定においては、自社の技術レベルや運用体制に適したソリューションを選ぶことが成功の鍵となります。たとえば専門エンジニアがいない企業では、複雑なLinuxサーバーより、GUIで操作できるWindows Serverが適しているかもしれません。オンプレミスでの運用が負担になるのであれば、クラウドへ移行するという手段も考えられます。
このように、将来性と自社の現状を踏まえて設計することが重要です。
4. 構築
構築フェーズでは設計書に基づいて実際にシステムを構築し、各段階で動作確認とテストを実施します。変更管理を徹底し、設計変更が発生した場合は影響範囲を評価して適切に対応します。
構築の進捗状況を定期的に確認し、スケジュール遅延やコスト超過のリスクを早期に察知して対策を講じることが重要です。
5. 導入・移行と運用テスト
導入・移行フェーズはリスクが高いため、慎重な計画と準備が重要です。段階的な導入と並行運用により業務への影響を低減することを目指しましょう。
また、運用部門主体の運用確認テスト(運用受入テスト)を実施し、現場からのフィードバックを収集することも重要です。
そして、本番環境への移行計画と切り替え時のリスク対策を万全にし、万が一に備えて切り戻し手順も事前に確認しておきましょう。
6. 社内教育と運用体制の確立
システムをリリースしたらそれで終わりではありません。ITインフラを安定稼働させるために社内の運用体制を確立することが重要です。
具体的には、新システムの操作研修とマニュアル整備を行い、部門ごとの推進リーダーを育成して社内サポート体制を構築しましょう。運用ルールとガイドラインを策定し、定期的な振り返りと改善活動の仕組みを作ることで、継続的な改善を図ります。
また、システム活用状況のモニタリングと効果測定の方法も確立しておくのも効果的です。投資対効果を定量的に評価できるため、長期的かつ安定的な運用につながるでしょう。
関連記事:ITインフラ運用とは?仕事内容や保守との違い・外注のメリットについて解説
ITインフラのソフトウェアに強い人材を確保する方法
ITインフラのソフトウェアに強い人材を確保する方法は、主に以下の3つです。
経験者を中途採用する
未経験者を育成する
フリーランス人材を活用する
経験者を中途採用する
即戦力が必要な場合は経験者の中途採用が効果的な選択肢の一つです。
ITインフラの経験者は、設計・構築・運用に関する幅広い知識を持っており、ソフトウェア導入初期から安定的な運用を実現できる可能性が高いからです。採用面接のときには「自社で使用予定の技術スタックに精通しているか」「同規模の企業での経験があるか」を重点的に確認しましょう。
また、経験者の採用は競争が激しく、給与水準も高くなる傾向があるため、魅力的な労働環境や成長機会を提示することが求められます。
関連記事:インフラエンジニア採用にエージェントを活用するメリットと選び方を解説
未経験者を育成する
未経験者の育成は中小企業にとって有効な人材確保戦略の一つです。
IT業界への転職希望者や新卒者の中には、高いポテンシャルを持った人材が数多く存在しています。育成には時間とコストがかかりますが、自社のITインフラ環境業務に特化した知識を身につけてもらえるため、長期的には価値のある投資となります。
研修プログラムの設計では、WindowsやLinuxなどのOS基礎知識から始めるのが一般的です。続いて、データベース管理システムやWebサーバーなどのミドルウェア、仮想化技術、クラウドサービスの運用管理まで段階的に習得できるよう配慮しましょう。
関連記事:インフラエンジニアの育成方法を解説!おすすめの研修や資格なども紹介
フリーランス人材を活用する
フリーランス人材の活用は柔軟性とコスト効率を両立できる優れた選択肢です。特定のITインフラ構築プロジェクトや基盤刷新に限定して専門性の高い人材を確保できるため、正社員採用に比べて採用リスクを大幅に軽減できます。
また、フリーランスエンジニアは多様な企業での経験を持っているため、最新のOS環境やクラウド基盤の構築ノウハウ、仮想化技術の運用ベストプラクティスなどを提供することが期待できます。
なお、契約のときは業務範囲や成果物を明確に定義し、セキュリティや機密保持に関する取り決めを徹底しましょう。
関連記事:インフラエンジニア案件をフリーランスに業務委託する方法とメリットを解説
ITインフラのソフトウェアに強い人材を探すならクロスネットワークにご相談ください
本記事では、ITインフラにおけるソフトウェアの位置づけと重要性、ITインフラで利用される主なソフトウェア、ITインフラでソフトウェアを導入するときの注意点などについて解説しました。
ITインフラでは多種多様なソフトウェアが開発されており、システムの安定稼働や運用効率の向上を通じて、生産性の向上や経営判断に役立つデータ活用を間接的に支えています。自社のインフラ要件を精査し、計画的に導入すれば、事業活動の効率化や安定運用を実現できるでしょう。
ただしソフトウェアを活用するためには高度な専門スキルが問われます。一朝一夕で技術を身につけるのは難しいケースも多いので、外部の即戦力を活用することも検討しましょう。
優秀なインフラエンジニアにソフトウェア導入を任せたい方は、ぜひクロスネットワークにご相談ください。クロスネットワークはインフラエンジニア専門のエージェントサービスで、通過率5%と厳しい審査に合格した人材のみ在籍しています。要件定義、ベンダーとの折衝など各分野で経験を積んだエンジニアを、クライアントの要望にあわせてスムーズにマッチングします。
採用後のやりとりもサポートしますので、トラブルを回避できるのもメリット。さらに、登録しているインフラエンジニアと合意があれば、正社員登用もできます。
エージェントに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週3日程度の依頼も可能なので、自社の必要リソースにあわせて柔軟に外注できます。
こちらよりサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力のインフラエンジニアをお探しの方は【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

新卒で大手インフラ企業に入社。約12年間、工場の設備保守や運用計画の策定に従事。 ライター業ではインフラ構築やセキュリティ、Webシステムなどのジャンルを作成。「圧倒的な初心者目線」を信条に執筆しています。