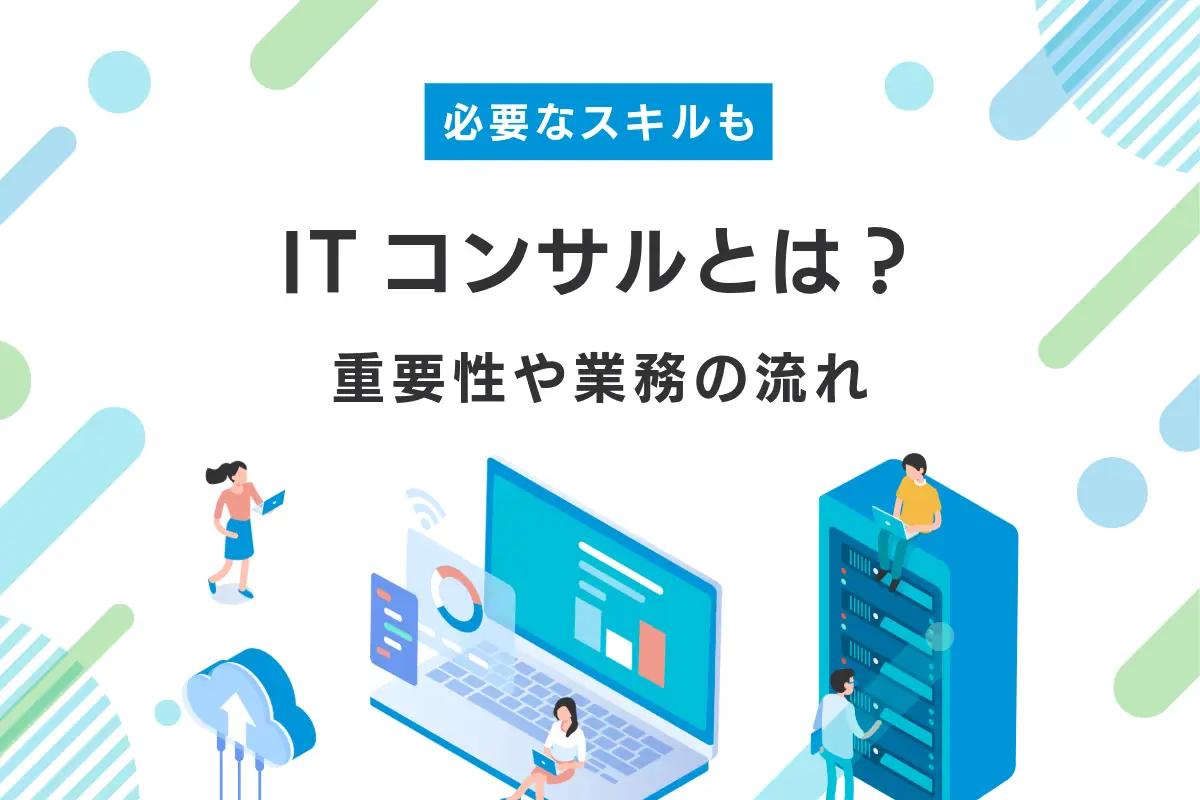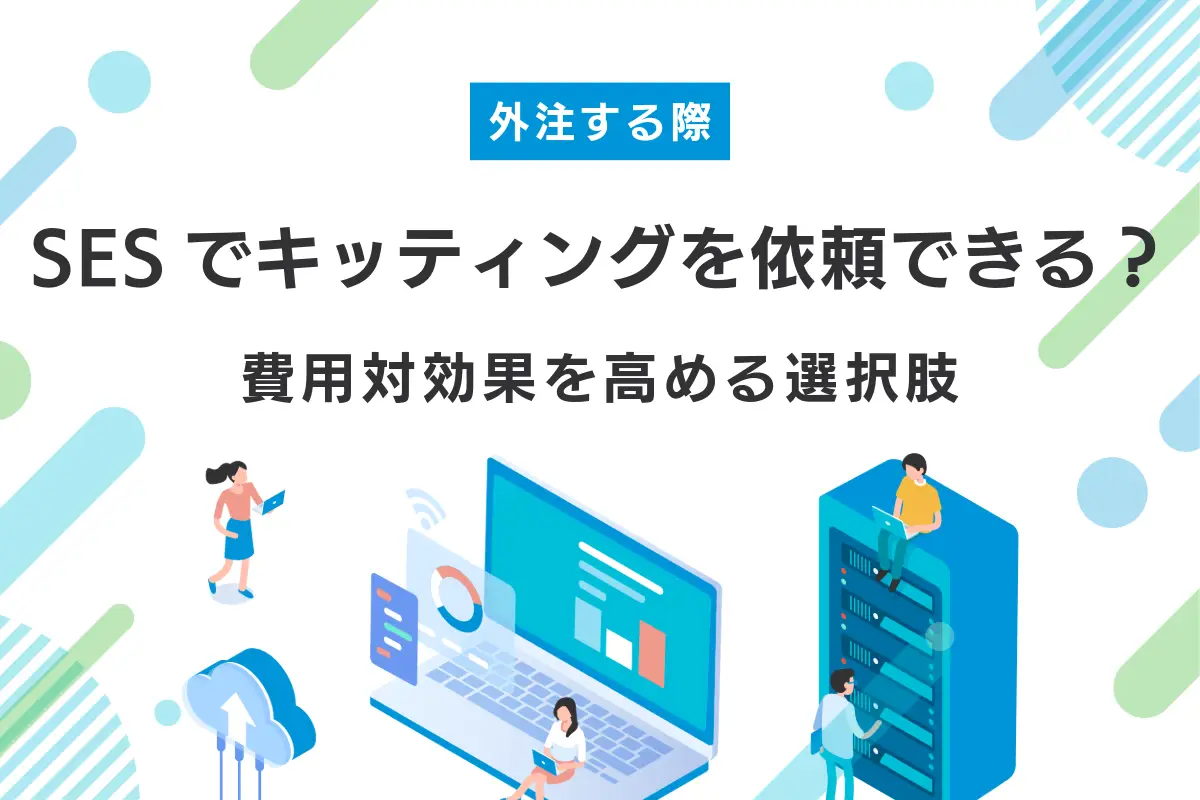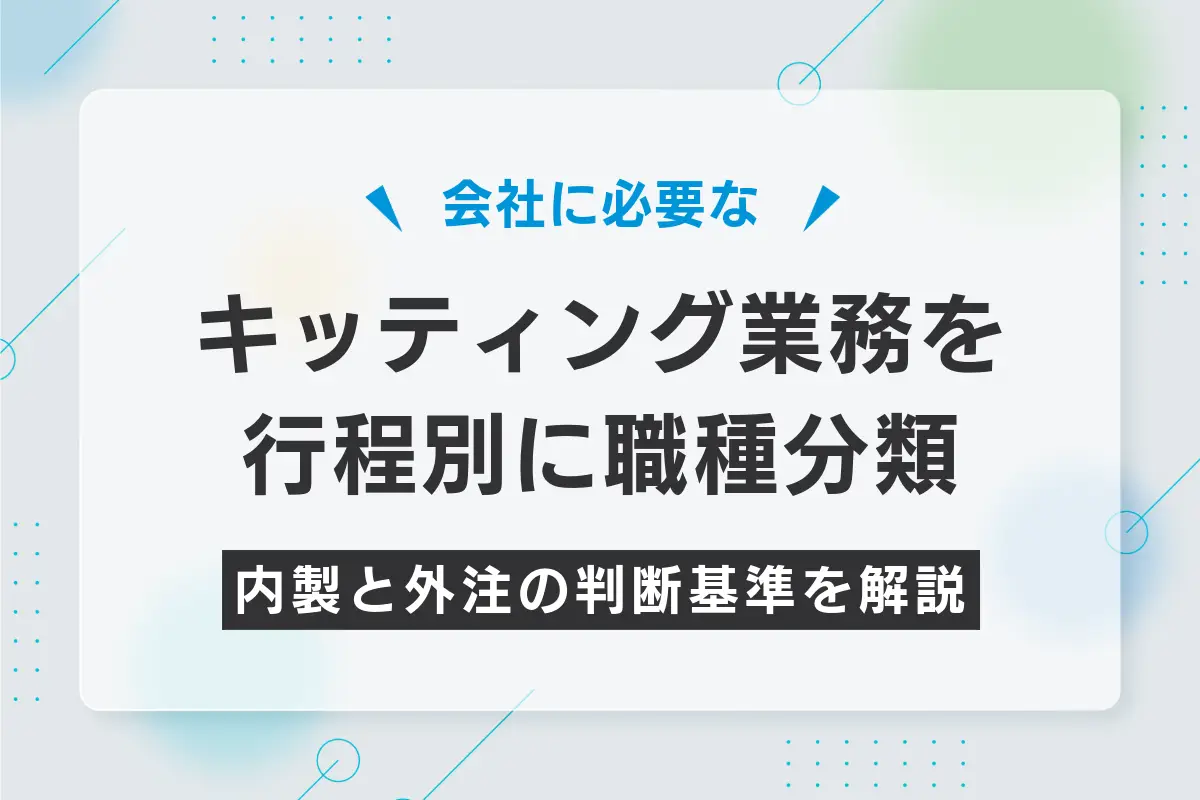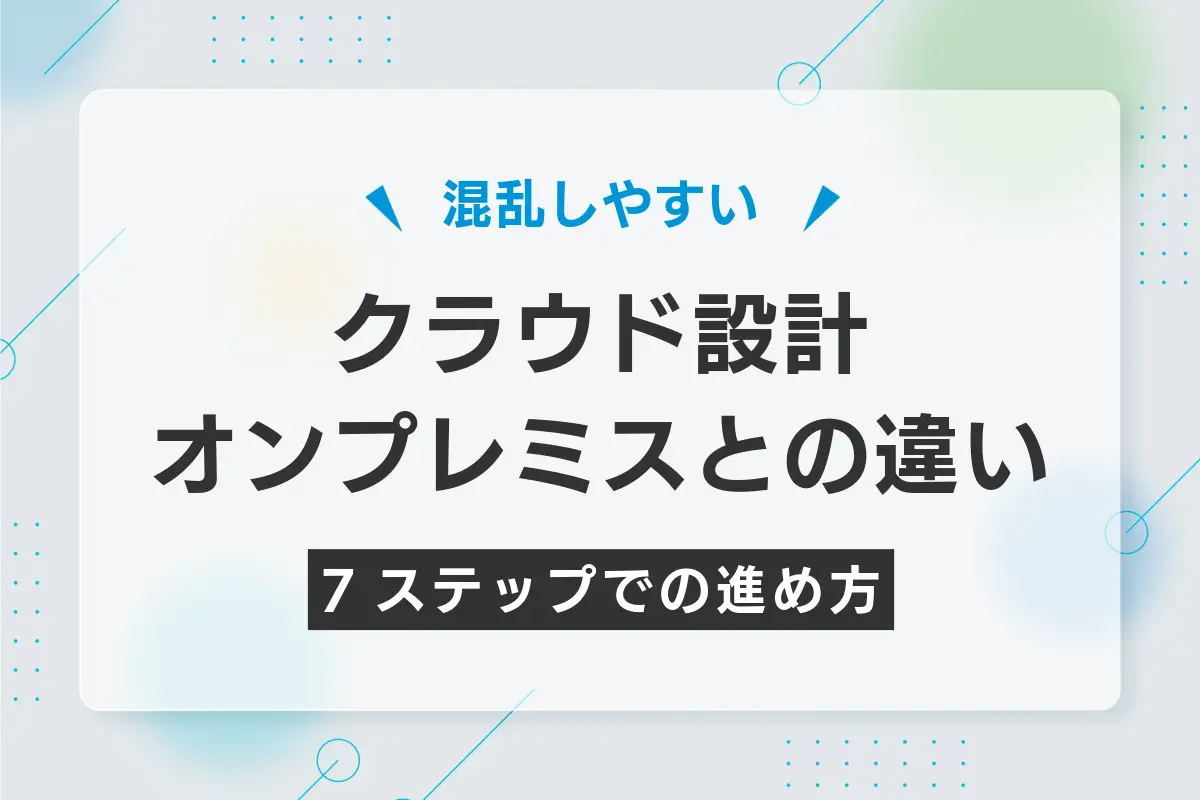
ITインフラの刷新やDX化に取り組んでいる企業が増えています。しかし、自社の技術力や知恵だけでは限界があるため、ITコンサルに頼る企業も多いです。
一方で、ITコンサルがどのような支援をしてくれるのかわからない経営者も多いかと思います。ITコンサルの役割を知らないまま契約すると、事業そのものが傾く可能性も否めません。
そこで、本記事では以下の内容について解説します。
ITコンサルを活用するメリット
ITコンサルの業務フロー
ITコンサルに必要な能力
ITコンサルを選ぶポイント
本記事を最後まで読めば、ITコンサルに依頼すべきことと、自社が求めるITコンサル像が明確になります。ITコンサルにサポートを依頼したい中小企業の経営者は、参考にしてください。
ITコンサルとは?
ITコンサルとは、ITを活用して企業の課題解決を支援するサービスのことです。具体的には企業の問題を特定し、ソフトウェアの導入やインターネットの活用で課題を解決します。
近年はITインフラの老朽化DXの加速、グローバル化により企業の経営環境はおおきく変化しています。IT戦略においても舵取りに悩む企業は多く、高度な専門知識が必要な分野ではITコンサルの力を借りることも珍しくありません。
また、組織改革と言われるほどの業務改善や事業の再編が伴うと、ステークホルダーとの関係や社員の士気に影響することもあります。そのような場合に第三者として業務改革をサポートするのも、ITコンサルの役割です。
SEとの違い
ITコンサルと一緒によく登場する職種としてSEが挙げられます。両者の特徴を下の表にまとめました。
比較項目 | ITコンサル | SE |
役割 | ITを使って経営課題を解決 | 顧客の要望どおりにシステム構築 |
顧客との関係 | 対等 | 顧客が上 |
提案内容に対する責任 | ある | ない |
求められるスキル | IT全般、経営 | IT全般 |
両者のおおきな違いは経営課題に関わるかどうかです。
SEの役目は顧客が求めるシステムを実現することですが、ITコンサルは経営課題を解決することが使命。そのため、SEの立場は顧客より下である一方、ITコンサルは解決案の提示や投資の助言もするので基本的に立場は対等です。
また、経営に関わる判断を支援するため、ITコンサルは提案内容そのものに対して責任を負わなければいけません。
費用相場は月40~250万円
ITコンサルの単価相場は、下のように依頼内容によって異なります。
依頼内容 | 月額契約 | 報酬体系別 |
IT戦略の立案 | 150万円〜200万円 | 顧問:数万円〜100万円 成果報酬型:利益やコストカット額などで決定 |
プロジェクトマネジメントのサポート | 60万円〜250万円 |
IT戦略の立案は経営課題に直接関わるため、求められるスキルも課題解決力や分析力、専門性など多岐に渡ります。それゆえ、報酬相場も高めの傾向にあります。プロジェクトのマネジメントのサポートにおいては、業務内容やプロジェクトの規模、工期によって変動するため、報酬幅も広いのが特徴。
また、報酬体系が多様なのもポイントです。必要に応じて依頼するスポット契約だと月数回の訪問で3万円程度の契約もありますが、密度の高いフォローアップだと100万円近くかかることもあります。
売り上げやコスト削減費用に応じて報酬を支払う成果報酬型のITコンサルもあり、その場合はコンサル側が定める成功報酬率で費用が決まります。
ITコンサルを活用するメリット
ITコンサルを活用する主なメリットは下のとおりです。
困難な課題を解決しやすくなる
社外の視点を得られる
新しい取り組みを始めやすくなる
困難な課題を解決しやすくなる
自社の力では太刀打ちできない課題も、ITコンサルがいれば解決の可能性が高まります。
自社の力だけだと先入観や社員の課題解決力が足かせになることがあります。そこで、問題の分析と課題解決力に優れたITコンサルに依頼すれば、問題の突破口を開きやすくなるでしょう。
また、問題解決の道すじは見えても、膨大な時間を費やす可能性が高いため、対処が後回しになっている企業も多いです。ITコンサルに課題の洗い出しから戦略の立案まで代行してもらえば、コア業務に集中しつつ経営改善も実現できます。
このように、ITコンサルがいれば自力で解決できない課題を乗り越えやすくなります。
社外の視点を得られる
社外から新しい技術や知見を取り入れやすいのも、ITコンサルに頼るメリットです。
ITコンサルは多様な業種・企業で課題解決の経験を積んでいるため、自社にはない価値観・視点・技術を提供してくれます。具体的には、解決に至る思考のプロセスや技術、ソフトウェアの導入提案などです。
何気ない解決策が自社にとってブレイクスルーになることもありますし、場合によっては他部署への水平展開、内製化も可能です。ITコンサルを活用して自社の課題解決力、技術力向上を図れるでしょう。
新しい取り組みを始めやすくなる
ITコンサルのサポートがあれば、新しいプロジェクトや事業に取り組みやすくなります。ITトレンドに精通したコンサルが多いため、最新技術の導入に足踏みする企業でも採用しやすくなるからです。
また、客観的な視点で業務改善やシステムの導入もしてくれます。自社の力だけで改善するのと比べて「導入しても改善が見られない」「現場の評判が悪い」と批判されるリスクも抑えやすくなるでしょう。
一度改善の結果が出れば、新しい取り組みへのハードルはかなり下がります。その第一歩を踏み出すうえで、ITコンサルは強い味方になってくれるはずです。
インフラにおけるITコンサルの主な領域
一口にITコンサルといっても、その役割は多岐に渡ります。ここでは、ITインフラにおけるITコンサルの主な領域を紹介します。
セキュリティ強化
プロジェクトマネジメントのサポート
IT資産の評価・把握
サプライチェーンの管理(SCM)
経営資源の効率化(ERP)
ナレッジマネジメント
セキュリティ強化
セキュリティの強化はITコンサルの得意とする分野の一つです。具体的には、取り組みの指針となるセキュリティポリシーを明文化します。
セキュリティポリシーを元にセキュリティのガイドラインを策定し、下の例のように運用の目的や用語の定義、ルールの見直しなどを行います。
出典:湘南工科大学
なお、セキュリティに関してはITコンサル、経営陣を主要メンバーとするセキュリティ委員会を設けるのが一般的。ITコンサルは情報セキュリティマネジメントの知識を生かして、セキュリティ対策、運用監視、評価を行い、委員会と連携して企業のセキュリティを強化します。
プロジェクトマネジメントのサポート
スムーズなプロジェクトマネジメントを支援するのもITコンサルの分野です。
プロジェクトマネジメントを取り巻く環境は厳しさを増しており、高度な専門性やコストカット、短納期化などが顕著に表れています。一人にプロジェクトマネージャーだけで対処するにしても限界があるため、ITコンサルが支援に入るケースが増えています。
具体的には、PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)と呼ばれるプロジェクトマネジメントを組織的にサポートする部署の仕組み作りを支援。PMOで必要な機能の標準化、他の企業の成功事例を元にマネジメントの目的を明文化します。
システムの品質を担保するために、各工程で問題がないか監理する仕組み作りもITコンサルの責務です。
IT資産の評価・把握
ITの利活用・投資を行うために、企業全体のIT資産を分析・評価しなければいけません。ITデューデリジェンスとも呼ばれ、以下のステップを踏んで企業のIT資産を評価します。
リサーチ | リサーチの目的、範囲の明確化 |
分析 | リサーチ結果・収集資料の整理 |
評価 | 評価報告書の作成 |
現状を棚卸しすることで、価値の高い資産と低い資産、改善の余地がある資産が見えてきます。経営に結び付いたIT戦略を実現できるよう、IT資産の効率化・最大化の役割を担うのもITコンサルの役目です。
サプライチェーンの管理(SCM)
サプライチェーンの管理・改善もITコンサルが関わる領域で、SCM(Supply Chain Management)とも呼ばれています。
近年は、市場のニーズにいち早く対応できるよう、生産・販売サイクルが短期化しています。自動車産業を例に挙げると、新モデルの企画・設計にかけていた期間の短縮が挙げられるでしょう。
海外企業との競争に勝つためにも部品、資材などの手配遅れがあってはいけませんが、過剰な在庫を抱えるのもリスクが伴います。
このような製品の生産・供給の最適化を図るためにサプライチェーンのボトルネックを調査するのも、ITコンサルの役割です。具体的には、コスト、リードタイム、サービス品質、納期などをKPIに設定し、継続的な改善を模索します。
経営資源の効率化(ERP)
企業の経営資源は有限です。加えてグローバリゼーションに伴う生産拠点の移転、分散など資源活用の環境も変化しています。
企業との厳しい競争に勝てるよう経営の効率化をサポートするのもITコンサルの仕事です。具体的には、ERP(Enterprise Resource Planning)と呼ばれる経営資源を統合管理して効率化を目指すシステムの導入をサポートします。導入場面でPMOのメンバーとして参画し、プロジェクト計画の策定や業務のモデル化などを行います。
ERP導入時に重要なのは、現場の協力体制を築くこと。関連する部門のキーパーソンと関係を構築し、エンドユーザーの満足度を維持しつつ全体最適なERPを実現することが求められます。
ナレッジマネジメント
ナレッジマネジメントとは、個人がもつ知識・技術などを組織で共有・活用する経営手法です。ホワイトカラーが多数を占めるIT分野において、知識を扱える人材の数が企業の競争力に直結します。
大手インフラ企業でもナレッジマネジメントの動きが顕著です。とある大手ガス会社ではナレッジマネジメントツールを活用し、ホワイトカラーのメイン業務である情報検索や資料作成の効率化を実現しました。
ただし、ツールだけでナレッジマネジメントを実現することは不十分です。経営層からナレッジマネジメントの重要性を発信し、現場の社員に理解させる必要があります。このような企業風土に変えるために入念な計画を立てて、経営コンサルティグと分野横断的に協力することもITコンサルの役割です。
ITコンサルの業務フロー
ここでは、ITコンサルの業務フローについて解説します。
受注前の調査
プロジェクトの提案
課題の構造化・検証
解決策の立案
システム開発・改修
受注前の調査
受注前に候補となるクライアント企業のことを徹底的に調査します。
具体的には、クライアントが抱える課題や案件の規模、受注のリスクを精査します。また、営業活動も兼ねてセミナーの開催や書籍、雑誌への寄稿を行うことも少なくありません。
案件の規模にもよりますが、複数の部門にまたがる場合は経営層へのトップアプローチが主流になります。ただし、現場を無視した営業・提案はプロジェクトが頓挫する遠因になり得るため、現場担当者への営業も含めてクライアントを調査をします。
プロジェクトの提案
受注前の調査で既存のITインフラの課題、経営陣の意向が把握できたらプロジェクトの提案をします。主に提案書に記載される内容は以下のとおりです。
クライアントを取り巻く環境
クライアントが抱える問題と原因
課題解決に向けたアプローチ方法
プロジェクトの体制・役割
コンサルの報酬
クライアントが複数のITコンサルから提案を受けた場合、類似案件の実績や各コンサルの強み、コンサルタントの実務経験を元に選別します。
課題の構造化・検証
提案内容に関して双方が合意したら、正式にプロジェクトスタートです。関係者を交えてキックオフミーティングを開き、経営層や現場を中心にインタビューします。
あわせてクライアントの課題を正確につかむために、業務資料やシステムの構成図、組織図などの資料提供も求められます。また、精度の高い解決策を提案するためにアンケートや現場視察が行われることも少なくありません。課題の構造化に使われるのがロジックツリーという思考フレームワークです。
上記のロジックツリーは顧客のパートナーになるために何をすべきか深堀りしたツリーですが、経営課題の構造化にも応用されます。
このように、ITコンサルの調査分析を元に課題の仮説を提示し、問題に対する認識を擦り合わせます。
解決策の立案
解決の方向性が見えたところで、具体的な案を策定します。ここで解決策が一つに定まるケースは少なく、複数案を提示されるのが一般的です。
たとえば業務プロセスやシステム化の範囲を複数設定し、投資効果やコスト、納期などの軸で評価します。ここでの解決策も仮説程度のものなので、経営陣に意見を聞きつつ、解決案の実現性・妥当性も考慮しなければいけません。
また、IT戦略が独り歩きしないよう、経営計画との整合性もチェックします。解決策を検証して問題がなければ、システム開発・改修に進みます。
システム開発・改修
解決策が固まったら、いよいよ実現に向けて新規システムの開発、もしくは既存システムの改修に移ります。ITコンサルは必要な技術(パッケージかスクラッチ開発かなど)や製品を精査し、下のようなRFP(Request For Proposal)を作成します。
出典:NotePM
RFPとは提案依頼書と呼ばれ、ベンダーにシステム開発の中身をスムーズに提案してもらえるよう、依頼側が作成する書類のこと。具体的な記載内容は下のとおりです。
概要:現状の課題、システム化の目的、ゴール、予算、対象部署、運用体制など
提案要件:システム化の範囲、開発言語、各工程の要件、教育・研修体制
なおSIerやベンダーがITコンサルをする場合は、コンサルフェーズの提案内容を前提にシステム開発が進みます。
そして、工程がスムーズに進むようプロジェクトを管理するのもITコンサルの役目です。提案内容が反映されているか、将来起こりうる変化にあわせて柔軟なシステム構造になっているかをチェックします。
関連記事:ITインフラの設計とは?構築との違いと流れ・外注のポイントを紹介
関連記事:ITインフラの構築とは?設計との違いと流れ・外注のポイントを解説
システムのレビュー
システムをリリースしたらそれで終わりではなく、運用後にコンサルどおりの結果を得られているかを評価します。具体的には、下のようにCOBITというIT基盤の活用度や成熟度を図るフレームワークを使って評価します。
出典:日本ITガバナンス協会
投資効果の検証は1回で終わらせるだけでなく、定期的なレビューで戦略を見直すことも少なくありません。
また、ITコンサル側としては継続的に契約してもらえるよう、次回コンサルの提案をすることがあります。投資効果も高く自社の満足度が高ければ、継続受注したりグループ企業に紹介したりするのも良いでしょう。
ITコンサルに求められる能力
ITコンサルは対処する課題がハイレベルなため、相応のスキルが必要とされます。ここではITコンサルに求められる主な能力について解説します。
課題解決力
ツール活用力
戦略の立案力
コミュニケーション能力
プロジェクトマネジメント力
業界に対する理解力
業務内容に対する理解力
課題解決力
課題解決力とは、企業の課題を発見、整理、分析して解決までの道のりを提案する能力で、ITコンサルに最も必要とされる能力の一つです。課題解決力とは主に下の表のように分類できます。
課題解決力の分類 | 概要・特徴 |
課題発見力 | クライアントが気づいていない問題を見つける |
論理的思考力 | 因果関係に基づいて考える力 |
分析力 | 問題の発生源である要因を特定すること |
近年は自社のITインフラを取り巻く環境が複雑化しており、解決の糸口が見いだせない企業が増えています。自社で解決しようにも問題解決に長けた人材が圧倒的に不足しているのが現状。そのため、ITコンサルの課題解決力で突破口を切り開こうとする企業は少なくありません。
※MECE:物事の要素を分解して、漏れやダブりなく問題を把握する思考法
論理的思考力
ITコンサルには高度な論理的思考力も求められます。論理的思考力を支えるのがフレームワークで、駆使することで客観的で有用な提案ができます。主なフレームワークを下の表にまとめました。
主なフレームワーク | 概要・特徴 |
SWOT | 企業の外部環境と内部状況を整理 |
5Forces | 企業を取り巻く競争環境を要因で評価 |
4P | 商品、価格、流通、販促の要素でマーケティング戦略を立案 |
AISAS | クライアントの購買プロセスを可視化したもの |
ただし、単にフレームワークを使っているだけでは良いITコンサルとは言えません。フレームワークを活用してゼロベースで物事を思考し、自分の言葉で提案できるかどうかが重要です。
戦略の立案力
ITシステムを利活用できるよう、経営ビジョン実現のために企業の方向性や方針を決めるスキルも重要です。
ITの活用は企業にとって多額の投資なので、経営に対してどれだけ貢献するか「費用対効果」を企業は厳しくチェックします。システム開発の要件定義・設計はSEでも可能ですが、投資計画の策定や予算取りのサポートまで踏み込むのはITコンサルしかできません。まさに「IT」と「経営」の両方を熟知したうえで戦略を立てるスキルが求められています。
優秀なコンサルタントは、立案力を鍛えるために経営者の交流会に参加する傾向にあります。経営者の生の声を聞き、現実的な戦略を作る力を養っているのです。
コミュニケーション能力
ITコンサルは企業の課題解決においてさまざまな人と関わります。それぞれの言い分を汲み取り同じ方向へ進むためには、高度なコミュニケーション能力が欠かせません。ITコンサルに必要なコミュニケーション能力は以下のように分けられます。
必要なコミュニケーション能力 | 概要・特徴 |
傾聴力 | 相手の話に耳を傾けて共感を得る |
理解力 | 表面的な発言だけでなく真意まで理解できる能力 |
ファシリテーション力 | 関係者の合意形成を円滑に進める力 |
交渉力 | お互いの妥協点を探って全体最適を目指す力 |
プレゼン能力 | クライアントに提案内容の実行を促す表現力 |
質の高い提案やプロジェクトへの本気度を測るうえでも、コミュニケーション力は欠かせません。
プロジェクトマネジメント能力やリーダーシップ
立案した解決策を実行するためには、プロジェクトを束ねる統率力が欠かせません。
ITコンサルにおけるプロジェクトマネジメントの特徴は、受注者の立場でありながらクライアントに指示しなければいけないこと。具体的には、目標達成のためのロードマップを作成し、確実に達成できるよう各工程で注意すべき点を提示します。
本来ITコンサルにクライアントを指揮下に置く権利はありません。しかし、クライアントは複数のプロジェクトを併行しているケースが多く、多忙な業務に追われてプロジェクトが頓挫することもあります。
プロジェクトを完遂できるよう、経営陣を通じてプロジェクトの重要性を発信してもらうことが重要。経営陣に動いてもらうためには、ITコンサルの専門性と強いリーダーシップが欠かせません。
業界に対する理解力
クライアントの課題解決のためには、業界に関係する知識が欠かせません。業界特有の法規制や商習慣、ライバル企業との関係を把握しないと、的外れな提案をする可能性があるからです。
たとえば、金融業界では規制緩和が進んでいる一方で、横並び意識のビジネスモデルが残っています。物流業界ではドライバーの労働時間や環境に関する法規制が厳しくなっているため、その点も考慮しなければいけません。
優秀なITコンサルは、業界の就職誌や白書で勉強しています。またクライアントのエンドユーザーの動向にも精通していると、精度の高い提案を期待できます。
業務内容に対する理解力
クライアントの業務内容に対する理解も欠かせません。解決策の実行には現場レベルの協力が不可欠だからです。
どの企業にも業界(もしくはクライアント)特有の業務知識も求められます。ただし業務内容が特殊であるほど、ITコンサル側で現場の実態を完璧に理解するのは難しいのが現状。そのため、ITコンサルは必要最低限の業務知識を書籍や資格から学び、クライアントとの対話を重ねて現状を観察します。
このように、業務に対して現場担当者と同じ目線を得ようとする姿勢も、ITコンサルには不可欠です。
ITコンサルを選ぶポイント
ITコンサルタントの質は幅広いです。加えて形のある商品と異なり、類似品を試すといったこともできません。そのため明確な基準をもって選ばないと「依頼しなければ良かった」と後悔してしまいます。
ここではITコンサルを選ぶポイントを解説します。
易しい言葉を使ってくれるか
デメリットも隠さず話してくれるか
顧客優先で動いてくれるか
実績は豊富か
コンサルタントとの相性は良いか
インフラエンジニアの関連資格を保有しているか
易しい言葉を使ってくれるか
優秀なITコンサルは、相手が理解できるよう誰にでも伝わる言葉で説明します。
とくにクライアントがITインフラに疎い場合は、バックグラウンドまで踏まえて丁寧に説明してくれると理想です。また、クライアントにメリットがあることを他社事例やロジックを使って筋道立てて話してくれるかも重要。
相手の知識レベル・理解力にあわせてコミュニケーションをしてくれるクライアントは信頼できます。
デメリットも隠さず話してくれるか
大前提として完璧な解決策を立案するのは難しく、何かしらのデメリットが伴う可能性が高いです。
省力化は実現できるがランニングコストが3割増える
UIが特殊でユーザーが操作に慣れるまで時間がかかる
設備の故障率は下がるが、いざ壊れたときに修理・交換の手間が増える
デメリットを隠すのは、クライアントに対して不誠実です。一方で、ITコンサル側にとって不利な情報も伝えてくれると信頼できると言えます。契約したときにも納得感をもってプロジェクトを進められるでしょう。
顧客優先で動いてくれるか
クライアントファーストの意識があるかどうかもチェックしましょう。
ITコンサルによっては、課題解決より自社の売り上げを優先することは珍しくありません。提案そのものが優れていれば問題ありませんが、特定のサービスや製品のアピールが強すぎるのであれば、見送った方が良いでしょう。裏を返せば、他社のサービスも紹介できるITコンサルは信頼できますし、知識・経験の豊富さの証明とも言えます。
クライアントが納得できる意思決定ができるよう、あらゆる角度から提案できるITコンサルは強い味方になってくれるでしょう。
実績は豊富か
ITコンサルに相応の取引実績があるかも確認しましょう。具体的には、創業年数や取引企業数、有名企業の有無などから総合的に判断します。
とくに、自社と似たような提案内容で取引した実績があると信頼できます。類似の取引例があれば、下記の項目を中心に質問してみましょう。
取引先を取り巻く環境
解決したい課題
解決に向けて注力した点・想い
実際に得られた結果(収益・コスト削減率など)
ITコンサルの公式サイトに事例記事があると理想です。
コンサルタントとの相性は良いか
どれだけ名の知れたコンサルティングファームでも、担当者との相性が悪ければプロジェクトはスムーズに進まないでしょう。たとえば、都合の悪い話はぐらかされてしまったり、クライアントの意図を汲み取ってくれなかったりなどです。
ITコンサルの契約期間は長期に渡るため、担当者との関係が築けなければプロジェクトそのものが危うくなります。自社の一員のように目線をあわせてくれそうか見極めましょう。複数のコンサルタントとコミュニケーションを取り、そこから相性の良い担当者を探すのも一つの手です。
インフラエンジニアの関連資格を保有しているか
必須ではありませんが、インフラエンジニアに関連する資格をもっていると基礎知識の証明になります。また、コンサルに関する資格は難易度が高く、資格を生かして豊富な人脈を形成しているコンサルが多いです。
結果として必要な知識を幅広く押さえている傾向にあるため、バランスの取れたコンサルを期待できるでしょう。
下記に代表的な資格を載せました。ITコンサルを選ぶときに参考にすると良いでしょう。
主な資格 | 概要・特徴 |
情報セキュリティマネジメント | 情報セキュリティに関する運用計画、策定、改善の知識・スキルを証明 |
中小企業診断士 | 経営コンサルティングの国家資格 |
ITコーディネーター | 経営とITの両方に精通していることを証明 |
ITストラテジスト | IT戦略スキルの基礎を証明 |
関連記事:ITインフラ業務におすすめの資格11選!取得へのロードマップ・仕事内容・即戦力の採用方法も紹介
フリーランスのITコンサルもおすすめ
一般的にITコンサルの依頼先はコンサルティングファームですが、フリーランスもおすすめです。主な理由は以下のとおりです。
ハイスキルな人材が多い
コストを削減できる
コミュニケーションがスムーズ
ハイスキルな人材が多い
フリーランスは多様な企業で実務経験を積んでいるため、質の高いコンサルを期待できます。とくにITインフラ関連だと特定の業務に対する知見も豊富なため、クライアントのバックグラウンドも考慮して解決策を提案してくれるはずです。
また、クライアント側としてもスキルセットや経験年数を決めてから人材を募ります。そのため、契約してから「期待していた提案ではなかった」と後悔するリスクも抑えられるでしょう。
コストを削減できる
コンサルティングファームとの契約に比べて、フリーランスは契約期間が短い傾向にあるので、その分コストを抑えやすくなります。正社員と異なり福利厚生費用や保険などの固定費がかからない点も魅力。
また、コンサルティングファームだと社内規定で報酬が厳密に決められているケースが多いですが、フリーランスだと融通が利きやすくなります。コンサルを受けたいけれど予算が厳しい中小企業にとって、フリーランスは適した手段と言えます。
コミュニケーションがスムーズ
企業相手と異なり、コミュニケーションの柔軟性が上がるのもフリーランスのメリットです。
コンサルティングファームだと社内規定に縛られることも多いため、臨機応変な対応が難しいのが現状。一方フリーランスのコンサルタントであれば、契約の範囲内で自由にやり取りできます。
ITインフラのプロジェクトはスピード勝負な面もあるので、コミュニケーションの柔軟さはフリーランスに依頼するメリットと言えます。
優秀なITコンサルを探すならクロスネットワークにご相談ください
本記事では、ITコンサルの業務フローと対応領域、必要なスキルなどについて解説しました。
システムの改修やDX化の促進など、自社のITインフラの方向性を決めるうえで、ITコンサルは頼もしい存在です。これからITインフラは高度化・複雑化すると予想されており、プロのサポートがあれば正しくプロジェクトを進められるでしょう。
ただし、一口にITコンサルといっても人材の質にばらつきがあるのが事実です。何を基準にITコンサルを選べば良いかわからない経営者は、本記事を読み返すと良いでしょう。
優秀なITコンサルを確保したい方は、ぜひクロスネットワークにご相談ください。クロスネットワークはインフラエンジニア専門のエージェントサービスで、通過率5%と厳しい審査に合格した人材のみ在籍しています。設計・構築・運用など各分野で経験を積んだITコンサルを、クライアントの要望にあわせてスムーズにマッチングします。
採用後のやりとりもサポートしますので、トラブルを回避できるのもメリット。さらに、登録しているインフラエンジニアと合意があれば、正社員登用もできます。
エージェントに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週3日程度の依頼も可能なので、自社の必要リソースにあわせて柔軟に外注できます。
こちらよりサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力のインフラエンジニアをお探しの方は【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

新卒で大手インフラ企業に入社。約12年間、工場の設備保守や運用計画の策定に従事。 ライター業ではインフラ構築やセキュリティ、Webシステムなどのジャンルを作成。「圧倒的な初心者目線」を信条に執筆しています。