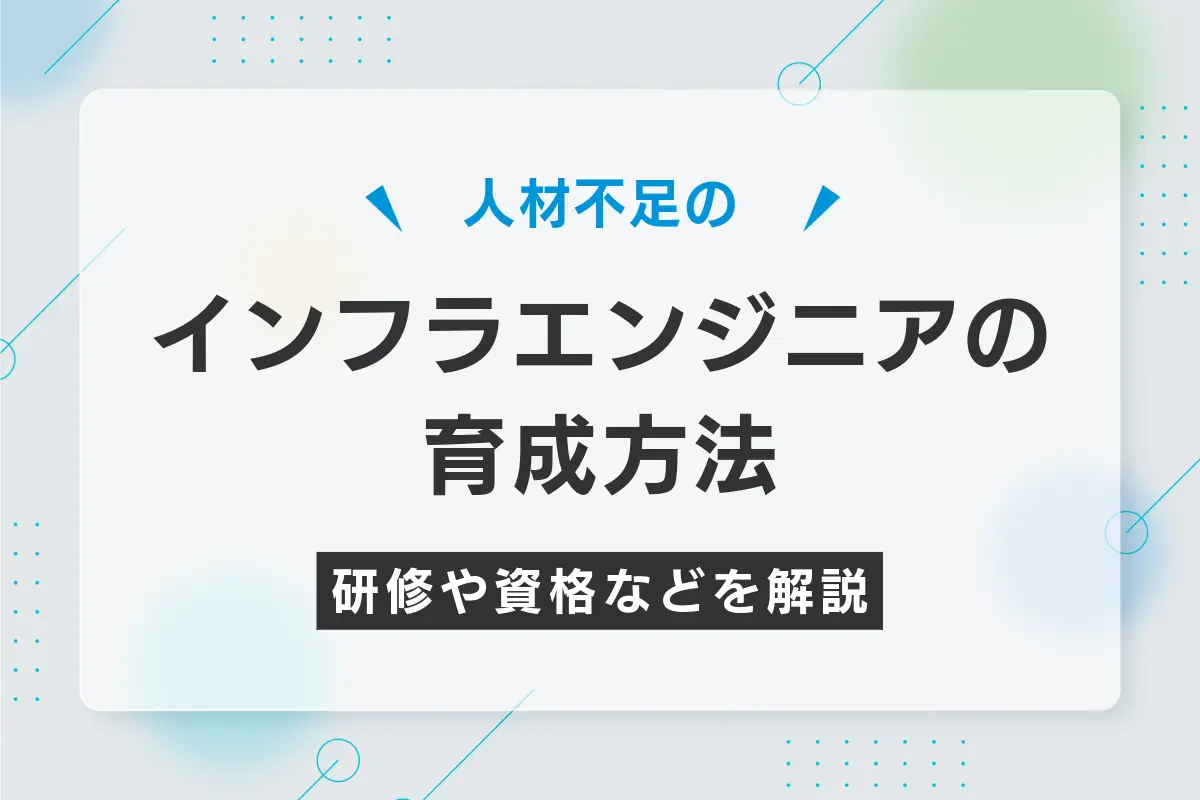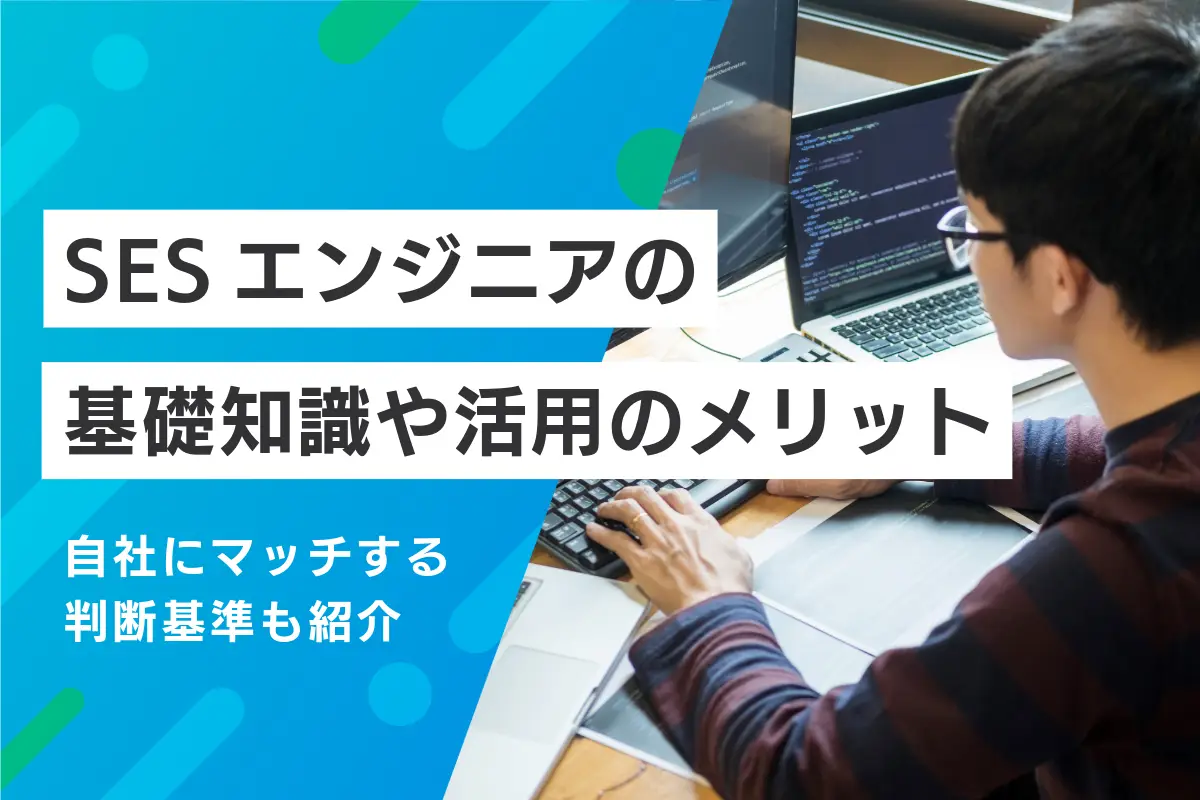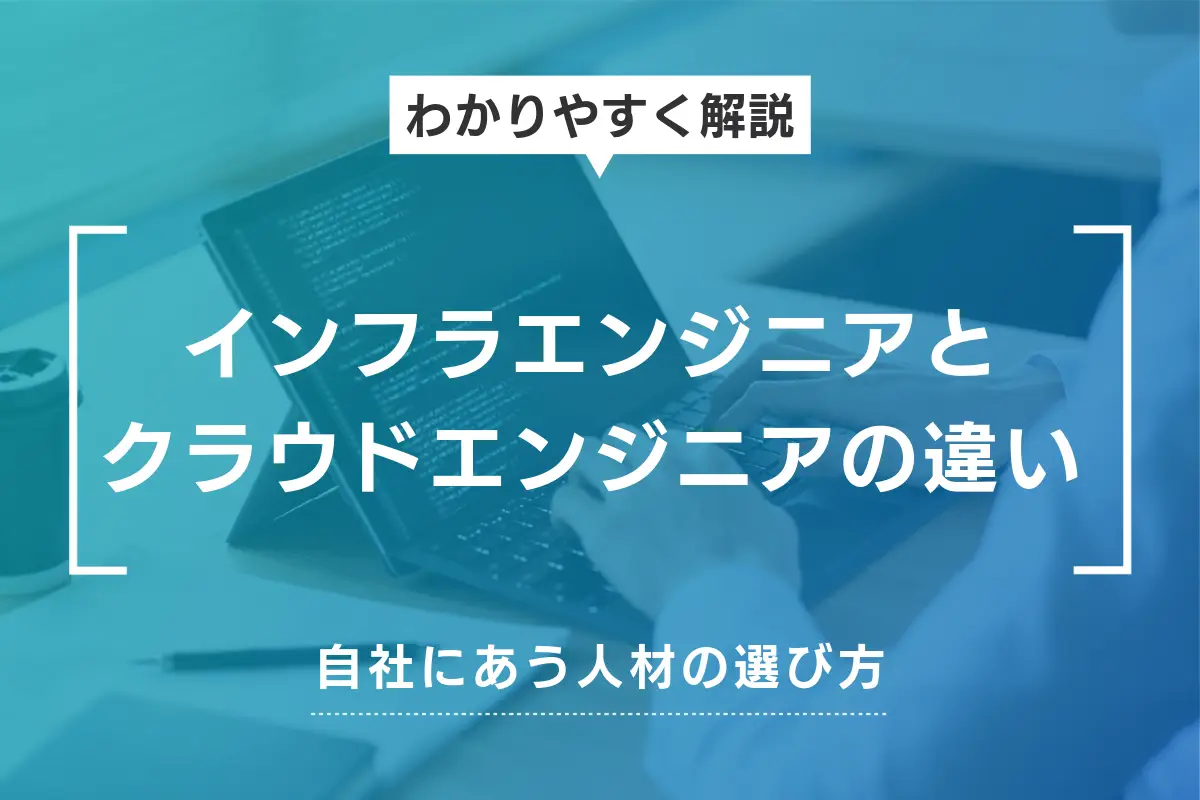昨今のIT人材不足と企業活動のDX化で、インフラエンジニアの業務はますます高度化しています。自社の若手にも早く戦力になってもらうために、育成に注力している企業も多いでしょう。
しかし「社員が成長しない」「指導がうまくいかない」と悩む経営者も少なくありません。育成が進まなければ、厳しい納期とコスト削減を乗り越えられないでしょう。
そこで本記事では、以下の内容について解説します。
インフラエンジニアの育成が難しい背景
インフラエンジニアを効果的に育成する方法
即戦力を採用する手段
インフラエンジニアの現場で12年以上働いている筆者の体験談も交えて解説します。インフラエンジニアの育成がうまくいかない中小企業の経営者、技術部門の指導者はぜひ参考にしてください。
インフラエンジニアの育成が難しい背景【指導面】
インフラエンジニアをうまく指導できない理由として、以下のような背景が考えられます。
価値観の違いが顕著
OJTが機能していない
上司と部下の関係構築が不十分
上司のスキル不足
中間管理職が忙しく育成に関与できない
教わる側のモチベーションが低い
価値観の違いが顕著
指導側と教わる側で価値観の違いが浮き彫りになって、育成がうまくいかないことがあります。とくに、世代間の考え方が異なるせいで衝突することは珍しくありません。
ベテランエンジニアの価値観 | 若手エンジニアの価値観 |
技術は盗んで学ぶもの | 教わっていないことはできない |
一概に世代で一括りにできるわけではないですが、指導側から見ると「やる気を感じられない」「若手が何を考えているかわからない」と悩む指導者もいます。
OJTが機能していない
OJTとはOn The Job trainingの略で、実務を通じて社員のスキルアップを図る取り組みです。エンジニアの育成においては典型的な方法ですが、OJTを実施しているものの機能していない企業が増えています。主な原因として下のような背景が挙げられます。
業務が高度化・複雑化している
開発工程の短納期化・コストカットでOJTに時間を割く余裕がない
余裕のない職場環境のため、OJTでも失敗を許さない風土ができてしまっている
専任の担当者以外が教育に無関心
いまでは、企業競争の激化でOJTが疎かになっている企業は少なくありません。
上司と部下の関係構築が不十分
上司と部下の関係構築ができていないのも、育成が進まない理由の一つです。価値観の違いも影響していますが、長期的な信頼関係を構築しにくい環境も起因しています。
年功序列や終身雇用が前提の時代なら、上司と部下が師弟のように絆を強められる企業も多かったかもしれません。しかし、現在では組織体制の変化が速く、転職もありきの時代で人材が定着しなくなりつつあります。
加えて、厳しい納期と開発に追われている現場では「新人でも即戦力が欲しい」と思う人も少なくありません。その結果「上が教えて下が真摯に学ぶ」という土壌ができにくくなっています。
上司のスキル不足
当然ですが、上司に相応の専門知識がなければ、エンジニアを育成することはできません。また、ITインフラを取り巻く環境は急速に変化しており、ネットワーク一つとっても5GやIoTなど次々に新技術・規格が誕生しています。
指導側がこれらに疎いと、教わる側も「この上司、先輩を信頼してよいのだろうか」と不安になるでしょう。時代の変化についていけていない一面を見せられると、部下や若手エンジニアの信頼を失うことになりかねません。
結果として教わる側の意欲を削ぐことになるでしょう。
中間管理職が忙しく育成に関与できない
課長・係長クラスの中間管理職が多忙でなのも、インフラエンジニア育成の阻害要因として挙げられます。中間管理職は納期やコストカットなどの目標達成を優先しなければいけないからです。
加えて、近年は深刻なエンジニア不足に悩まされている企業も多く、本来マネジメントに集中すべき管理職がプレーヤーとして現場に出ることも珍しくありません。
筆者の職場でも、10年ほど前までは係長が主導でOJTの計画や未経験者の指導に積極的に関わっていました。しかし、人手不足の影響で自ら現場に出ることが増えています。そのため、若手の育成も鈍化してしまい、厳しい工程からできるエンジニアに仕事が集中するという悪循環が発生しつつあります。
このように、中間管理職が多忙を極めた結果、エンジニアが成長しない企業は一定数います。
教わる側のモチベーションが低い
当然ですが、教わる側に意欲がないと育成はうまくいきません。モチベーションが低い背景はさまざまですが、以下のような要因が挙げられます。
業務がどう顧客や自社に役立っているのか想像できない
仕事を通じて成長を感じられない
上司・先輩に評価されている気がしない
やりがいや業務の意義を感じられなければ、積極的に教わろうとしない社員も出てくる可能性があります。
インフラエンジニアの育成が難しい背景【組織面】
インフラエンジニアが育たないのは指導上の理由だけではありません。下記のように、組織を取り巻く変化が原因で育成がうまくいかないケースも考えられます。
人手不足が加速している
開発期間と費用に余裕がない
業務がタコツボ化している
技術に理解のある教育担当がいない
対面のコミュニケーションが減少している
人手不足が加速している
近年は多くの企業で深刻なエンジニア不足が発生しています。下の表は経済産業省が発表したIT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果です。2030年までに約79万人のIT人材が不足するとの試算を出しました。
出典:経済産業省
加えてAIやIoT、ビッグデータなどITインフラと関連が深い分野では需要が拡大すると見込まれており、人材の不足感はますます高まるでしょう。市場の拡大と人材の減少が重なれば、育成に手をかける余裕はなくなります。
開発期間と費用に余裕がない
システムの開発期間と予算に余裕がないのも、インフラエンジニアの育成が進まない理由の一つです。
近年は企業間の競争力を強化するために、ITインフラにおいても高機能化、多機能化が進んでいます。一方で、経営の合理化で予算が削減されるという矛盾が発生しているケースも珍しくありません。OECDの調査によると日本のICT投資額は1997年をピークに減少傾向にあります。
出典:総務省
このように、経営の合理化も影響して、インフラエンジニアの育成に歯止めがかかっていると考えられます。
業務がタコツボ化している
ITインフラそのものが巨大化・複雑化しており、エンジニアの業務が細分化されている傾向にあります。そのため、自分の業務の専門性は高められている一方で、開発の全体像を掴めていないエンジニアも少なくありません。
極端な話を言えば「自分のフィールドにはめっぽう強いけれど、隣の同僚の業務を知らない」というタコツボ化が発生しているケースがあるのです。その影響で、自分の業務しか見えていないエンジニアが増え、構造を理解しながら教えられる指導者が不足している企業もいます。
当然ですが、ITインフラは一部のハードウェア、ソフトウェアだけで成り立っているわけではありません。各機器、プログラムの相互関係があって初めて機能します。そのような全体像を教えられるエンジニアが希少になっているため、育成がうまくいかない企業もいます。
技術に理解のある人事の教育担当がいない
技術を理解している教育担当がいないのも、インフラエンジニアの育成が滞っている背景です。
一般的に新入社員の教育では、人事主導で集合研修を行った後に、現場でOJTを組むのが主流です。若手がスムーズにオンボーディングできるよう、人事にも技術畑出身の社員を配置する企業が多いのですが、現場の業務が忙しくて人を回せないケースが増えています。
そうなると技術を理解する教育担当がいなくなるため、初期の研修ではビジネスマナーや経営の基礎などありふれた内容しか教えられなくなります。
技術的なことはOJTに丸投げすることもあり、結果として技術の基礎も身に付かないまま業務に当たる新人も少なくありません。
対面のコミュニケーションが減少している
対面でのコミュニケーションが減少傾向にあるのも、インフラエンジニアの育成が進まない一因と言われています。
かつては、開発の困りごとや相談があれば、オフィスで話すことが一般的でした。しかし、近年はリモートワークの普及でチャットツールでのコミュニケーションが主流になりつつあります。また、エミュレーターや解析プログラムなどのツールも発達しており、ますます仕事が自己完結しやすい環境になっています。
このように、上司とのコミュニケーションを介さなくても業務ができてしまうため、エンジニアを育成する機会が失われていると言えるでしょう。
一人前のインフラエンジニアに育成する方法【指導面】
ここでは、指導面からインフラエンジニアを効果的に育成する方法を解説します。
指導者の失敗談を共有する
教わる側の好奇心を刺激する
コーチングを意識した指導をする
専門外の分野を学ばせる
資格を取得させる
指導者の失敗談を共有する
指導者の経験談を話すと、部下との信頼関係を醸成しやすくなります。部下が直面している課題と重なる部分を示せるため、部下からの共感を得やすくなるからです。
具体的には、以下のような体験談を話すと距離が縮まる可能性があります。
知らないプログラミング言語で実装しなければいけなかったこと
ひたすらツールを使って運用監視をしていたこと
障害を起こしたときに上司がフォローしてくれたこと
部下が上司に親近感をもってくれると自分の業務に意義を感じられ、仕事への学習意欲が高まるでしょう。
教わる側の好奇心を刺激する
教わる側の好奇心に火をつけることも、インフラエンジニアの育成には不可欠です。たとえば設計専門の部署であれば、実際に構築の現場を見せると良いかもしれません。
自分が描いた図面やコードがどう機能しているのか理解できる
現場のエンジニアの仕事ぶりが見える
エンドユーザーの感想を聞ける
インフラエンジニアの業務は地味なケースが珍しくありません。そうなると「やらされ仕事感」を覚えるのも無理はないでしょう。
そこで、自分の業務が後の工程にどう影響するのか見せると、知的好奇心をくすぐることができるはずです。加えて、ふだん交流のないエンジニアやエンドユーザーからフィードバックを貰えたら、若手の励みになります。
コーチングを意識した指導をする
コーチングとは自ら答えを出せるようにする育成方法のことで、ティーチングとは下の表のような違いがあります。
| 比較項目 | コーチング | ティーチング |
目的 | 自ら答えを出す | 答えを教える |
取り組む姿勢 | 教わる側が主体 | 指導者が主体 |
主役 | 教わる側 | 指導者 |
解決方法 | 教わる側が編み出す | 指導者のやり方 |
コミュニケーション | 双方向 | 一方向 |
指導者の位置づけ | 動機付け、助言 | 指導、許可 |
コーチングは原則教わる側が主体で勉強するので、自然と考える習慣が身に付きます。
コーチングのコツは相手に質問を投げかけること。上司と部下では知識、スキル差があるので最初はティーチングがメインになるかもしれませんが、徐々にコーチングにシフトしていきましょう。
現場の業務が忙しい場合は、ヒントを与えてチャレンジさせるだけでも成長を期待できます。
専門外の分野を学ばせる
エンジニア育成となると専門技術にフォーカスを当てがちですが、専門外の分野を学ばせることも重要です。自分の業務が他の工程とどう関連しているか理解できるため、仕事の意義を自覚しやすくなるからです。
たとえば、設計担当の新人であれば前工程の企画や要求定義、後工程の構築やテストなどを勉強させると良いでしょう。
企画でどのような構想が練られているかわかれば、設計指示の意図を理解できます。後工程で自分が描いた図面がどのように反映されているのか、自分の設計によって現場の構築がやりやすいのか進めにくいのかが理解しやすくなります。
専門外まで視野を向けると、仕事に対する解像度は高くなるでしょう。
資格を取得させる
業務への関連資格を取得させることも、インフラエンジニアの育成に適しています。
資格取得のメリットは、専門知識を体系的に網羅できること。資格試験では、合格に必要なスキルレベルと想定受検者を明らかにしているからです。
近年はクラウドやデータベース、セキュリティなどジャンルに特化した資格が誕生しているため、ピンポイントに専門知識を身に付けさせるうえでもおすすめです。
ただし、取得を指示するだけでは教わる側も得られるものは少ないかもしれません。成長のチャンスに繋がっていることも伝えましょう。
関連記事:ITインフラ業務におすすめの資格11選!取得へのロードマップ・仕事内容・即戦力の採用方法も紹介
一人前のインフラエンジニアに育成する方法【組織面】
指導の良し悪しが育成に影響を与えるのは言うまでもありませんが、指導改善だけでは限界があります。ここでは、組織面からインフラエンジニアの育成を支える方法を解説します。
コミュニケーションの場を工夫する
教育体制を見直す
関連会社の研修に派遣する
社外の研修サービスを活用する
ベテランエンジニアとの交流を促進する
コミュニケーションの場を工夫する
チャットツールやソフトウェアの発達で、気軽にコミュニケーションを取る場が減っています。
フラットなコミュニケーションができるよう、オープンスペースやコミュニティカフェなど、インフォーマルな場を作りましょう。原則としてインフォーマルなスペースは議題も決まっていませんし、部署や役職を超えて人が交流しやすくなります。
若手の相談に関して言えば、教育担当だけでなく偶然居合わせた管理職や他部署のエンジニアが知恵を貸してくれることもあります。このような場が定着すれば、職場全体で若手を育成する気運が高まるでしょう。
教育体制を見直す
エンジニアの教育体制を刷新するのも重要です。
効果的な方法は、技術部門のなかにエンジニア育成専門の部署を設けることです。教育という目的がはっきりしているので、技術への理解が不十分な社員が教育することもOJTの負担が増えるリスクも低くなります。
ただし、人材育成の部署では、人を育てることに強い関心があるエンジニアを配属させなければいけません。ITインフラ全体を俯瞰できるようなスキル、実務経験があるかもチェックしましょう。
関連会社の研修に派遣する
関連会社の研修や他企業とのプロジェクトに派遣するのも有効です。社外で開発に加わるとバックグラウンドや価値観、スキルが異なる人と仕事をするため、自分の立ち位置に自覚的になれる可能性が高まります。
たとえば、派遣した部下は新人でも他のメンバーは実務経験が豊富なエンジニアかもしれません。そうなれば嫌でも技術力の差を痛感するでしょう。ましてや自社を代表して派遣されているのであれば、責任感を覚えるはずです。
このように、社外のプロジェクト・研修に参加することは、若手の視野を広げるカンフル剤になり得ます。
社外の研修サービスを活用する
OJTや教育だけで不十分な場合は、社外の研修サービスを利用しましょう。
技術的知見の豊富な講師が在籍しているサービスが多いからです。指導ノウハウも蓄積されているので、効率良く新人のスキルを上げることができます。
研修サービスを選ぶポイントは以下のとおりです。
受講形式:集合型、オンライン講義、e-ラーニングなど
研修内容:ケーススタディや実務ツールなど実践に即しているか
研修後のフォロー:自由に質疑応答できるか、復習用に教材が提供されるか
研修で自社の育成が行き届かない分を補えるかどうかが重要です。下の表におすすめの研修サービスをピックアップしたので、目的にあわせて選びましょう。
研修サービス | 概要・特徴 |
サーバー、ネットワークなどITインフラの基礎を学習 | |
ITインフラ教育で20年以上の実績を保有 | |
専用マシンを使った講義 |
ベテランエンジニアとの交流を促進する
どの企業にも凄腕と呼ばれるトップエンジニアが在籍しているはずです。レガシーなシステムから最新のプログラミング言語まで技術に明るく、長年培った経験で迅速にトラブルシューティングをするエンジニアもいます。
そのような敏腕エンジニアと交流する機会があれば、新人にとっておおきな刺激になるでしょう。
所属部署にいないのであれば、畑違いでも構わないので他部署を巻き込みましょう。企業間交流という名目で社外のエンジニアに会うのもおすすめです。
優秀なインフラエンジニアに共通する特性
ここでは優秀なインフラエンジニアに多く見られる特性について解説します。
徹底的に考え抜く
常にメモを取る
成果を発信する
物事を客観視する
その道のプロと繋がる
他部署を巻き込む
ユーザーニーズを意識している
徹底的に考え抜く
どれだけ上司の教え方がうまくても、想定通りに工程を進められることはそう多くありません。「設計に従って構築したのに疎通テストがうまくいかない」「プログラムを統合するとエラーが発生する」といったケースは多々あります。
そのような場合でも諦めず、自分なりに仮説を立てて粘り強く解決策を模索する人は成長する傾向にあります。
また、自ら知恵を絞って対処したトラブルは簡単に忘れません。似たようなトラブルに直面しても、前回よりスピーディに対処できるでしょう。
常にメモを取る
成長の早いエンジニアは常にメモを取っている傾向にあります。
そして、ただ言われたことを記録しているだけでなく、振り返りがしやすくなるよう図式や箇条書きを駆使している人もいます。筆者の職場でも、一目置かれている同僚は先輩から教わった内容をビジュアル化し、他の業務と関連付けてまとめていました。
成果を発信する
教わったことや学んだ技術を積極的にアウトプットする人も、成長速度が速いケースが多いです。公式な場で言えば、社内誌や報告会、学会、ポスターセッションなどが当てはまるでしょう。
もっとライトな方法で言えば、ブログやSNSも活用できるはずです。学んだ内容を整理できるだけでなく、第三者からフィードバックを貰うことができます。そのため、業務をこなすだけのエンジニアより成長が見込めます。
物事を客観視する
優秀なエンジニアは不測の事態に直面したときに、一歩引いた視点で対処することが多いです。具体的には、エラーが発生したときに他者の責任を追及するのではなく「自分が組んだプログラムや設計図に不備はないか」と冷静に現状を把握して調査します。
視野を狭めず状況を客観視するのは難しいですが、技術力がなくても冷静な視点があるエンジニアは伸びしろを期待できます。
その道のプロと繋がる
できるエンジニアは、自分にない技術・知識をもっている人とパイプを作る傾向にあります。
ITインフラは大規模かつ複雑なので、専門外のエンジニアも多数います。他部署のキーマンと交流があれば「設計のことはAさんに聞こう」「ネットワークなら○○課長が詳しい」と学ぶルートを構築できるでしょう。
なお、キーマンと繋がりたい場合、自分がその部署のキーマン的な役割を果たさないと相手にしてもらえません。他部署からも頼りにされるよう、強制的に学ぶ姿勢を維持しています。
このように、その道のプロと関係を築いて成長する環境を作っているのも、できるエンジニアの特徴です。
他部署を巻き込む
部署の垣根を超えて交流する人が多いのも、成長が速いエンジニアの特性です。
疑問や相談があれば他部署へ頻繁に顔を出し、必要とあれば営業やマーケティングなど異なる職種を巻き込むこともあります。とくにITインフラは全社的に利用されるので、他箇所の事情に関心があるエンジニアは重宝されます。
筆者の職場でも、他部署への関係構築に余念のない新人が在籍しており、情報収集のために労働組合を活用した猛者もいました。
他部署を巻き込むと、プロジェクトが的外れな方向に行くリスクを抑えられ、結果として全社最適なITインフラを構築しやすくなります。他部署と関係が良好なエンジニアは成長を期待できます。
ユーザーニーズを意識している
エンジニアだと、どうしても設計や構築など技術的な部分に関心を寄せてしまいがちですが、優秀なエンジニアはユーザーニーズに立ち返るよう意識しています。
たとえば、社内のポータルシステムを作るときでも、仕様上は問題ないがUIを損なっていないかという観点で見ます。ユーザー像が見えにくいのであれば、優秀なエンジニアは直接エンドユーザーに聞く(もしくは自分がエンドユーザーになる)ことを怠りません。
このようなエンジニアは、技術力が伸びるだけでなくユーザー視点の提案もできるので、上流工程での活躍も期待できます。
インフラエンジニア育成に注力できない企業がやるべきこと
育成環境を整えたくても、時間とお金に余裕がない企業もいるでしょう。ここでは、育成に注力できない企業がやるべきことを紹介します。
開発会社に外注する
経験者を中途採用する
フリーランスエンジニアに委託する
開発会社に外注する
開発会社にITインフラ業務を外注するのも、エンジニア不足に悩む企業におすすめしたい手段です。構築に必要な機材、端末の準備が不要なので、設備投資を抑えることができます。
また、開発に必要な人員を削減できるため、工期が厳しい企業にとって時短のメリットも出てきます。浮いた時間を新規営業や研究開発に回せば、自社の競争力が向上するでしょう。
注意点として開発コストが割高になるケースが多いです。とくにスクラッチ開発(ゼロからシステムを構築)だと、費用が数千万円単位になることも珍しくありません。開発会社に依頼する前にコストを回収できそうか検討しましょう。
経験者を中途採用する
即戦力を求めているのであれば、経験者を中途採用するのも有効な方法です。
すでに豊富な知識・実務経験を有しているため、基礎教育や長期のOJTを省略することができます。プロジェクトによっては、自社のエンジニアを育成する役割も期待できるでしょう。
ただし、エンジニアはただでさえ人材不足なうえに、経験者は転職市場で引く手数多です。優秀なエンジニアを採用できるよう、複数の手段を確保することが重要です。
代表的なルートを下の表にまとめたので、自社の現状にあわせて使い分けましょう。
インフラエンジニアを中途採用するルート | 概要・特徴 |
転職エージェント | 企業に人材をあっせんする業者 |
スカウト採用 | 自社から直接エンジニアにアプローチする |
リファラル | 社員の友人・知人を紹介してもらう |
SNS | 求人サイトのように費用がかからない |
関連記事:インフラエンジニアの中途採用は難しい?即戦力人材を迅速に獲得するコツを解説
フリーランスエンジニアに委託する
フリーランスエンジニアとは、企業に雇用されず業務委託契約を結んでプロジェクトに参加するエンジニアのことです。業務内容や必要なスキルセット、報酬を固めて案件を公募し、応募してきたエンジニアと商談を進めて、合意できたら契約を締結します。
近年は柔軟な報酬体系とワークスタイルから、フリーランスを目指すエンジニアが増えています。クラウドソーシングサービス大手のLancersによると、2021年でフリーランスの人口は1,670万人で、労働人口の2割を超えました。
出典:Lancer
自分のスキルと経験次第で収入を上げられることから、今後もフリーランスに転向するインフラエンジニアは増えるでしょう。
関連記事:インフラエンジニア案件をフリーランスに業務委託する方法とメリットを解説
インフラエンジニアリングの外注先には、フリーランスへの業務委託以外にも派遣やSESなどが挙げられますが、外注の経験がないために不安を感じる方も多いのではないでしょうか。以下の資料では、混同しやすい契約形態を比較・解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。
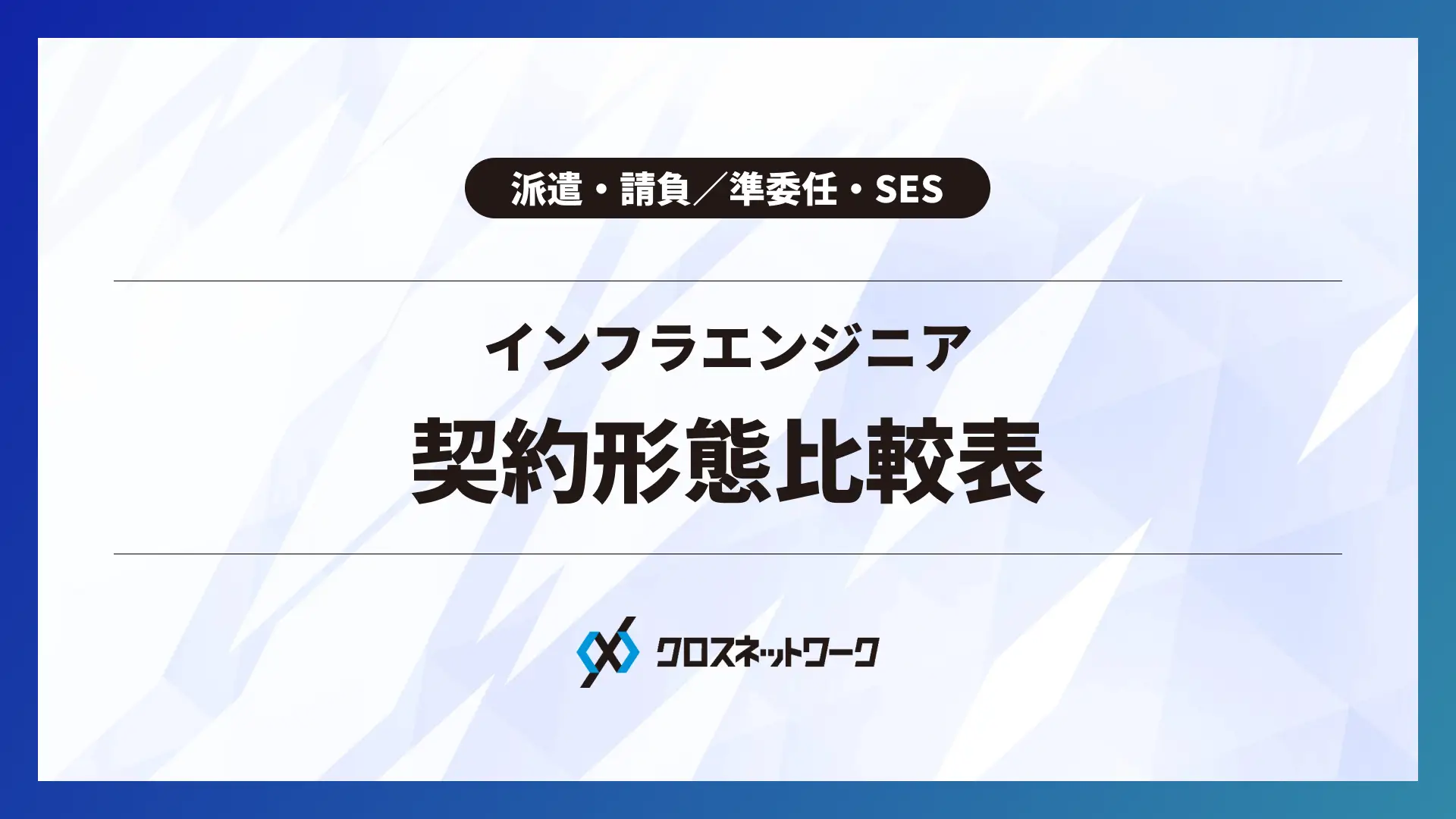
フリーランスのインフラエンジニアを活用するメリット
数ある採用手段のなかで、フリーランスのインフラエンジニアを活用するメリットを紹介します。
育成の手間が省ける
人件費を抑制できる
最新の技術・知見を得やすい
育成の手間が省ける
フリーランスエンジニアに委託すると、教育の手間を省くことができます。多様な業界・企業で実務経験を積んでいるため、即戦力として働いてくれるからです。
企業側も求めるスキルを決めて応募しているため、契約後のミスマッチが起こりにくいのも特徴です。下はクロスネットワークの案件例ですが、委託する業務と必須スキル、勤務条件などを明記しています。
委託内容 | 既存システムのインフラを保守、改修 |
想定給与 | スキル見合い |
必須スキル | Linux,AWS経験 |
勤務条件 | 週5日 月135時間ほど |
出典:クロスネットワーク
本来教育すべき部分をスキップできる点が、フリーランスを活用する強みと言えます。
人件費を抑制できる
社員の雇用・育成と比較して、人件費を削減しやすくなります。フリーランスは原則プロジェクトベースで契約するため、必要がなければ契約を解除できるからです。
また、スキルや実務経験、委託内容に応じて報酬を設定することができます。下の表はクロスネットワークの案件例を比較したものです。募集ポジションやスキルなどで報酬がおおきく変わることがわかるでしょう。
案件例 | 大手通信会社のヘルプデスク | 生成AIを活用した自社サービスでのフルスタックエンジニア |
報酬(月額) | 40万円~45万円 | 90万〜100万円 |
スキル | 通信事業者での経験 | TypeScriptの使用経験 3年以上 |
出典:クロスネットワーク
また、フリーランスエンジニアは社会保険や福利厚生費用などが発生しません。そのため、正規雇用より人件費の削減を見込めます。
最新の技術・知見を得やすい
フリーランスエンジニアは他企業での経験が豊富なため、自社にはない技術や知見を取り入れやすくなります。とくにエンジニア不足が乏しい中小企業であれば、フリーランスをハブに自社人材の技術力の底上げを図ることも可能です。
筆者の勤め先でも、外部のエンジニアに最新機器の導入やDX化の支援をしてもらった結果、生産性向上を実現しました。業務外でも技術トレンドを積極的に教えてくれるため、社内エンジニアの意識改革に役立ったことを覚えています。
即戦力の確保と自社エンジニアの育成、技術力アップを図るうえで、フリーランスエンジニアは頼もしいパートナーになってくれるでしょう。
即戦力のインフラエンジニアをお探しならクロスネットワークにご相談ください
本記事では、インフラエンジニアの育成が難しい背景と効果的な育成方法、できる人材の特性などについて解説しました。
近年はIT人材の不足と業務の複雑化で、インフラエンジニアの育成が急務になっています。しかし、価値観の違いや組織体制の影響で思うように人材が育たない企業も少なくありません。
1日でも早く若手を即戦力にするためには、教育体制とコミュニケーションの改善が不可欠です。本記事を繰り返し読めば、停滞しているエンジニア育成の突破口を拓けるでしょう。
一方で「育成に手間をかけられない」「すぐに即戦力が欲しい」という企業も多いはず。
経験豊富なインフラエンジニアを確保するなら、ぜひクロスネットワークにご相談ください。クロスネットワークはインフラエンジニア専門のエージェントサービスで、通過率5%と厳しい審査に合格した人材のみ在籍しています。ITインフラの設計、構築などの多様なジャンルに長けたエンジニアを、クライアントの要望にあわせてスムーズにマッチングします。
採用後のやりとりもサポートしますので、トラブルを回避できるのもメリット。さらに、登録しているインフラエンジニアと合意があれば、正社員登用もできます。
エージェントに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週3日程度の依頼も可能なので、自社の必要リソースにあわせて柔軟に外注できます。
こちらよりサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力のインフラエンジニアをお探しの方は【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

新卒で大手インフラ企業に入社。約12年間、工場の設備保守や運用計画の策定に従事。 ライター業ではインフラ構築やセキュリティ、Webシステムなどのジャンルを作成。「圧倒的な初心者目線」を信条に執筆しています。