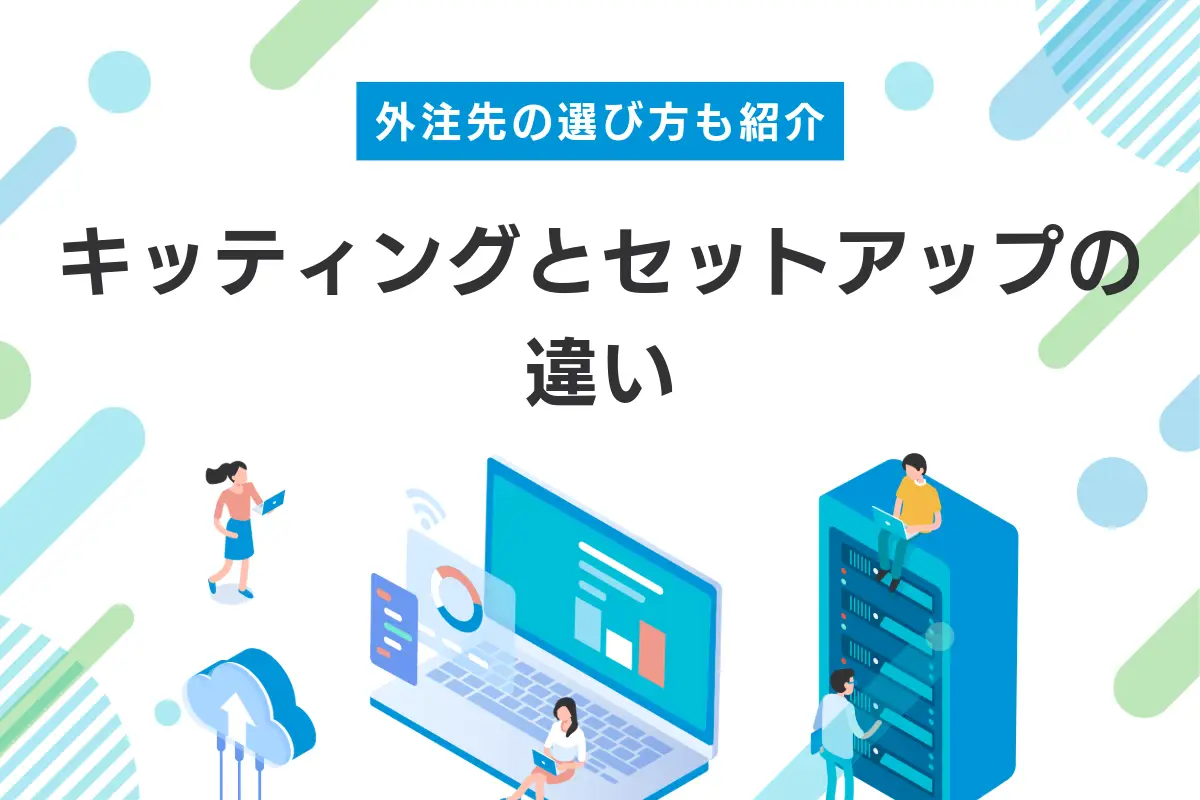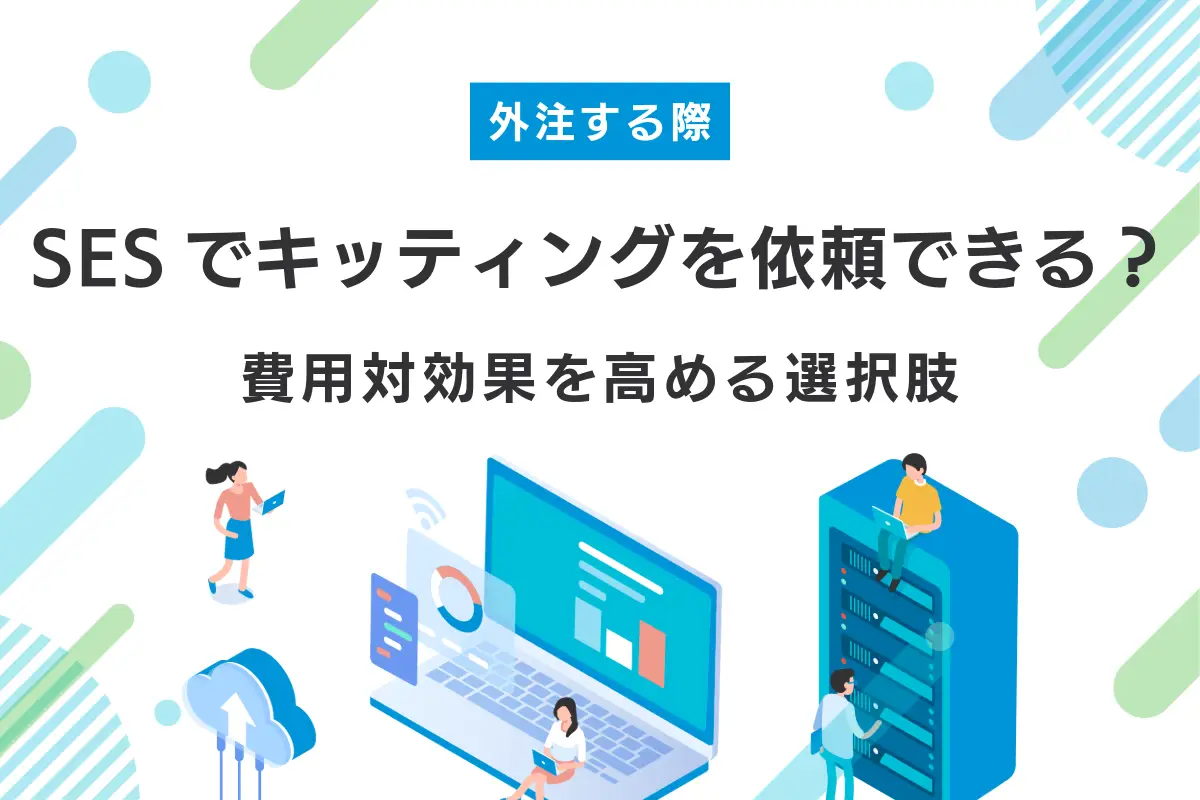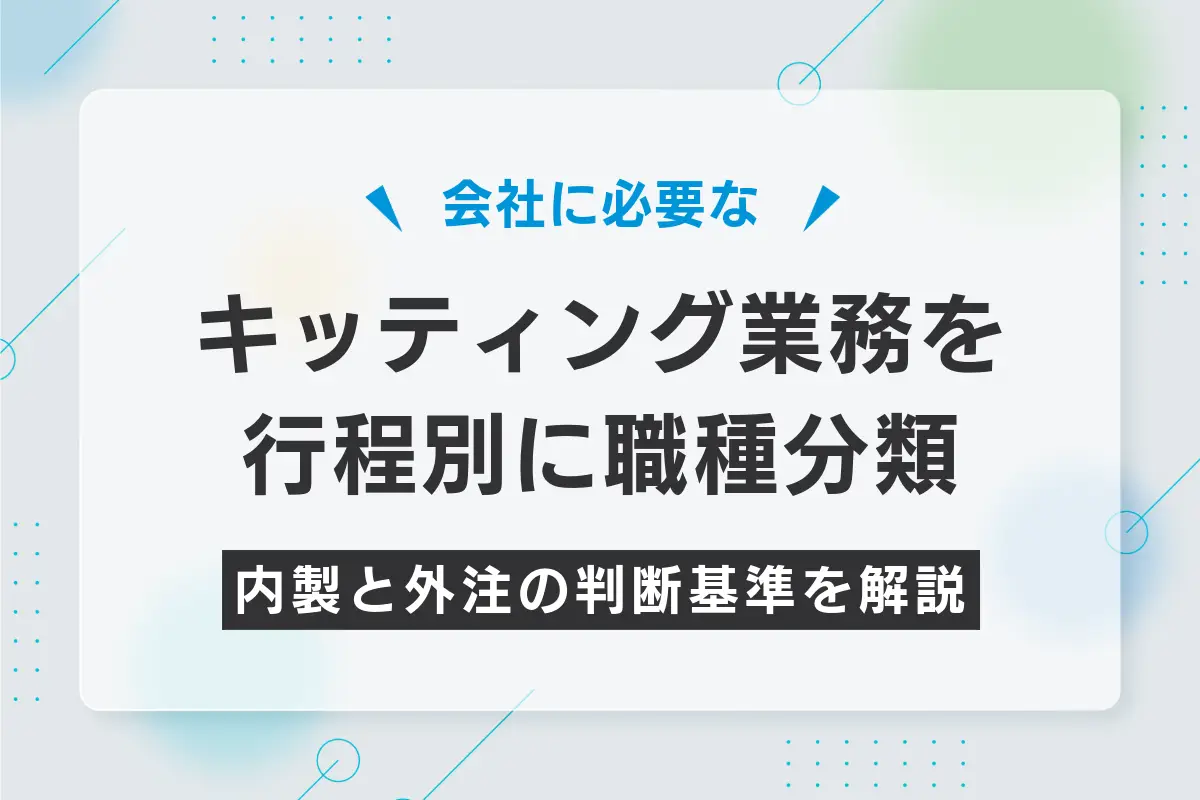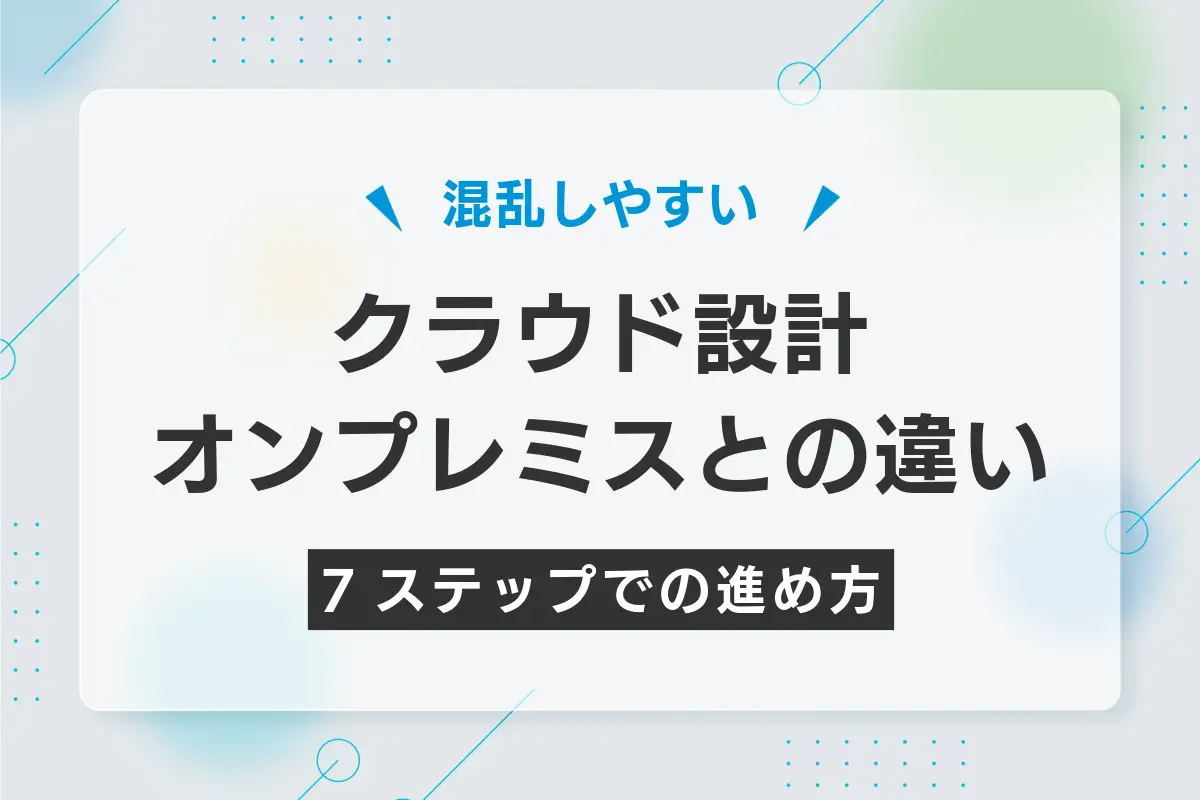
「キッティング」や「セットアップ」という言葉はよく耳にしても、実際にどこまでが自社対応で、どこから外注すべきか判断に迷うことはありませんか。
導入規模がおおきくなるほど作業範囲が複雑化し、適切な切り分けができないと貴重な予算を浪費してしまう恐れがあります。
本記事ではキッティングとセットアップの違いを、作業内容、対象範囲、所要時間、必要なスキルを中心に解説します。あわせて、外注する場合に有効なフリーランスの活用方法についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
キッティング・セットアップとは?
PC導入プロジェクトで外部業者に委託するときに、見積書に「キッティング」と「セットアップ」という項目が分かれて記載されているケースがあります。両者の違いは以下のとおりです。
キッティング:PCを業務で使える状態に整える作業(共通環境の構築)
セットアップ:ユーザー個別の環境設定を行う作業
それぞれの作業内容を正確に理解して、社内説明や外注するときの見積もり比較に役立てましょう。
キッティングとは|PCを業務で使える状態に整える作業
キッティングとは、業務で使用するPCを利用可能な状態に整える作業です。
具体的には、マスターイメージ(OSや標準アプリを含む雛形)を作成し、ほかのPCに複製する方法で進めます。たとえば、Windows OS、Microsoft Office、ウイルス対策ソフトなどを一斉導入する作業が該当します。
キッティングの特徴は効率化で、大量台数でも短時間で完了できる点です。数十台のPCに同じ設定をする場合、1台の環境を複製することで作業時間を大幅に短縮することができます。
PCを業務で使える状態にするための土台作りと考えるとわかりやすいでしょう。
セットアップとは|ユーザー個別の環境設定を行う作業
セットアップとは、各ユーザー固有の環境を構築する個別対応作業です。
キッティングで全社員共通の土台を整えたあと、ユーザーごとに異なる設定を追加していく工程です。具体的には、ユーザー名の設定、部署専用アプリのインストール、プリンター接続、メール設定などを実施します。
たとえば、営業部にはCRMツール、経理部には会計ソフトなど、部門や役職に応じた設定が必要なため、時間と専門知識を要する作業と言えます。
キッティングが「全社共通の基本環境を構築する工程」であるのに対し、セットアップはその環境を「ユーザーや部署ごとの要件に合わせて調整する工程」と覚えておくと良いでしょう。
キッティングとセットアップの違い
キッティングとセットアップは、どちらもPCを業務で使える状態に整える作業ですが、作業範囲やスキル、作業時間には明確な違いがあります。
キッティングとセットアップの違いを以下の表にまとめました。
キッティングとセットアップの比較表
項目 | キッティング | セットアップ |
作業内容 | OSや標準アプリの導入、共通セキュリティ設定など | アカウント設定やVPN構築など個別対応 |
対象範囲 | 全社員に共通する環境を構築(マスターイメージを展開して複数端末に適用) | 各ユーザーや部門ごとに異なる設定を追加・調整 |
所要時間 | 1台あたり2~3時間が目安(自動化すれば数十分程度に収まることも) | 1台あたり30~90分が目安(設定内容により異なる) |
必要な | 初級~中級(手順書があれば専門スキルがなくても可) | 中級~上級(ネットワーク設定やアカウント管理の知識が必要) |
キッティングとセットアップの違いを明確に理解しておくことで、外注先への依頼内容を整理しやすくなり、社内対応と外注の切り分けやコスト最適化の判断にも役立ちます。
ただし、外注先によって作業範囲の定義が異なることもあるため、見積書の作業内容が不明確な場合は確認が必要です。
作業内容の違い
キッティング作業には、下のように全社員のPCに共通して必要な設定を行います。
- マスターイメージ作成
- OSインストール
- 標準アプリ導入
- 全社共通セキュリティ設定
- ウイルス対策ソフト導入
- BIOSパスワード設定
- 資産管理タグ貼付
一度マスターとなるPCを準備すれば、ほかのPCには複製を行うのみです。
一方、セットアップ作業には以下のようなユーザーや部門ごとの個別設定が含まれます。
- ユーザーアカウント作成
- アカウント管理
- 部署別アプリ導入
- VPN設定
- 個別アクセス権限設定
たとえば、営業部には顧客管理システム、経理部には会計ソフトというように、部署や役職によって必要なアプリケーションが異なります。
対象範囲の違い
キッティングの対象範囲は、全社員に共通する基本設定です。マスターイメージを一度作れば、数十台規模でも同じ環境を効率的に展開できます。
一方、セットアップの対象範囲は、各ユーザーや部門ごとに異なる設定が必要な部分です。部署、役職、業務内容に応じた個別設定を行うため、台数が増えるほど作業工数が比例して増加します。
所要時間の違い
所要時間の違いを知ることで、プロジェクトのスケジュール感や見積もりの妥当性を判断しやすくなります。
キッティングを手作業で行う場合、1台あたり2~3時間かかることもありますが、これはあくまで一般的な目安です。ただし、クローニング(マスターイメージの複製)のように自動化を活用すると、1台あたり15~60分、数十台規模でも数日というスケジュール感です。
一方、セットアップは1台あたり30~90分が目安とされていますが、設定の複雑さや部署ごとの要件によっておおきく変動します。トラブル対応や追加の設定依頼で予定より延びることも多いため、余裕をもったスケジューリングが重要です。
必要なスキルの違い
キッティングに必要なスキルは初級~中級レベルです。マスターイメージ作成には中級スキル(OSのインストールやグループポリシー設定など)が求められますが、イメージ展開は手順書があれば初級者でも対応できます。
一方、セットアップには中級~上級レベルが求められ、アカウント管理やネットワーク設定、各種アプリの知識など幅広い知識が必要です。ユーザーごとに異なる要望に対応する柔軟性も必要なため、経験豊富な担当者でないと難しい場合もあります。
また、作業を正確かつ効率的に進めるには、ネットワークやセキュリティ構成の理解も欠かせません。そのため、企業によってはシステム全体を把握できるインフラエンジニアがキッティング工程を監修するケースもあります。
キッティング・セットアップの社内対応と外注の判断基準
キッティングとセットアップでは作業内容や対象範囲、所要時間、必要なスキルが異なるため、自社の状況を踏まえてどこまで社内で対応できるか判断することが重要です。キッティング・セットアップの社内対応と外注の判断基準は、主に以下の3つです。
- 社内人材のスキルは十分か
- 作業要員を確保できるか
- 期日までの余裕はあるか
上記のうち一つでも不足している場合は外注を視野に入れましょう。
社内人材のスキルは十分か
社内に求められるスキルがあるだけでなく、そのスキルがキッティング・セットアップ作業に適しているかを確認することが重要です。
たとえば、ヘルプデスク経験があっても、マスターイメージの作成やVPN設定など、構築寄りのスキルをもたない場合は対応が難しくなります。
また、特定の環境(Windowsなど)にしか対応できない場合、機種やOSの違いによる設定ミスのリスクもあります。
判断基準としては、作業範囲に応じて必要なスキルセットが網羅されているかを確認し、対応が限定的な場合は外注を検討するのが現実的です。
とくにネットワークやアカウント管理の領域では、インフラエンジニアに監修を依頼することで品質を確保できます。
作業要員を確保できるか
キッティングとセットアップでは、必要な作業要員が異なります。
キッティングでは、他の業務と並行できる余裕があるかが重要です。作業手順が標準化されていれば日常業務の合間に進めることも可能ですが、短期間で多くの端末を導入する場合には、専任の担当者を一定期間確保する必要があります。
一方、セットアップでは、専任で作業できるかどうかが鍵と言えます。個別対応が中心の作業であるため、並行して進めると設定漏れやミスが発生しやすく、品質を維持するのが難しくなります。
判断基準としては、通常業務に支障をきたす可能性がある場合や、専任の担当者を確保できない場合は外注による対応を検討するのが現実的です。
期日までの余裕はあるか
納期までの時間的余裕も、内製化と外注を判断する重要な要素です。初めての作業だと予想外のトラブルで予定より時間がかかることも多いため、余裕のあるスケジュール設定が必須です。
納期が厳しい場合は、品質を確保するため外注が効果的な選択肢と言えます。たとえば「新入社員研修までに100台のPCが必要」と言われた場合、社内対応のみでは設定ミスのリスクが高くなるかもしれません。しかし外部委託であれば、豊富な経験をもつ技術者が効率的に進行できるため、品質と納期の両立が期待できます。
判断基準としては、納期が迫っている場合は外注、余裕があればキッティングのみ内製化といった対応を検討しましょう。
キッティング・セットアップの主な外注先
外注をする場合でも、委託先によって得意分野、価格帯、対応範囲がおおきく異なります。キッティング・セットアップの主な外注先は以下のとおりです。
- キッティング代行
- SES
- 派遣
- フリーランス
プロジェクトの規模や予算に応じて最適な外注先を選定しましょう。
キッティング代行
キッティング代行は、業務端末の設定を専門にしている業者です。
メリットは、作業が速く品質も安定しており、マスターイメージ作成も対応可能な点です。数百台規模の導入といった大量案件の経験が豊富なため、作業を効率的に進めることができます。
また、専用のクローニング設備を保有している業者も多く、複数台の端末を並列で一括設定できる環境が整っているのも強みです。
デメリットは、個別ユーザー向けのセットアップが限定的である点です。。標準構成を展開する工程には強い一方で、部署・役職ごとのアプリ設定やネットワーク設定などの細かなカスタマイズは別途費用が必要になる場合があります。
そのため、「キッティングのみ委託し、セットアップは社内で実施」といった分担が現実的です。
関連記事:キッティング代行とは?メリットや活用が適しているケースなどを紹介
SES
SES(システムエンジニアリングサービス)は、エンジニアのスキルと稼働時間を企業に提供する契約形態です。
メリットは、キッティングの進め方や設定内容など細かい要望に対応できる点です。現場に常駐するため「この部署は特別なアプリが必要」といった急な変更にも対応しやすくなります。
また、契約期間をプロジェクト進捗に応じて調整できるため、短期間の集中対応にも適しています。
デメリットは、エンジニアのスキルにばらつきがあることです。スキル要件を満たしていないと、作業効率や品質に影響が出る可能性があります。SESは時間単価制の契約が一般的なため、進捗が遅れると結果的にコストが増加するリスクもあります。
そのため、事前にスキル要件や対応範囲を明確にし、稼働後のフォロー体制を確認しておくことが重要です。
関連記事:インフラエンジニアのSES採用とは?フリーランスとの比較も解説
派遣
派遣は、人材派遣会社がエンジニアを提供し、自社で作業する形態です。
メリットは自社に指揮命令権があることです。SESは業務の進め方や技術的判断を委託先が行うのに対し、派遣では自社が直接指示できるため、キッティングの作業手順や優先順位を柔軟に調整できます。
また、ほかの社内業務との調整がしやすく「この部署から先に設定してほしい」といった要望にも即座に対応できるでしょう。
デメリットは、自社に専門性がなければ正確な指示を行えない点です。自社に専門人材はいるが作業要員が不足しているときに、派遣は適した選択肢と言えるでしょう。
関連記事:インフラエンジニアを派遣会社で採用するメリット|他の契約との違いも解説
フリーランス
フリーランスとは、企業と業務委託契約を結んで案件を遂行する外部の専門人材のことで、キッティング・セットアップにおける専門性を活用することができます。
複数企業でPC導入プロジェクトを経験しているため、業界の導入事例や最新のイメージ展開ツールにも精通している人材も多いです。自動化の実装経験がある人材も豊富で、効率的なキッティング・セットアップを提案してもらえることもあります。
また、作業の台数や複雑さに応じて報酬・契約期間を設定できるため、導入規模に見合った投資判断ができるでしょう。
ただし、個人との契約になるため大規模案件には不向きなケースもあることに注意が必要です。小規模かつコスト最適化を実現したい企業に適しています。
関連記事:インフラエンジニア案件をフリーランスに業務委託する方法とメリットを解説
キッティング・セットアップをフリーランスエンジニアに依頼するならクロスネットワークにご相談を
本記事ではキッティングとセットアップの違いについて解説しました。
キッティングは全社員のPCに共通して必要な設定を行う作業であり、セットアップはユーザー固有の環境を構築することです。作業内容、対応範囲、所要時間、必要なスキルなどが異なるため、それぞれの違いを理解したうえで内製化・外注の切り分けを判断することが重要です。
外注するときでも委託先によって得意分野や価格帯、対応範囲が異なります。限られた予算のなかで契約の柔軟性と対応スピードを重視したい場合は、フリーランスエンジニアの活用が有効です。
とくに、キッティング・セットアップで重要なアカウント管理やセキュリティポリシーの適用など、専門知識を要する領域では、経験豊富なインフラエンジニアの力が必要となるケースもあるでしょう。
クロスネットワークでは、即戦力としての活躍を期待できるフリーランスのインフラエンジニアを迅速にマッチングいたします。プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。
クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の依頼にも対応しているので、解決したい課題やご要望に応じて柔軟な外注をサポートいたします。
サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。インフラ構築に課題があるなら、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

新卒で大手インフラ企業に入社。約12年間、工場の設備保守や運用計画の策定に従事。 ライター業ではインフラ構築やセキュリティ、Webシステムなどのジャンルを作成。「圧倒的な初心者目線」を信条に執筆しています。