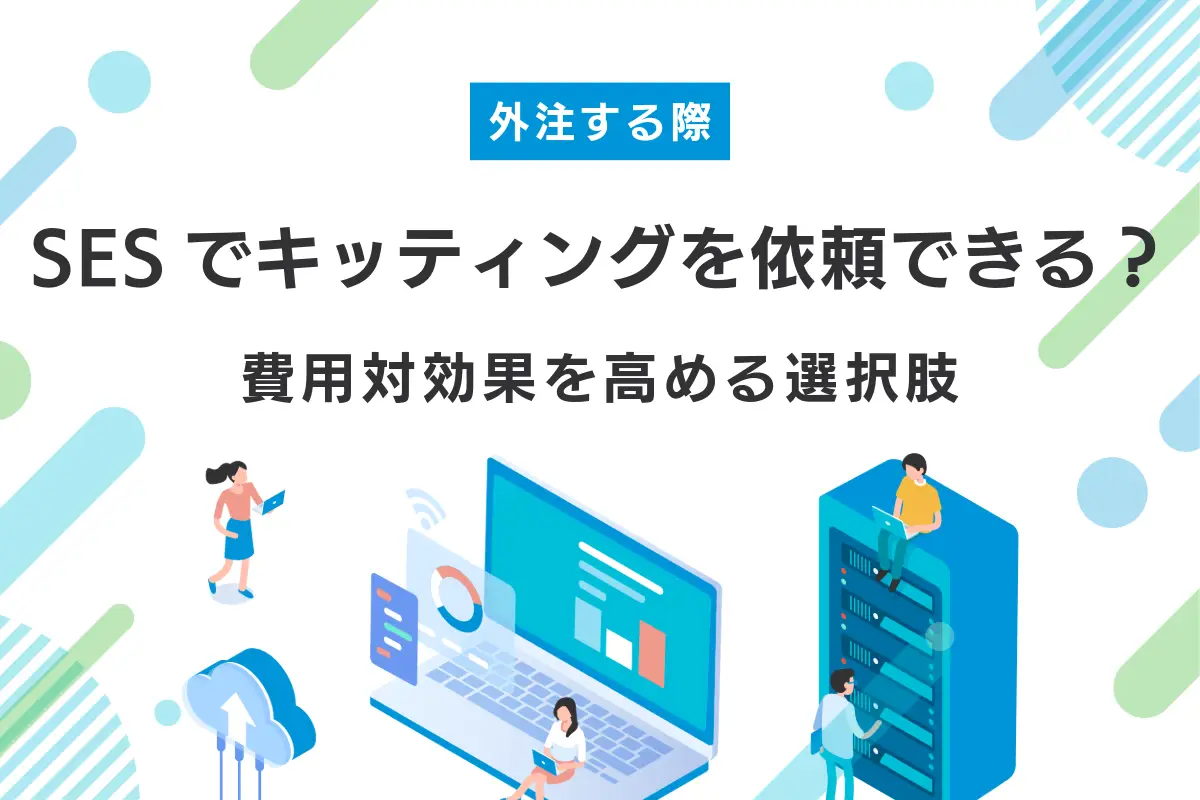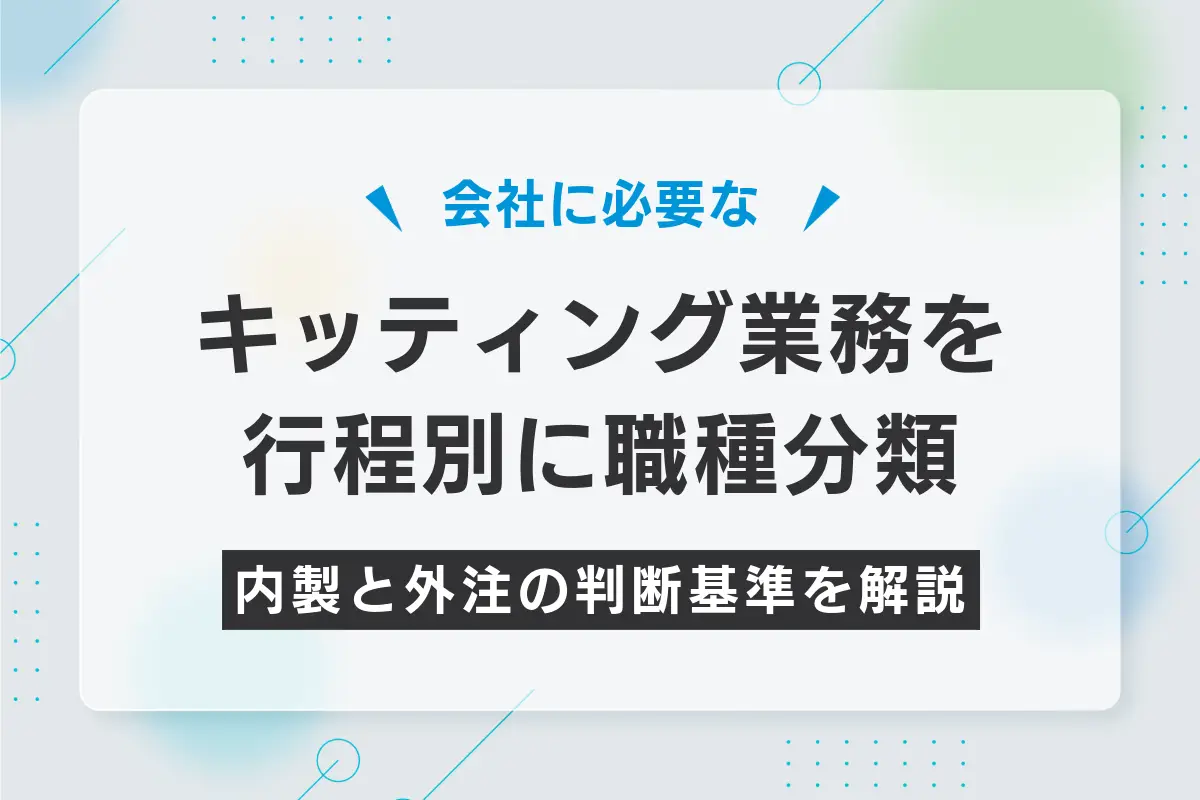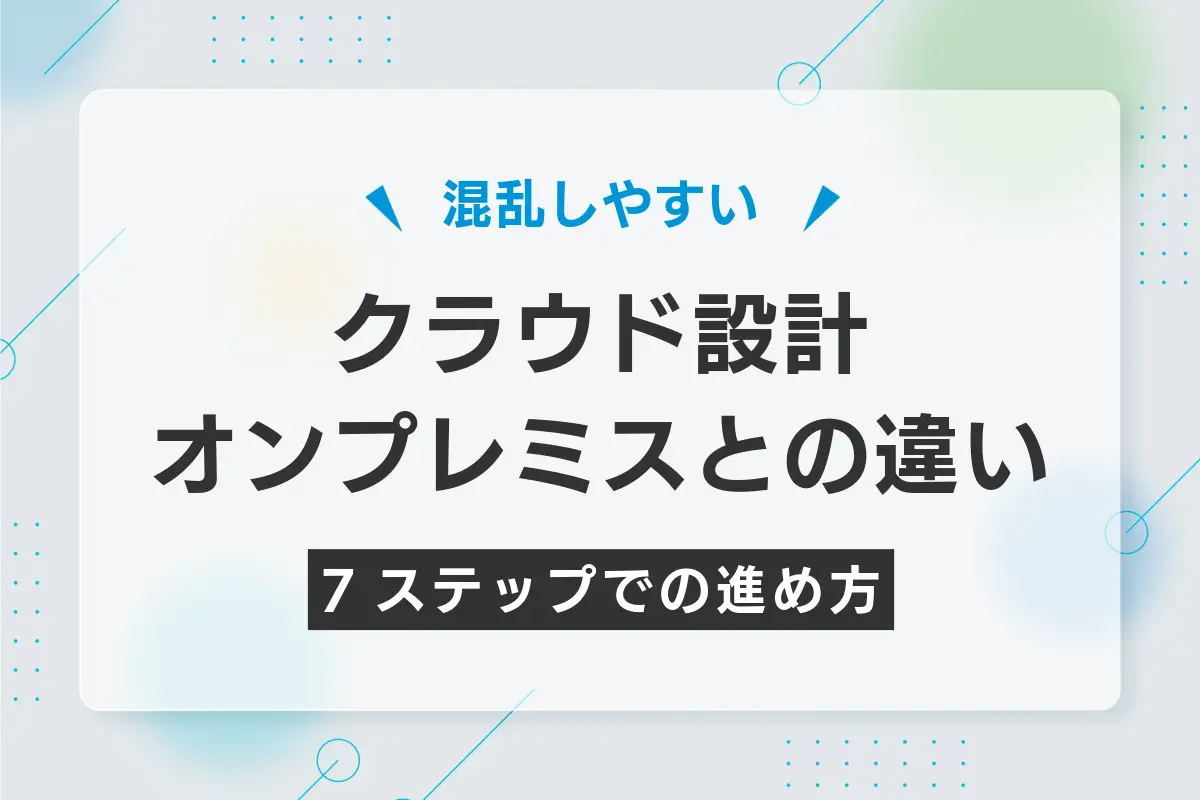
「数十台のサーバーが届いたが、開梱とラッキングだけで何日かかるだろう・・・」
「単純作業の繰り返しで、IPアドレスの設定ミスが起きないか不安」
このようなお悩みはありませんか?
サーバーキッティングは、OSをインストールするだけの単純作業ではありません。サーバーの安定性や運用負荷を左右する重要な工程です。
本記事では、サーバーキッティングの作業内容や注意したいポイントなどをわかりやすく解説します。
サーバーキッティングとは
サーバーキッティングとは、サーバーを業務ですぐに使える状態にセットアップする一連の作業のこと。
単なる初期設定ではなく、システムの安定稼働や運用効率を左右する、インフラの土台作りとも言える重要な工程です。
キッティングは、作業を行う場所によって大きく2つに分かれます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
- 出荷前キッティング(工場・倉庫で実施)
- オンサイトキッティング(サーバーを設置する現地で実施)
出荷前キッティング(工場・倉庫で実施)
出荷前キッティングとは、サーバーが納品される前に、製造工場や倉庫などで実施する初期設定作業です。
以下のようなハードウェアレベルの汎用的な設定を行います。
電源の投入・通電確認
CPU・メモリ・ストレージなどの認識確認
OSのインストールおよび標準設定
出荷前キッティングは、メーカーや販売代理店側で実施することが多く、情シス担当者やインフラエンジニアが直接作業するケースは稀です。
オンサイトキッティング(サーバーを設置する現地で実施)
オンサイトキッティングとは、サーバーが納品された後、現地で行う設定作業です。
情報システム部門やインフラエンジニアが主体となって、以下のような個別設定を行います。
ネットワーク・セキュリティの詳細設定
業務で利用するミドルウェアの導入
本番稼働に向けた最終的な環境構築
現場のインフラ環境に最適化し、サーバーを安全かつ安定的に稼働させることが目的です。
サーバーキッティングの主な作業内容
ここからは、サーバーキッティングの主な作業内容を以下の3つに分けて解説します。
- ハードウェアの設置・動作確認
- ソフトウェアのインストール・動作確認
- 各種ドキュメントの作成・管理
ハードウェアの設置・動作確認
サーバーキッティングは、ハードウェアの設置と動作確認からスタートします。
主に以下のような対応の流れが基本です。
- サーバー機器の開梱・ラッキング
- HDD・CPU・メモリなどの構成確認
(出荷前キッティングが仕様通りに行われているか) - 電源・ネットワークケーブルの配線
- ハードウェア周りの動作確認
(初期不良や設定・配線のミスがないか)
納品されたサーバーを開梱したら、一般的にはサーバーラックに設置します。複数人で慎重にラッキング作業を進めるのが安全です。
ラッキングが完了したら、出荷前キッティングが仕様書通りに行われているかどうかを確認します。
電源やLANケーブルなどを配線し、ハードウェアの初期不良や設定・配線のミスがなければ対応完了です。
ソフトウェアのインストール・動作確認
ハードウェアの対応が完了したら、ソフトウェアのインストールと動作確認に移ります。
- サーバーOSが正常に起動するかどうかを確認する
- ネットワーク・セキュリティの設定を確認する
(出荷前キッティングが仕様通りに行われているか) - 業務に必要なソフトウェアやアプリケーションをインストールする
(出荷前キッティングに含まれない個別対応) - サーバーが正常稼働するかどうかを確認する
サーバーOSが正常に起動したら、ネットワーク・セキュリティ設定を行います。
- 社内環境にあわせてIPアドレスが設定されているか
- ファイアウォールが設定されているか
- プリインストールされた不要機能が削除されているか
| 【元インフラエンジニアのひと言】 あらかじめインストールされている機能のうち「業務で使わないもの」は削除しておくのが理想的です。サーバーの脆弱性につながるリスクもあるため、セキュリティ対策としても欠かせません。 個人的な経験としては、プリインストールされたセキュリティソフトが残っていたことで、本来使用したい対策ソフトの機能と干渉してしまうケースもありました。 |
各種設定の確認が完了したら、サーバーの正常稼働をチェックしましょう。
- インストールしたソフトウェアが正常に起動するか
- 各デバイス間でネットワークが正しく疎通しているか(ping)
- 設定したパラメータにミスや漏れがないか
各種ドキュメントの作成・管理
ハードウェアとソフトウェアの動作確認が完了したら、ドキュメントを作成します。
- 作業手順書
- パラメーターシート
- 資産・ライセンス管理台帳
各種ドキュメントを作成しておくことで、キッティングの担当者が変わったときの引き継ぎもスムーズです。
サーバー障害の発生時には、原因を特定するための重要な手がかりとなります。
ちなみに、出荷前キッティングで作成された資料がある場合は、その内容と実際のサーバー設定に相違がないことをチェックするのも忘れずに。
サーバー本体を資産として識別するため、資産管理ラベルを貼り付ける作業も忘れずに実施しましょう。
このように、サーバーキッティングは、重い機器の搬入や配線、精密な設定など、想像以上に現場の負担が大きい作業です。
クロスネットワークなら、最短3営業日でエンジニアのアサインが可能。
1台からのスポット依頼はもちろん、数百台規模の大規模プロジェクトまで柔軟に対応します。
サーバーキッティングに失敗しないためのポイント
キッティング作業の手戻りを防ぎ、サーバーの安定稼働を実現するために、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 設定の工夫でサーバー運用の負担を減らす
- 構成の工夫でサーバー性能を最大限に引き出す
- 物理サーバーと仮想サーバーの違いを理解する
設定の工夫でサーバー運用の負担を減らす
以下のようなサーバーキッティングの工夫は、運用開始後の負担軽減につながります。
- 各サーバーに一貫した命名規則を適用する
- タイムスタンプがずれないように時刻同期設定を入れる
(ADサーバをNTPサーバとして設定するのが一般的) - 不要なサービス・ポートを無効化する
ホスト名やIPアドレスなどに命名規則を定めると、サーバーの役割や設置場所を名前から推測できます。
システムログのタイムスタンプがずれると障害発生時の原因特定が難しくなるため、社内の基準サーバー(NTPサーバー)との時刻同期設定を入れておきましょう。
OSのインストールによって有効化されるサービスには、業務で利用しないものも少なくありません。
利用しないサービスがサーバーのリソースを圧迫するだけでなく、セキュリティホールとなる可能性もあるため無効化または削除しておくと安心です。
複数のLANポートを搭載しているサーバーであれば、使用しないポートを設定で閉じておきましょう。
構成の工夫でサーバー性能を最大限に引き出す
サーバーの性能を最大限に引き出すためには、ハードウェア構成が用途と合致しているかをキッティング時に最終確認することが重要です。
- 書き込み速度と冗長性が求められるならRAID 10
- 容量効率と冗長性のバランスを取りたいならRAID 5またはRAID 6
また、将来的な事業やサービスの拡大を想定し、サーバーのスペックに拡張の余地を残しておきましょう。
スペック不足になると、後からサーバーを買い足したり、パーツを交換したりといった工事が発生してしまいます。
物理サーバーと仮想サーバーの違いを理解する
主なサーバーの種類は、物理サーバーと仮想サーバーの2つ。
サーバーキッティングの基本的な流れは同じですが、細かな観点や注意点には違いがあるため事前に把握しておきましょう。
| サーバーの種類 | 主な注意点 |
|---|---|
| 物理サーバー |
|
| 仮想サーバー |
|
近年主流の仮想サーバーでは、専用ツールをインストールしたりリソースを過不足なく割り当てたりする仮想化特有の作業が求められます。
仮想化のノウハウに不安が残る場合は、専門知識をもつインフラエンジニアを活用するのも効果的です。
関連記事:キッティング作業で求められるエンジニアスキル|人材確保のコツも解説
複雑なサーバキッティングには外部委託がおすすめ
情シス担当者のリソースが限られている場合は、専門業者への外部委託を検討するのがおすすめです。
外部リソースを活用することで、以下のようなメリットがあります。
- 自社にないノウハウを導入できる
- 複数のサーバーを短期間でキッティングできる
- 注力したいコア業務にリソースを集中できる
自社にないノウハウを導入できる
サーバーキッティングを外部委託するメリットは、自社にない専門的なノウハウを取り入れられることです。
導入実績が豊富な委託先であれば、自社に不足するノウハウを補うように質の高いサーバーキッティングを依頼できます。
また、仮想化やクラウド化への切り替えを検討している企業にも外部委託がおすすめです。
ツールを用いた効率化や複雑な動作検証など、情シス担当者が学ぶには時間のかかる実践的な対応や判断を期待できます。
複数のサーバーを短期間でキッティングできる
数十台規模のサーバーを導入するような大規模なプロジェクトでは、体制の整った専門業者を活用するのが有効です。
自社の限られたリソースで多数のサーバーをキッティングすると、膨大な時間と労力がかかる可能性もあります。
新サービスの立ち上げや拠点の拡大など、スピードが求められる場面において、必要な人員を即座に確保できることは大きなメリットです。
関連記事:キッティングサービスの大手企業5選|依頼先の選び方や注意点も解説
注力したいコア業務にリソースを集中できる
サーバーキッティングを外部委託することで、社内リソースを本来注力すべきコア業務に集中できます。
一時的な作業に多くの時間を取られ、コア業務に着手する余裕がなくなってしまうのは情シス担当者のよくある悩みです。
必要なタイミングに必要な期間だけ外部リソースを活用すれば、社員を増やすよりも固定費(人件費)を大幅に削減できます。
自社にあった外部委託先を選ぶポイント
委託先の選定を誤ると、想定通りの成果が得られない可能性もあります。
外部委託先を選ぶ際は、以下のポイントをチェックしましょう。
サーバキッティングの豊富な実績がある
- セキュリティ対策に取り組んでいる
- ツールを用いた効率化・自動化を提案できる
- 柔軟な対応を依頼できる(フリーランスもおすすめ)
サーバキッティングの豊富な実績がある
サーバーキッティングの実績があるかどうかを確認しましょう。
- 自社が導入したいサーバーOSやメーカーの対応実績があるか
- 類似環境(物理/仮想/クラウド)でのキッティング実績があるか
実績の有無は、公式サイトに掲載されている導入事例から把握できます。
確認できる事例が少ない場合は、問い合わせ時に具体的な実績について質問しておくと安心です。
専門知識を要するキッティング環境の構築には、サーバーだけでなく、ネットワークやセキュリティ設定などの基礎知識をもつインフラエンジニアが対応するケースもあります。
サーバーの仮想化やクラウド環境との連携を伴うキッティングでは、インフラエンジニアのスキルが業務効率化と安定稼働に大きく貢献するでしょう。
セキュリティ対策に取り組んでいる
キッティング作業では、企業の機密情報や個人情報を取り扱うケースもあります。
業者のセキュリティ対策に対する取り組みとして、以下の点をチェックしておきましょう。
- 第三者認証の取得状況(プライバシーマークやISMSなど)
- 作業場所のセキュリティ管理体制(監視カメラ、入退室管理など)
- NDA(秘密保持契約)締結の可否
上記に加えて、情報漏洩防止の運用ルールが整備されているかどうかも確認しておくと安心です。
ツールを用いた効率化・自動化を提案できる
膨大な設定作業をすべて手作業で行う業者は、ヒューマンエラーのリスクが高くなります。
業者を選ぶ際は、作業を自動化しているかを確認しましょう。
自動化技術を持つ業者であれば、作業ミスを極限まで減らし、大量のサーバーも短期間で納品可能です。
関連記事:キッティング作業で求められるエンジニアスキル|人材確保のコツも解説
柔軟な対応を依頼できる(フリーランスもおすすめ)
自社特有の要件や部分的な作業依頼にも対応してくれるかどうかを確認してみましょう。
コストや柔軟性を重視する場合は、フリーランスのインフラエンジニアに依頼するのもおすすめです。
フリーランスは、組織運営費や中間マージンが発生しないため、適正かつリーズナブルな価格での依頼が可能です。
エージェントサービスを活用すれば、自社の要件にマッチする人材をスムーズに見つけられます。

サーバーキッティングに強い人材探しならクロスネットワークで!
サーバーキッティングは業務利用を目的とする対応であり、ハードウェアとソフトウェアを総合的に構築するスキルが求められます。
単純にサーバーをセットアップするだけではなく、システムの安定稼働や将来の拡張性を考慮する知識が必要です。
だからこそ、無理に社内リソースで対応すると、本来であれば効率化につながるキッティングのメリットを失ってしまう可能性があります。
社内リソースの負担を軽減するなら、企業の状況やリソースにあわせて「外部委託(フリーランス)」という選択肢を検討するのも効果的です。
経験豊富なフリーランスのインフラエンジニアを確保するなら、エージェントサービス「クロスネットワーク」にご相談ください。
クロスネットワークでは、キッティング作業に対応できるインフラエンジニアを迅速にマッチングいたします。
プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。
クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でアサインできます。
サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。
柔軟な契約条件でインフラエンジニアを確保するなら、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。
平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。