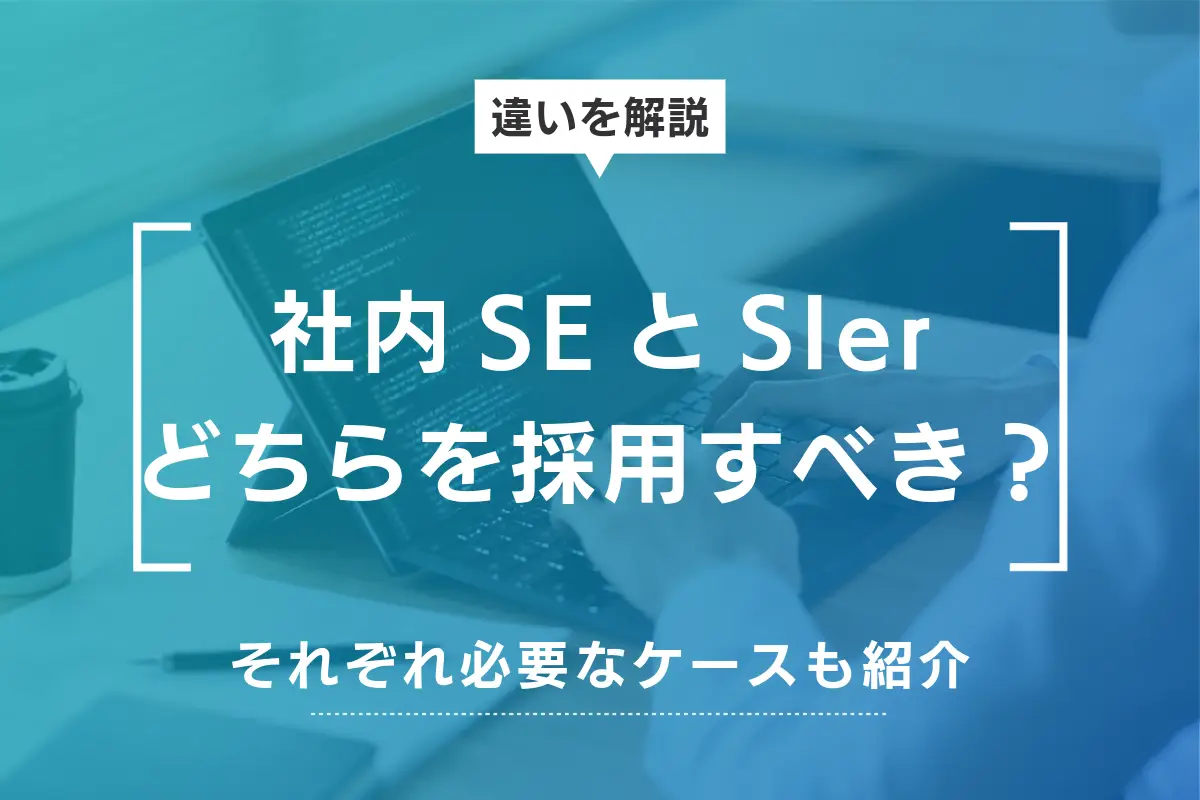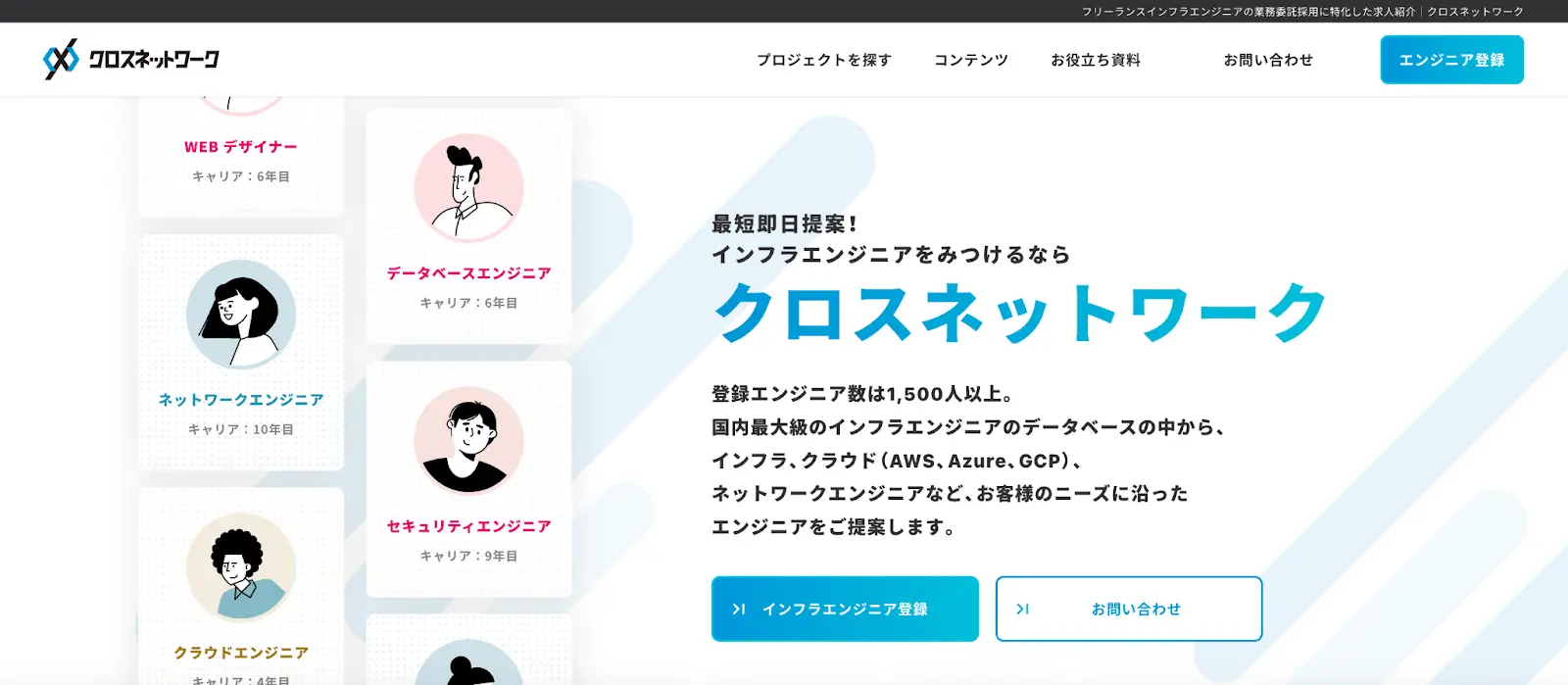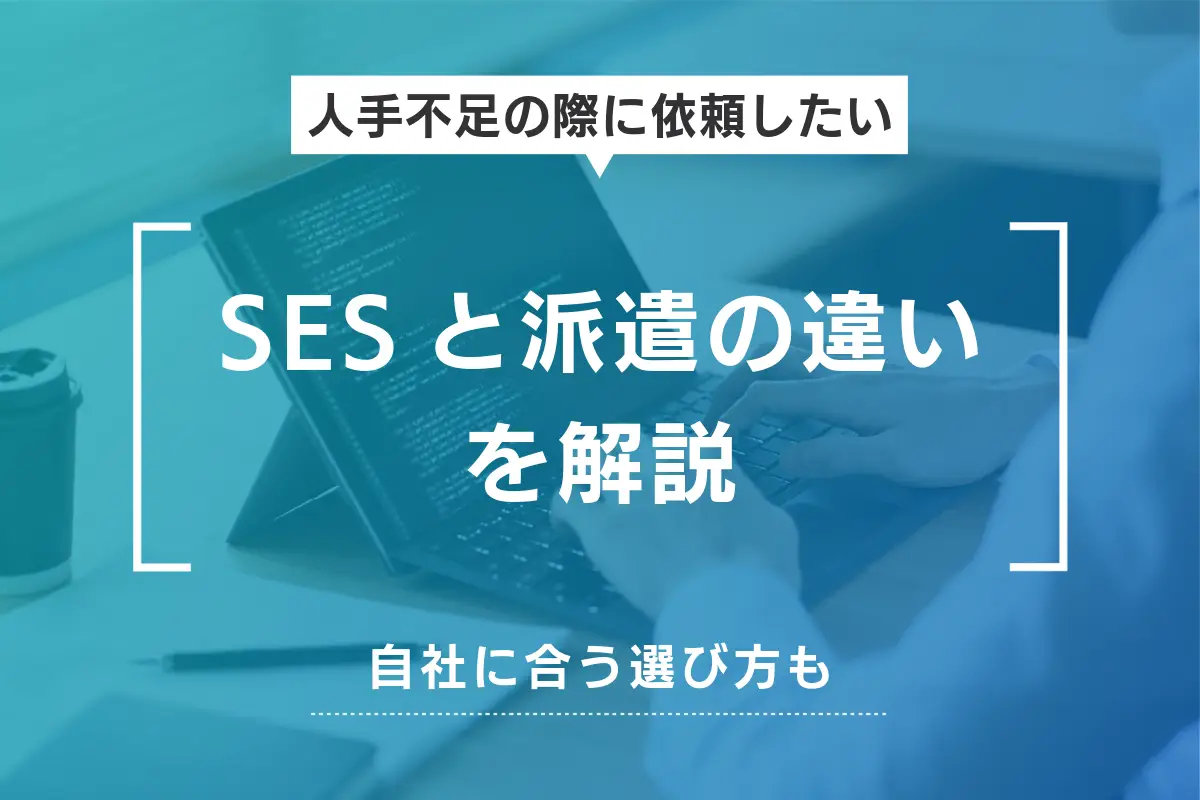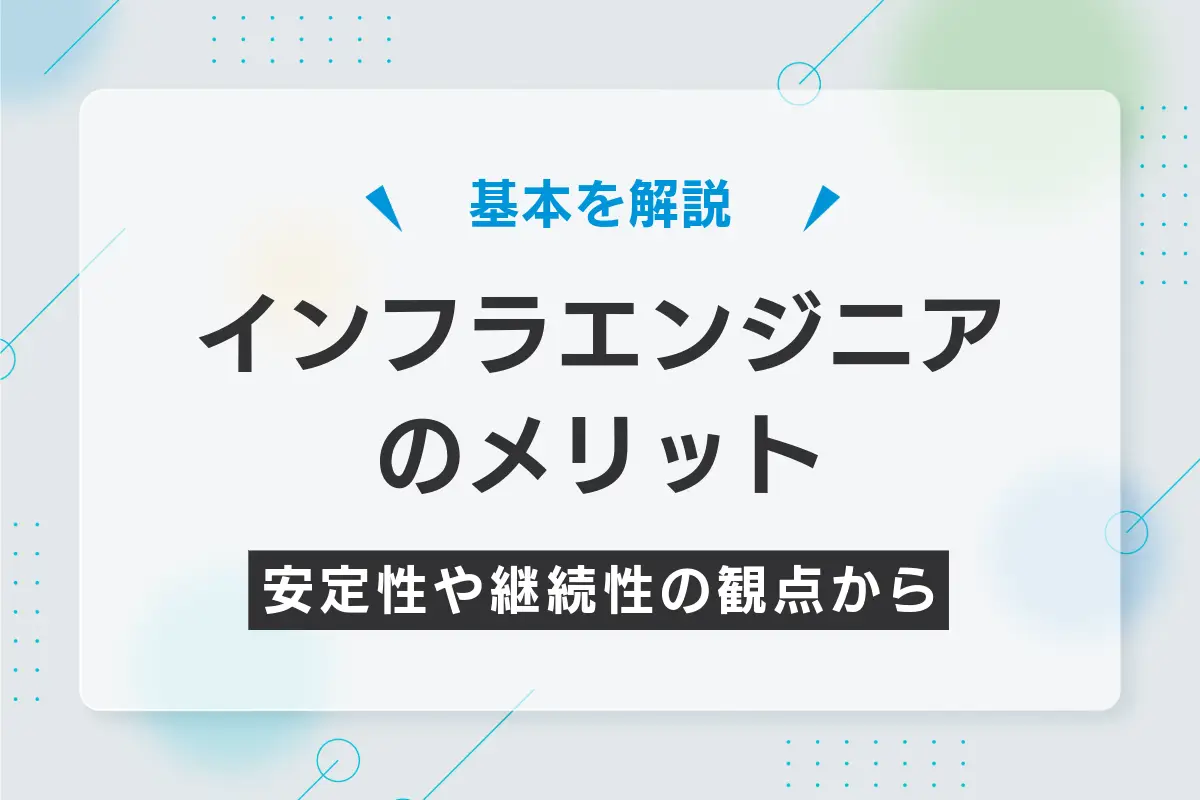社内SEとSIer出身のエンジニアのどちらを採用すべきか悩んでいませんか?
既存インフラの保守が課題となっており、エンジニア不足に直面している企業は多いかと思います。
なるべく経験豊富な人材を採用したいけれど、社内SEとSIer出身のエンジニアどちらが良いか判断できない採用担当者は少なくありません。
そこで、本記事では社内SEとSIerの違いを業務内容、スキル、待遇・年収を中心に解説します。
自社に適した人材を確保する方法についても紹介するので、参考にしてください。
SIerと社内SEの違い
IT部門責任者として採用を検討する場合、社内SEとSIerの違いを正確に理解することが重要です。
まずは、社内SEとSIerそれぞれの違いを詳しく見ていきましょう。
社内SEとは|社内システムを担当するエンジニア
社内SEは、社内システムやITインフラを企画・運用するエンジニアです。
自社の情報システム部門に所属し、社内で使用するシステムの企画から開発、運用までを一貫して担当します。
外部ベンダーに開発を依頼する場合は、発注側の立場で自社の要件を的確に伝える橋渡し役となります。
また、社内ユーザーからの問い合わせ対応やトラブルシューティングなど、日常的なサポート業務も担当することが多いです。
長期的な視点で自社のITインフラを発展させる役割を担うため、ビジネス理解力とコミュニケーション能力が重要と言えるでしょう。
関連記事:SIer企業のインフラエンジニア採用課題と即戦力確保の方法を解説!
SIerとは|システムの設計~保守までを一貫して請け負う企業
SIer(システムインテグレーター)とは、顧客のシステム開発やITインフラ構築を受託する企業のことです。
SIerに所属するエンジニアは、クライアント企業の要求に応じたシステム設計から構築、テスト、必要に応じて保守までを一貫して請け負います。
受注側の立場で仕事を進めるため、クライアントの要件を正確に理解し、それを技術的に実現する能力が求められます。
複数のプロジェクトを並行して進行することも多く、納期管理や品質確保のためのプロジェクトマネジメント能力も欠かせません。
技術トレンドへの対応が迅速であり、最新技術に触れる機会が多いことも特徴です。
もし、「社内SEを採用したいが、優秀な人材が見つからない」「SIerに依頼するとコストが合わない」とお悩みなら、クロスネットワークにお任せください。
クロスネットワークなら、採用難易度の高いインフラエンジニアを最短3日でご紹介可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
社内SEとSIerの業務内容の違い
社内SEとSIerはどちらも企業のITインフラを支えるうえで重要ですが、下の表のように業務内容や責任範囲が異なります。
社内SEとSIerの業務内容の比較表
項目 | 社内SE | SIer |
主な業務範囲 | 社内システムの企画・要件定義から運用・保守まで幅広く対応 | 顧客要件に基づくシステム設計・開発・テストが中心 |
立場 | 自社内のIT部門として内部からシステム構築・運用 | 外部の委託先として顧客企業向けにシステム提供 |
業務の焦点 | 社内の課題解決に直結する | 技術的専門性を生かした受託開発 |
日常業務 |
|
|
プロジェクト | 主に自社内のプロジェクト管理 | 複数クライアント・プロジェクトを並行して管理 |
必要スキル |
|
|
業界知識 | 自社業界に特化した深い知識 | 多様な業界・業種の知識を横断的に習得 |
責任範囲 | 社内ITシステム全体の安定運用と業務効率化 | 契約した開発案件の納期・品質・コスト管理 |
キャリア特性 | 長期的な視点での自社システム発展に貢献 | 多様なプロジェクト経験を通じた幅広い技術習得 |
社内SEの業務内容
社内SEの業務は社内システムの企画・要件定義から運用・保守まで幅広く、社内の課題解決に直結します。
システム開発を外部委託する場合は、ベンダー選定や発注、プロジェクト管理などの調整業務が中心となります。
一方、中小企業や内製志向の企業では、社内SEが直接システム開発を手がけることも少なくありません。
また日常的な問い合わせ対応やトラブル解決、PC・ソフトウェアの管理、ネットワークやサーバー・クラウド環境の運用、セキュリティポリシーの策定・運用など、IT環境全般の維持管理も担います。
SIerの業務内容
SIerの業務は顧客要件に基づくシステム設計・開発・構築・テストが中心で、専門性を生かした受託開発が主要な仕事です。
クライアントの業務内容や課題を理解し、それを解決するためのシステムを提案・構築する能力が求められます。
また、複数のプロジェクトを並行するのもSIerの特徴です。
異なる業界・業種のクライアントのシステム開発に関わるため、さまざまなビジネスモデルや業務フローに触れる機会があります。
納期と品質の責任を負いながらプロジェクトを遂行するため、高度な技術力だけでなく、進捗管理やリスク管理などのプロジェクトマネジメントスキルも重要です。
社内SEとSIer出身エンジニアのスキルの違い
両者の業務内容が異なれば当然保有スキルも変わります。以下の表で両者が有するスキルを比較しました。
社内SEとSIer出身エンジニアの保有スキル比較表
スキル分野 | 社内SE | SIer出身エンジニア |
専門性の方向性 | ジェネラリスト志向(広く浅く) | スペシャリスト志向(狭く深く) |
専門分野 | 幅広いIT基礎知識 | 特定技術領域の深い専門知識 |
ビジネス理解 | 自社のビジネスを深く理解 | 多様な業界・業種の知識を横断的に習得 |
プロジェクト管理 | 外注の場合の進捗管理や品質管理 |
|
コスト管理 | 限られた予算内で最大効果を追求する能力 | コスト制約のなかでのプロジェクト推進能力 |
コミュニケーション |
| 顧客との要件定義や仕様調整など対外的な折衝経験 |
チーム連携 | 専門家や外部ベンダーとの連携能力 |
|
品質管理 | 外部委託先の成果物を評価する能力 | コードレビューなどの品質管理プロセスへの精通 |
社内SEの保有スキル
社内SEに求められるのは、幅広いIT知識とビジネス理解力、社内調整能力です。
社内SEは社内の多様な部門のニーズに応えるため、特定の技術に特化するよりも幅広い知識をもつ傾向にあります。
業務システムやインフラ、セキュリティなど多岐にわたる領域の基礎知識をもち、必要に応じて専門家や外部の委託先と連携する能力も求められます。
社内SEの強みは、自社のビジネスプロセスを深く理解し、経営戦略に沿ったIT施策を立案できること。
経営層の意向を汲み取り、限られた予算内で最大の効果を得るためのコスト管理能力も不可欠です。
また、プロジェクト管理や外部委託先の管理のスキルも重要で、外注の場合は要件定義から納品までの進捗管理や品質管理の能力も求められます。
SIer出身エンジニアの保有スキル
SIer出身エンジニアは、システム設計から開発、テストまでの一連の流れを経験している人が多く、技術的な課題解決力が高いのが特徴です。
複数のプロジェクトや業界の経験が豊富で、多様なビジネスモデルや業務知識を短期間で吸収できる人材も多いです。
また、顧客との要件定義や仕様調整など対外的な折衝経験も積んでおり、厳しい納期やコスト制約のなかでプロジェクトを推進できるでしょう。
加えて、チームでの開発経験からメンバー間の連携や役割分担、コードレビューなどの品質管理プロセスにも精通している傾向にあります。
社内SEとSIer出身エンジニアのどっちを採用する?
ここまで社内SEとSIerの違いについて解説してきましたが、実際にどちらを採用すべきか迷う人事担当者も多いかと思います。
企業の置かれた状況にもよりますが、自社の課題と将来の展望を踏まえて、人材を選択することが大切です。
社内SEを採用するべきケース
長期的な視点でのシステム運用や社内調整が重要な場合は、社内SEの採用が適しています。
継続的なシステム運用や改善が必要な企業では、安定してシステムを管理できる社内SEの存在が重要です。
とくに、自社のビジネスモデルが複雑で業界特有の知識が必要な場合は、長期的にビジネスを理解できる社内SEが効果的でしょう。
また、内製化によるコスト削減とノウハウの蓄積を重視する場合も、社内SEの採用が有効です。
外注コストを削減し、自社に技術やノウハウを蓄積することで、長期的には投資対効果が高まります。
SIer出身エンジニアを採用するべきケース
ITインフラの刷新や新技術の導入といった変革期には、SIer出身エンジニアの採用が適している可能性が高いです。
大規模なシステム刷新や新規構築プロジェクトを控えている場合、プロジェクト管理経験が豊富なSIer出身者が力を発揮するからです。
要件定義から設計、開発、テスト、リリースまでの一連のプロセスを経験している人材は、プロジェクトの成功確率を高める可能性があります。
また、専門技術や最新技術の導入が必要な場合も、特定分野に精通したSIer出身エンジニアが適しています。
クラウド移行やAI導入、セキュリティ強化など、専門性の高い技術領域では、その分野での実績がある人材が即戦力となるでしょう。
社内SEとSIer出身エンジニアの採用における課題
社内SEとSIer出身エンジニアはそれぞれに強みがありますが、いずれも簡単に採用できるわけではありません。
採用課題を理解しておくことは、自社に合った人材を確保するための戦略を立てるうえで重要です。
ここでは、社内SEとSIer出身エンジニア、それぞれの採用課題を整理します。
社内SE採用の課題
社内SEは安定した労働環境・充実した福利厚生・良好なワークライフバランスという3つの魅力を兼ね備えているため、エンジニアからの人気が集中しています。
しかし、中途採用市場における優秀な社内SE経験者の絶対数が限られているのが現状です。
社内SEには技術力だけでなく自社の業務プロセスへの深い理解と部門間の調整を円滑に進めるコミュニケーション能力が求められるからです。
このような複合的なスキルセットをもつ人材を見つけることは難しく、求人倍率が高止まりしています。
一方で、採用に成功した場合のメリットとして社内SEは定着率が比較的高い傾向があります。
安定志向の強い人材が多いため、一度採用できれば長期的な人材確保につながり、採用コストの回収期間も比較的短くなるでしょう。
SIer出身エンジニア採用の課題
SIer出身エンジニアは、大規模システムの設計・開発から複数の委託先との調整を含むプロジェクトマネジメントまで、幅広い経験を積んでいる人が多いです。
金融・製造・流通など多様な業界のシステム構築に携わってきた経験から、業界横断的な知識と問題解決能力を備えている人材も少なくありません。
しかし、豊富な経験と高度なスキルゆえに、年収水準や待遇への期待値が高めに設定される傾向があります。
とくに大手SIer出身者の場合は前職の給与水準が高いため、中堅企業では提示できる条件に限界があることも多いでしょう。
また、一部の職場では深夜残業や休日出勤が常態化していた経験から、転職の動機として「ワークライフバランスの改善」を重視する人材も数多くいます。
そのため、自社の労働環境や働き方改革の取り組みなどを明確に提示できなければ、採用後のミスマッチにつながるでしょう。
高度な技術力をもつSIer出身者ほど大手企業や外資系企業、成長著しいスタートアップ企業との人材獲得競争に巻き込まれやすくなります。
それでも採用に成功すれば、大規模なシステム刷新プロジェクトやAI・クラウドなどの先端技術の導入に対応しやすくなります。
社内SE・SIer出身エンジニアを確保する方法
社内SEやSIer出身エンジニアの採用は競争が激しく、容易ではありません。
そのため、自社のニーズに合った人材を戦略的に確保することが成功への鍵となります。ここでは人材確保における以下の3つの方法を解説します。
- 未経験者を育成する
- 経験者を中途採用する
- フリーランスを活用する
未経験者を育成する
効果的な育成のためには、OJT(実務を通じた訓練)とOFF-JT(研修など)を組み合わせて、段階的にスキル習得の計画を立てましょう。
新卒採用や異業種からの転職者を社内SEとして育成する場合、自社のビジネスプロセスとそれに基づくITの役割や必要性を同時に教育できるというメリットがあります。
とくにITに関する基礎知識はあるものの、実務経験の少ない人材は、社内の業務を深く理解しながら成長できる社内SEとして適性が高い傾向にあります。
一方で、短期間でSIer出身者並みの専門的な技術スキルを身につけるのは難しく、実践的な開発経験を積むには相応の時間が必要です。
関連記事:インフラエンジニアの育成方法を解説!おすすめの研修や資格なども紹介
経験者を中途採用する
即戦力となる経験者の中途採用は、短期間で成果を出したい場合に効果的な方法です。なお、社内SEとSIer出身者では採用時に見極めるべきポイントが異なります。
社内SE経験者の場合は、過去に携わったシステム企画や運用プロジェクトの内容、外部の委託先管理経験、社内調整能力などに注目しましょう。
一方、SIer出身者の場合は、技術的専門性、プロジェクト管理能力、クライアント対応経験などが重要な評価ポイントとなります。
注意点として、中途採用の市場では優秀なIT人材の獲得競争が激しくなっています。そのため給与や福利厚生だけでなく「やりがい」や「成長機会」といった非金銭的な魅力も重要です。
関連記事:インフラエンジニアの中途採用は難しい?即戦力人材を迅速に獲得するコツを解説
フリーランスを活用する
フリーランスの活用は、社内SEのように幅広い業務を支える人材から、SIer出身エンジニアのように専門性の高い人材まで、必要なスキルを柔軟かつ迅速に取り入れたい場合に最適な方法です。
プロジェクト単位はもちろん、数日から数週間のスポットでの柔軟な人材活用が可能だからです。
そのため、システム刷新や新技術導入など特定期間だけ専門的なスキルが必要な場合にメリットがあります。
たとえば、クラウド移行プロジェクトの3か月間だけAWS専門のエンジニアを確保する、設計レビューのために1週間だけアーキテクトを起用する、といった活用が可能です。
また採用コストや育成コストの面でも優位性があり、採用活動や研修にかかる時間的・金銭的コストを大幅に削減できます。
ただし、企業の中核となるシステムや長期的な運用が必要な領域では、ナレッジの蓄積や継続性の観点から、正社員の社内SEなど自社人材との適切な役割分担が重要です。
関連記事:インフラエンジニアへの外注とは?業務委託のメリットとおすすめのエージェントも紹介
社内SE・SIer出身エンジニアをお探しの方ならクロスネットワークがおすすめ
この記事では、社内SEとSIer出身エンジニアのどちらを採用すべきか、それぞれの業務内容や必要なスキル、確保する方法などを中心に解説してきました。
どちらが自社に適しているか明確になったものの、実際に正社員として採用するとなると多くの予算と時間を費やすことになります。
そこでおすすめしたいのが、フリーランスのインフラエンジニア専門エージェントサービスクロスネットワークです。
クロスネットワークでは、社内SE・SIerの経験が豊富なインフラエンジニアを含む1500名以上の厳選された人材から、ニーズにあわせて最適な即戦力人材を最短即日でご提案、最短3日でのアサインも可能です。
「社内SEとSIer出身エンジニアのどちらが必要かわからない」「必要な稼働量にあわせて人材を活用したい」と言ったお悩みにも業界に精通したコンサルタントが案件内容をヒアリングし、最適な採用要件をアドバイスします。
詳細なサービス内容については、無料ダウンロードが可能なサービス資料をご覧ください。
ご相談はお問い合わせページより承っており、平均1営業日以内にご提案します。インフラエンジニア採用でお困りの際は、ぜひクロスネットワークにご相談ください。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

新卒で大手インフラ企業に入社。約12年間、工場の設備保守や運用計画の策定に従事。 ライター業ではインフラ構築やセキュリティ、Webシステムなどのジャンルを作成。「圧倒的な初心者目線」を信条に執筆しています。