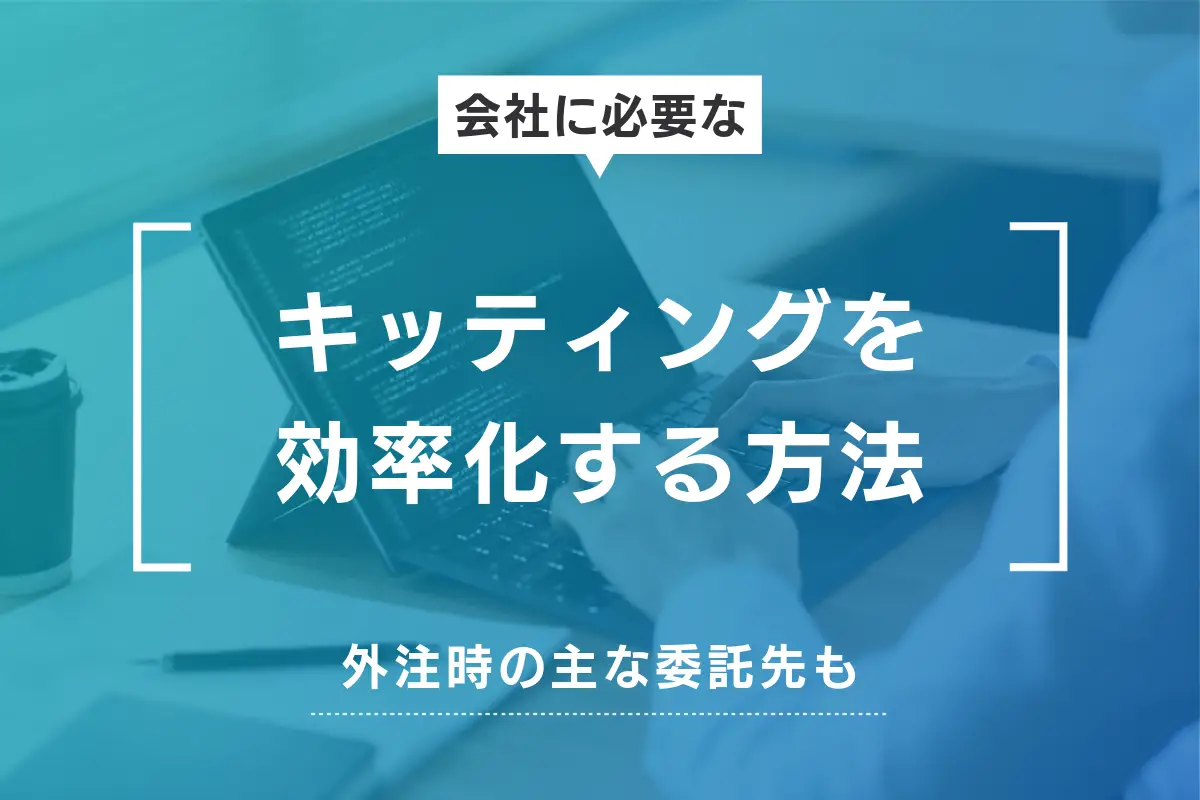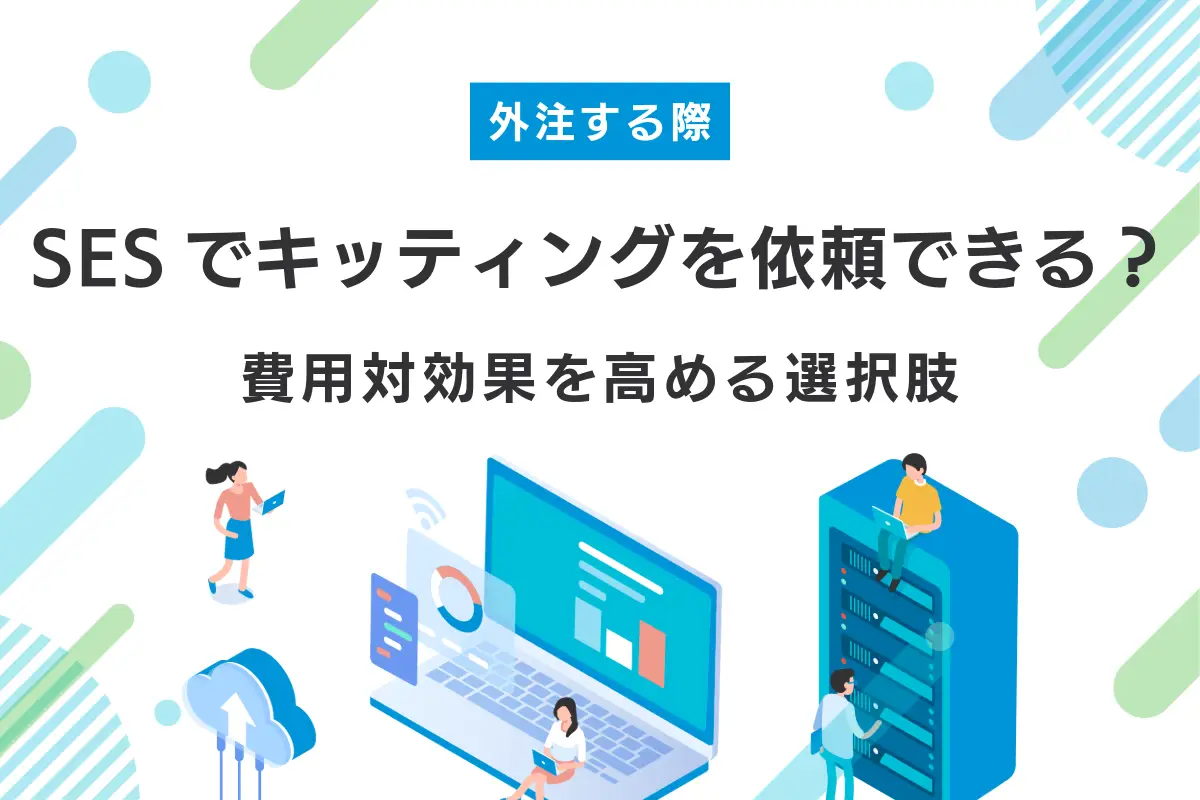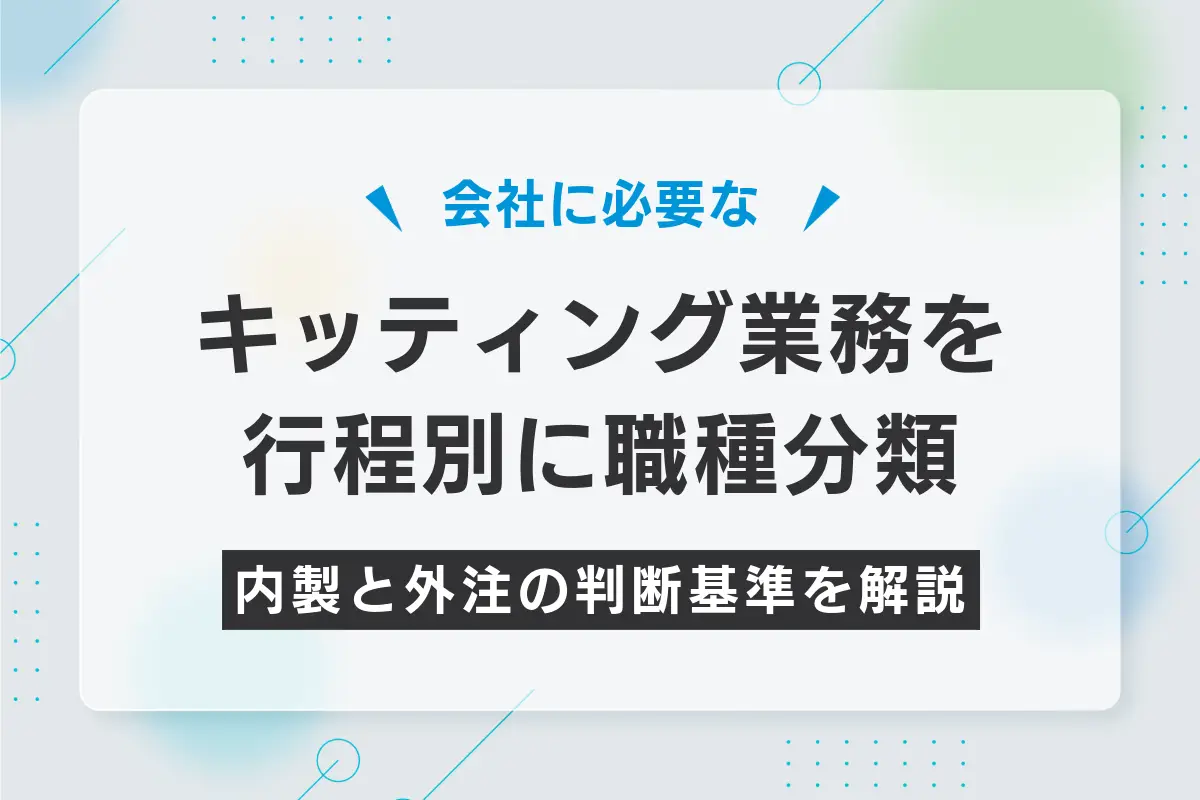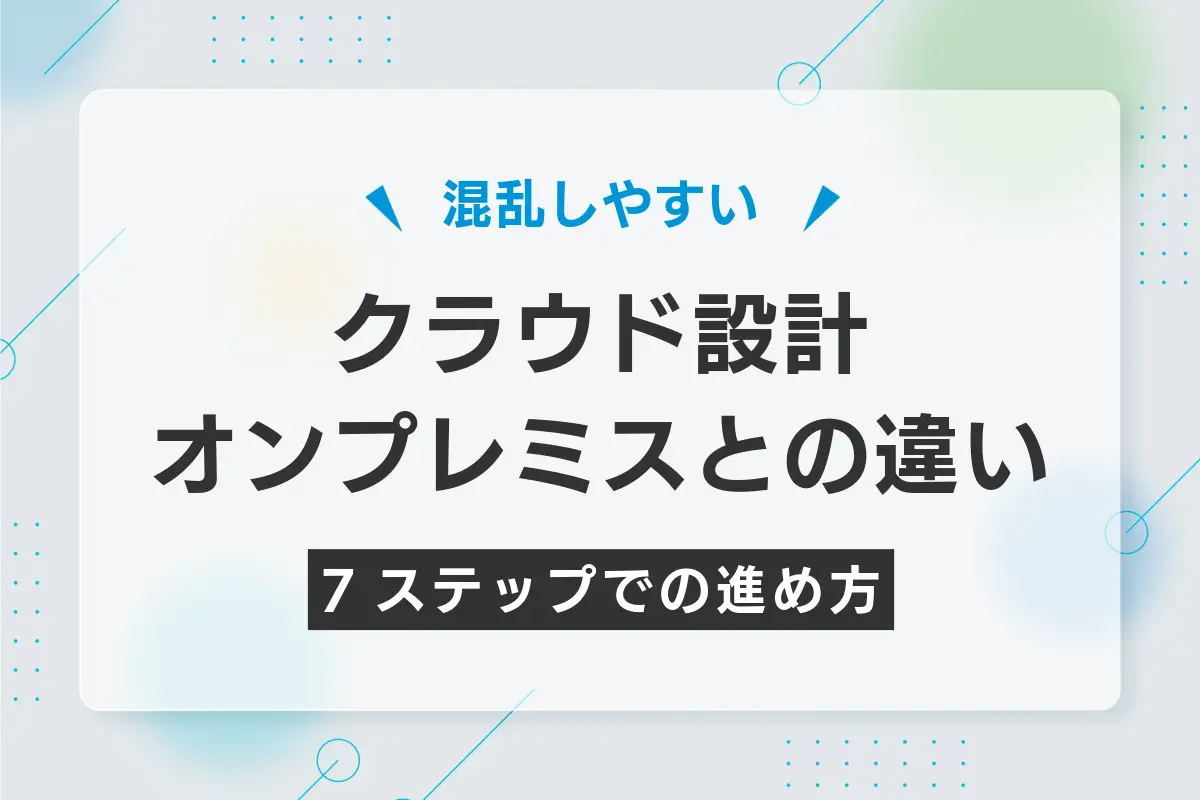
新拠点の設立や人員増に伴い、PCのキッティング作業が負担で困っていませんか?手作業中心の運用では、設定ミスのリスクや属人化による作業のばらつきなどの課題が残り、結果的に業務効率やシステムの安定性にも影響を及ぼす恐れがあります。
そこで、本記事ではキッティングを効率化する方法について解説します。あわせて、外注する有効な手段としてフリーランスについても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
キッティングとは|業務端末を利用できる状態にする作業
キッティングは、工場から出荷されたデバイスに必要なソフトウェアのインストールや各種設定を行い、業務で使用できるよう準備する作業です。
具体的な作業内容としては、開梱から本体・付属品の取り出し、OSの初期設定、社内ネットワークへの接続設定などが挙げられます。
さらに、業務で使用するアプリケーションのインストール、ウイルス対策ソフトなどのセキュリティ設定、資産管理用のラベル貼付や台帳への登録まで、多岐にわたる作業が含まれます。
キッティングの目的
キッティングの主たる目的は下の表のとおりです。
目的 | 概要 |
従業員が業務を開始できる環境の提供 | PCを配布後すぐに利用できる状態を整え、業務開始をスムーズにする。 |
企業のセキュリティポリシーに準拠した安全な端末の配備 | ウイルス対策や暗号化設定、セキュリティ対策などにより、情報漏洩リスクを防止する。 |
品質の均一化と管理の効率化 | 全従業員のPCに同じ設定を行い、トラブル対応の迅速化と管理の負担軽減を図る。 |
IT資産の適切な管理と追跡可能性の確保 | シリアル番号、購入日、保証期間などを記録して、端末の管理や紛失・盗難時に迅速に対応できる。 |
キッティングは単なる初期設定作業ではなく、業務効率の向上、セキュリティの確保、IT資産管理の適正化という企業経営に直結する重要な役割を担っています。適切なキッティングを実施することで、従業員の生産性向上と企業の情報資産保護を同時に実現できます。
セットアップとの違い
セットアップとキッティングでは作業範囲が異なります。
セットアップは、PCのOS起動やインターネット接続など、個人が自宅で行うレベルの基本的な初期設定です。家電量販店で購入したPCを自宅で使い始めるときの設定を想像すると理解しやすいでしょう。
一方、キッティングはセットアップを含むより包括的な作業です。業務用アプリケーションのインストール、企業のセキュリティポリシーに沿った設定、資産管理台帳への登録など、企業で使用するためのあらゆる設定が含まれます。
つまり、セットアップは「単に使用できる状態」にする作業であるのに対し、キッティングは「業務ですぐ使用できる状態」にすることと言えます。
関連記事:キッティングとセットアップの違いは?おすすめの外注先も紹介
キッティングの効率化が重要な背景
キッティング作業の効率化が求められる背景には、以下の3つが挙げられます。
- 大量導入や短納期対応による負担増
- 手作業中心による生産性の低下
- 属人化による品質・進行リスク
上記の課題が未解決だと担当者の負担が増大し、優先すべきコア業務の遂行が難しくなります。
大量導入や短納期対応による負担増
キッティングでおおきな負担とされているのが、大量のPCを短期間で準備しなければならないことです。
とくに、新入社員の一斉入社や事業拡大に伴う拠点開設では、数十台から場合によっては数百台のPCを、入社日や開設日という変更できない明確な期限までに準備する必要があります。
納期を優先するあまり、作業品質に差が生じたり深夜残業や休日出勤が常態化して人件費が増加したりといった運用上の負担が増えるでしょう。
さらに、機器の搬入・運搬・保管など、物理的な作業スペースや調整コストも発生しやすく、全体の効率を圧迫する要因とされています。
手作業中心による生産性の低下
キッティングの大部分を手作業に頼っている限り、生産性の向上には限界があります。
開梱、OS設定、アプリケーションインストール、動作確認といった工程をすべて手作業で行うため、担当者ごとの作業スピードや精度にばらつきが生じるでしょう。自動化やテンプレート化が進まない場合、処理台数の増加に対応できず、作業工数や人件費が膨らんでしまいます。
さらに深刻なのは、設定ミスが許されないというプレッシャーと高い集中力の要求により作業負担が蓄積し、結果的に品質低下を招くリスクもあります。
属人化による品質・進行リスク
見落とされがちなのが、キッティングの属人化という問題です。
属人化とは、特定の担当者しか対応できない状況のことで、不在や退職のときに業務が停滞し、納期や品質維持に支障をきたすリスクを生みます。マニュアルや手順書が整備されていないケースでは、担当者間で作業手順が統一されず、トラブル対応にも時間がかかってしまいます。
作業者間のスキル差により品質にばらつきが生じることも少なくありません。スキルレベルが十分でない場合、確認工数が増え、結果として全体の作業効率低下にもつながるでしょう。
キッティング効率化が企業にもたらすメリット
キッティングには短納期対応や属人化、手作業による生産性の低下といった課題があるため、効率化すれば以下のようなメリットを得られます。
- 作業時間の短縮と人的リソースの最適化
- 設定ミスの減少によるセキュリティ強化
- 品質の均一化による運用・管理の安定化
- 人件費や運用コストの最適化
作業時間の短縮と人的リソースの最適化
キッティングを効率化することで、1台あたりの作業時間を大幅に削減できます。
手作業で行うと1台あたり数時間かかっていた作業が、クローニング技術や自動化ツールを導入することで数十分に短縮可能です。時間短縮による年間の総工数削減で人件費の削減も期待できます。
また、大量キッティング時の納期短縮も実現できるため、新入社員の入社日や新拠点の開設日に対応しやすくなります。
キッティングに費やしていた時間を、セキュリティ強化やシステム企画といった付加価値の高い業務に充当できれば、企業全体の生産性や競争力の向上にもつながるでしょう。
設定ミスの減少によるセキュリティ強化
標準化・自動化によるヒューマンエラーの低減は、企業の情報資産を守るうえで重要な要素です。手作業で何十台ものPCを設定していると、どうしても設定漏れや入力ミスが発生してしまいます。
しかし、マスターイメージを作成してクローニングや自動化ツールを活用すれば、すべてのPCに同じ設定が適用されるため、作業ミスを削減できるでしょう。また、マニュアルとチェックリストを整備し、各工程で確認を行うことで、ウイルス対策ソフトのインストール漏れや暗号化設定の失念といった致命的なミスを防げます。
トラブル発生件数の減少と手戻り作業の削減により、企業全体のセキュリティレベルを継続的に向上させることができます。
品質の均一化による運用・管理の安定化
キッティングを効率化することで、すべてのPCを同一品質で設定でき、安定的な運用・管理を実現できます。
標準化された設定で端末間の機能差を解消できるため、トラブル発生時の原因も迅速に究明することが可能です。ソフトウェアのアップデートやセキュリティパッチの適用も、すべてのPCが同じ構成であれば一括で実施できるので、作業効率が向上するでしょう。
情報セキュリティの観点では、すべての端末が企業のセキュリティポリシーに準拠していることを保証できるため、監査対応もスムーズに行えます。万が一、セキュリティインシデントが発生した場合でも、同じ設定であれば影響範囲の特定や対策も迅速に実施できます。
人件費や運用コストの最適化
企業全体のコスト最適化もキッティングの効率化がもたらすメリットの一つです。
自動化やクローニングの活用により通常の勤務時間内で作業が完了すれば、時間外労働や割増賃金の発生を抑えられます。浮いた人員を営業活動や研究開発などのコア業務に再配置することで、企業全体の価値向上にもつながるでしょう。
また、効率化によるヒューマンエラー防止の実現で手戻り作業が減少すれば、再設定にかかる時間やユーザーサポートの工数などを削減できます。
結果としてコストの最適化と企業価値向上の両方を実現することが可能です。
キッティングを効率化する方法
キッティングの生産性を向上させることで、上述したようにリソースとコストの最適化や品質の均一化などさまざまなメリットを得られますが、アプローチの手段は多岐にわたります。
キッティングを効率化する主な方法は、以下のとおりです。
- 作業手順の標準化・テンプレート化
- 作業スケジュールの最適化
- 自動化・MDMツールの導入
- クローニング技術の活用
- IT資産管理ツールとの連携
なお、上記のような自社内での業務改善とは別に、外部リソースを活用する方法もありますが、ここでは主に社内対応で効果的な手法を紹介します。
作業手順の標準化・テンプレート化
キッティング作業を効率化する第一歩は、作業手順の標準化とテンプレート化です。
標準作業手順書を作成することで、誰がキッティング作業を担当しても同じ品質を保てるようになります。記載内容は、開梱から引き渡しまでの全工程の手順、確認ポイント、トラブル時の対処方法、使用するツールやソフトウェアの一覧などです。
ウイルス対策ソフトのインストール漏れや、セキュリティ設定の失念といったミスを防ぐには、各工程ごとにチェック項目を設け、完了時に必ず確認する仕組みを整えることが重要です。
設定テンプレートの作成と管理方法も効率化の鍵です。よく使用する設定値をテンプレート化しておくことで、毎回同じ設定を手入力する手間が省けます。
作業スケジュールの最適化
キッティング作業の効率化において見落とされる傾向にあるのが、作業スケジュールの最適化です。
トラブル発生時の対応時間を見込んだ計画立案が重要なため、全体の作業時間の一定割合をバッファとして確保しておきましょう。
複数人での作業分担とコミュニケーション体制の構築も重要です。開梱担当、設定担当、確認担当といった役割分担を明確にし、進捗状況を共有する仕組みを整えることで、作業の滞りを防げます。
また、段階的な作業進行とマイルストーン設定も効果的です。たとえば、まず全体の1割を完了させて動作確認を行い、問題がなければ残りの作業に取り掛かるといったアプローチを取ることも有効でしょう。小さくステップを踏むことで、大規模な手戻りを防止できます。
自動化・MDMツールの導入
大規模なキッティング案件では、自動化・MDMツールの導入が効果を発揮します。
MDMとは、PCやスマートフォン、タブレットなどの企業のデバイスを一元管理するための仕組みです。代表的なツールとしては、Windows Autopilot、Microsoft Intune、Omnissa Workspace ONEなどが挙げられます。
自動化により、OS設定やアプリ配布、ポリシー適用を一括実行でき、PCをネットワークに接続するだけで必要なアプリケーションのインストールやセキュリティ設定が自動で反映されます。
ツール選定時には、既存システムとの連携性、導入・運用コスト、サポート体制、将来的な拡張性などを総合的に評価しましょう。ツールの選定や設計段階では、システム構成管理に長けたインフラエンジニアが関与すると、運用面の安定化が期待できます。
クローニング技術の活用
クローニング技術の活用も大量キッティングの効率化に適しています。
クローニングとは、マスターイメージを複数のPCにコピーする技術のことです。代表的なソフトとしては、Symantec GhostやClonezillaなどが挙げられます。
メリットは作業時間の短縮と品質の均一化を実現できることです。手作業で1台ずつ設定していた作業を、クローニングを使えば数十台単位で同時に処理できるため、作業時間が大幅に短縮されます。また、同じマスターイメージから複製することで設定の差異が解消され、品質も安定します。
導入するときには、マスターイメージ作成後に少数の端末でテストを行い、問題がないことを確認してから本格展開に進むのが有効です。
IT資産管理ツールとの連携
IT資産管理ツールとキッティング作業を連携させることで、作業効率と管理精度が向上します。
たとえばインベントリ情報(※)を収集する場合、従来は手作業でExcelに入力していた情報を、ツールが自動的にデータベースに登録してくれます。PCのシリアル番号、購入日、保証期間、ソフトウェアのライセンス情報なども一元管理されるため、保守契約の更新漏れやライセンス違反のリスクも低減できるでしょう。
また、ネットワーク接続時に情報を自動登録できるほか、セキュリティ対策の適用状況も一目で確認できるため、脆弱性を素早く発見・対処できます。
(※)インベントリ情報:PC、サーバー、ソフトウェアなど企業や組織が保有するIT資産の詳細なデータ
キッティングの主な委託先
前章で紹介した効率化の方法を実践しようとしても、スキル・人員の不足で実現できない場合もあります。社内対応が難しい場合は外注も視野に入れるのが得策です。
ここでは、主な委託先の特徴とメリット・デメリットを解説します。
キッティング代行
キッティング代行は、開梱から設定、配送まで一貫対応してくれる専門業者です。
日常的に大量のキッティングを行っているため、作業手順が確立されており、ミスが少なく高品質な仕上がりを期待できます。
代行業者選定時のポイントは、実績、セキュリティ体制、納期対応力の3点です。実績については、自社と同規模の案件や同業種での対応経験を確認しましょう。セキュリティ体制については、情報セキュリティ認証の取得状況、作業場所の管理体制、機密保持契約の内容などを確認することが重要です。
納期対応力については、急な追加依頼や納期変更に対処できるかを事前に確認しておきましょう。
関連記事:キッティング代行とは?メリットや活用が適しているケースなどを紹介
PCレンタル・リース業者
端末の購入ではなくレンタルやリースを検討している場合、キッティングサービスが付帯する業者があります。
PCの調達からキッティング、配送までをワンストップで依頼できるうえに、購入費不要のため初期費用を抑えられる点もメリットです。月額料金制のため、キャッシュフローの改善にもつながります。
デメリットは、長期利用の場合は総コストが購入を上回る可能性があることです。レンタル・リース料金は月額制のため、契約期間が長期化すると、結果的に割高になるケースがあります。
また、カスタマイズの自由度が制限される点も注意が必要です。レンタル・リース業者が提供する機種やスペックの範囲内での選択となるため、自社の要件に合致しないことがあります。
SES
SES(システムエンジニアリングサービス)は、高度な技術力をもつエンジニアに作業を委託できるサービスです。
メリットは、専門性の高い技術者を活用できる点です。キッティングに加えてネットワーク設定やサーバー構築などの周辺業務にも対応でき、技術的な問題が発生したときにも迅速に解決できます。
デメリットは、コストが高いことです。SESはエンジニア単価に加えて、管理費などの中間コストも加算されます。そのため、小規模案件では費用面で見合わない場合があります。また、SESは通常1~3か月単位の契約を前提としているケースが多いので、数日から数週間程度のスポット案件には適していない可能性が高いです。
関連記事:インフラエンジニアのSES採用とは?フリーランスとの比較も解説
派遣
派遣スタッフを活用することで、必要な期間だけ人員を確保してキッティング作業を進める方法もあります。
メリットは自社に指揮命令権があり、細かい指示が可能なことです。SESと異なり、派遣スタッフに対して直接指示を出せるため、自社の作業手順やルールに沿ってキッティングを進められます。
デメリットとしては、派遣スタッフのスキルに個人差がある点が挙げられます。派遣会社が紹介するスタッフのIT知識やキッティング経験のレベルはさまざまなので、事前にスキル要件を明確に伝えることが重要です。
また、自社の作業手順やシステム環境について教育が必要になるため、即戦力として期待できない場合もあることに注意が必要です。
関連記事:インフラエンジニアを派遣会社で採用するメリット|他の契約との違いも解説
フリーランス
フリーランスは、企業と業務委託契約を結んで案件を請け負う人材のことです。
契約の柔軟性がおおきな魅力で、必要な時期だけスポット依頼や小ロットでも対応できます。報酬もキッティングの難易度や期間に応じて提示できるため、コストを最適化しやすくなります。
また、キッティングだけでなく、ネットワーク設定やサーバー構築などの関連業務にも対応できる人材が多いのもメリットです。将来、ほかの業務を依頼するときにも相談しやすくなるでしょう。
一方で、フリーランスにおいても個人によってスキルや対応範囲が異なるため、契約前に実績や得意分野をしっかり確認しておくことが重要です。
「導入台数は少ないが納期が迫っている」「今後のインフラ環境整備を見越して依頼したい」という企業に有効です。
関連記事:インフラエンジニア案件をフリーランスに業務委託する方法とメリットを解説
キッティングの効率化をフリーランスに依頼するならクロスネットワークにご相談を
本記事では、キッティングの効率化が重要な理由と具体的な方法について解説しました。
自動化・連携ツールの導入や作業マニュアルの整備などで、キッティングの効率は飛躍的に向上します。さらに作業計画も入念に策定すれば、万が一の遅延や要員の減少にも迅速に対応できるでしょう。
一方で、自社人材のスキル・要員不足で効率化が難しい場合もあります。セキュリティポリシーや端末管理に関する高度な設定などが伴う場合、インフラエンジニアとしても知見が必要なケースもあるため、外部委託も視野に入れるとよいでしょう。
委託先を選ぶときには自社の要件(PCの導入規模・予算など)に適しているか精査する必要があります。とくに契約の柔軟性、対応スピード、コストを重視したい場合はフリーランスエンジニアの活用が効果的です。
クロスネットワークでは、キッティングの効率化にも精通したフリーランスのインフラエンジニアを迅速にマッチングいたします。プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。
クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の依頼にも対応しているので、解決したい課題やご要望に応じて柔軟な外注をサポートいたします。
サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。インフラ構築に課題があるなら、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

新卒で大手インフラ企業に入社。約12年間、工場の設備保守や運用計画の策定に従事。 ライター業ではインフラ構築やセキュリティ、Webシステムなどのジャンルを作成。「圧倒的な初心者目線」を信条に執筆しています。