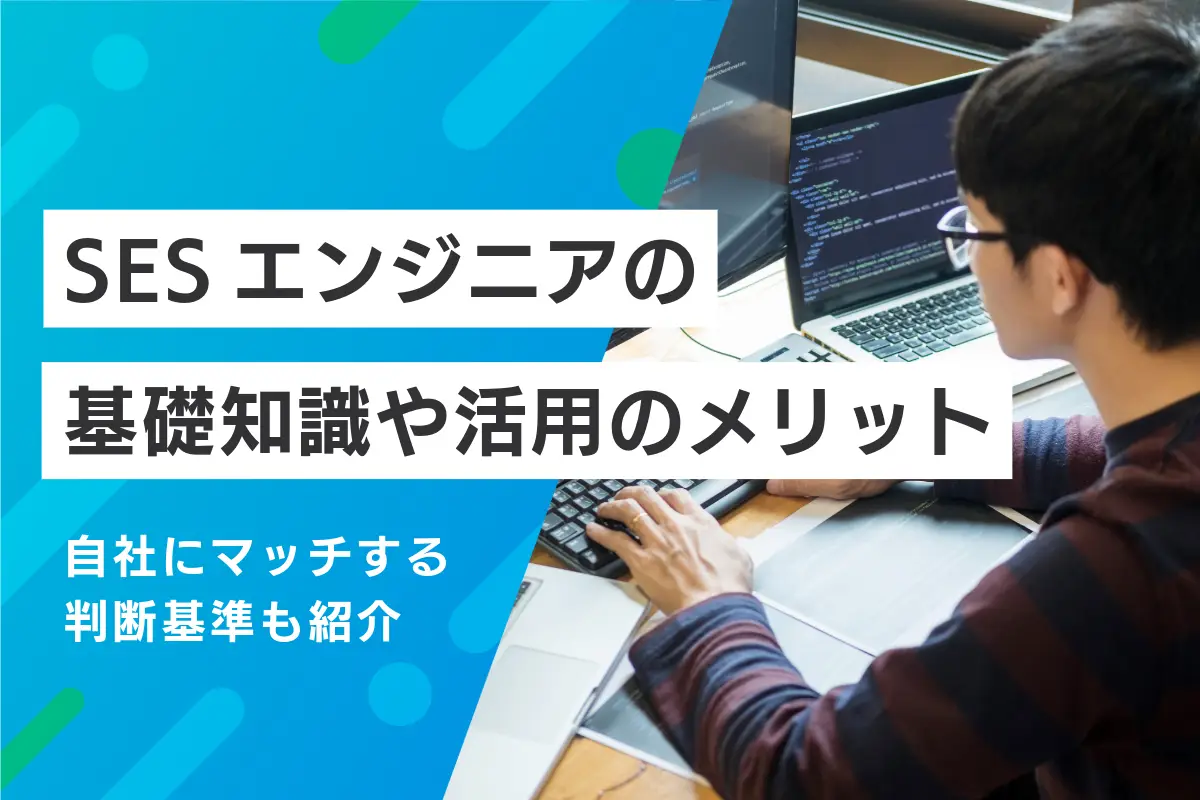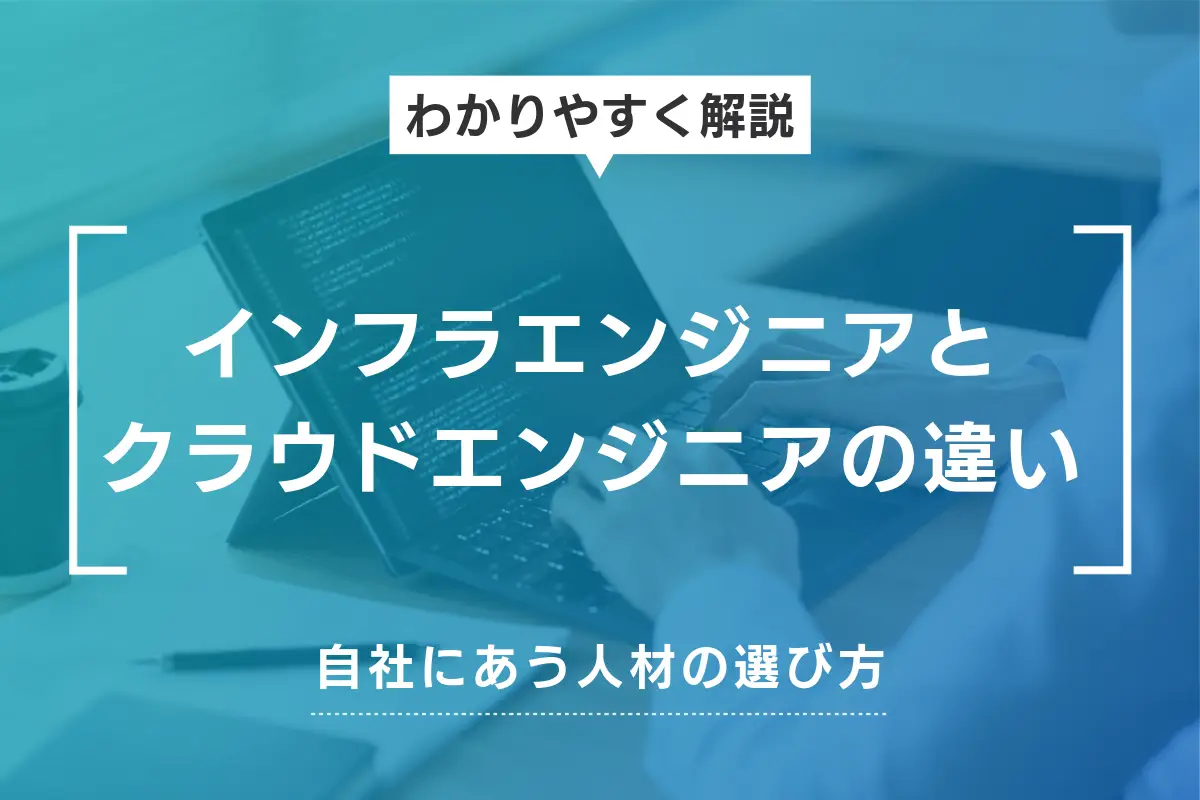ITインフラを安定稼働させるうえで、ネットワークの品質は重要です。近年は既存インフラの改修やDX化の加速により、ますますネットワークの質が企業活動の生産性に影響するでしょう。
自社でも社内ネットワークの刷新に向けた動きが活発になるなかで「どうやってネットワークを構築すれば良いかわからない」と悩む企業も多いです。多額の資金を投入して失敗するような事態は避けたいでしょう。
そこで、本記事では以下の内容について解説します。
ITインフラにおけるネットワークの構成要素
ネットワーク開発の流れ
ネットワーク開発に必要な知識・人材
ネットワーク開発の注意点
本記事を最後まで読めば、一からネットワークを構築、もしくは改修するために必要な物と流れを理解し、自社で対応可能か判断できます。新規のネットワーク構築や既存ネットワークの保守にお悩みの中小企業経営者は、参考にしてください。
ITインフラのネットワークとは?
ITインフラにおけるネットワークとは、PCやタブレットなどのIT端末を使って情報のやり取りができる通信環境のことです。
ネットワークの規模や種類は多岐に渡ります。たとえば、家庭のネットワークであればWi-Fiルーターを介してインターネットを使うことができますが、企業では多くのPCやサーバーが複雑に接続されて成り立っています。このネットワークがインターネットに接続されていることで、世界中のどこにいても情報のやり取りが可能になっているのです。
ネットワークの技術は急速に進歩しており、クラウドや5G、IoTなどその種類もさまざまです。このように企業活動を支えるうえで、ネットワークは不可欠と言えます。
ネットワークとインフラの違い
ネットワークと混同されやすい用語としてインフラが挙げられます。両者の違いを下の表にまとめました。
ネットワーク | 専用端末で情報をやり取り、共有できる状態のこと |
インフラ | 人々の生活を支えるための基盤 |
ネットワークとは、情報のやり取りやデータの共有、コミュニケーションが取れるよう相互に接続されている状態のことです。一方、インフラとは日常生活を支える基盤そのもののことで、ガスや電気、水道、交通機関など対象は多岐に渡ります。つまり、インフラがネットワークを内包していると言えます。
ITインフラのネットワークは主に4種類
ITインフラで使われるネットワークは主に次の4種類です。
LAN
WAN
イントラネット
インターネット
LAN
出典:総務省
LANとはLocal Area Networkの略で、家庭やオフィスなど限られたエリアで利用できるネットワークのことです。比較的狭い場所に設けられ、オフィスであればPCやプリンター、タブレットなどの機器に接続して利用します。
LANは下の表のように有線と無線の2つに分けられます。
比較項目 | 有線LAN | 無線LAN |
通信状態・速度 | 安定 | 時々不安定 |
セキュリティ | 強い | 有線と比べて弱い |
設置のしやすさ | ケーブルが多い | ルーターのみで良い |
有線LANの特徴は通信速度や接続状態が安定していること。セキュリティも比較的強く、企業のLANで重宝されています。一方で多くのケーブルを必要とするため、導入の負担がおおきいことに注意が必要です。
無線LANは電波の届くところであればどこでも通信できるので、工場のような移動の多い場所でネットワークを使うときに便利です。設定もルーターの設置のみで使えることが多く、手軽に導入したい企業におすすめ。ただし悪意ある第三者から通信を傍受されるリスクがあるので、入念なセキュリティ対策が必要です。
WAN
出典:東京情報大学
WANとはWide Area Networkの略で、広範囲のエリアを跨ぐネットワークのことです。上の図のように遠隔地同士のLANを接続するために使われ、WANの構築・管理は主に通信キャリアが担っています。
WANと混同されやすいのがインターネットですが、両者の違いは対象ユーザーが変わること。インターネットは端末とネットワークがあれば誰でも利用できますが、WANは特定の組織のユーザーしかアクセスできません。
そのため「機密情報を別の事業所に送りたい」「出張先から社内の資料を参照したい」という場合にWANを利用する企業が多いです。
イントラネット
イントラネットとは直訳すると「内部ネットワーク」と呼ばれ、特定の組織内で利用できるネットワークのことです。顧客情報や社内資料など社外に知られたくない情報を安全にやり取りできます。
イントラネットはインターネットと同じ技術を使っているため、安価かつ短期間で導入することができます。また、アプリやデータベースとも容易に連携できるため、ネットワーク構築の難易度が下がる点も魅力です。
インターネット
インターネットは世界中のネットワークと結びついたネットワークです。インターネットサービスプロバイダー(ISP)を経由して、世界中のあらゆる情報を参照できたりコミュニケーションを取ることが可能です。
遠隔地と接続できる点ではWANと同じですが、両者の違いはアクセスできる範囲にあります。WANは特定の組織でのみ利用できますが、インターネットは端末があれば誰でもアクセスできるのが特徴。
そのためセキュリティ上のリスクが高まりますが、近年ではWebブラウザ側でのセキュリティ対策も強化されています。LANやWANと比べて低コストかつ手軽に導入できるので、スピード勝負のベンチャー企業で組織的に利用しているケースが増えています。
ITインフラにおけるネットワークの構成要素【ハードウェア】
ネットワークでは、さまざまな役割を持った機器が複雑に接続されています。
ここでは、ネットワークで主に必要なハードウェアを紹介します。
PC・タブレットなどの端末
ルーター
スイッチ
ケーブル
PC・タブレットなどの端末
ネットワークで情報をやり取りするためにはPC、タブレットなどの端末が欠かせません。端末の性能は快適にネットワークを使えるかどうかに影響するため、慎重に選ぶ必要があります。
業務用にPCを選ぶポイントは下のとおりです。
保証の期間:一般的には1年程度で法人向けだと3~5年の商品も充実
OSのエディション:ドメイン参加(※)や暗号化機能、リモートデスクトップなど
必要なスペック:グラフィック用なら高スペック、事務作業用なら標準レベルなど
必要な端末は使用目的、用途によって異なります。何のために端末を使うのか明らかにしてから選定しましょう。
※ドメイン参加:ドメイン内の他の端末と共通のアカウント情報や権限を使えること
ルーター
ルーターとは、複数の端末をネットワークに接続する装置のこと。
ネットワークの最適経路を導き出す「ルーティング」と、データ通信の可否を決める「フィルタリング」の2つの機能を搭載しています。つまり、ルーターのおかげで正しいデータを安全にやり取りできるのです。
ルーターを選ぶ主なポイントは以下のとおりです。
ルーターの通信速度:回線の最大通信速度にあわせること
使用環境:戸建て用、マンション向けなど
機器の台数:接続可能数を超えると通信速度が落ちる
なお、無線ルーターを使う場合は設置個所に注意が必要です。コンクリートや木材などの遮蔽物が近くにあると電波が不安定になるため、オフィスの中央や天井近くに置くのがおすすめ。通信の安定性を優先する場合は有線で接続しましょう。
スイッチ
出典:ヤマハネットワーク製品
スイッチとは、受信したデータを特定の相手に送る装置のことです。どのデバイスがどのポート(通信の出入り口)に接続しているか記録しており、その情報を元に必要なデータを送ることができます。
近年は、L3スイッチと呼ばれるルーターとスイッチの両方の機能を搭載したスイッチも普及。デバイス間だけでなく、ネットワークを介したデータ転送も可能なため、大規模ネットワークやデータセンターなどでも利用されています。
ケーブル
出典:StarTech
有線、無線に関わらず、ネットワークを構築するためにはケーブルが必要になります。データの送受信手段として重要な役割を果たし、通信品質に直結します。主に使われるケーブルは下の表のとおりです。
ケーブルの種類 | 特徴・用途 | |
ツイストペアケーブル (LANケーブル) | UTP | 比較的低コスト |
STP | 外部ノイズを遮断 | |
光ファイバーケーブル | SMF | 長距離の高速通信が可能 |
MMF | 短距離の高速通信が可能 | |
ネットワークを構築するときには、伝送距離や速度、費用、配線環境などを考慮してケーブルを選ぶ必要があります。
ITインフラにおけるネットワークの構成要素【ソフトウェアなど】
ネットワークはハードウェアだけでは機能せず、それらを動かすソフトウェアが不可欠です。ここでは、ネットワークで主に必要なソフトウェアを紹介します。
サーバー
ネットワークOS
ミドルウェア
ファイアウォール
ロードバランサー
サーバー
サーバーとはユーザーのリクエスト(要求)に対し、ネットワーク経由で何らかのサービスを提供するコンピューターのことです。主なサーバーの種類は下のとおりで、ソフトウェアとして機能しています。
サーバーの種類 | 概要・特徴 |
Webサーバー | WebアプリケーションやWebサイトを提供 |
メールサーバー | メールのやりとりを担うサーバー |
アプリケーションサーバー | クライアントのリクエストに応じてアプリケーションを実行 |
データベースサーバー | リクエストに従いデータの更新、追加、削除などを行う |
ファイルサーバー | 同一ネットワーク内の他者とファイルを共有するサーバー |
サーバーはネットワークの中核的な役割を果たし、ITサービスを提供し続けるうえで不可欠です。
ネットワークOS
ネットワークOSとは、ルーターやスイッチなどの機器で使用するOSで、ベンダーが自社の機器とあわせて販売しているケースが一般的です。
代表的なネットワークOSとして、シスコシステムズ社のIOS、XE、XR、NX-OSなどが挙げられます。これらのOSは、運用コストの削減やネットワーク要件に準じた設計ができるほか、拡張性にも優れています。
また、近年ではネットワークOS単体でも販売されており、OSをもたないホワイトボックススイッチとかけ合わせ利用する企業も多いです。
ミドルウェア
ミドルウェアとは、アプリケーションとOSの中間に位置するソフトウェアです。アプリケーションは特定の目的に特化したソフトウェアで、チャットツールや経理、文章作成などその種類は多岐に渡ります。
一からアプリケーションを開発するとおおきな手間になるため、データやネットワークへのアクセスなどの汎用機能を提供する役割をミドルウェアが担っているのです。
またシステムの負荷分散や冗長性を確保できる点も特徴で、運用効率を上げることができます。
ファイアウォール
出典:総務省
ファイアウォールとは防火壁と訳され、上の図のように外部からの不審なアクセスを遮断することができます。ファイアウォールは、ルーターに内蔵されていたりプロバイダ―の契約者を対象に機能を提供していたりします。
ただし、ファイアウォール単体で不正アクセスを防ぐのは難しいのが現状です。そのため、ファイアウォールの二重設定や通信の暗号化など、ほかのセキュリティ対策と組み合わせて利用するのが一般的です。
ロードバランサー
ロードバランサーとは負荷分散装置と呼ばれ、外部からの通信を複数のサーバーに分散する役機能をもっています。具体的には一時的にアクセスを集約して、リソースに余裕のあるサーバーへ優先的に接続します。
ロードバランサーを使う理由は、特定のサーバーへの過集中を防ぐためです。たとえば、一つのサーバーで社内ポータルを運営すると、大量のアクセスが集中したときに処理速度が低下する恐れがあります。最悪の場合はサーバーダウンに繋がるでしょう。
サーバーを増築するのはシンプルな手段ですが、リソースの使用効率が悪くなる恐れがあります。複数のサーバーで負荷を振り分けるために、ロードバランサーが必要なのです。
ITインフラのネットワーク開発フロー
ネットワークの構造は大規模かつ複雑になりやすいので、然るべきステップを踏まなければいけません。ここではネットワーク開発のフローについて解説します。
企画
設計
構築
テスト
運用保守
企画
まず、どのようなネットワークを作りたいのか企画しましょう。下のように自社の現状と理想を踏まえて構築の目的を言語化します。
新たに工場を建設するのでWANとLANを施設したい
オフィスを増築するのでLANを拡張したい
既存ネットワークのコストを削減したい
新しい工場にネットワークを新設するのであれば、工場内だけでネットワークが完結すれば良いのか、一部のPCだけWANに接続すれば良いのかなど方向性を決めやすくなります。オフィス増設でLANを拡張するのであれば、機材選定だけに注意すれば良いかもしれません。また、既存ネットワークのコストカットが優先であれば、クラウド移行が候補として有力です。
このように企画段階で方向性を決めて、各工程スケジュールも決めます。
設計
企画で構築目的が固まったら設計に移行します。設計とはネットワークを実装するための大枠を決めるフェーズです。具体的には、下のようなネットワーク構成図を作成して、各機器の役割と接続関係を定義します。
出典:東北大学
また、ネットワーク機器の選定も設計の重要な業務。端末の機種やハードディスクの容量、CPUの性能などを検討し、メーカーや商社に見積りを出します。ネットワーク機器は構築コストを左右する要素なので、過不足なく調達しなければいけません。
なおスムーズに設計するために、過去の事例を参照するケースが多いです。ネットワーク設計はある程度パターン化されており、過去の設計物を流用できることもあるからです。
必要な機器とネットワーク構成を決めて、作業手順書を作成したら構築に進みます。
関連記事:ITインフラの設計とは?構築との違いと流れ・外注のポイントを紹介
構築
設計が完了したら現地でネットワークを施工します。
迅速に構築をするためには事前準備が欠かせません。構築作業は複雑になりやすいにもかかわらず、現地での作業時間が限られていることが多いからです。とくに既存ネットワークの切り替えとなると、現行のネットワークに影響のない時間帯でしか施工できません。
主に事前準備でやることは以下のとおりです。
使用予定の機器で仮設定
遠隔地同士で通信テスト
作業計画書に役割分担、作業手順、制限時間を明記
当日は作業計画書に沿って決められたとおりに機器の設置、配線、セットアップなどをします。なお、イレギュラーが発生した場合には影響レベルと残りの作業時間を加味して、工事の続行、もしくは中止・延期すべきか判断します。
関連記事:ITインフラの構築とは?設計との違いと流れ・外注のポイントを解説
テスト
構築が完了したら、設計どおりに稼働するか以下の流れでテストします。
- 単体テスト:起動、ログイン、VPNへの接続など装置単体の機能を確認
- 結合テスト:多くの装置を接続して通信の可否、セキュリティ設定などを確認
- 切り替え準備:新規ネットワークへの移行計画、手順を策定
ネットワークの規模にもよりますが、テストスケジュールは1時間単位で組まれることが多いです。結合テストもクリアしたら新規ネットワークへ切り替えします。
また、万が一切り替えがうまくいかなかった場合、タイムリミットを決めて切り戻しの判断もしなければいけません。
運用保守
ネットワークを構築したらそれで終わりではなく、むしろ運用保守からが本番です。運用保守とは、ネットワークが安定稼働できるよう監視やソフトウェア、ソフトウェアの改修を行うことです。
主な業務内容を下の表に記載しました。
主な運用保守業務 | 概要特徴 |
オペレーション | ユーザーIDの付与、管理職の権限更新など |
構成管理 | ネットワーク構成図、設計書の改訂など |
障害監視 | 障害の有無を監視 |
性能監視 | 通信量の監視 |
トラブル対応 | 不具合の原因調査、復旧、恒久対策の立案など |
問い合わせ対応 | ユーザーからの質問に対応 |
一般的に、オペレーションや構成管理などの定例作業はリリース前から業務内容を固めます。また、トラブル対応や問い合わせ対応は同時多発的に発生することもあり、ネットワークに影響のある案件から優先的に対応しなければいけません。
運用保守はネットワーク全体の理解に繋がることとルーティン作業が主であることから、未経験者に任せることも多いです。ただし、保守は未知のトラブルに対応することもあるため一定数の経験者を確保することも重要です。
関連記事:ITインフラ運用とは?仕事内容や保守との違い・外注のメリットについて解説
ITインフラのネットワーク開発に必要な専門知識
ネットワークは高度化・複雑化しており、必要な知識も多岐に渡ります。ここではネットワーク開発に必要な専門知識を紹介します。
ネットワーク
セキュリティ
クラウド
5G
IoT
ネットワーク
当然ですが、ネットワークに対する深い理解が必要です。とくにネットワーク機器の設定、操作スキルは不可欠。一口に機器設定と言っても、製品によって仕様や役割は異なるため、各製品の特徴にも精通していることが理想です。
ネットワーク機器で高いシェアを誇っているのがシスコシステムズ社で、多くの企業で利用されています。具体的にどの機器を使うかはプロジェクトの規模や構築目的によって異なります。シスコシステムズ社運営の認定資格で知識を補うと良いでしょう。
未経験者であれば、実機を使ってネットワークを構築した経験があると、今後のネットワークスキル向上に期待できます。
関連記事:ネットワークエンジニアに必要なスキルとは?勉強方法やおすすめの資格も紹介
セキュリティ
安全なネットワーク構築においてセキュリティの知識は不可欠です。ネットワークは外部に接続されており、悪意ある第三者のターゲットになっているからです。
下のグラフは、情報通信研究機構(NICTER)が観測したサイバー攻撃関連の通信数を表しています。2015年~2023年の間で観測数が約10倍近く急増しました。
出典:総務省
サイバー攻撃を許すと、機密情報の盗難やデータの改ざん、ポータルサイトの閉鎖など深刻な被害が発生します。過去にはデータベースのセキュリティ対策を怠ったせいで顧客のクレジットカードが不正利用され、訴訟沙汰に発展した事例もあります。
ネットワーク構築で求められる主なセキュリティ対策を下の表にまとめたので、基礎だけも押さえておきましょう。
主なセキュリティ対策 | 概要・特徴 |
ウイルス対策ソフトの導入 | 無償で利用できるソフトもある |
ファイアーウォール | 外部からの不審なアクセスを遮断 |
IPS・IDS | 不審な通信を検知・遮断し管理者に通知 |
データ・通信の暗号化 | データを第三者に解読できない文字列に書き換えること |
セキュリティパッチの適用 | ソフトウェアの脆弱性を修正するソフトウェア |
システムのアップデート | 端末やソフトウェア、OSを最新の状態に保つこと |
認証技術の導入 | システムユーザーが正当な対象者なのか判別できる |
フィルタリング | 条件を付けて通信をふるいにかけること |
多層防御 | 複数の防御手法を使って攻撃のハードルを上げること |
関連記事:ITインフラにおけるセキュリティとは?重要性と企業の被害事例・対策も解説
クラウド
クラウドとは、ネットワーク経由でコンピューターリソースを使うシステムのことです。自社でサーバーやソフトウェアなどのリソースを保有しなくて良いため、安くかつ手軽に導入できる点がメリットです。
下の表は総務省の通信利用動向調査の結果で、2020年時点で企業の約7割がクラウドサービスを利用していると回答しました。出典:総務省
とくに、パブリッククラウドと呼ばれるクラウド事業者のサービスは、今後も普及すると予測されます。下に代表的なパブリッククラウドについてまとめました。
代表的なパブリッククラウド | 概要・特徴 |
AWS(Amazon Web Service) | IaaS(※1)をベースにサービスを提供 |
Microsoft Azure | 企業向けのセキュリティ機能が充実 |
Google Cloud | AIや機械学習など最先端の技術に対応 |
認定試験も実施しているので、導入予定のサービスにあわせて取得すると良いでしょう。人材採用のときにも求職者が関連資格を保有しているかチェックしましょう。
(※1)IaaS:コンピューターリソースやネットワークを提供するサービス
(※2)オンプレミス:自社でITリソースを保有すること
5G
5Gとは第5世代移動通信システムと呼ばれ、これからのデータ通信を大きく変える通信規格として期待されています。普及率も顕著で、2019年~2022年の間に日本の5G基地局(マクロセル)の市場規模は約10倍に増加しました。出典:総務省4Gより高速・低遅延の通信を実現でき、接続可能台数も1㎞²あたり約100万台のポテンシャルを有しています。そのため、5Gによりストレスフリーな動画再生やVRの普及に拍車がかかるでしょう。
ネットワーク設計においても、5Gを見越したサーバー設計や端末の選定が求められるようになります。
IoT
出典:総務省IoT(Internet of Thing)とはモノとインターネットを繋ぐ技術のことです。これまでインターネットに繋がっていたのは、PCやスマートフォンのような電子端末が主流でした。しかし、上の図のようにIoTでは自動車や家電、工場機械などあらゆるモノがネットワークで制御されつつあります。
IoTのおかげで、多様なマシン・データの利活用が進んでいます。たとえばドローンで建造物の構造を調査したり、カメラで人の流動を予測したりなどです。モノとネットワークの通信量は比較的少ないですが、5Gを活用した多重接続で活用の幅を広げられるでしょう。ネットワークエンジニアは、接続対象のモノの特性や用途に応じてネットワークを設計するスキルが求められます。
ITインフラのネットワーク開発における注意点4つ
ここではネットワークを開発するときの注意点を紹介します。
開発の目的を明確にする
ネットワーク監視を疎かにしない
マニュアルを整備する
専門のエンジニアを確保する
開発の目的を明確にする
まず、何のためにネットワークを構築するのか明らかにしましょう。一口にネットワークと言っても目的・用途は多岐に渡ります。
工場内で使えるネットワークを新設したい
ネットワークの運用コストを3割削減したい
以前サイバー攻撃の被害に遭ったのでセキュリティを強化したい
工場でネットワークを構築するのであれば、場内で使えるネットワークと社外で通信して良いPCなどを検討する必要があります。工場の形態によっては汚れ・熱に強いハードウェアが要るかもしれません。
運用コストの削減が目的の場合、オンプレミスからクラウドへの移行が有効な可能性が高いです。セキュリティの強化であれば、ネットワーク構造は変えずに対策ソフトの導入から検討するという選択肢も考えられるでしょう。
このように、ネットワーク構築の目的によって以降の工程がおおきく変わります。
ネットワーク監視を疎かにしない
出典:Mackerelネットワークは24時間稼働しているため、いつ不具合やサイバー攻撃の被害に遭うかわかりません。金融や電力、鉄道など業種によっては24時間体制でエンジニアが常駐しなければいけない企業もあります。通信量やサーバーの負荷の増減など、少しの変化が不具合に発展することもあるので定期的に観測しましょう。
常に人を配置する余裕がないという企業は、上の図のような監視ツールの導入がおすすめです。あらかじめ異常を定義しておけば、人によって判断が異なるといったリスクも排除できます。
関連記事:ITインフラの運用自動化とは?重要性とメリット成功事例も紹介
マニュアルを整備する
どの社員でも一定水準の業務を遂行できるよう、マニュアルを整備することも大切です。具体的に作るべき主なマニュアルは下のとおりです。
マニュアルの種類 | 概要・特徴 |
設計・仕様マニュアル | 設計や詳細な機能についての資料をマニュアル化 |
運用マニュアル | ネットワークの監視、問い合わせ対応のマニュアル |
障害対応マニュアル | 障害発生時の初動や原因調査、復旧手順などを明記 |
なお、マニュアルは未経験者でも理解できるように作成しましょう。前提知識を明記して専門用語をなるべく使わないことが重要です。文章だけで伝わりにくい場合は図解や表、動画で補足するのも一つの手です。
また、マニュアルは完璧に作る必要はありません。業務のルールや手順は変わることがあるので、たたき台を作って運用しながら改善しましょう。
専門のエンジニアを確保する
ネットワークの構造は複雑かつ大規模になりがちなため、必要な知識、スキルも多岐に渡ります。
たとえば、ネットワークの構築において機器を選定するためには伝送距離や通信量の最大値、セキュリティ機能について理解しておかなければいけません。構築時もシミュレーション、トラブルシューティングの経験が求められます。
このような知識経験は一朝一夕で身に付くものではないので、専門エンジニアの助けが必要になります。
ITインフラのネットワーク整備は誰を採用すれば良い?
エンジニアに種類が多様化しており、それぞれに専門分野があります。ここではITインフラのネットワーク整備ができるエンジニアを紹介します。
ネットワークエンジニア
インフラエンジニア
クラウドエンジニア
ネットワークエンジニア
ネットワークエンジニアとは文字通り、ネットワークの要件定義から設計、構築、運用を担うエンジニアのことです。
ネットワーク要件に基づいてルーターやケーブル、サーバーなどの機器を選定し、構成図に基づいて構築します。リリース後はネットワークが安定して稼働できるよう管理、監視します。
また、5GやIoTなどネットワーク技術の変化が激しいのも特徴。クライアントのネットワーク要件も多様化しており、ニーズに応じた技術、通信規格を採用するのも仕事です。
関連記事:即戦力のネットワークエンジニアを採用するコツとは?採用率を高めるポイントも解説
インフラエンジニア
インフラエンジニアとは、ITインフラにまつわる業務全般を担うエンジニアのことです。具体的には、サーバーやデータベースの設計、構築、運用保守、セキュリティシステムの構築など多岐に渡ります。
ネットワークエンジニアと被る業務も多いですが、インフラエンジニアの方が守備範囲が広いのが特徴です。求められる知識・技術が幅広いため、人材不足が深刻化しているのも近年の傾向です。
プログラミング学習者メディアのプロリアプログラミングの調査によると、企業がIT人材不足と感じる職種の2位にインフラエンジニアが挙げられています。
出典:プロリアプログラミング
既存インフラの改修とDX化の加速、新技術の普及などで、今後もインフラエンジニア不足は進むでしょう。
関連記事:ネットワークエンジニアとインフラエンジニアの違いとは?採用ポイントも解説
インフラエンジニアの獲得には、正社員やフリーランス、派遣やSESなどさまざまな方法が挙げられますが、それぞれの違いがよく分からないという方も多いのではないでしょうか。以下の資料では、混同しやすい契約形態を比較・解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。
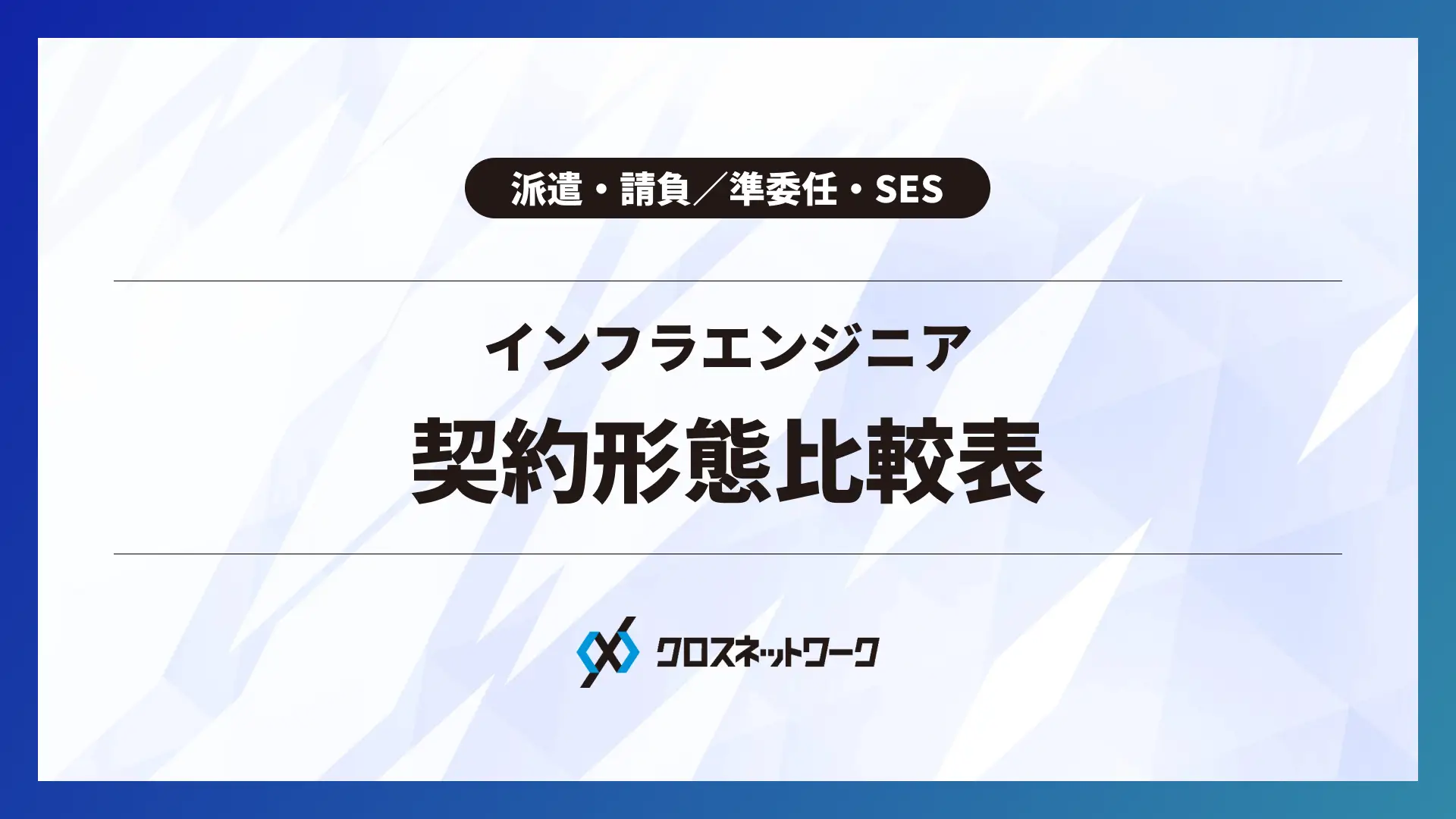
クラウドエンジニア
クラウドエンジニアとは、クラウド環境を活用してITインフラを設計、構築、運用するエンジニアのことです。クラウドは安価に環境を構築できる点から利用する企業も多く、とくにAWSやGoogle Cloudのようなパブリッククラウドを扱えるエンジニアの需要が高まっています。
また、オンプレミスとクラウドをかけ合わせたハイブリッドクラウドも多いです。リソースの分散や柔軟性の高いITインフラを構築できる反面、構成が複雑になりやすいのがネック。
いずれの環境にも精通できるよう、オンプレミスにも明るいクラウドエンジニアが求められています。
関連記事:ネットワークエンジニアとクラウドエンジニアの違いと課題別の適任者を解説
フリーランスのネットワークエンジニアに委託するメリット
昨今はエンジニア不足が深刻になっており、優秀な人材を採用するルートを確保しなければいけません。数ある採用手段のなかでフリーランスにを活用するメリットを解説します。
即戦力の専門人材を採用できる
正規雇用と比べて人件費が割安
柔軟にコミュニケーションを取りやすい
即戦力の専門人材を採用できる
即戦力のネットワークエンジニアを確保できるのは、フリーランスのおおきなメリットです。他の業界や企業で実務経験を積んでいるため、育成の手間がかからないからです。
企業側としてもプロジェクトに必要なスキルセット・経験を定めて募集できるのもポイント。契約してから「スキルが足りなかった」と後悔するリスクも抑えられます。
また自社にはない技術をもっている人材も多く、社内エンジニアの視野を広げるうえでもおすすめです。
正規雇用と比べて人件費が割安
正社員を雇用するより人件費を抑えやすいのもフリーランスの魅力です。フリーランスエンジニアとはプロジェクトベースで契約することが多く、依頼側の需要にあわせて要員を調整できるからです。
案件の報酬もエンジニアの経験年数、スキル、業務の難易度にあわせて設定できるのもポイント。また、フリーランスは福利厚生費用や社会保険がかかりません。育成にかかるお金も削減できるので、予算に制約がある中小企業にとって助けになるでしょう。
関連記事:フリーランスのインフラエンジニアと契約した場合の単価相場とは?|単価交渉のコツも解説
柔軟にコミュニケーションを取りやすい
コミュニケーションに柔軟性があるのも、フリーランスを活用する利点です。開発会社だと専用の窓口や営業部署を介することが多く、どうしてもコミュニケーションラグが発生します。
一方、フリーランスエンジニアは直接本人へ連絡できるため、やり取りがスムーズに進みやすいと言えます。また、工期の調整や急な仕様変更が発生しても、契約の範囲内なら臨機応変に対応してくれる人材が多いです。
開発会社だと社内規定により対応が難しい(もしくは遅れる)場合もあるので、融通の利く人材が欲しい方はフリーランスが適しているでしょう。
ただ、インフラエンジニアをフリーランスとして活用するだけでなく、正社員として採用するのも一つの方法です。それぞれのメリット・デメリットについて、事前に知っておくことが重要となります。
以下の資料では、インフラエンジニアの採用と外注について、メリット・デメリットなどを解説しています。インフラエンジニアを求めている企業担当者は、ぜひダウンロードしてみてください。
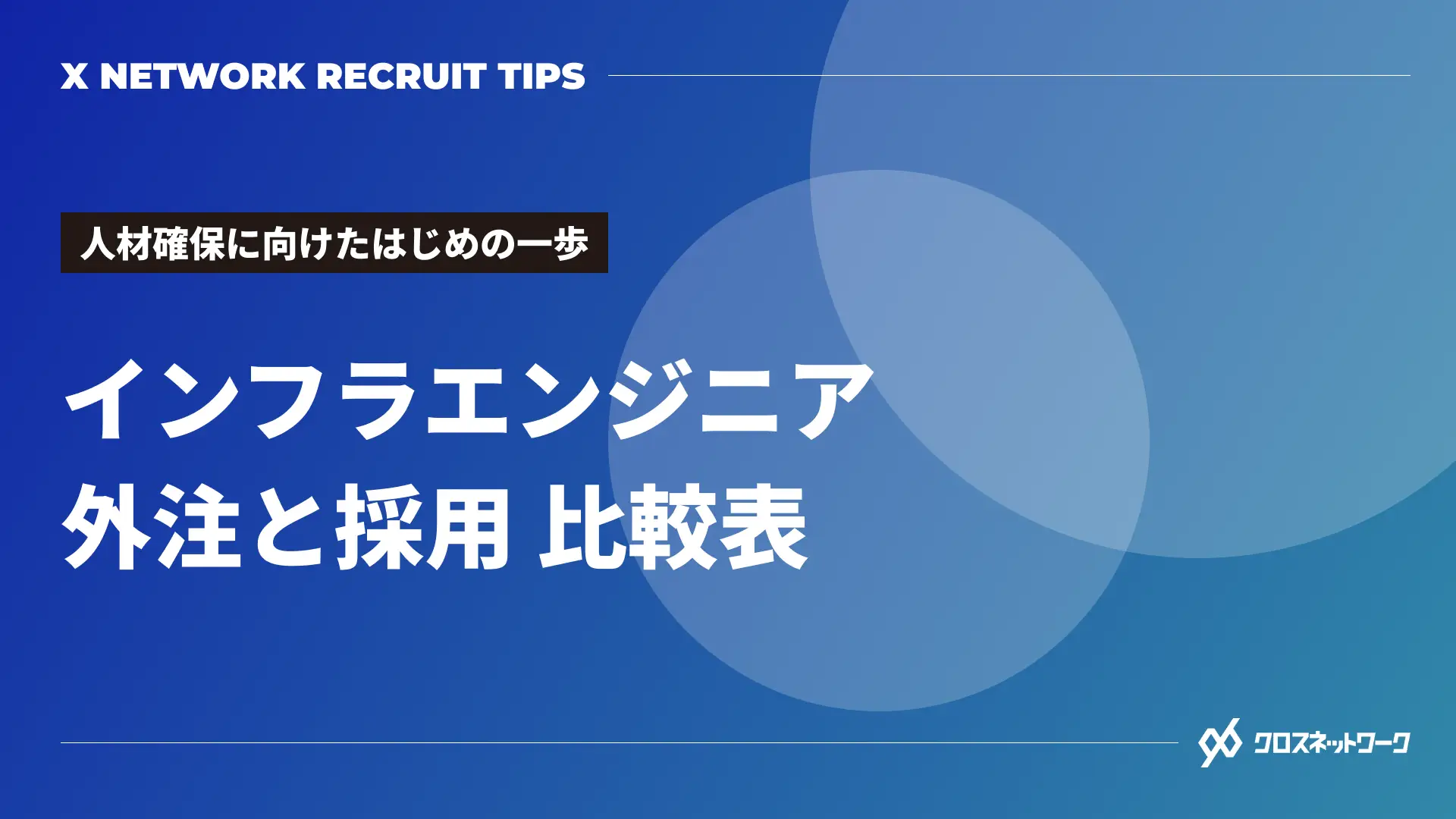
高スキルなネットワークエンジニアを探すならクロスネットワークにご相談を
本記事では、ITインフラにおけるネットワークの概要と構成要素、開発の流れ、注意点などについて解説しました。
DX化の流れで、企業のネットワークインフラは複雑化・多機能化しており、必要な構成要素も増えつつあります。また、然るべき手順を踏んで開発しないと、後に思わぬトラブルを呼ぶ可能性も否定できません。
しかし「自社に知見のあるエンジニアがいない」「開発会社に外注するとコストが高くなる」という企業もいるでしょう。コストメリットとネットワーク品質の両方を追求するなら、フリーランスエンジニアに委託するのがおすすめです。
優秀なネットワークエンジニアをお探しの方は、ぜひクロスネットワークにご相談ください。クロスネットワークはインフラエンジニア専門のエージェントサービスで、通過率5%と厳しい審査に合格した人材のみ在籍しています。ネットワーク開発と最新技術に長けたエンジニアを、クライアントの要望にあわせてスムーズにマッチングします。
採用後のやりとりもサポートしますので、トラブルを回避できるのもメリット。さらに、登録しているインフラエンジニアと合意があれば、正社員登用もできます。
エージェントに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週3日程度の依頼も可能なので、自社の必要リソースにあわせて柔軟に外注できます。
こちらよりサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力のインフラエンジニアをお探しの方は【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

新卒で大手インフラ企業に入社。約12年間、工場の設備保守や運用計画の策定に従事。 ライター業ではインフラ構築やセキュリティ、Webシステムなどのジャンルを作成。「圧倒的な初心者目線」を信条に執筆しています。