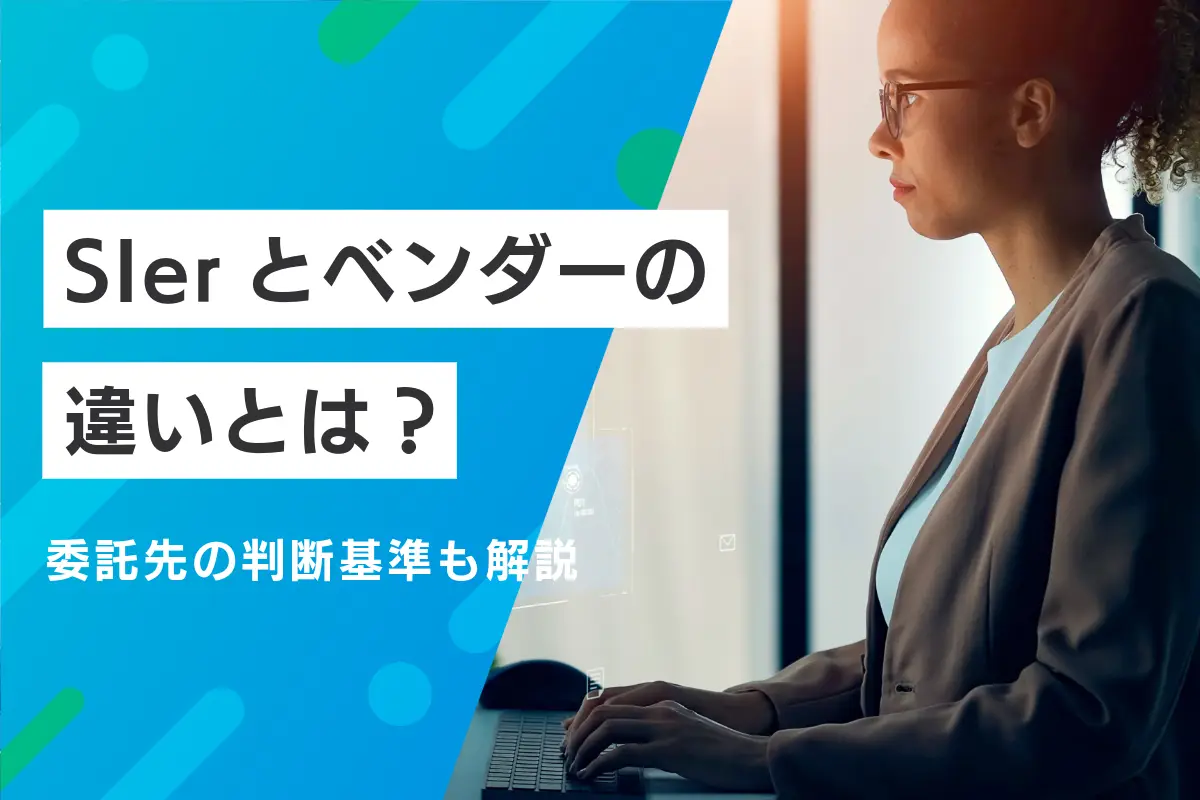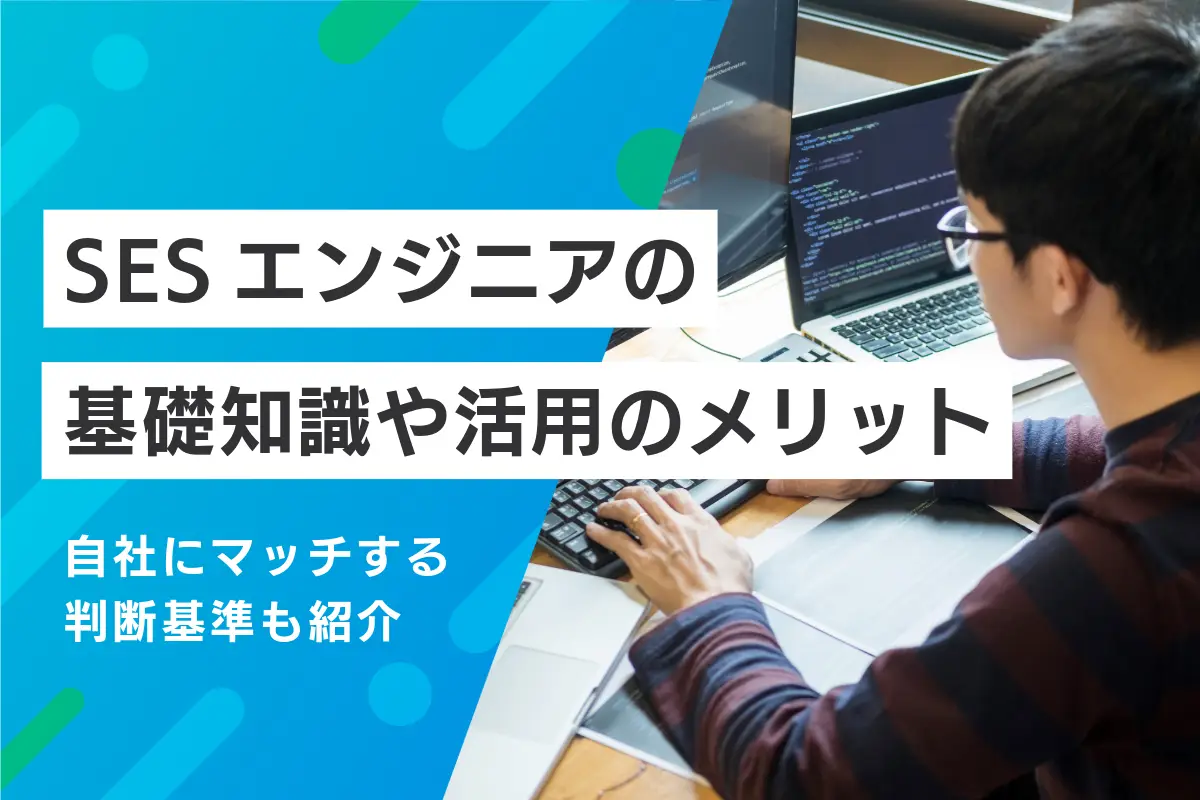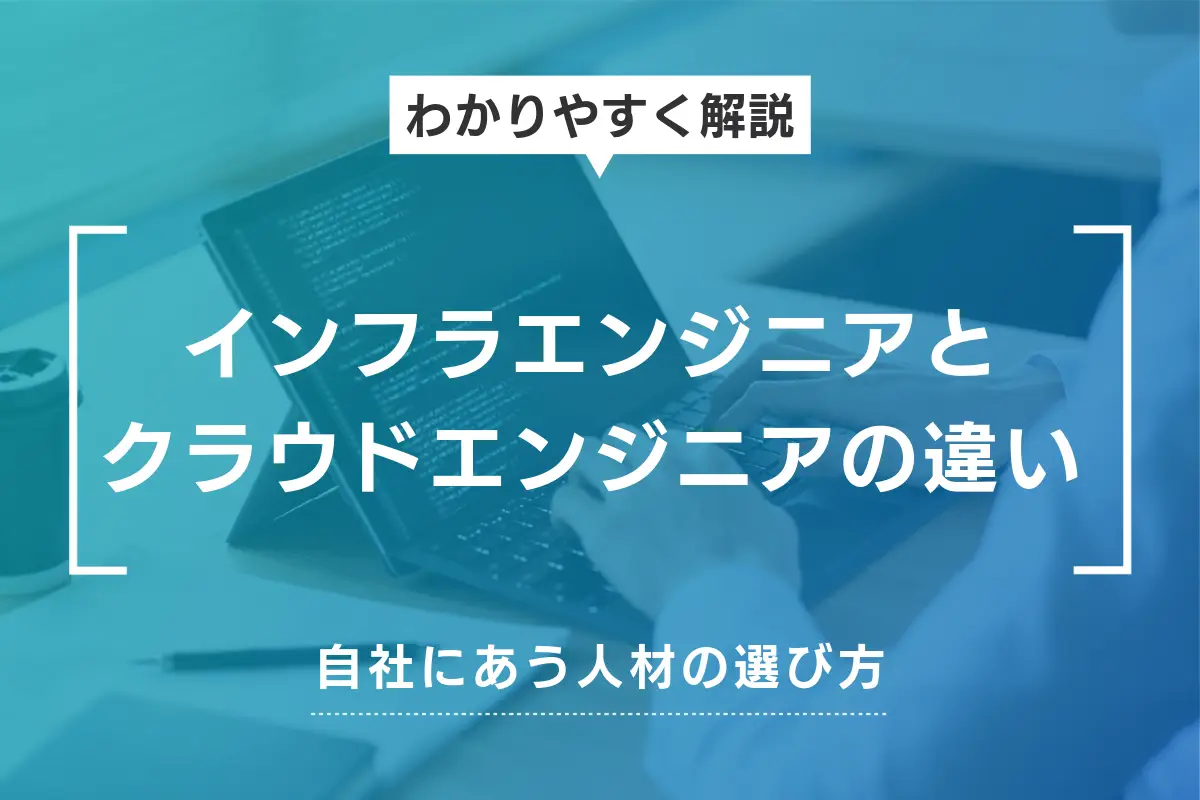システム開発やインフラ構築の外部委託先として、SIerとベンダーは頼りになる存在です。
しかし、両者の違いがわからず「どちらが自社に適しているのか」の判断に迷うこともあるのではないでしょうか。
プロジェクトの規模や期間によっては、SIerとベンダー以外の選択肢も検討しておくのが理想的です。
そこで今回は、SIerとベンダーの違いを解説します。自社の課題解決にマッチする委託先を選ぶための判断基準も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
SIerとベンダーの違いとは
SIerとベンダーは、いずれもITシステムに関する業務を外部に委託するときのパートナーとして位置づけられています。
- SIerはシステム開発を一貫して請け負う企業
- ベンダーは自社製品で事業課題を解決する企業
両者が混同されやすい理由として挙げられるのは「メーカー系」とよばれるSIer企業の存在です。
メーカー系SIerは親会社のハードウェアやソフトウェアを扱うため、自社製品を提供するベンダーと事業内容が類似しています。
なお、SIerにはメーカー系を含む5つの分類があります。詳細については、関連記事をぜひチェックしてみてください。
関連記事:SIerの仕事内容を解説|実はフリーランスで解決できるケースも?
SIer|システム開発を一括請負する企業
SIer(システムインテグレーター)は、システム開発やインフラ構築を一貫して請け負う企業です。
以下のように、要件定義から導入後の運用・保守までサポートしています。
- システムの全体像を描く要件定義
- システム化を実現するための設計
- プログラムをつくる開発
- 完成したシステムの動作確認(テスト)
- テストを通過したシステムの導入
- 導入後の安定稼働をサポートする運用・保守
SIerが担う役割は、顧客に適したシステム・インフラの構築です。
システム開発だけでなく、インフラ構築も含めた総合的なプロジェクト開発を依頼できます。
ベンダー|自社製品・ソフトウェアを提供する企業
自社開発のパッケージ製品やサービス・ソフトウェアを活用し、事業課題の解決や製品導入をサポートする企業がベンダーと呼ばれています。
| IT系ベンダーの主な種類 | 提供する製品・サービス例 |
|---|---|
| ハードウェアベンダー |
|
| ソフトウェアベンダー |
|
| パッケージベンダー |
|
ベンダーの強みは、自社製品に関する深い専門知識です。機能や特性を熟知しているため、製品を最大限に活用するための導入方法を提案できます。
また、顧客の業務フローにあわせて、機能のカスタマイズや他システムとの連携もサポートしています。
導入後の研修やトラブル発生時のサポートも提供しているため、自社の課題解決につながる「製品」を求める企業におすすめです。
SIerとベンダーの違いからわかる委託先の選び方
| 特徴の比較 | SIer | ベンダー |
|---|---|---|
| プロジェクト規模 | 大規模 | 中規模(製品導入レベル) |
| 依頼コスト | 比較的高額 | 導入製品や依頼内容次第で変動 |
| 業務範囲 | プロジェクトの企画から 運用・保守までサポート | 自社製品の導入から 運用・保守までサポート |
SIerとベンダーの「どちらが自社に適しているか」の判断基準は、プロジェクトの目的によって異なります。
それぞれの得意分野や役割の違いを理解しながら、自社の目的に適した委託先を選定しましょう。
- 大規模なプロジェクトを依頼するならSIer
- 製品・サービス導入による業務改善を求めるならベンダー
SIer|大規模なプロジェクトの依頼におすすめ
以下の要件に該当する場合は、SIerへの依頼が適しています。
- プロジェクトの企画から運用・保守まで依頼したい
- 大規模・複雑なプロジェクトを依頼したい
自社のリソースでは対応が難しいプロジェクトも、SIerであれば一貫して依頼できます。
プロジェクトの企画から運用・保守まで依頼したい場合
企画から運用・保守まで一貫して請け負うSIerには、システム全体を俯瞰して設計・開発に対応できる魅力があります。
インフラ構築とシステム開発の知見が求められるプロジェクトでも、SIerであればシステム全体を広くカバーする体制構築が可能です。
また、発注側に専門知識がなくても、SIerが窓口を担いながら必要な技術や人材の調整をサポートできます。
要件定義から運用・保守まで一貫して任せられるため、発注側のプロジェクト管理の負担も軽減可能です。
大規模・複雑なプロジェクトを依頼したい場合
以下のように、大規模で複雑な要件がともなうプロジェクトにもSIerへの依頼が適しています。
- 全社的な基幹システムの刷新
- 複数ベンダーとの連携が必要なプロジェクト
会計・人事・販売管理など、大規模なプロジェクトでは複数のシステムを連携させる必要があります。
また、複数のベンダーが提供する製品を組み合わせるケースも少なくありません。
SIerには特定の製品に縛られない中立的な立場として、プロジェクト全体を取りまとめる管理体制が整っています。
社内リソースでは実現が難しいプロジェクトを「主導してほしい」と考える企業にとって、開発チームそのものを外部委託できるSIerは頼りになる存在です。
ベンダー|製品・サービス導入による業務改善におすすめ
以下の要件に該当する場合は、ベンダーへの依頼が適しています。
- 特定分野に強みをもつ製品・サービスを導入したい
- 製品・サービス導入後の長期的なサポートを求めたい
ベンダーは自社製品の専門家であり、知見やノウハウを活かした提案が期待できます。
特定分野に強みをもつ製品・サービスを導入したい場合
システムの安定稼働や運用効率化など、業務課題を解決するための「パッケージ製品の導入」を検討している企業にはベンダーがおすすめです。
たとえば、サーバー障害に備えて「データの消失を防ぎたい」という目的がある場合は、バックアップソフトの導入によってリスクを最小限に抑えられます。
また、24時間体制でインフラの稼働状況を把握したい場合には、監視ソフトを導入すれば問題発生時の検知や対応の効率化が可能です。
ベンダーは製品の機能や特性を熟知しているため、標準機能や一部のカスタマイズで「顧客の要件を満たせるかどうか」の的確な判断が可能です。
また、ゼロからシステムを開発するSIerと比較しても、導入までのコストや時間を削減できる可能性が高まります。
製品・サービス導入後の長期的なサポートを求める場合
以下のように、製品やサービス導入後の長期的なサポートを求める企業にもベンダーがおすすめです。
- システム導入後の運用サポート
- トラブル時の対応サポート
- 機能・セキュリティのアップデート
ベンダーには、自社製品に関する深い知識やノウハウがあります。
導入した製品に不具合が発生したときには、原因の特定や復旧対応のスムーズなサポートが可能です。
また、インフラのクラウド移行にともなうカスタマイズやバージョンアップなど、自社環境の変化にあわせたサポートも期待できます。
もし「SIerは予算オーバー」「ベンダーだと柔軟性がない」とお困りなら、フリーランスエンジニアを活用するのもひとつの方法です。
フリーランスのインフラエンジニア専門エージェントサービス「クロスネットワーク」なら、即戦力エンジニアを直接確保でき、コストを抑えた柔軟な開発体制を実現できます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
SIerとベンダーだけでは解決しきれない3つの課題
先述のとおり、SIerやベンダーには自社の課題を解決する役割や強みがあります。
しかし、すべてのプロジェクトに適している委託先とは限りません。
それぞれの企業がもつ強みや組織構造は、ときには弱みとしてはたらくケースもあります。
とくに以下3つの観点はSIerやベンダーの苦手分野となるため、事前に把握しておきましょう。
- 小規模・スピード重視の依頼に対応しづらい
- 中間マージンによってコストが高くなりやすい
- 専門分野や最新技術に特化した人材を確保しにくい
小規模・スピード重視の依頼に対応しづらい
小規模でスピード感が求められる依頼は、SIerやベンダーでは効率的に対応できない可能性があります。
とくに大規模かつ長期的なプロジェクトを前提とするSIerは、スピード重視の小規模な依頼でコストが割高になるケースも少なくありません。
チームでプロジェクトを進める組織体制や契約形態を組むため、規模に対する間接費用の割合が高くなってしまう傾向があります。
また、システムの仕様や導入する製品など、全体の計画を固めてから段階的に進める開発手法(ウォーターフォールモデル)が主流です。
プロジェクトの途中で仕様変更や追加タスクが発生しても、柔軟に軌道修正できない可能性も少なくありません。
中間マージンによってコストが高くなりやすい
SIerやベンダーに依頼すると、中間マージンによってコストが高くなりやすい傾向にあります。
マージンとは、SIer企業が得る利益や管理コストなど、エンジニアの報酬とは別に支払われる費用のことです。
とくにSIerが手掛ける大規模プロジェクトは、各業務を完結させるために複数の下請け企業が連携しています。
一部の業務を他社へ再委託する「多重下請け構造」が生まれやすく、実際に手を動かすエンジニアまでに何層ものマージンが発生するケースも少なくありません。
また、ベンダーに依頼する場合には、自社製品の「サポート範囲外の対応」を外部の協力会社に再委託するケースがあります。
ベンダーの管理費が加算される可能性もあるため、想定外の追加コストが発生するケースも想定しておきましょう。
専門分野や最新技術に特化した人材を確保しにくい
SIerやベンダーでは、専門分野や最新技術に特化した人材を見つけにくい可能性があります。
SIerの強みは、幅広い業界のシステム開発に対応できる総合力です。
しかし、特定の技術分野に深く特化したエンジニアが少ない可能性も否定できません。
とくに信頼性や安定性が重視される大規模なプロジェクトでは、実績が豊富で広く利用されている技術を採用する傾向にあります。
また、自社製品の技術サポートに長けているベンダーは、他社製品の導入や連携に対応しきれないケースも少なくありません。
既存技術や自社製品の優先度が高くなりやすいSIerやベンダーでは、専門分野や最新技術に特化した依頼に対応しきれない可能性があることも想定しておきましょう。
コスト・柔軟性を重視するならフリーランス活用も選択肢に
| 特徴の比較 | SIer/ベンダー | フリーランス |
|---|---|---|
| プロジェクト規模 | 中~大規模 | 小~中規模 (依頼内容によって変動) |
| 依頼コスト | 比較的高額 | 低コストで依頼可能 |
| 業務範囲 | 企画・導入から 運用・保守までサポート | 契約に応じて柔軟にサポート |
SIerやベンダーでは対応が難しい課題は、フリーランスエンジニアの活用によって解決できる可能性があります。
フリーランスエンジニアの活用は、以下3つの観点で効果的な選択肢です。
- 小規模・短期間のプロジェクトを依頼しやすい
- 直接契約で不要なコストを削減しやすい
- 専門分野に特化した人材を確保しやすい
これまで紹介したSIerやベンダーとは異なる特徴をもつフリーランスのメリットを把握しながら、より自社に適した人材確保を実現しましょう。
小規模・短期間のプロジェクトを依頼しやすい
フリーランスエンジニアには、以下のように小規模かつ短期間のプロジェクトを依頼しやすいメリットがあります。
- 社内リソースでは対応できない部分的な業務
- 繁忙期に少人数(1~2名)のスポット対応
- PoC(実証実験)やプロトタイプ開発
サービスの繁忙期に1〜2名だけスポットで増員したい場合にも、フリーランスであればスムーズに人材を確保できます。
とくに新規サービスを検証するための実証実験(PoC)や試作品の開発など、スピードと試行錯誤が求められる対応にはフリーランスが適任です。
また、契約上の合意に基づいて仕様や進め方をすり合わせられるため、状況に応じて柔軟な軌道修正を図れます。
小さな単位で素早く開発サイクルを回したい企業にもおすすめです。
関連記事:フリーランスのインフラエンジニアに業務を委託する流れとは?単価相場や注意点も解説
直接契約で不要なコストを削減しやすい
中間マージンが発生しない直接契約のフリーランスエンジニアであれば、支払うコストを「エンジニアの報酬のみ」に最適化できます。
中間マージンが発生しないことで、以下の効果も期待できます。
- 同じ予算でより高いスキルのエンジニアに依頼できる
- プロジェクト全体のコストを削減できる
また、依頼する業務の範囲や期間にあわせて、必要なスキルをもつ人材を的確に確保できるのもフリーランスのメリットです。
たとえば、以下のようにフェーズごとの適材適所な人材を確保できます。
- プロジェクトの立ち上げ期にはインフラ構築に強いエンジニア
- 開発が本格化したらアプリケーション開発が得意なエンジニア
エンジニアの人件費をプロジェクトの進捗にあわせた変動費として扱えるため、事業の状況に応じて柔軟なリソース配分が可能です。
必要最小限の外部リソースに絞って依頼できるため、効率的なコスト管理を実現できます。
関連記事:フリーランスのインフラエンジニアと契約した場合の単価相場とは?|単価交渉のコツも解説
専門分野に特化した人材を確保しやすい
フリーランスには、特定の専門分野や最新技術に特化したスキルをもつエンジニアも少なくありません。
フリーランスとして活動するエンジニアは、自身の市場価値を高めるために専門スキルを深く追求する傾向があるためです。
そのため「AWSの知見が豊富なエンジニア」のように、依頼したい業務内容や求めるスキルにあわせてピンポイントな人材を確保できます。
専門性の高いフリーランスエンジニアを探すときは、フリーランス専門のエージェントを活用するのも効果的です。
自社のプロジェクト要件や技術的な課題を理解したうえで、最適なスキルをもつエンジニアのマッチングをサポートしてくれます。
なお、フリーランスエージェントに依頼する場合には、マージンが発生するケースもあります。ただし、SIerと比較しても低コストに設定されているのが一般的です。

エンジニアのリソース不足を解消するならクロスネットワークにご相談を
混同されがちなSIerとベンダーには、以下のように明確な違いがあります。
- SIerはシステム開発を一貫して請け負う企業
- ベンダーは自社製品で事業課題を解決する企業
自社のプロジェクトを依頼するなら、それぞれの違いを理解したうえで目的や課題にあった委託先を選定するのが効果的です。
ただし、小規模なプロジェクトや専門分野に特化した対応のように、SIerやベンダーが不得意とする領域もあります。
そのようなときは、フリーランスの活用を検討するのも効果的です。
クロスネットワークでは、即戦力としての活躍を期待できるインフラエンジニアを迅速にマッチングいたします。
プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。最短3営業日でのアサインも可能。
また、週2〜3日の依頼にも対応しているので、解決したい課題やご要望に応じて柔軟なリソース確保をサポートいたします。
サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。
インフラ構築のリソース不足に課題があるなら、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。