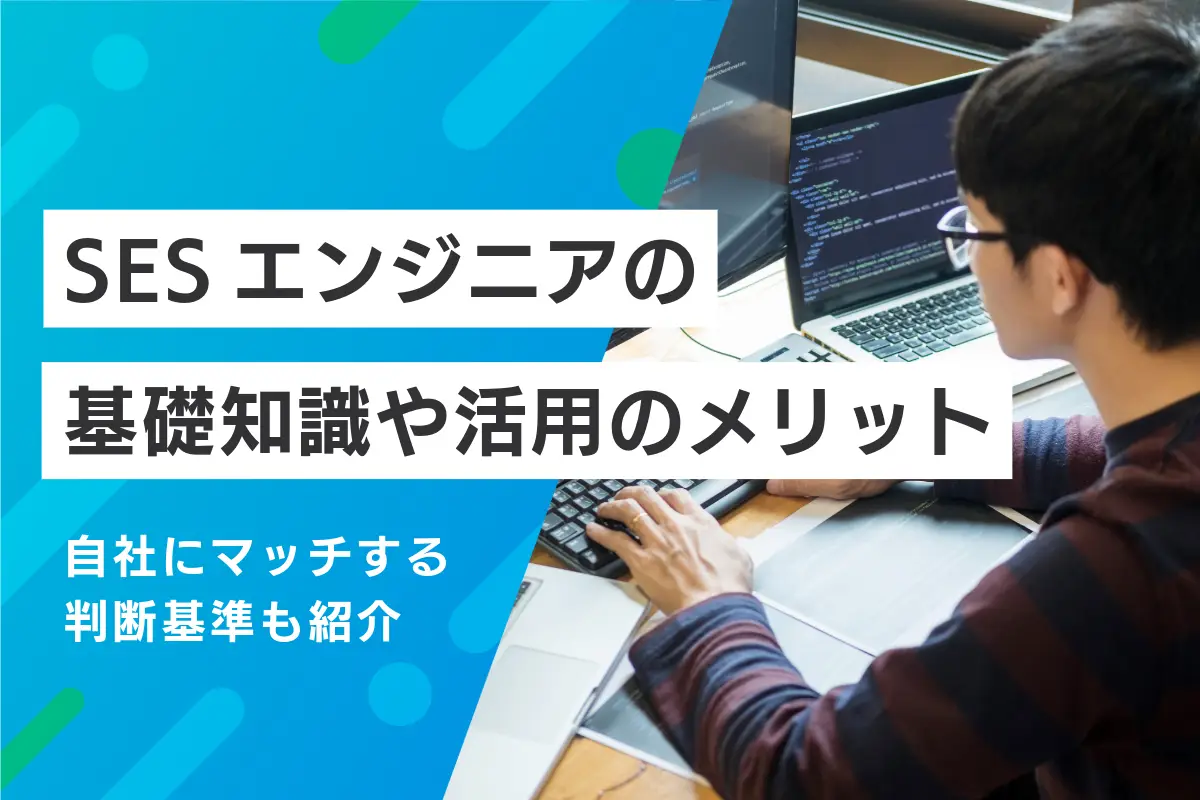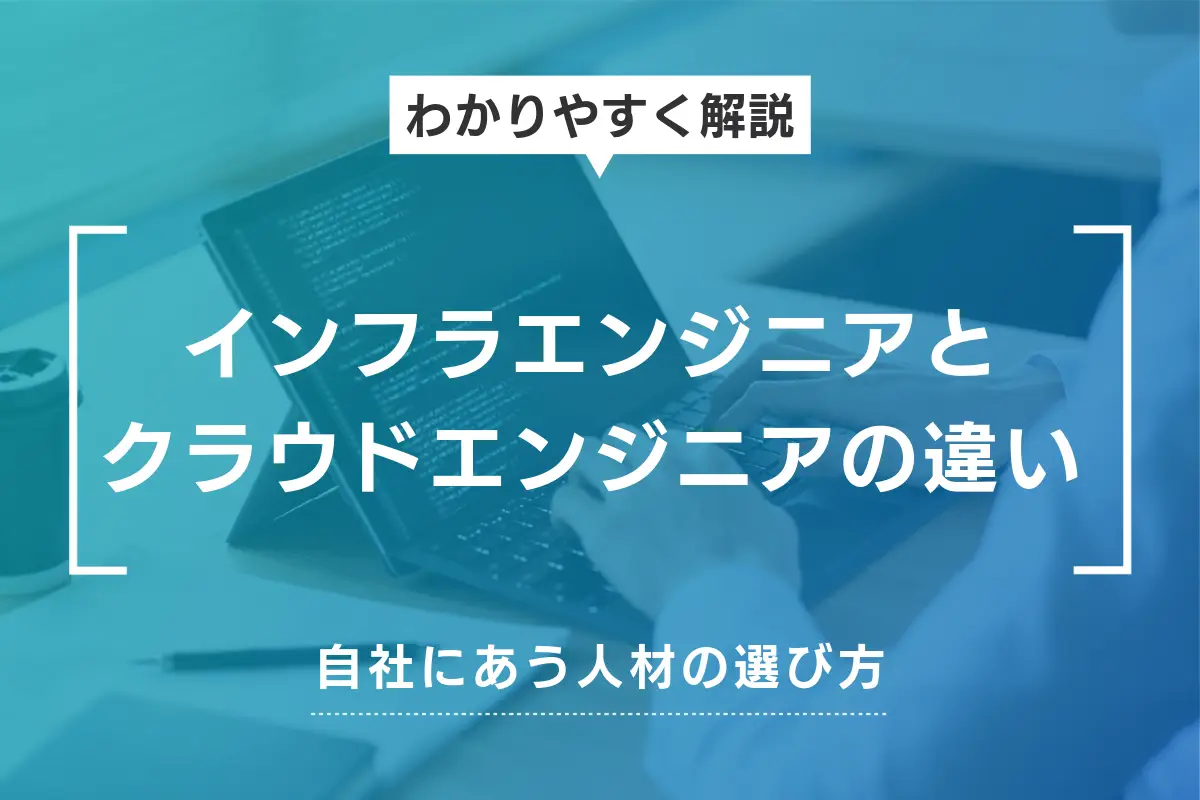近年、社内のDX推進やクラウド移行など企業を取り巻くIT環境は大きく変化しています。自社でも複数のプロジェクトが立ち上がり、内製では補いきれないためSIerに協力を依頼したい企業も多いでしょう。
しかしSIerの単価相場がわからず、どこに依頼すべきか迷うケースは珍しくありません。依頼する立場としてはできる限りコスト効率と品質の両立を重視するため、失敗は避けたいもの。
そこで本記事では以下の内容について解説します。
SIerの単価が決まる仕組みと相場
SIerの単価を決める要素
単価に見合ったSIerを選ぶポイント
SIerとの単価交渉を有利に進める方法
SIerの代わりにフリーランスへ依頼するメリット
本記事を最後まで読めば、適正な単価でSIerに依頼して、予算内で高品質なシステム開発を実現できるでしょう。自社のITインフラ整備にお悩みの経営者、IT事業責任者の方は参考にしてください。
SIerの単価とは何か?基本的な概念と人月単価の仕組み
SIer業界における「人月単価」は、プロジェクト規模を測る独特の指標です。「エンジニア1人×1か月=○○万円」という計算方法で、単価100万円のエンジニアを3人、4か月間アサインすれば、総額は100万円×3人×4か月=1,200万円となります。
この単価の構成要素は以下のように分けられます。
エンジニアの直接人件費:約5~6割
管理部門や営業などの間接費:2~3割
企業の利益分:1~2割
つまり、発注者が支払う100万円のうち、実際にエンジニアの手取りとなるのは50~60万円程度に留まります。
さらに複雑な構造として、大手SIerを起点とした多重下請けシステムが存在します。元請けから2次請け、3次請けへと案件が流れる過程で、各段階において1~3割の中間マージンが発生する仕組みです。最終的に実作業を担当するエンジニアが受け取る単価は、元請け価格の5~7割程度まで圧縮されるケースも珍しくありません。
この業界構造を理解すれば、中間マージンを削減するために直接中堅SIerと契約交渉する戦略も見えてきます。
大手SIerの単価相場
SIerの単価は、以下のように企業規模やブランド力によって大きく異なります。
外資系SIer:300万円~/月
中堅SIer:120万円~160万円/月
国内大手SIer:150万円〜200万円/月
スキルや経験年数にもよりますが、エンジニアの単価相場は60万円~120万円程度です。これに加えて営業費用や開発環境への投資といった間接費が3割前後上乗せされます。
外資系SIer企業は、戦略立案から実装まで一貫したサービスを提供し、世界各国の事例やノウハウを集約した独自のアプローチによるソリューションを提供します。そのため、月額単価は300万円と相場が高くても需要がある状況です。
一方、国内大手は長年の実績と信頼性、大規模プロジェクトの遂行能力を持つことから、中堅SIerより2~5割程度高い単価設定が可能となっています。
また、中堅SIerは大手よりも2割以上安価な傾向にあり、対応の柔軟性や特定の分野への強みなどを有しているケースが多いのも特徴。
確かに大手や外資系SIerは、知名度や実績、体制の安心感を背景に、同じ内容でも単価が高くなりやすい傾向があります。しかし、必ずしも高単価=高品質とは限りません。プロジェクトの規模や要求レベルによっては、中堅SIerの方がコストパフォーマンスが良い場合もあります。
そして費用対効果を重視するなら、SIerだけに絞らずフリーランスという選択肢も比較対象に入れておきましょう。
というのもフリーランスは、必要な領域だけをピンポイントで依頼しやすく、要件によっては「全部まとめてSIerに任せる」よりも、予算内で必要品質を確保しやすくなる可能性があります。
フリーランス採用をスムーズに進めたい場合は、クロスネットワークの利用がおすすめ。要件に合う人材の提案を受けられるため、探すところから一人で抱え込まずに進められます。
サービスの詳細は、無料ダウンロードが可能なサービス資料をご覧ください。
SIerの単価が決まる要素
SIer単価は、企業の技術力や依頼内容などによって変動します。提示された単価が適正かどうかを判断するためには、なぜその金額になるのか理由を知ることが重要です。
ここからは、単価が決まる5つの要素を解説します。
エンジニアスキルレベル
プロジェクトの難易度
契約形態・責任範囲
地域
企業規模
エンジニアのスキルレベル
エンジニアのスキルレベルは単価を決定する最も重要な要素です。レベル別の単価相場を以下の表にまとめました。
エンジニアのスキルレベル別単価相場
スキルレベル | 月額単価 | 経験年数 | 主な業務内容 |
初級SE | 80万円~100万円 | 3年未満 | 基本的な設計書作成やプログラミング(上級者の指導が必要) |
中級SE | 100万円~120万円 | 5年程度 | 要件定義から詳細設計まで独立遂行、顧客折衝も対応 |
上級SE | 120万円~200万円 | 10年以上 | アーキテクチャ設計、技術選定、チーム指導、新技術導入判断 |
プロジェクトマネージャー | 200万円~300万円 | - | プロジェクト全体統括、予算・納期・品質の責任者 |
月額単価には、エンジニアに渡るお金以外にも営業や組織運営費といった間接費用も含まれるため、単価が割高になる傾向にあります。
また、初級SEと上級SEでは相場に2倍以上の価格差が生じるケースもあります。このように同じプロジェクトでもSIerに所属するSEのスキルによって単価が大きく変わるのです。
関連記事:【一覧表】インフラエンジニアに求めるスキル15選!資格も紹介
プロジェクトの難易度
同じエンジニアでも以下の表のように担当するプロジェクトの難易度によっても単価は変動します。
プロジェクト種別 | 単価倍率 | 特徴・理由 |
レガシーシステム移行 | 通常+2~4割 |
|
AI導入・クラウド移行 | 通常の5~10割 |
|
短納期案件 | 通常+2~3割 |
|
基準となる「通常」は標準的な開発・構築プロジェクトを想定しています。ここに難易度の高い工程やタイトな納期、新技術の活用といった要素が加わると2~5割以上の割増料金が発生します。
契約形態・責任範囲
契約形態によっても単価は変わり、請負契約は準委任契約より3割~5割高くなるのが一般的です。準委任契約では作業時間に対して料金を支払いますが、成果物の完成責任はSIer側にありません。一方、請負契約では完成責任を負うため、リスクプレミアムとして単価が上乗せされる仕組みになっています。
SLA(サービスレベルアグリーメント)を設定する場合、稼働率99.9%保証などの厳しい条件では単価が1~2割上昇します。システムの可用性を保証するために、冗長化設計や24時間監視体制など追加コストが発生するためです。
また、瑕疵担保責任の期間が長いほど単価は高くなる傾向にあります。納品後の不具合対応リスクを価格に転嫁する必要があるため、この上乗せは避けられません。
地域
下の表のように、エンジニアが作業する地域によっても単価は変動します。
地域別の単価相場(中級SEの場合)
地域分類 | 対象地域 | 月額単価 | 首都圏との差 | 備考 |
大都市圏 | 東京・大阪 | 100万円程度 | 基準 | 全国の基準価格 |
地方都市 | 札幌・仙台・福岡など | 70万円~80万円 | -3~4割 | オフィス賃料・人件費の地域差を反映 |
リモートワーク | 地方在住者 | 80万円程度 | -20割 | 完全リモート対応可能なプロジェクト限定 |
オフショア(中国・インド) | 中国・インド | 30万円~50万円 | -5~7割 | 通訳が必要になってコストが上がる |
オフショア(東南アジア) | ベトナム・フィリピン | 20万円~40万円 | -6~8割 |
大都市圏を基準にすると地方都市はその6~7割程度です。リモートワークが中心の案件だと、地方在住エンジニアなら東京価格の8割程度で活用できるケースが増えています。
オフショア開発を活用するとさらに安くなる傾向にありますが、言語の壁やコミュニケーションコスト、品質管理の難しさなどを考慮する必要があります。
企業規模
SIerの企業規模は単価に直結し、大手と中小では同じ作業でも5割以上の価格差が生じるケースがあります。
企業規模別の単価相場
企業規模 | 従業員数 | 単価水準(大手比) | 主な特徴・強み | 注意点 |
大手SIer | 1万人以上 | 基準(100%) |
| プレミアム価格 |
中堅SIer | 1,000~5,000人 | 大手の7~8割 |
| 品質と価格のバランス重視 |
中小SIer | 300人以下 | 大手の5~6割 |
| 倒産リスク・人材流動性に注意 |
なお、企業規模が小さいほど倒産リスクや人材の流動性が高いため、長期プロジェクトでは注意が必要です。プロジェクトの重要度とリスク許容度を考慮して、適切な規模のSIerを選定しましょう。
単価に見合ったSIerを選ぶポイント
適正な単価でSIerを選ぶには、プロジェクトの目的と要件を明確にして、相性の良いパートナーを見極めることが成功の鍵となります。予算オーバーを防ぐためにも、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
依頼の目的を明らかにする
担当者との相性を確かめる
過去の取引実績を調査する
依頼の目的を明らかにする
SIerへの依頼目的が曖昧なまま見積もりを取ると、各社の提案内容がバラバラになり、適正な単価比較ができなくなってしまいます。DX推進なのか、レガシーシステムの統合なのかプロジェクトの具体的な目標を明文化することから始めましょう。
「3年以内に基幹システムをクラウド化し、運用コストを3割削減する」といった数値目標を設定すると、SIer側も具体的な提案がしやすくなります。
次に重要なのが、コスト削減、品質、納期のいずれを重視するのかという優先順位の明確化です。
予算に制約がある場合は「品質は標準レベルで構わないのでコストを最小限に抑えたい」と伝えることで、無駄な機能提案を避けられます。逆に、ミッションクリティカルなシステムであれば「多少コストが上がっても、品質と安定性を最優先したい」という方針を示すことが重要です。
担当者との相性を確かめる
技術力や単価以上に重要なのが、プロジェクトマネージャーとの相性であり、これがプロジェクトの成否を左右するケースも少なくありません。初回の打ち合わせで、技術的な質問に対してわかりやすく説明してくれるか、専門用語を多用せずに伝えてくれるかをチェックしましょう。
質問に対して「それは仕様の問題ですね」で済ませるのではなく、代替案を提示してくれるような柔軟性も重要な判断基準です。定例会議でのコミュニケーションスタイルも確認しておくべきポイントで、進捗報告が形式的なものか、実質的な議論ができるかでおおきな差が生まれます。
過去の取引実績を調査する
SIerの過去実績を詳しく調査することで、単価の妥当性だけでなく、プロジェクト遂行能力も客観的に評価できます。まず確認すべきは、同じ業界で、同規模のプロジェクトを成功させた実績があるかどうかです。
たとえば、金融業界のシステムと製造業のシステムでは要求される品質基準が異なるため、業界特有の知見をもっているかが重要になります
また技術トラブルが発生した際の平均復旧時間(MTTR)と重大障害の発生頻度も確認しておきましょう。可能であれば、実際にそのSIerと取引したことがある企業の担当者から、生の声を聞くことをおすすめします。
SIerとの単価交渉を有利に進める方法
単価交渉で最も重要なのは、主導権を握るための準備と戦略です。経営陣への説明責任を果たしながら、質の高いシステム開発を実現するために、以下の交渉テクニックを活用しましょう。
- 複数社と比較検討する
- 市場相場のデータを準備する
- プロジェクトの要件を詳細に定義する
これらの方法を組み合わせることで、SIer側も納得できる形で、適正な単価での契約締結が実現できます。
複数社と比較検討する
3~5社から相見積もりを取ることで各社が競争意識をもつため、単価が下がるケースが多いです。ただし、単純に安い会社を選ぶのではなく、技術提案の内容、単価の内訳、納期の実現可能性を総合的に評価することが重要です。
たとえば、A社が月100万円、B社が月120万円でも、B社の方が工期を1か月短縮できれば、トータルコストは逆転する可能性があります。各社の強みと弱みを分析し、プロジェクトの特性に最も適したSIerを選定することで、コストパフォーマンスを最大化できるでしょう。
クラウド移行が得意なA社と、セキュリティに強いB社を組み合わせて、それぞれの専門分野を生かすという選択肢もあります。さらに、メインベンダーとは別にセカンドベンダーを確保しておくことで、価格交渉力が格段に向上します。
ただし、極端な値下げ要求は品質低下や関係悪化を招く可能性があります。そのため、お互いが納得できる落としどころを見つけることが、長期的な成功につながるでしょう。
市場相場のデータを準備する
客観的な市場データを準備することで、交渉に説得力が生まれ、SIer側も無理な単価設定ができなくなります。経済産業省が公開している「IT人材白書」や、情報サービス産業協会(JISA)の統計データは、公的な根拠として非常に有効です。
これらのデータには、エンジニアのスキルレベル別、地域別、業界別の平均単価が記載されており、交渉の基準値として活用できます。同業他社がどの程度の単価で発注しているかという情報も重要で、業界団体の会合や勉強会で情報交換すると良いでしょう。
プロジェクトの要件を詳細に定義する
要件が曖昧なままだと、SIer側はリスクを考慮して予備費用を見積もりに含めざるを得なくなってしまいます。機能要件だけでなく、性能要件、セキュリティ要件、運用要件など、非機能要件も含めて詳細に定義することが重要です。
「レスポンスタイムは3秒以内」「同時接続ユーザー数は1,000人」といった具体的な数値目標を設定しましょう。成果物の品質基準と検収条件を事前に明文化することで、完成後のトラブルを防ぎ、追加費用の発生リスクを最小化できます。
また「軽微な変更は月2回まで無償対応、それ以上は1人日あたり10万円」といった明確なルールがあれば、予算管理の負担が軽減されます。プロジェクトスコープ(範囲)の境界線を明確にし、どこまでがSIerの責任で、どこからが自社の責任なのかを文書化しましょう。
SIerの代わりにフリーランスへ依頼するメリット
SIerはITインフラの構築をワンストップでサポートしてくれる強い味方です。一方で、一定のプロジェクト規模や予算がないと契約できない、もしくは割高になってしまうケースもあります。
そこでおすすめしたいのがフリーランスエンジニアの活用です。フリーランスエンジニアとは企業に所属せず、個人で企業と契約を結んでシステム開発や運用・保守などを担う人材のこと。
ここではSIerの代わりにフリーランスへ依頼するメリットを3つ紹介します。
コストを適正化できる
契約の柔軟性が高い
社外の知見を取り入れやすい
コストを適正化できる
SIerの単価には実際の開発作業以外に、営業費用や管理部門の間接費が3~4割が含まれており、フリーランスならこの部分を大幅に削減できます。
SIerが月額100万円で提示している案件でも、実際にエンジニアが受け取るのは60~70万円程度というケースが一般的です。フリーランスエンジニアと直接契約すれば、同じスキルレベルの人材を月額80万円程度で確保でき、品質を落とさずに2~3割のコスト削減が実現します。
さらに、プロジェクトの規模や期間に応じて単価を柔軟に調整できるのもメリットです。短期間の緊急対応なら日額単価での契約、長期プロジェクトなら月額固定での契約など、予算と要件に最適な契約形態を選択できます。
このような適正価格での発注により、浮いた予算を他の重要プロジェクトに振り分けることも可能になり、IT投資全体の最適化につながります。
関連記事:フリーランスのインフラエンジニアと契約した場合の単価相場とは?|単価交渉のコツも解説
契約の柔軟性が高い
フリーランスとの契約は、SIerのような複雑な稟議プロセスが不要です。プロジェクトの状況に応じて素早く契約条件を変更できるため、変化の激しいIT開発においておおきなアドバンテージとなります。
短期集中型のプロジェクトであれば、必要な期間だけスポット契約で対応し、長期的な保守運用が必要なら年間契約に切り替えるといった柔軟な対応が可能です。急な仕様変更が発生した場合でも、フリーランスなら即座に対応方針を協議し、追加工数の見積もりから実装まで最短1~2日で着手できます。
プロジェクトの進捗に応じて、稼働時間を週3日から週5日に増やしたり、開発フェーズが終わったら保守フェーズの契約に切り替えたりと、機動的な契約見直しも可能です。このような柔軟性により、無駄な待機時間や過剰なリソース確保を避け、常に最適なコスト構造を維持できます。
関連記事:インフラエンジニアの発注手順|事前検討すべき要求事項とコスパ戦略を解説
社外の知見を取り入れやすい
優秀なフリーランスエンジニアは複数の企業でプロジェクトを経験しているため、業界を超えた豊富な知見と最新の技術トレンドを取り入れることができます。具体的には、金融業界で培ったセキュリティノウハウや製造業で習得したIoT連携など、多様な経験を活用して新しい解決策を生み出してくれるでしょう。
最新のクラウドネイティブ技術やDevOpsの実践方法など、社内では習得が難しい専門技術も、経験豊富なフリーランスなら即座に導入できます。組織では「これまでこうやってきたから」という慣習にとらわれがちな部分も、外部の視点から「他社ではこのような効率的な方法がありますよ」と提案してもらえます。
さらに、フリーランスとの協業を通じて、社内エンジニアへの技術移転も自然に進み、組織全体の技術力向上にもつながるという副次的効果も期待できるでしょう。
SIerの代わりにフリーランスへ依頼するならクロスネットワークがおすすめ
本記事ではSIerの単価相場、単価を決める要素や交渉を有利に進める方法などを解説しました。同じ依頼内容でもSIerの企業規模や技術レベル、拠点とする地域によって単価は大きく変動します。SIerへの依頼目的を明確にし、市場の相場を分析すれば適切な単価で契約できるでしょう。
「SIerより安価に依頼できる取引先を見つけたい」「柔軟な仕様変更に対応してもらいたい」という企業はフリーランスも視野に入れましょう。SIerとは異なりフリーランスは個人単位での契約になるため、コスト効率向上やスピーディな対応を期待できます。
「人材の探し方がわからない」「適切に報酬を設定できるか自信がない」という方はクロスネットワークにご相談ください。
クロスネットワークでは、1500名以上の厳選されたインフラエンジニアからニーズに合わせて最適な即戦力人材を最短即日でご提案、最短3日でのアサインも可能です。
「どのようなインフラエンジニアが必要かわからない」「どれくらいの稼働が必要かわからない」といったお悩みにも業界に精通したコンサルタントが案件内容をヒアリングし、最適な採用要件をアドバイスします。
また、週2〜3日からの柔軟なアサインも可能です。
詳細なサービス内容については、無料ダウンロードが可能なサービス資料をご覧ください。
ご相談はお問い合わせページより承っており、平均1営業日以内にご提案します。インフラエンジニア採用でお困りの際は、ぜひクロスネットワークにご相談ください。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

新卒で大手インフラ企業に入社。約12年間、工場の設備保守や運用計画の策定に従事。 ライター業ではインフラ構築やセキュリティ、Webシステムなどのジャンルを作成。「圧倒的な初心者目線」を信条に執筆しています。