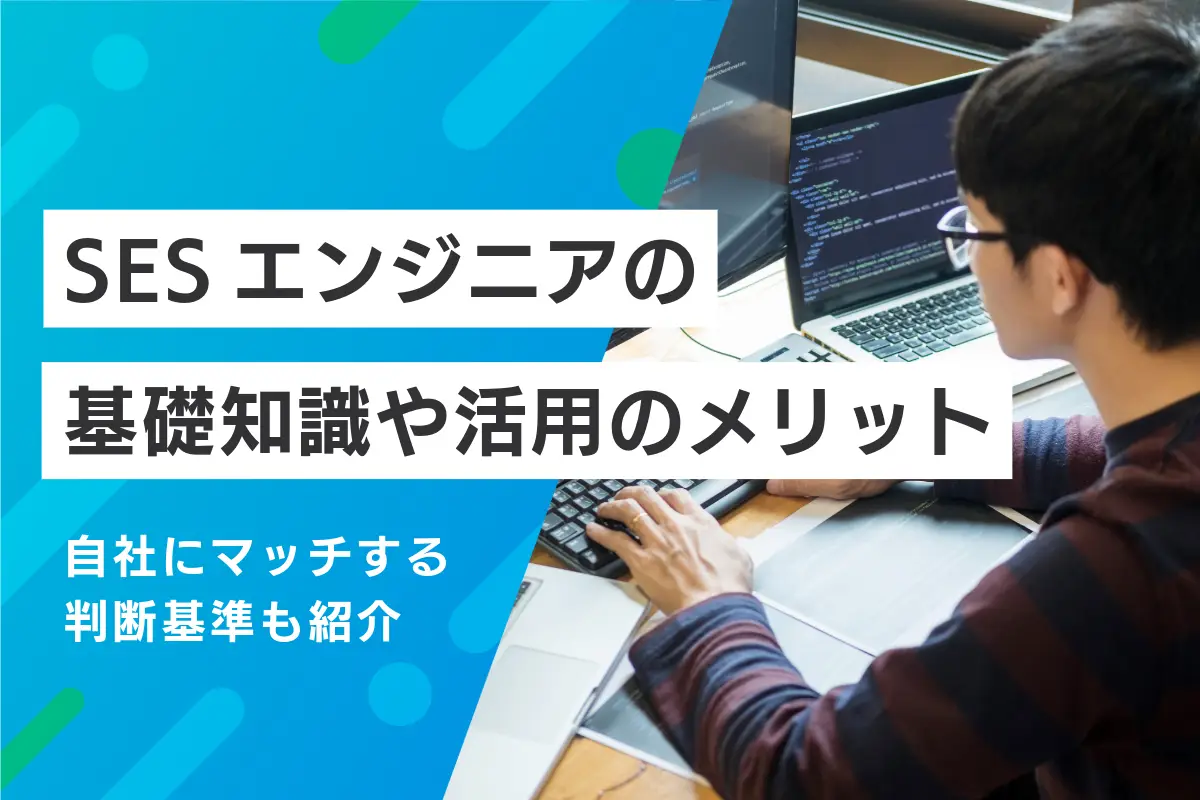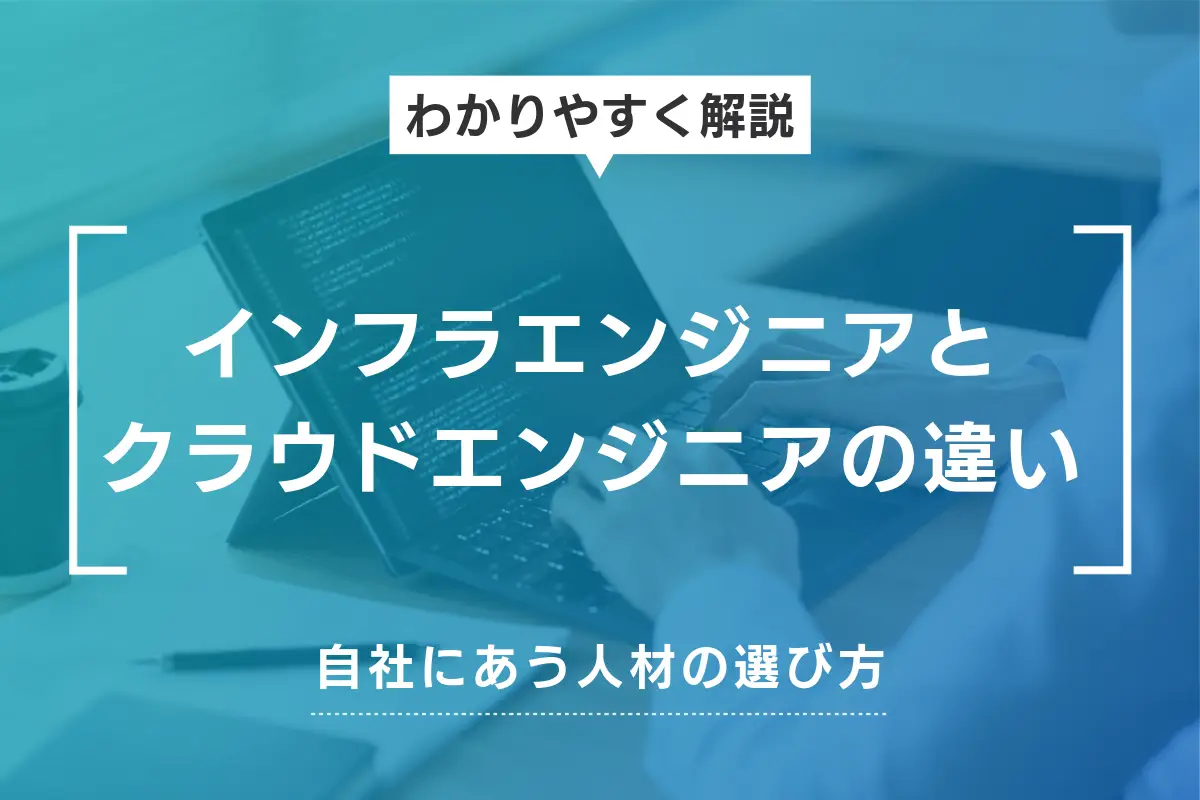社内のインフラ構築やクラウド移行を進めたいのに、エンジニア不足に課題を感じていませんか?とくに通信エンジニアの人材不足は、さまざまな企業で直面しやすい課題です。
システム障害やセキュリティ強化など、事業を支える通信インフラの構築には通信エンジニアの知見が欠かせません。そこで今回は、通信エンジニアの主な役割や仕事内容を解説します。さらにネットワークエンジニアとの違いや「採用しないリスク」も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
通信エンジニアとは|通信インフラを専門に扱う技術者
通信エンジニアは、通信インフラの構築や保守を専門的に担当する技術者です。インターネット接続や拠点間のネットワークなど、企業の情報伝達に活用する通信経路を構築しています。
また、通信エンジニアが担当するのは、オフィス内で利用するLANやWANなどのインターネット回線だけではありません。モバイル回線や光ファイバーといった、より物理的な通信インフラの構築や保守にも深くかかわっています。
インフラ構築における通信エンジニアの役割
通信エンジニアの主な役割は、社内外の通信インフラを安定稼働させるための設計・構築です。企業の事業活動を円滑に進めるため、主に以下のような業務を担当します。
- 電話線や光ファイバーを使ったネットワークの設計・構築
- 電話機や通信機器(無線・有線)の設置・設定
- LAN・WANケーブルを使ったネットワークの設計・構築
- ネットワーク機器やセキュリティ製品の設置・設定
さらに、通信エンジニアの役割は、インフラを設計・構築するだけでは終わりません。完成した通信インフラが安定稼働するように監視したり、障害が発生したときに対応したりする運用・保守も担います。
通信エンジニアとネットワークエンジニアの違い
通信エンジニアとネットワークエンジニアの主な違いは、担当するインフラの領域です。
| 職種 | 担当領域 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 通信エンジニア | 社内外の通信インフラ |
|
| ネットワークエンジニア | 企業内のネットワーク通信 |
|
通信エンジニアの担当領域は、社内外をつなぐ広範囲な通信インフラです。たとえば、以下のような業務が挙げられます。
- 光回線やVPNを用いて本社と支社を結ぶ通信インフラの構築
- モバイル回線に用いる無線ネットワークの構築
- 物理的な配線工事や通信機器の設置
とくに法的な資格が求められる機器の取り扱いや、無線通信にかかわる専門知識が求められる場面で活躍します。
一方でネットワークエンジニアは、主に企業内のネットワーク通信を担当する技術者です。オフィス内をつなぐLANの設計やネットワーク機器を設置する役割があります。
関連記事:ネットワークエンジニアの仕事内容とは?年収や資格・将来性などもわかりやすく解説
通信エンジニアの主な仕事内容
通信エンジニアの仕事内容を理解することで、企業の担当者として以下の効果を期待できます。
- 採用候補者に依頼したい業務内容を具体的に伝えられる
- 採用候補者の業務経験を具体的に把握できる
主な仕事内容を以下4つの分類で解説するので、それぞれの工程における役割を把握しておきましょう。
- 通信インフラの要件定義・設計
- ネットワークの構築・テスト
- 通信インフラの運用・保守
- ネットワークのセキュリティ対策
通信インフラの要件定義・設計
まずは、インフラ構築の目的を明確化するため、事業部門や顧客から「要求事項」や「解決したい課題」などをヒアリングします。そして、ヒアリングした内容をもとに、以下のような要件を技術的な仕様に落とし込む工程です。
- 事業に求められる通信速度
- システムが停止しないための可用性
- 外部攻撃に耐えうるセキュリティレベル
また、予算や納期を考慮しながら、実現可能な構築スケジュールを計画するのも通信エンジニアの役割です。仕様や計画が定まったら、ネットワークの構成図や仕様書・設計書といったドキュメントを作成します。
ネットワークの構築・テスト
要件定義・設計フェーズで定めた仕様に基づき、通信機器の設置やネットワーク配線の構築を実施します。設置するルーターやスイッチなどの機器には、コマンドラインや管理画面から設定を組み込む作業も必要です。
| 【元インフラエンジニアのひとこと】 選定した通信機器は、設置前に設定を組み込むのが一般的です。とくに社会や企業を支える通信インフラでは、ネットワークエラーが事業に致命的な影響を及ぼす可能性もあります。 私が担当していたインフラ構築ではテスト用の簡易的なネットワークを構築し、通信の流れや機器の設定に問題がないことを事前確認していました。そのため、ネットワークの構築は「事前検証→機器の設置→本番環境での検証」の流れで対応するのが基本です。 |
通信機器の設置やネットワークの構築が完了したら、以下のような観点でテストを実施します。
- 通信インフラが設計どおりに疎通しているか
- ネットワークが想定される負荷に耐えられるか
- セキュリティの脆弱性が見つからないか
テスト時に問題や改善点が見つかった場合は、原因を調査しながら設定の修正を実施します。
通信インフラの運用・保守
通信インフラの運用・保守は、構築したネットワークを継続的に安定稼働させるための管理業務です。たとえば、設置した機器に異常がないかどうかを目視や監視ツールによって24時間365日体制で確認します。
ネットワークのトラフィックデータを収集・分析しながら、パフォーマンスの低下や障害の予兆を検知する役割も欠かせません。障害の予兆を検知したり実際に発生してしまったときには、迅速な原因特定と復旧作業に取り掛かります。
また、ドキュメントの管理も通信エンジニアの重要な役割です。障害の再発防止や運用の継続性を確保するため、以下のように各種ドキュメントの作成や更新を実施します。
- 障害発生時の対応手順を運用マニュアルにまとめる
- 再発防止策をドキュメント化する
- 仕様変更や機能追加にあわせて設計書を更新する
ネットワークのセキュリティ対策
ネットワークのセキュリティ対策は、情報資産の漏えいリスクを低減するための業務です。以下のような製品やシステムを活用しながら、通信エンジニアは情報資産を保護します。
| 製品やシステムの代表例 | 主な特徴 |
|---|---|
| ファイアウォール | 外部ネットワークからの通信を制御し、不正アクセスを遮断する |
| WAF(Web Application Firewall) | Webアプリの脆弱性を狙った攻撃や不正アクセスを検知・遮断する |
| IDS(不正侵入検知システム) | ネットワーク上の通信異常や不正アクセスを検知する |
| IPS(不正侵入防御システム) | ネットワーク上で検知した通信異常や不正アクセスを遮断する |
リモートワークが普及した近年では、社外から安全に社内ネットワークへアクセスするVPN(Virtual Private Network)の導入も進んでいます。また、技術的な対策だけでなく、組織全体の情報セキュリティ方針である「セキュリティポリシー」の策定をサポートするケースも少なくありません。
採用時に評価すべき通信エンジニアのスキル・資格
通信エンジニアの採用活動において候補者を客観的に判断するためには、求められるスキルを具体的に理解しておく必要があります。まずは以下の観点に分けて、スキルや経験を評価しましょう。
- ネットワーク構築・設計の基礎スキル
- ネットワーク機器の取り扱い・運用スキル
- 各社ベンダー製品の取り扱い経験
また、技術的なスキルの評価に迷うときは、客観的な指標として保有資格をチェックするのも効果的です。
ネットワーク構築・設計の基礎スキル
通信エンジニアには、ネットワークを構築・設計するための基礎スキルが求められます。とくに以下の知識や経験は、通信インフラの土台として欠かせません。
- TCP/IPプロトコルの仕組みを理解しているかどうか
(IPアドレス・サブネットマスク・ポート番号など) - ネットワークの基礎知識や設定経験があるかどうか
(ルーティング・スイッチングなど)
また、ネットワーク構築・設計の基礎スキルを客観的に評価するため、以下の資格を保有しているかどうかも1つの判断基準です。
| 資格 | 概要 |
|---|---|
| CCNA |
|
| ネットワークスペシャリスト |
|
ネットワーク機器の取り扱い・運用スキル
通信エンジニアには、物理的な機器の取り扱いや運用スキルも求められます。とくに以下の知識や経験は、通信インフラの仕組みを理解するうえで欠かせません。
- データセンターやサーバルームでの物理的な機器設置・設定の経験
- 光ファイバーやLANケーブルなどの物理的な配線にかかわる知識
ネットワーク機器の取り扱い・運用スキルを客観的に評価するには、以下の資格保有をチェックするのも効果的です。
| 資格 | 概要 |
|---|---|
| 工事担任者 |
|
| 無線従事者 |
|
| 電気通信主任技術者 |
|
各社ベンダー製品の取り扱い経験
通信エンジニアのスキルを評価するうえで、各ベンダーの製品にかかわる知識と取り扱い経験も重要な判断材料です。とくにネットワーク機器の設定方法やコマンドは、ベンダーごとに異なるケースも少なくありません。
自社で導入している(あるいは導入を検討している)製品に精通した通信エンジニアであれば、採用後すぐに活躍が期待できます。以下は、ネットワーク製品やセキュリティ製品の代表的なベンダーの一例です。
| 製品の分類 | 代表的なベンダー |
|---|---|
| ネットワーク製品 |
|
| セキュリティ製品 |
|
通信エンジニアを採用しない企業の想定リスク
通信エンジニアには、社内外の通信インフラの安定稼働を支える重要な役割があります。とくに通信インフラは安定稼働を前提に構築されるため、障害や不具合の発生時には素早く復旧対応に着手できる通信エンジニアの存在が欠かせません。
業務や事業に及ぼす影響を最小限に抑えるためには、復旧までに時間をかけない体制構築が必要です。そこで、通信エンジニアの需要(採用すべき理由)を理解するため、想定される3つのリスクを解説します。
システム障害・セキュリティ事故対応の遅延リスク
通信インフラの障害やセキュリティ事故の発生時に、専門知識をもつ通信エンジニアがいないと初期対応が遅れてしまいます。とくに原因の特定や切り分けに時間がかかると、事業やサービスの停止時間が長引いてしまうリスクも想定すべきです。
セキュリティに影響する外部攻撃を受けたときには、初期対応に遅れることで情報漏洩やデータ改ざんなどの被害が拡大するリスクもあります。
また、社内に専門知識のある通信エンジニアがいなければ、再発防止策を技術的に策定・実行できません。再発リスクを低減するためにも、初動に素早く対応できる組織体制の構築が求められます。
通信インフラ構築に必要な人材不足による遅延リスク
通信プロトコルやネットワーク機器の設計・構築に対応できるエンジニアが不足すると、新規事業やサービスの立ち上げが計画通りに進まない可能性もあります。
とくに専門性が求められる通信エンジニアは、採用活動が長引いてしまうケースも少なくありません。関連職種のインフラエンジニアも同様に、人材不足や企業間の競争激化によって専門知識が求められる人材の採用難易度が高まっています。
関連記事:インフラエンジニアの採用が難しい理由と優秀な人材を獲得する方法を解説
また、システム部の担当者が本来のコア業務を兼任することで、業務全体の生産性が低下してしまう可能性もあります。専門外の業務ほど大きな負担がかかるため、通信インフラの専任者を確保するのが理想的です。
外部ベンダー依存によるコスト負担の増加リスク
社内に技術的な判断基準のあるエンジニアがいない状況では、以下のリスクが懸念されます。
- 外部ベンダーの提案を的確に判断できないまま通信インフラを構築してしまう
- 意図せずオーバースペックな通信回線やネットワーク機器を導入してしまう
また、トラフィック増加や回線障害の対応をベンダーに都度依頼すると、保守費用や対応コストが積み重なってしまうリスクも想定されます。インフラ構築を担当したベンダーに依存してしまう「ベンダーロックイン」の状況に陥る可能性があるため、ノウハウが社内に蓄積できるような対策を心がけましょう。
【契約形態別】通信エンジニアを確保する3つの手段
通信エンジニアを確保する手段は、正社員採用だけではありません。契約までのリードタイムやコストの負担を考慮するなら、企業の状況にあわせて以下の選択肢も検討するのが効果的です。
- SES
- エンジニア派遣
- 業務委託(フリーランス)
それぞれの契約形態には異なる特徴があるため、自社の課題やプロジェクトの性質にあわせて最適な手段を選択しましょう。
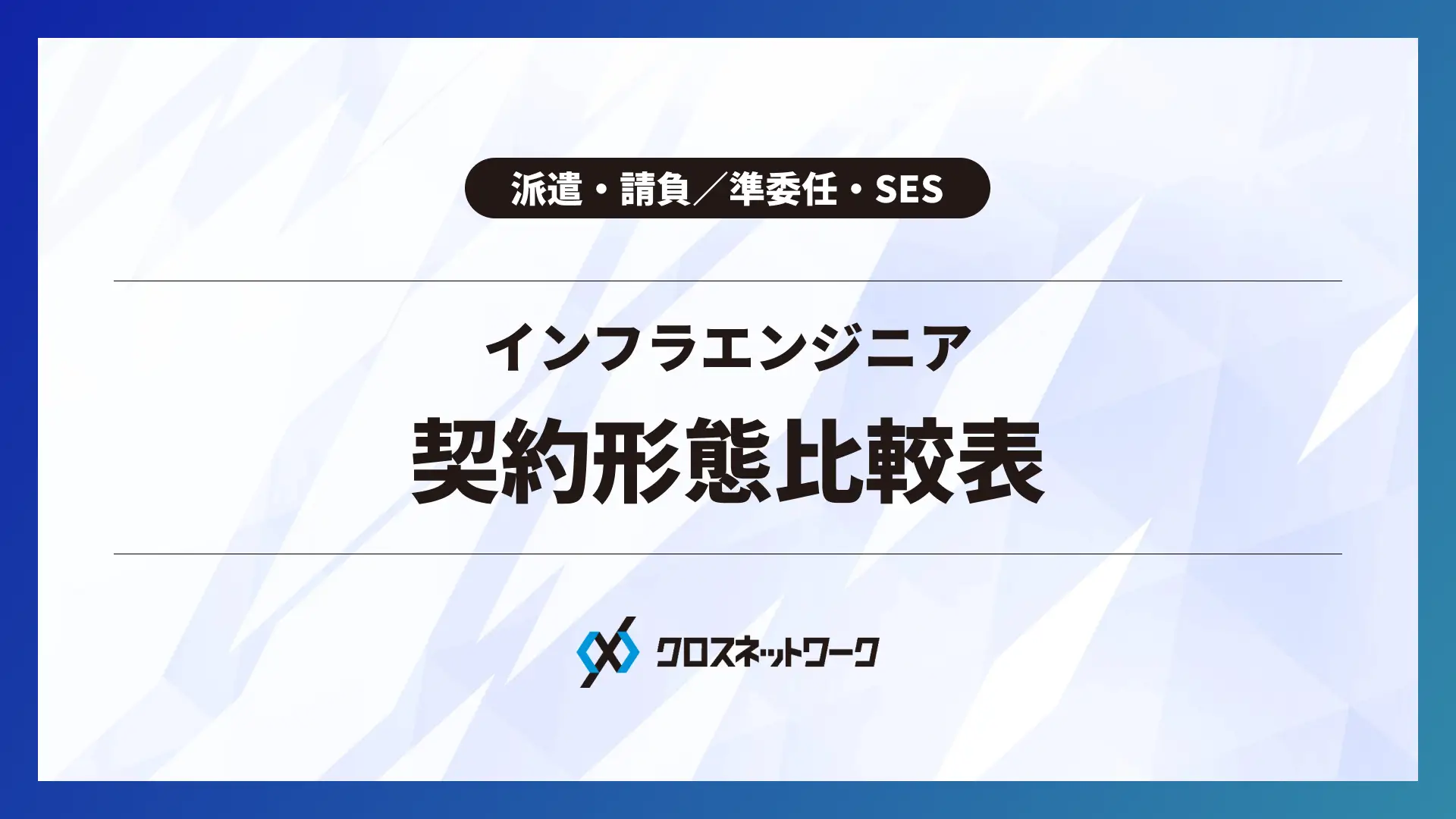
SES
SES(システムエンジニアリングサービス)は、必要な期間だけ外部のエンジニアを確保できる契約形態です。SES企業と契約を結び、所属エンジニアを自社のプロジェクトにアサインできます。
SESを活用するメリットは、一時的なリソース不足を迅速に解消できることです。プロジェクトの繁忙期や人員の離脱をカバーするための人材確保に適しています。
ただし、エンジニアの所有権と指揮命令権がSES企業側にあるため、発注側は直接的に業務指示を出せない注意点があります。一般的に成果物に対する責任を負わない準委任契約を結ぶため、自社の担当者による品質・進捗の管理も必要です。
関連記事:インフラエンジニアのSES採用とは?フリーランスとの比較も解説
エンジニア派遣
エンジニア派遣もSESと同様に、あくまでも一時的なリソース確保の側面が強い契約形態です。派遣会社から紹介されたエンジニアに対して、自社が直接指揮命令を行いながら業務を進めます。
自社の担当者が業務の進め方や優先順位を直接指示できるため、SESに比べてマネジメントしやすいのも特徴的です。そのため、自社のルールや開発スタイルに沿って作業を進めてほしい企業に適しています。
ただし、派遣社員を受け入れられる期間は、派遣法によって原則として「最長3年まで」と定められています。また、派遣されるエンジニアのスキルレベルに差があり、必ずしも期待どおりの人材が確保できるとは限りません。
関連記事:インフラエンジニアを派遣会社で採用するメリット|他の契約との違いも解説
業務委託(フリーランス)
業務委託を活用するメリットは、特定の技術領域に特化したエンジニアを確保しやすいことです。とくにフリーランスとして活動する通信エンジニアには、専門分野で豊富な実務経験を積んでいる即戦力としての活躍が期待できます。
また、週2〜3日の稼働や運用・保守の長期対応など、SESやエンジニア派遣では依頼が難しい柔軟な契約条件の提示も可能です。さらに、自社の一員としてプロジェクトに参画するため、社内に新しい技術やノウハウを共有・蓄積しやすい特徴もあります。
ただし、基本的に個人と契約するため、信頼できる人材かどうかの判断や契約・労務管理が必要です。契約面の不安を感じる場合は、人材紹介や契約のサポートを依頼できるエージェントサービスの活用も検討してみましょう。
関連記事:フリーランスのインフラエンジニアに業務を委託する流れとは?単価相場や注意点も解説
優秀な通信エンジニアを探すならクロスネットワークがおすすめ
通信エンジニアは、社内外の通信インフラ構築に欠かせない存在です。安定稼働を実現するための要件定義から運用・保守まで幅広い役割を担います。
とくに通信インフラの障害が発生したときには、被害を最小限に抑えるための迅速な初期対応が求められます。しかし、必要に迫られてから採用を検討しても、自社のニーズに適した人材をスムーズに確保できるとは限りません。
通信エンジニアを確保する手段は、正社員採用が一般的です。しかし、人材確保までのスピードや柔軟性を求める場合は、自社の状況やリソースにあわせて「外部委託」という選択肢も検討してみましょう。
クロスネットワークでは、インフラ構築のスキルに優れたフリーランスの通信エンジニアを迅速にマッチングいたします。プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。
クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の依頼にも対応しているので、解決したい課題やご要望に応じて柔軟な外注をサポートいたします。
サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。柔軟な契約条件で通信エンジニアを確保するなら、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。