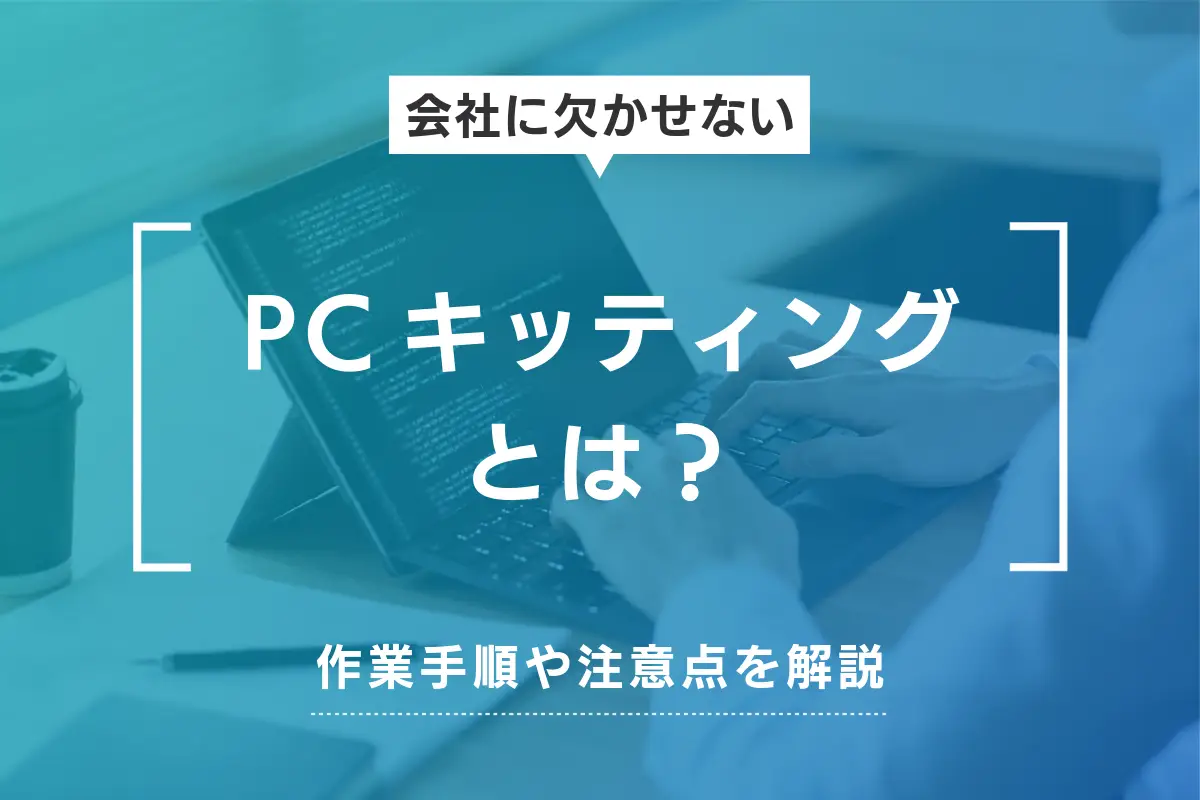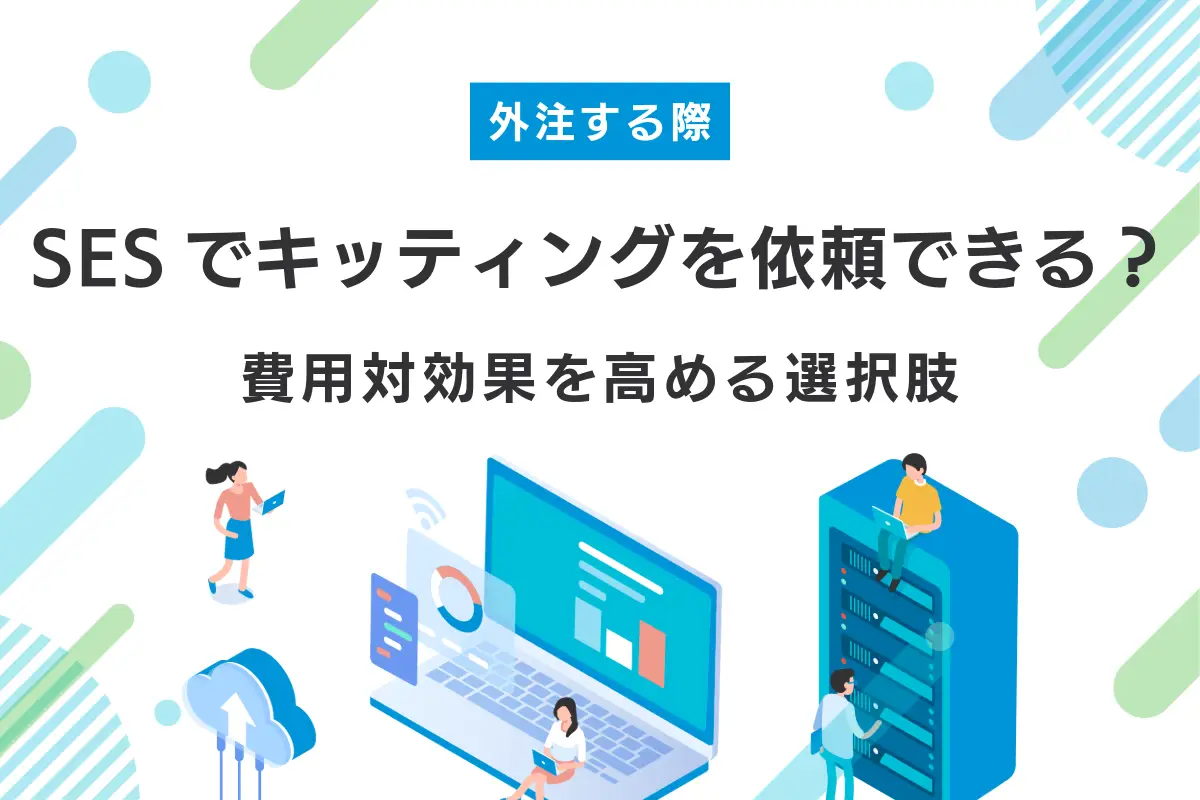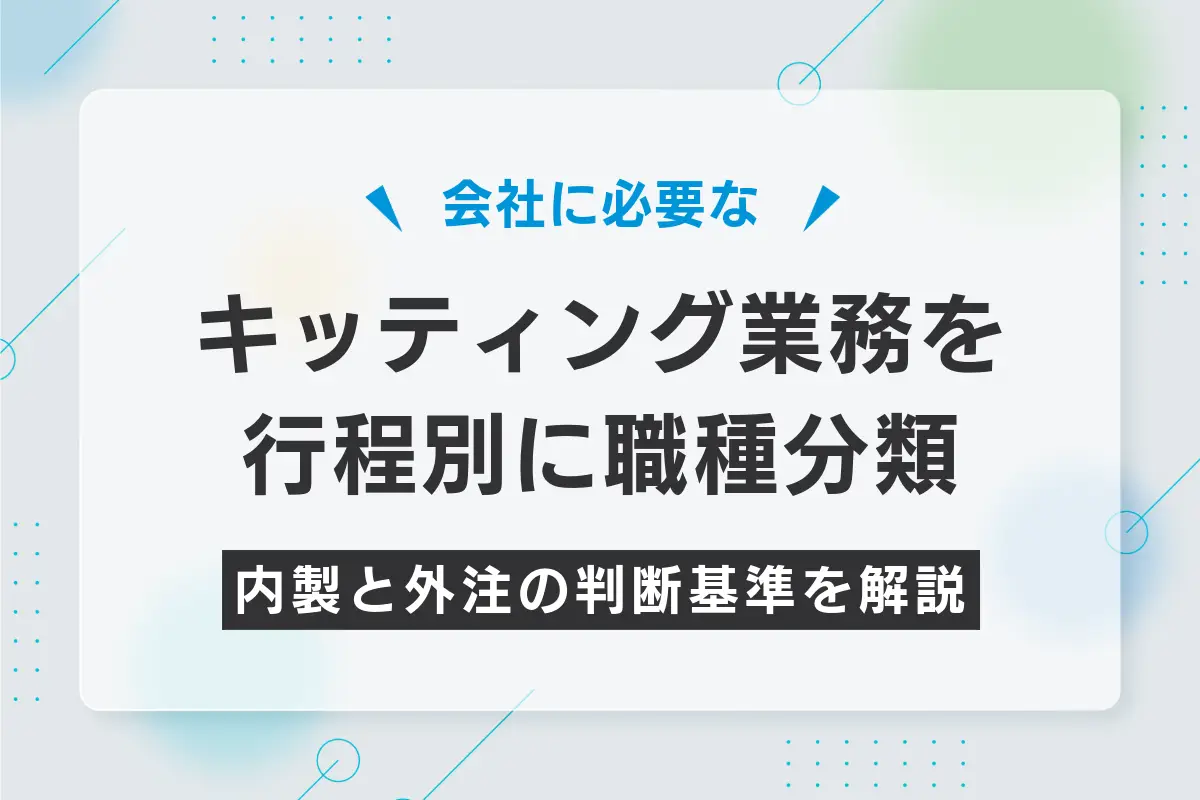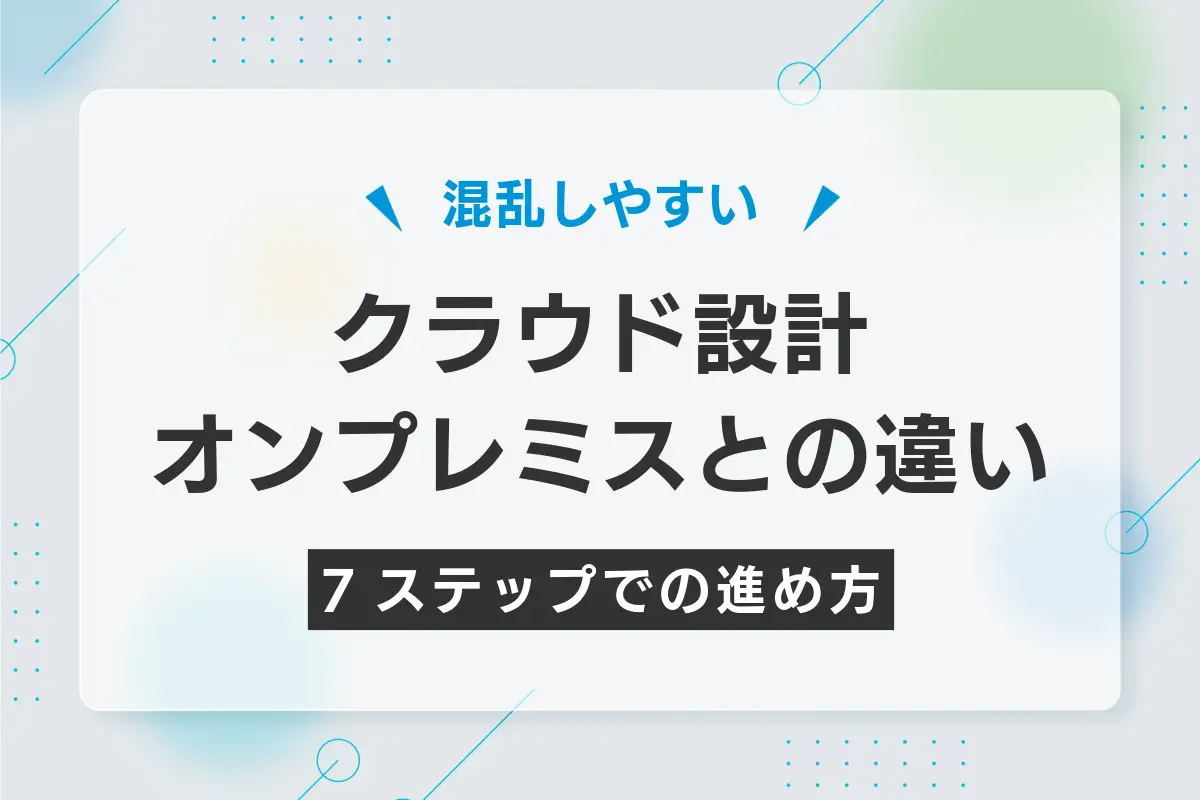
新入社員の入社やPCの入れ替え時期など、PCセットアップの問い合わせ対応に追われて「本来の業務が進まない」と悩んでいませんか?
社員にPCの初期設定を任せると効率的に思えますが、実際には情報システム部門への問い合わせが殺到しがちです。そこで、セットアップではなく「PCキッティング」を導入すれば、社員の手間なく業務で利用できる状態に整えられます。
そこで今回は、PCキッティングの主な流れを「手作業」と「クローニング」に分けて解説します。また、リソース不足を解消する外部委託のメリットも解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
PCキッティングとは
PCキッティングとは、業務用の端末を「すぐに使える状態」に準備する一連の業務です。新しい端末を受け取った従業員が設定不要で業務を開始できる状態に整えるため、以下のように幅広い作業が含まれています。
- OSやソフトウェアのインストール
- 社内ネットワークへの接続設定
- 周辺機器やケーブルの設置
PCキッティングの目的は、全社で統一されたセキュリティポリシーの適用や業務アプリケーションの標準化です。社員が個別に設定する手間を省けるだけでなく、情シス担当者が問い合わせに対応する負担の軽減にもつながります。
キッティングとセットアップの違い
キッティングとセットアップには、対応する目的と作業範囲に違いがあります。
| セットアップ |
|
| キッティング |
|
OSのインストールやアカウント設定など、一般的にセットアップは初期設定まで対応する意味合いで用いられています。PCを例に挙げると、ログインできる状態まで設定する業務です。
キッティングの場合は、業務用のソフトウェアやデバイスの設定、社内ネットワークへの接続設定などにも対応します。キッティングの一部にセットアップが含まれており、業務で使える状態まで設定する業務です。
関連記事:キッティングとセットアップの違いは?おすすめの外注先も紹介
PCキッティングの代表的な2つの手法
PCキッティングの手法は、以下の2種類が一般的です。
- 手作業:個別設定に適している
- クローニング:マスターイメージを複製できる
どちらの手法にもメリットとデメリットがあるため、目的や導入台数に応じて使い分けるのが効果的です。
手作業:個別設定に適している
手作業によるPCキッティングは、1台ずつ手動で設定する基本的な手法です。OSのセットアップから業務アプリ・ネットワークの設定まで、一つひとつ人の手で進めていきます。
とくに、キッティングするPCの台数が少ない場合に効果的です。ただし、1台ずつキッティングするため、以下のようなデメリットを考慮する必要があります。
- 導入台数が増えると作業工数が膨大になりやすい
- 手作業によるヒューマンエラーが発生しやすい
- 担当者によって品質やペースにばらつきが出やすい
しかし、導入台数が少ない場合や端末固有の特殊な設定を入れたいときには、個別で対応する手作業のキッティングが適しています。部署や役職によってインストールするソフトウェアが異なる場合や、研究開発部門のように端末固有の特殊な設定が必要なケースに柔軟な対応が可能です。
次項の見出しで解説する「クローニング」と呼ばれる手法を用いる場合も、コピー元の端末を手作業で作成する必要があります。そのため、PCキッティングにおいて、手作業の工程が完全になくなるわけではありません。
クローニング:マスターイメージを複製できる
クローニングは、基盤となる1台のPC(マスターイメージ)を別PCに展開(コピー)する手法です。設定が統一されたPCをスムーズに展開できるメリットがあります。
インストールしたソフトウェアや各種設定を複製できるので、作業工数だけでなく手作業によるミスの軽減も可能です。また、マスターイメージの設定情報がすべてのPCに反映されるため、品質を均一化できる板のようなメリットも得られます。
- ソフトウェアのバージョン違いが発生しない
- 必要な設定が漏れたり間違ったりしない
- PCトラブルの原因を特定しやすい
ただし、クローニング用のツールが必要になるため、仕組みの理解や使い方の把握が求められます。マスターイメージの作成段階で設定ミスがあると、すべてのPCに不具合が反映されてしまうため注意が必要です。
関連記事:キッティングを効率化する方法は?外注時の主な委託先も紹介
PCキッティング作業の主な流れ
ここからは、一般的なPCキッティングの流れを代表的な2つの手法に分けて解説します。
| 項目 | 手作業 | クローニング |
|---|---|---|
| 概要 | すべての工程を人の手で実施する | マスターイメージを展開(複製)する |
| 主な流れ |
|
|
| 適しているケース |
|
|
クローニングを用いる場合でも手作業のキッティングが必要なため、どちらの流れも理解しておきましょう。
手作業によるPCキッティング
手作業によるPCキッティングでは、すべての工程を人の手で順番に進めていきます。主な流れは、以下のとおりです。
- PC梱包の開封
- 通電と周辺機器の接続確認
- OSの初期設定
(言語、地域、アカウント作成など) - ネットワーク設定
(社内LAN・Wi-Fiの接続など) - 業務アプリ・セキュリティソフトのインストール
- 共通設定
(初期パスワード・プリンタ・共有フォルダ・不要データの削除など) - 個別設定
(端末専用ソフトのインストール・スタンドアロン設定など) - 動作確認
- Active Directory設定・管理台帳への登録
- 資産管理ラベルの貼り付け
手作業のキッティングが完了したPCは、マスターイメージとしてクローニングに活用可能です。クローニングによって端末設定を複製すれば、OSの初期設定以降の工程を自動化できます。
ただし、以下のように端末固有のアプリや設定が必要な場合は、手作業で個別設定の反映が必要です。
- セキュリティ設定が異なるPC(経理・会計用など)
- 特定業務で専用端末が必要なPC(CAD・計測機器制御など)
- スタンドアロンで使用する端末(ゲストユーザー用PC)
クローニングでは、共通的な設定のみを切り出して展開するのが効果的です。役職や部署によって個別対応が必要な場合は、クローニング後に手作業でキッティングしましょう。
クローニングによるPCキッティング
クローニングの主な流れは、以下のとおりです。
- マスターイメージ用のPC作成
(手作業によるPCキッティングで1台用意する) - マスターイメージ用のPCでWindowsの標準ツール「Sysprep」を実行
(SIDなどのPC固有の情報を削除して複製できる状態にする) - クローニング用ツールでPCのディスクイメージを抽出・保存する
(抽出したデータがマスターイメージとなる) - マスターイメージを複製したいPCに展開する
(社内ネットワークまたはUSBメモリなどでデータ転送する) - PC固有の情報を設定
(コンピュータ名やIPアドレスなど) - 動作確認
- Active Directory設定・管理台帳への登録
- 資産管理ラベルの貼り付け
クローニングには、手作業で実施していた一部の対応を自動化できる魅力があります。たとえば、マスターイメージから共通の設定やインストールソフトのコピーが可能です。
また、数十台のPCをまとめてキッティングできるので、新入社員の端末や全社的な端末のリプレイスに便利です。一般的なクローニングには、以下のような市販の専用ツールが活用されています。
ただし、PC固有の設定であるコンピュータ名やIPアドレスなどは、端末ごとに手作業で設定する必要があることを留意しておきましょう。
クローニング作業を実施するうえでの注意点
クローニングには、事前に把握しておきたい注意点があります。見落としがあるとライセンス違反やシステムトラブルの原因となるため、とくに以下のような観点に注意しましょう。
- ボリュームライセンスを利用する(WindowsOSの場合)
- マスターイメージには複製したい情報のみを設定する
- 事前にマスターデータの動作検証を実施する
ボリュームライセンスを利用する(WindowsOSの場合)
| OEMライセンス |
|
| ボリュームライセンス |
|
クローニングには、インストールされたOSのライセンス契約に注意が必要です。PC本体とセットで提供されているOEM版のライセンスは、ほかの端末への複製が許可されていません。
OEM版のライセンスが含まれたマスターイメージを複製するとライセンス契約違反となってしまうため、企業向けの「ボリュームライセンス」と呼ばれるライセンス契約が必要です。
マスターイメージには複製したい情報のみを設定する
クローニングではPCの端末情報を複製するため、マスターイメージに以下のような識別情報を含めるべきではありません。
- コンピュータ名(ホスト名)
- アカウント情報
- IPアドレス
- OEMライセンスのプロダクトキー
複数のPCで識別情報が重複すると、ライセンス認証やドメイン参加などの不具合が発生します。また、一時的にインターネットや社内サーバーに接続できなくなる通信障害が発生するケースも少なくありません。
識別情報の重複を避けるため、マスターイメージの作成時に以下のようなツールでPCの固有情報を削除するのが一般的です。
- Sysprep(WindowsOSの標準ツール)
- ディスクユーティリティ(MacOSの標準ツール)
事前にマスターデータの動作検証を実施する
動作検証に不備のあるマスターイメージを展開してしまうと、不具合が発生するPCが大量に複製されてしまいます。複製された大量のPCを修正するには、手戻りによる大幅な作業工数がかかるため注意が必要です。
マスターイメージの作成時には、以下のような動作検証を一つひとつ確実に実施しておきましょう。
- インストールしたソフトウェアが正常に動作するか
- ネットワークや共有フォルダに問題なく接続できるか
- マウスやプリンターなどの周辺機器が正しく認識されるか
PCキッティングのリソース不足は外部委託で解消できる
社内の情シス担当者だけでは、PCキッティングに十分なリソースを割けない可能性もあります。クローニングを実施する場合でも、動作検証やマスターイメージの準備が必要です。
そこで、社内のリソース不足を解消するため、専門業者への外部委託を検討してみましょう。ここからは、PCキッティングを外部委託するメリットを解説します。
関連記事:キッティング作業は正社員が担当すべき?外部委託の判断基準も解説
繁忙期に複数台のキッティングを依頼できる
新入社員の入社時期や全社的なPC入れ替え時期など、短期間に大量のキッティング作業が必要な場合に外部委託が効果的です。自社でキッティングの人員を増やすことなく、必要なときに必要な分だけ外部リソースを活用できます。
PCキッティングを専門的に請け負う代行業者であれば、複数台のPCを効率的に処理するノウハウや設備を保有しています。作業が集中しやすい繁忙期でも、品質を保ちながら迅速な対応が期待できるでしょう。
関連記事:キッティング代行とは?メリットや活用が適しているケースなどを紹介
専門知識が必要な対応を委託先に一任できる
PCキッティングの作業には、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。たとえば、専用ツールを用いるクローニングでは、操作手順やライセンス管理に関する知識が必要です。
外部委託を活用すれば、専門知識が必要な対応を経験豊富な専門家に一任できます。リモートで端末をキッティングできる「Windows Autopilot」のように、最新手法の導入サポートにはエンジニアのスキルを活用するのも効果的です。
関連記事:キッティング作業で求められるエンジニアスキル|人材確保のコツも解説
社内リソースを本来のコア業務に割り当てられる
PCキッティング作業を丸ごと外部委託することで、情シス担当者のリソースを本来注力したいコア業務に集中できます。とくに一時的な作業や小規模な作業などを柔軟に依頼したい場合は、フリーランスのエンジニアを活用するのも効果的です。
また、エージェントサービスを活用すれば、自社の要件にマッチする人材をスムーズに見つけられます。契約手続きや交渉も代行してくれるメリットがあるため、フリーランスとの契約が初めてでも安心です。

PCキッティングに強い技術者を探すならクロスネットワークがおすすめ
社内にPCキッティング作業を導入すれば、業務端末の設定を効率化できるだけでなく、従業員がスムーズに業務を開始できます。ただし、手作業によるキッティングにはヒューマンエラーのリスクがあり、クローニングによる効率化には専門知識が必要です。
キッティング作業のメリットを最大限に引き出すためには、企業の状況やリソースにあわせて「外部委託」を検討してみましょう。とくにキッティング作業の経験豊富なエンジニアを確保するなら、エージェントサービス「クロスネットワーク」がおすすめです。
クロスネットワークでは、PCキッティング作業の経験豊富なインフラエンジニアを迅速にマッチングいたします。プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。
クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の依頼にも対応しているので、解決したい課題やご要望に応じて柔軟な外注をサポートいたします。
サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。柔軟な契約条件でインフラエンジニアを確保するなら、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。