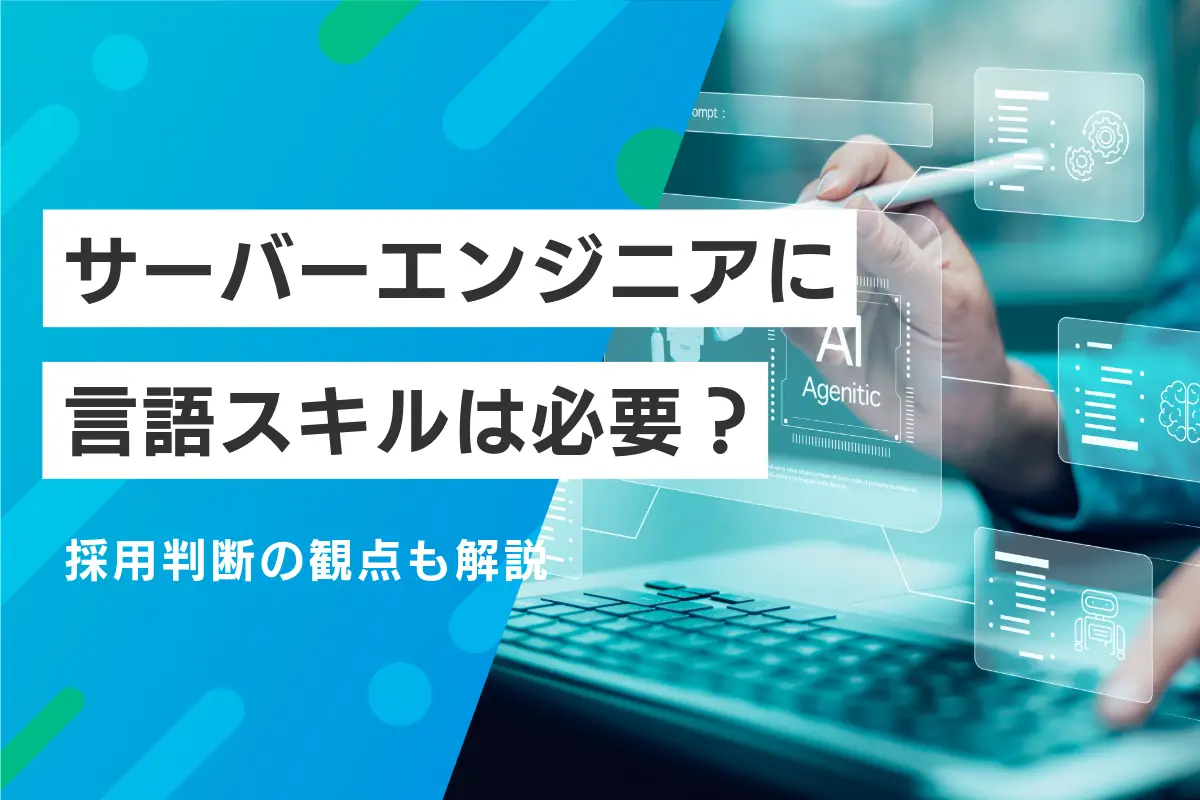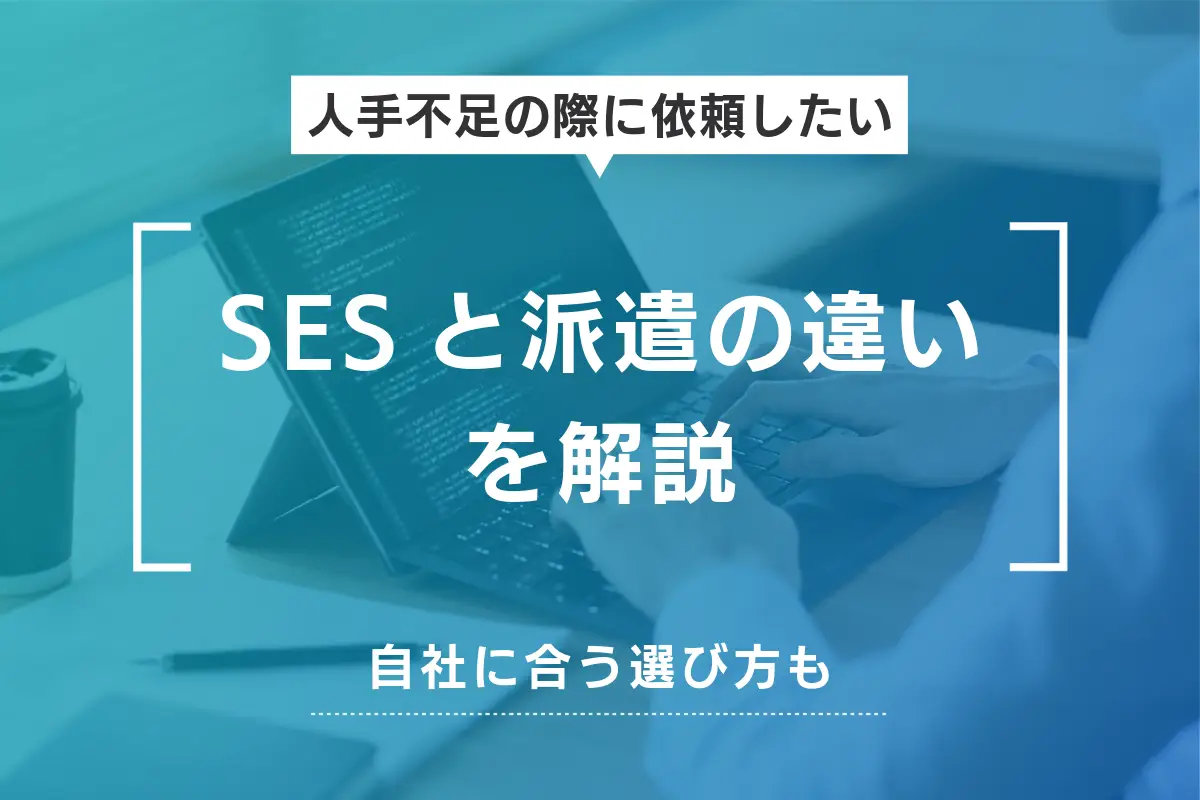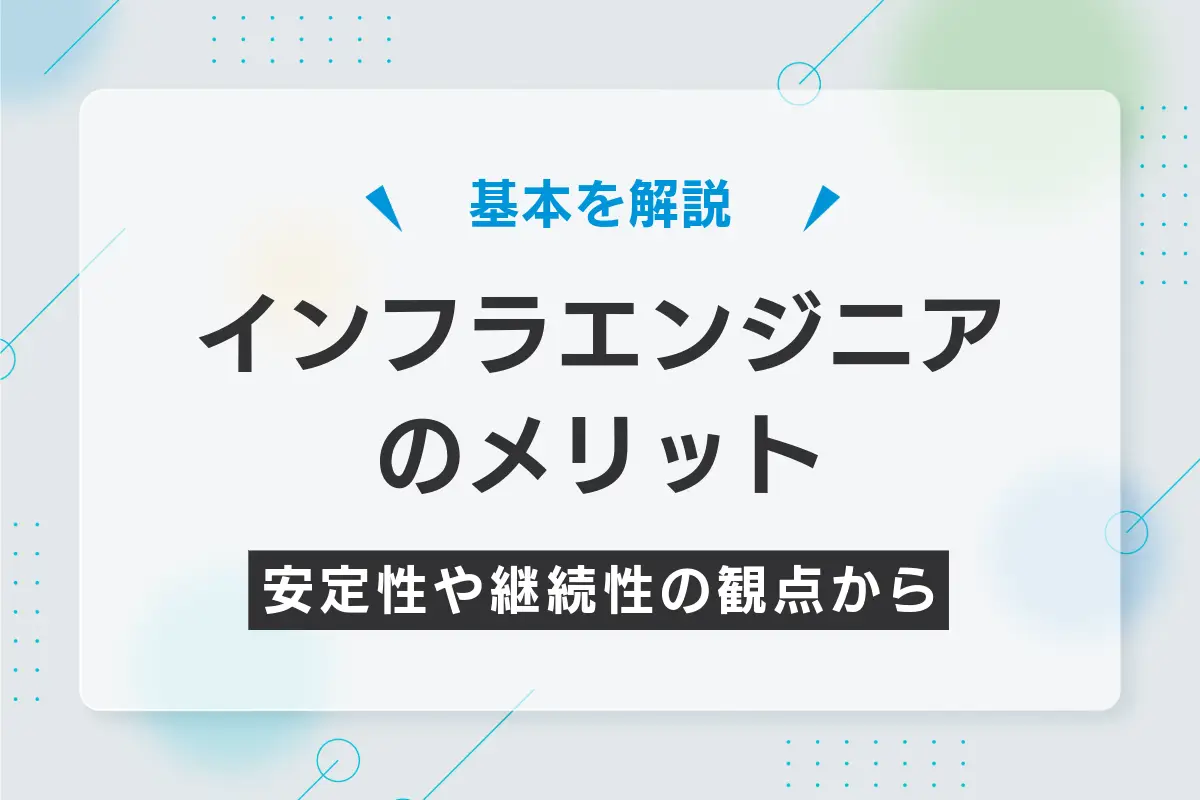サーバーエンジニア採用の評価基準として「プログラミング言語の知識」が必要かどうかに悩んでしまいますよね。スキルのミスマッチを防ぐためには、採用前に募集要項を明確化しておくのが理想的です。
そこで今回は、サーバーエンジニアにおけるプログラミング言語の必要性について解説します。インフラエンジニア経験のある筆者が、課題解決に役立つ主要言語や採用判断のコツも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
【結論】サーバーエンジニアにプログラミング言語の知識は必要
結論として、インフラ業務の質と効率を向上させるためには、サーバーエンジニアにプログラミング言語のスキルが求められます。
- プログラミングスキルでインフラ業務の運用を効率化できる
- インフラ構成のコード化(IaC)が重要視されている
クラウド化が推進されるなか、複雑なインフラ業務の手作業による運用には効率化が求められています。定型業務の自動化やインフラ構成をコード管理する手法には、プログラミング言語の知識が必要です。
プログラミングスキルでインフラ業務の運用を効率化できる
プログラミング言語の知識を用いてスクリプトやバッチ処理を作成すると、以下のような日々の運用業務(とくに手作業の定型業務)を効率化できます。
- サーバーの初期設定
- 日常的なシステム監視
- 問題解析に用いるログ収集
- 障害発生時の一次対応
一連の作業手順を自動実行させるスクリプトやバッチ処理の作成には、プログラミング言語のスキルが必要です。オンプレミス環境はもちろん、クラウドサービスを利用する場合も業務の自動化・効率化に言語スキルを活用できる場面は少なくありません。
インフラ構成のコード化(IaC)が重要視されている
インフラ技術のトレンドとして「IaC(Infrastructure as Code)」と呼ばれる手法が重要視されています。IaCとは、サーバーやネットワークといったインフラ構成をプログラムコードのようにテキストファイルで管理する手法です。
IaCを導入すると、インフラを自動構築できる時短効果はもちろん、手作業による設定ミスといったヒューマンエラーの防止効果も期待できます。また、同じ設定のインフラ環境を正確に再現できるため、テスト環境の構築や障害時の復旧もスムーズです。
IaCは「コードで管理する手法」のため、プログラミングのようにコードを書くスキルがあると仕組みをスムーズに理解できます。なお、今回は自動化に活用できるプログラミング言語を中心に解説するため、IaCで利用される「データ言語」については関連記事で解説します。
関連記事:インフラエンジニアにプログラミングスキルは必要?主な使用言語も紹介
サーバーエンジニアが扱う主要プログラミング言語
サーバーエンジニアの業務で使用頻度が高いプログラミング言語やスクリプト言語を5つ紹介します。
- Bash(シェルスクリプト)
- PowerShell
- Python
- Go
- Ruby
サーバーエンジニアのスキルセットを見極めるなら、各言語の特徴や活用シーンを把握しておきましょう。
関連記事:サーバーエンジニアのスキルセットとは?クラウド領域における必要性も解説
Bash(シェルスクリプト)
Bashは、LinuxやCentOSなどのUNIX系OSで標準的に利用されるスクリプト言語です。サーバーエンジニアがインフラを運用するうえで、基本的かつ使用頻度の高い言語といえます。
Bashを用いたシェルスクリプトは、コマンドによる作業の自動化や簡易的なデータ処理に活用するのが一般的です。たとえば、以下のような処理を実装できます。
- 深夜にサーバーデータを自動バックアップする
- 出力されたエラーログを管理者に通知する
また、主要なクラウドサービスでは、ブラウザ上でコマンド管理できるツール「Cloud Shell」を活用するときにBashの知識が役に立ちます。
PowerShell
PowerShellは、Windows環境向けのスクリプト言語です。Linux環境におけるBashのように、Windows Serverをコマンド管理する役割があります。
また、OSの細かな設定変更やMicrosoft社の製品(Active DirectoryやExchange Serverなど)の操作を効率化する用途にも便利です。Windows系のサーバーでインフラを構築・運用するなら、PowerShellの知識をもつサーバーエンジニアがいると重宝します。
Bashと同様に、クラウド環境でもPowerShellの知識が役立ちます。OSに依存しない柔軟な対応を期待するなら、PowerShellとBashの両方を扱えるエンジニアが適任です。
Python
Pythonは、インフラ分野で需要が高まっている汎用的なプログラミング言語です。文法がシンプルで読みやすく、プログラミング経験が浅い人でも習得しやすい特徴があります。
また、プログラムによく使う機能をまとめた「ライブラリ」が豊富に揃っていることも人気を集める理由です。Webアプリケーション開発からデータ分析、さらには機械学習まで幅広い用途に対応できます。
サーバーエンジニアの業務では、クラウドサービスをはじめとするAPIの操作や連携にもPythonが活用されています。
Go
Go(Golang)は、Google社が開発したプログラミング言語です。プログラムの実行速度に優れた特徴があり、とくにサーバーサイドで処理を同時実行する「並列処理」に活用されています。
Goの特徴は、作成したプログラムが「1つの実行ファイル」にまとまるシングルバイナリを生成できることです。シングルバイナリによって、Goをインストールしていない環境でも処理を実行できます。
また、コンテナ技術の代表格である「Docker」や「Kubernetes」は、Goで開発されたツールです。Goの言語スキルがあるサーバーエンジニアは、主要ツールの仕組みを深く理解し、より高度な活用を期待できます。
Ruby
Rubyは、日本で開発されたオブジェクト指向のプログラミング言語です。Pythonと同様に、シンプルに記述しやすい使い勝手の良さが人気を集めています。
サーバーの構成管理を自動化する「Chef」や「Puppet」は、Rubyで開発されたツールです。レシピやマニフェストと呼ばれる設定ファイルを記述したり、機能を拡張したりするときにRubyの知識が役立ちます。
また、Web開発で用いられるフレームワーク「Ruby on Rails」との連携にも便利です。開発言語をRubyに統一できるので、システム開発チームとのスムーズな意思疎通や問題解決につながります。
【採用判断】言語スキルをもつサーバーエンジニアの見極め方
サーバーエンジニアの採用において、言語スキルの評価基準は設定に悩みがちな課題です。まずは以下の観点で、自社に必要な言語スキルを判断しましょう。
- 自社のインフラ環境に適しているかどうか
- 求める業務内容に適しているかどうか
特定の言語スキルではなく、状況に応じて複数の言語を使い分けられるサーバーエンジニアの採用が理想的です。
自社インフラに適したプログラミング言語で判断する
| 自社のインフラ・状況 | 関連性の高い言語(一例) |
|---|---|
| Linuxを使用している | Bash |
| Windows Serverを使用している | PowerShell |
| クラウド環境の構築・操作 | Python |
| コンテナ技術の活用 | Go |
| Webサービス(Ruby on Rails)との連携 | Ruby |
サーバーエンジニアの言語スキルを評価するなら、自社のインフラ環境との関連性を確認すべきです。たとえば、社内のサーバーOSがLinuxで構成されているなら、基本的な操作や自動化に用いるBashの知識が欠かせません。
さらに、事業の目的や状況に応じて必要な言語が異なります。クラウドサービスを活用したインフラ構築を進めるなら、Pythonを使った各種APIの操作スキルが役立ちます。自社のインフラに適した言語スキルかどうかで、採用候補者の評価を判断しましょう。
業務内容や課題に適したスキルレベルで判断する
サーバーエンジニアに任せたい業務や解決したい課題にあわせてスキルレベルを判断しましょう。同じ言語を扱えるサーバーエンジニアでも、経験や習熟度によって任せられる業務範囲は異なります。
たとえば、情報処理推進機構(IPA)の定義によると、以下のようにスキルレベル(ITSS)が定められています。
| スキルレベル(ITSS) | 期待できるスキル |
|---|---|
| レベル1 | ITにかかわる最低限の基礎知識を理解している(実務未経験者や新入社員に該当) |
| レベル2 | 指導者のもとで基礎知識や実践スキルを発揮できる |
| レベル3 | 単独(指導者なし)で応用的な知識や実践スキルを発揮できる |
| レベル4 | よりハイレベルなスキルで業務の課題発見・解決をリードできる |
(参考:2.ITスキル標準とは-ものさしとしてのスキル標準|IPA 独立行政法人 情報処理推進機構)
採用後のミスマッチを防ぐためにも、要件にあわせたスキルレベルを具体的に設定しておくのが理想的です。スキルレベルを設定しておけば、入社後のエンジニアの育成目標としても活用できます。
言語スキルが高いサーバーエンジニアを探すポイント
言語スキルが高いサーバーエンジニアを探すなら、以下のポイントを意識しましょう。
- 募集要項に必要言語を明記する
- 過去の業務経験を具体的に質問する
採用後のミスマッチを防ぐためには、自社の課題解決に貢献できる人材かどうかの見極めが必要です。
募集要項に必要言語を明記する
 出典:フリーランスインフラエンジニア・業務委託採用|クロスネットワーク
出典:フリーランスインフラエンジニア・業務委託採用|クロスネットワーク
採用におけるミスマッチを防ぐコツは、募集要項に求めるスキル(言語・レベル)を明記することです。採用側の意図が候補者に正しく伝わらないと、条件にあわない応募が増えるだけでなく、選考に不要な工数がかかってしまいます。
募集要項には、具体的な言語名や経験年数を示すと効果的です。さらに、依頼の背景や目的を添えると、候補者自身も「どのように貢献できるか」を具体的にイメージできます。
大手エンタメ企業のオンラインプラットフォームジニアリングに取り組むことができます。 ・k8sの運用 ・CDパイプラインの運用 ・Terraformによるリソース管理 ・エコシステム導入(Istioのようなk8sのエコシステムが中心です 【開発環境】 言語:Go インフラ環境:GCP, AWS CI:Github Actions Monitoring: Datadog, PagerDuty 【担当工程】 案件定義/基本設計/詳細設計/開発/結合T/ユーザーT/保守改修/研究開発/基盤設計 障害対応(オンコール対応)
#クライアントワーク #フルリモート #リモートワーク #週4日〜5日稼働
たとえば、クロスネットワークの募集要項では、依頼内容に加えてインフラ環境や利用サービスも記載しています。募集要項の具体性を高めることで、自社のニーズに適したサーバーエンジニアからの応募が期待できるでしょう。
過去の業務経験を具体的に質問する
候補者との面談では、過去の業務経験について具体的に質問するのが効果的です。スキルシートや職務経歴書だけでは把握しづらい候補者のスキルを評価できます。
以下は具体的な質問例です。
- プログラミング言語を活用して業務課題を解決した経験はありますか?
- 作成したツールやスクリプトで工夫したポイントはありますか?
- もし〇〇の課題解決を依頼したら、どのような対応から始めますか?
さまざまな質問をとおして、課題に対する候補者のアプローチ方法や他メンバーへの配慮なども確認できます。言語の知識だけでなく、候補者の仕事への向き合い方も総合的に判断してみましょう。
| 【元インフラエンジニアのひとこと】 業務効率化のために作成したスクリプトが、サーバーOSのアップデートによって正常に動作しなくなった経験があります。スクリプトを作成したメンバーはすでに退職しており、開発環境や改修方法を誰も把握していない状況でした。 この経験から、業務効率化のためにツールやスクリプトを作成するときは、他メンバーが使ったりメンテナンスしたりできるような配慮の重要性に気づきました。面談時の質問をとおして、チームでインフラを構築する配慮や工夫に対する意識も確認すると、より信頼できるエンジニアに出会えるはずです。 |
即戦力のサーバーエンジニア採用ならフリーランスの活用がおすすめ
スキルの高い即戦力となるサーバーエンジニアを確保したいなら、フリーランス人材の活用がおすすめです。
- 条件にマッチする人材を確保しやすい
- 最新のトレンド技術を導入しやすい
- 採用・教育にかかるコストを削減できる
ここからは、上記3つの観点でフリーランスエンジニアの活用メリットを解説します。
条件にマッチする人材を確保しやすい
フリーランス市場では、特定の言語スキルや専門技術に特化したサーバーエンジニアを見つけやすい傾向があります。一般的なフリーランスにはプロジェクト単位で業務を委託するため、企業側も「Pythonでインフラ運用を自動化してほしい」のように具体的なスキル要件の提示が可能です。
たとえば「コンテナ技術を導入するため、Go言語とKubernetesの知見が豊富なエンジニア」といったピンポイントなニーズにも応えられます。募集要項に解決したい課題や求める言語スキルを明記すれば、より柔軟かつスムーズに候補者の選定が可能です。
最新のトレンド技術を導入しやすい
経験豊富なフリーランスのサーバーエンジニアを活用すれば、最新のスキルや技術を自社に導入しやすくなります。とくにクラウド領域は技術の進化が早く、コンテナ化やIaCなどの手法が豊富です。
社内のエンジニアだけで技術トレンドを追いながら、継続的に習得していくには負担がかかります。そこで、さまざまな企業のプロジェクトに参画するフリーランスエンジニアの知見を取り入れるのが効果的です。
自社でエンジニアを教育する時間やコストを削減しながら、新しいスキルや技術の導入をスムーズに進められます。
採用・教育にかかるコストを削減できる
正社員採用と比較して、フリーランスの活用には採用や教育にかかるコストの削減効果を期待できます。正社員を採用する場合は、月々の給与のほかに以下の付帯費用も必要です。
- 社会保険料(厚生年金・健康保険)
- 労働保険料(労災保険・雇用保険)
- 住宅・通勤手当
- 賞与
- 採用にかかるコスト
一方で、フリーランスとの契約は、業務委託が基本です。必要な期間や業務範囲を限定して依頼できるため、トータルコストを必要最低限に抑えられます。
とくに即戦力となる人材であれば、契約後の教育コストがほとんどかかりません。トータルの費用と時間を考慮すれば、フリーランスの活用は費用対効果の高い選択肢です。自社に適した業務形態を把握したい場合は、無料ダウンロードできる以下の資料も参考にしてみてください。
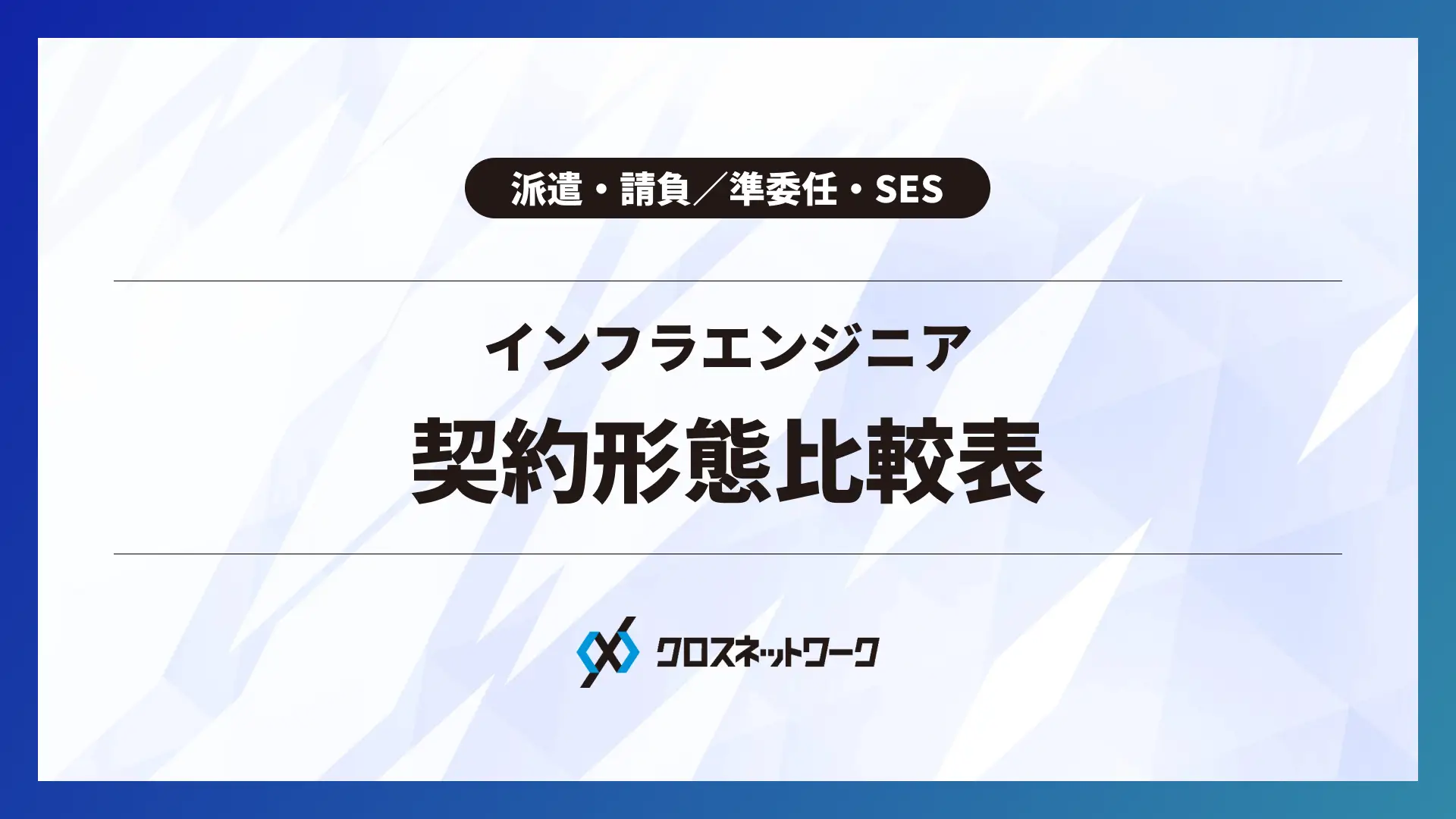
言語スキルに優れたサーバーエンジニア採用なら「クロスネットワーク」にご相談を
自社のインフラ課題を解決するなら、業務のボトルネックを解決できるサーバーエンジニアの存在が欠かせません。とくにインフラの構築・運用業務の効率化・自動化を求めるなら、言語スキルに強い人材を確保するのが理想的です。
しかし、クラウドの普及により、インフラ業務は複雑化しています。さまざまな業務に対応できる社内体制を整えるには、どうしてもエンジニアの教育に時間がかかってしまうはずです。そこで、柔軟な条件で即戦力を採用しやすいフリーランスエンジニアへの依頼を検討してみましょう。
クロスネットワークでは、即戦力としての活躍を期待できるサーバーエンジニアを迅速にマッチングいたします。プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。
クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の依頼にも対応しているので、ご要望に応じて柔軟な外注をサポートいたします。
サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。言語スキルに強いサーバーエンジニアをお探しの方は、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。