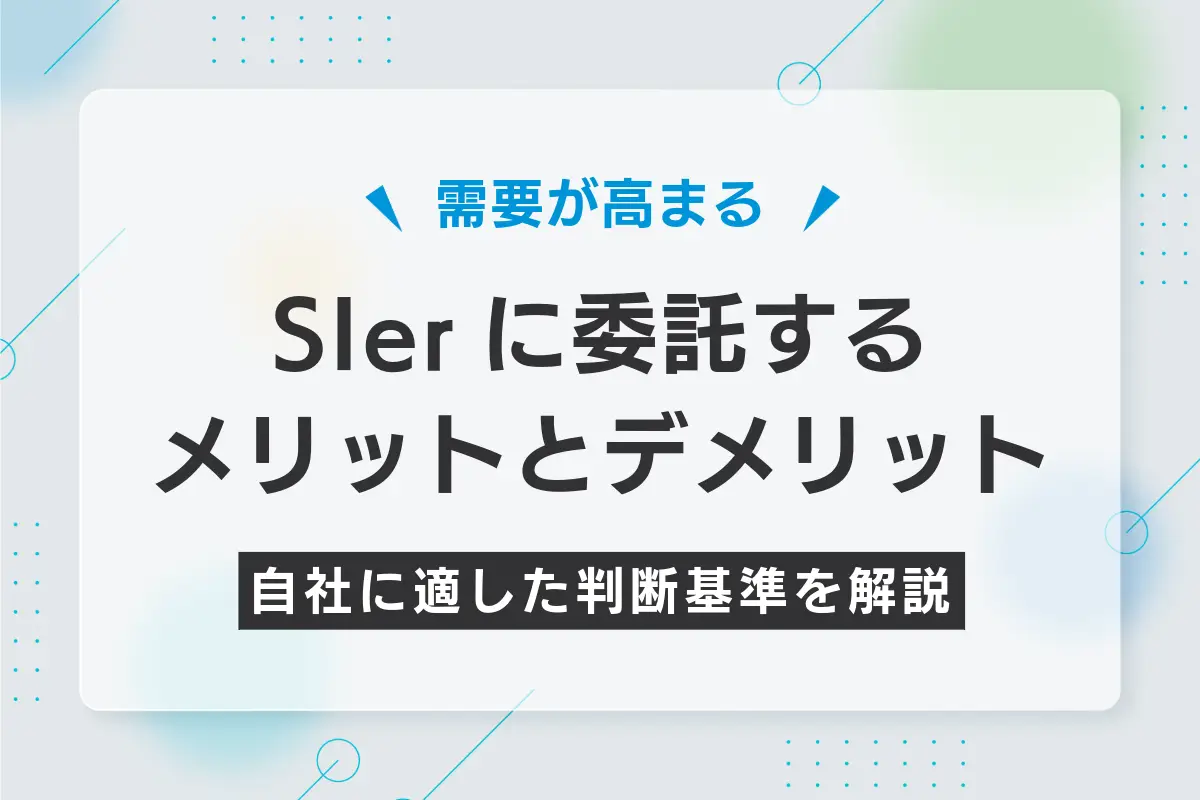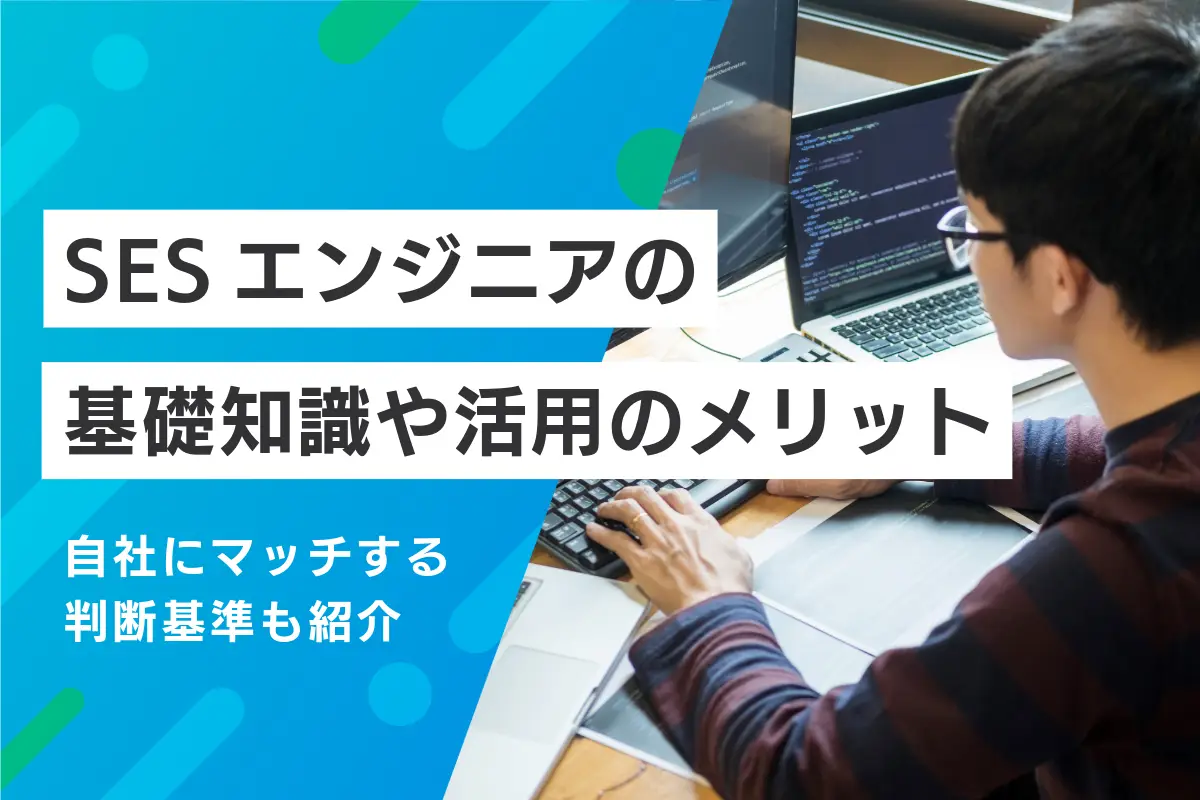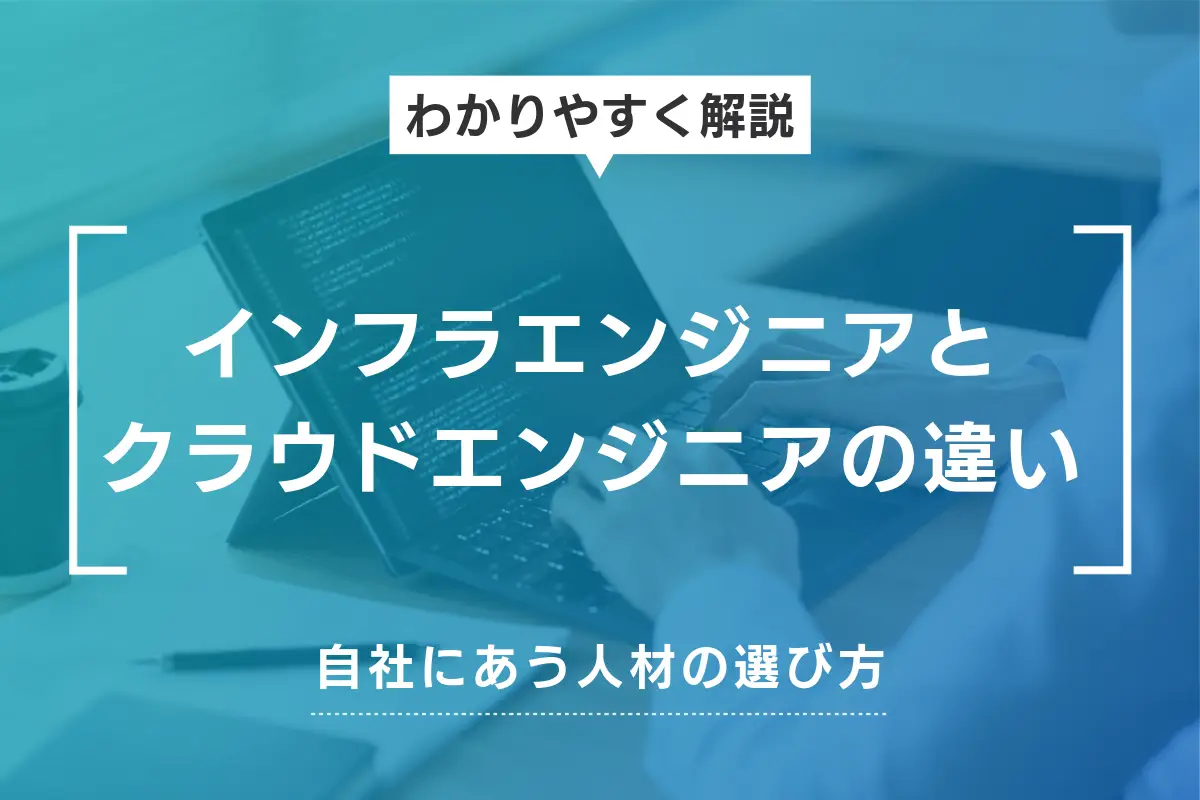システム開発やインフラ構築の外部委託を「SIer」に依頼すれば、プロジェクト全体を一貫して任せられるメリットがあります。
しかし、依頼のコストや柔軟性にかかわるデメリットも無視できません。
本記事では、外部委託を検討している企業に向けて、SIerのメリット・デメリット、フリーランス活用のメリットや判断基準について解説します。
SIerの種類
SIerの種類は、大きく分けて5つに分類されます。
まずは、それぞれの違いをおさらいしておきましょう。
| 分類 | 特徴 | 強み | 代表的な企業 |
|---|---|---|---|
| メーカー系 | ハードウェアメーカーから独立 | 親会社のハード・ソフトを用いた対応が得意 | 株式会社日立ソリューションズ NECソリューションイノベータ株式会社 |
| ユーザー系 | 大手企業のIT部門から独立 | 親会社の業界やビジネスに精通している | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 日鉄ソリューションズ株式会社 |
| 独立系 | SIer事業を目的として設立された企業 | クライアントの要望に合わせて自由度の高い提案が可能 | 株式会社オービック 株式会社大塚商会 |
| 外資系 | 海外IT企業の日本法人 | 海外企業のITサービスを導入しやすい | 日本オラクル株式会社 日本IBM株式会社 |
| コンサル系 | ITコンサルティングファームでプロジェクトを担当 | 顧客の経営課題や業務改善を企画段階からサポート | 株式会社キーエンス 株式会社野村総合研究所 |
信頼できるSIerを選定する3つのポイント
数多く存在するSIerから自社の課題解決に貢献する1社を見つけるためには、以下の選定基準が欠かせません。
委託先の候補をやみくもに探すのではなく、3つのポイントを意識して信頼できるSIerを選びましょう。
- SIerの分類(得意分野)を確認する
- SIerの開発体制を確認する
- SIerの過去の実績を確認する
1.SIerの分類(得意分野)を確認する
前述した通り、SIerの種類は「メーカー系」「ユーザー系」「独立系」「外資系」「コンサル系」の5つに分類されます。
メーカー系のSIerは、親会社の製品に関する深い知見を保有しています。
すでに社内で特定のメーカー製品を利用している企業であれば、メーカー系のSIerが有力な候補です。
また、商社や金融機関などの情報システム部門が独立した「ユーザー系」は、親会社が属する業界の豊富な業務知識があります。
業界に特化したシステム・インフラの構築を検討している場合は、ユーザー系SIerに相談するのも効果的です。
自社のプロジェクトが解決したい課題を明確にしたうえで、選定する分類の候補を絞り込みましょう。
2.SIerの開発体制を確認する
「多重下請け構造」や「ベンダーロックイン」といったリスクを避けるため、SIerの開発体制を事前に確認しておくことも重要です。
多重下請け構造を避けたい場合は、プロジェクトを担当するメンバーの構成について可能な範囲で確認しておきましょう。
依頼先のSIerに所属しているのか、あるいは協力会社の担当者なのかを知ることで、開発体制や責任の所在を明確化できます。
また、ベンダーロックインを防ぐためには、契約前に納品物の範囲や社内共有のフローなどを定めておく必要があります。
プロジェクトを委託先に丸投げするのではなく、社内に技術的なノウハウを残すための主体的な取り組みが欠かせません。
3.SIerの過去の実績を確認する
SIerが公開している過去の実績を確認すれば、技術力や課題解決力を客観的に評価できます。
特に自社と同業種または同規模のプロジェクトを担当した実績があるかどうかは、依頼後のミスマッチを防ぐためにもチェックしておきたいポイントです。
業界特有のセキュリティ要件や法規制を深く理解しているSIerであれば、要件定義から開発までのスムーズな進行を期待できます。
自社と類似するシステム・インフラの構築経験があれば、過去の対応から得られる知見が品質向上につながるはずです。
可能であれば過去の実績をもとに、自社プロジェクトの懸念事項を「どのように解決できそうか」と相談してみるのもおすすめです。
プロセスやノウハウまで踏み込んで確認しておけば、信頼できるパートナーかどうかを見極められます。
SIerに外部委託する3つのメリット
SIerへの外部委託には、以下のように自社で対応が難しい案件やプロジェクト管理を一任できるといったメリットがあります。
- プロジェクト全体を管理・進行してくれる
- 大規模・複雑なプロジェクトを依頼できる
- 社内リソースをコア業務に集中できる
まずはメリットを理解しながら、SIerへの外部委託が自社の状況に適した選択肢かどうかを見極めてみましょう。
プロジェクト全体を管理・進行してくれる
システム開発やインフラ構築は、要件定義から導入後の運用・保守まで多岐にわたる工程が必要です。
SIerに外部委託すれば、プロジェクト全体の進行管理や課題対応を任せられます。
また、SIerとの契約は、成果物の完成責任を負う「請負契約」が一般的です。
そのため、社内にITの事業部門がなくても、安心してプロジェクトを進められます。
契約範囲に応じて導入後のシステム監視や障害対応も含めて依頼できるため、大規模かつ長期的なプロジェクトの管理・進行役としてSIerは頼りになる存在です(監視や保守は準委任契約になるケースが多い)。
大規模・複雑なプロジェクトを依頼できる
基幹システムや公共事業案件など、自社のリソースでは対応が難しい大規模かつ複雑なプロジェクトを依頼できるのもSIerに外部委託するメリットです。
豊富な開発・構築実績や多数のエンジニアを有するSIerであれば、プロジェクトに必要な人材を一括で確保できます。
大規模なプロジェクトでは複数人のエンジニアを確保する必要があるため、自社のリソースのみで対応するのは比較的難易度の高い判断です。
設計から実装・テストまで包括的に対応するSIerに外部委託すれば、自社に開発ノウハウがなくてもプロジェクト全体を一任できます。
社内リソースをコア業務に集中できる
システム開発やインフラ構築をSIerに一任することで、社内のリソースを本来注力したいコア業務に集中させられます。
エンジニア不足が深刻化する現代では、採用活動が長期化するケースも少なくありません。
関連記事:インフラエンジニアの採用が難しい理由と優秀な人材を獲得する方法を解説
SIerに外部委託すれば、プロジェクトに必要なリソースをまとめて確保できます。
自社でエンジニアを採用したり教育したりする負担を軽減できるため、会社全体の生産性を高めるためにも社内リソースの最適化は重要な取り組みです。
「SIerのような管理体制は必要だけれど、コストは抑えたい」「大規模な開発ではないため、もっと柔軟に依頼したい」という場合は、「クロスネットワーク」の活用をおすすめします。
クロスネットワークでは、即戦力として期待できるフリーランスエンジニアを迅速にマッチングします。
タスク単位や機能単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。
SIerの外部委託で考慮したい3つのデメリット
SIerへの外部委託には、プロジェクトのリソース不足を解消できるメリットがあります。しかし、以下のように考慮しておきたいデメリットも存在します。
- 依頼コストが高額になりやすい
- 小規模案件やスポット対応に適していない
- 委託先に依存する状態に陥りやすい
外部委託に失敗しないためにも、デメリットをあらかじめ理解したうえで、自社のプロジェクトに適しているかどうかを慎重に判断しましょう。
依頼コストが高額になりやすい
SIerに外部委託する場合は、コストが高額になりやすいデメリットを考慮しておくのが理想的です。
プロジェクト全体の管理責任を担うSIerには、会社の利益を含む中間マージンの支払いも考慮する必要があります。
また、大規模なプロジェクトを請け負うため、下請け企業や孫請け企業に再委託する「多重下請け構造」に陥りやすい傾向があります。
複数の会社を経由するたびに中間マージンが発生するため、エンジニアの人件費と実際の発注金額に想定外の差を感じるケースも少なくありません。
ただし、プロジェクトの品質管理が徹底される安心感もあるため、コストだけでなく自社のリソースや業務負担も含めて総合的に判断しましょう。
小規模案件やスポット対応に適していない
柔軟性やスピード感が求められるプロジェクトには、SIerへの外部委託が適していないケースもあります。
SIerは、大規模なプロジェクトを管理・進行する強みがある反面、契約手続きや開発体制の構築といった準備段階に時間がかかる可能性も少なくありません。
そのため、以下のような要件には、SESやフリーランスといった選択肢も検討しておくのが効果的です。
- 開発・実装をスピーディに進めたい
- 大規模な管理体制を求めていない
- 試作レベルで簡易的に依頼したい
また、SIerは「ウォーターフォール型」の開発手法を採用するのが一般的です。
プロジェクトの計画に沿って順番に工程を進めていく手法であるため、状況にあわせて柔軟に方針転換するような対応には適さないケースも想定しておきましょう。
委託先に依存する状態に陥りやすい(ベンダーロックイン)
SIerにプロジェクト全体を一任すると、特定の委託先に依存してしまう「ベンダーロックイン」という状態に陥るケースも。
プロジェクトを丸ごと任せられる点は大きなメリットです。
それゆえ、システムの仕様やインフラ構成といった技術情報が自社に蓄積されにくいというリスクも生じます。
インフラの改修や再構築を検討するとき、自社で仕様や構成を把握していなければ初期開発を担当したSIerに頼らざるを得ません。
また、ほかの開発会社へ乗り換えようとしても、システムの内部構成を把握できない状況ではスムーズに引き継ぎできなくなってしまいます。
事業のコストや柔軟性を長期的な視点で見るのであれば、自社に技術的な知見を蓄積する取り組みが必要です。
SIerのデメリットをカバーするならフリーランスの活用が効果的
大規模プロジェクトの外部委託先として、SIerは頼りになる選択肢です。
しかし、契約の柔軟性や高額なコストなど、考慮しておきたいデメリットもあります。
SIerのデメリットに対して懸念事項が残ってしまう場合は、解決策としてフリーランスエンジニアの活用を検討するのも有効です。
特に、小規模な案件やスピーディな構築が求められるプロジェクトでは、フリーランスの柔軟性や専門性が役立ちます。
関連記事:SIerの仕事内容を解説|実はフリーランスで解決できるケースも?
中間マージン不要でコストを削減しやすい
フリーランスエンジニアの活用には、最小限のコストで依頼しやすいメリットがあります。
一般的なSIerへの外部委託では、エンジニアの報酬とは別に、プロジェクト管理費や企業の利益といった中間マージンが発生します。
| エンジニアの報酬単価 | 60万円/月 |
| SIer企業のマージン率 | 報酬総額の40% ※マージン率は企業によって異なる |
| 依頼元企業の支払総額 | 100万円/月 ※60万円+(100万円×40%) |
上表は、報酬単価「60万円/月」のエンジニアに支払われる総額費用の一例です。
設定されるマージンの割合(マージン率)はSIer企業によって異なるため、想定より数十万円の差額が発生するケースも少なくありません。
関連記事:フリーランスのインフラエンジニアと契約した場合の単価相場とは?|単価交渉のコツも解説
状況に応じて柔軟に人材を確保しやすい
プロジェクトの状況に応じて人材を確保できる柔軟性もフリーランス活用のメリットです。
緊急時や繁忙期といった状況にあわせて柔軟な体制構築を実現できます。
大規模プロジェクトの対応力を強みとするSIerは、契約から体制構築までに時間がかかる傾向にあります。
オーバースペックな体制構築により、小規模案件やスポット対応に必要以上のコストがかかるケースも少なくありません。
ウォーターフォール型の開発手法を採用するSIerとは異なり、フリーランスは仕様変更に柔軟に対応するアジャイル開発や段階的な検証(PoC)にも対応しやすいメリットがあります。
関連記事:フリーランスのインフラエンジニアに業務を委託する流れとは?単価相場や注意点も解説
自社主導の開発体制で社内にノウハウを残しやすい
フリーランスであれば自社の開発チームとコミュニケーションを取りながら業務を進められるため、技術的な知見や開発・構築ノウハウを社内に蓄積できます。
ドキュメントやソースコードを自社の資産として管理すれば、プロジェクト終了後も社内リソースで運用・改善への取り組みが可能です。
将来的な内製化を見据えている企業としては、外部の専門知識を取り入れる機会としての価値も得られます。
また、専門的なノウハウに強みのあるフリーランスエンジニアを効率的に探したい場合は、専門のエージェントサービスを活用するのも効果的です。
「クロスネットワーク」では、企業の要望にあった人材紹介から契約手続きまで一貫したサポートを提供しています。
SIerとフリーランスのどちらに委託すべき?
自社のプロジェクトを進めるうえで、どちらに委託するほうがよいのでしょうか。
その結論は、プロジェクトの目的や規模、自社の状況によって異なります。
以下3つのパターンに分けて、自社にあった委託先を解説します。
- 全体設計・プロジェクト管理なら「SIer」
- リソース不足・スポット対応なら「フリーランス」
- ハイブリッド活用(SIerとフリーランスの併用)
プロジェクト全体の設計・管理を依頼するなら「SIer」
プロジェクト全体の設計・管理を依頼するなら、SIerへの委託が適しています。
SIerの強みは、要件定義から導入後の運用・保守まで、プロジェクト全体を一貫して請け負える体制です。
そのため、社内にインフラ構築やシステム開発のノウハウが不足している企業でも、プロジェクト全体を安心して任せられます。
成果物の納品まで責任をもって完遂してくれるため、プロジェクト管理にともなう発注側の負担も軽減可能です。
ただし、依頼時のコストや柔軟性には、少なからずデメリットもあります。
SIerにプロジェクト全体を一任する場合は、デメリットを理解したうえで自社の要件にマッチしているかどうかを慎重に判断しましょう。
適材適所でリソース不足を解消するなら「フリーランス」
適材適所でリソース不足を解消するなら、フリーランスエンジニアの活用が適しています。
スポット的な業務委託のように、企業の状況にあわせて契約内容を調整しやすい柔軟性がフリーランスの魅力です。
フリーランス市場には、クラウドやAIといった専門分野のスキルに優れたエンジニアも多数存在します。
正社員採用では確保しづらい即戦力の人材を「一定期間のみ確保できる」のは、フリーランスならではのメリットです。
また、フリーランスエージェントを活用する場合に発生するマージンは、一般的にはSIerほど高額ではありません。
コスト面を重視したい企業にもフリーランスエンジニアの活用がおすすめです。
フェーズや規模で役割分担するのも効果的(双方の活用)
SIerとフリーランスのどちらかを選ぶのではなく、プロジェクトの目的やフェーズに応じて役割分担するのも効果的です。
たとえば、プロジェクトの土台を固める上流工程(要件定義や基本設計)は、実績豊富で管理体制が整っているSIerに。
実装やテストといった下流工程は、コストを抑えながら柔軟に稼働できるフリーランスに依頼するといった役割分担が考えられます。
安定性が必須のインフラ構築はSIer、柔軟性が鍵となるアプリ開発はフリーランス、といった適材適所の使い分けも効果的です。
プロジェクトを効率的に進めるためにも、負荷の高さや対応の柔軟性を切り分けながら、コストとリスクを分散するような役割分担を検討してみましょう。
エンジニアのリソース不足を解消するなら「クロスネットワーク」にご相談を
SIerへの外部委託には、プロジェクト全体を一貫して任せられるメリットがあります。
しかし、コストの高さや依頼の柔軟性にデメリットもあるため、自社の要件にマッチしない可能性も念頭に置いておきましょう。
依頼のスピード感やコストを重視したい場合は、柔軟な条件で即戦力を採用しやすいフリーランスエンジニアに依頼するのがおすすめです。
クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。
週2〜3日の依頼にも対応しているので、ご要望に応じて柔軟な外注をサポートいたします。
サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。
フリーランスのインフラエンジニアをお探しの方は、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。
平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。