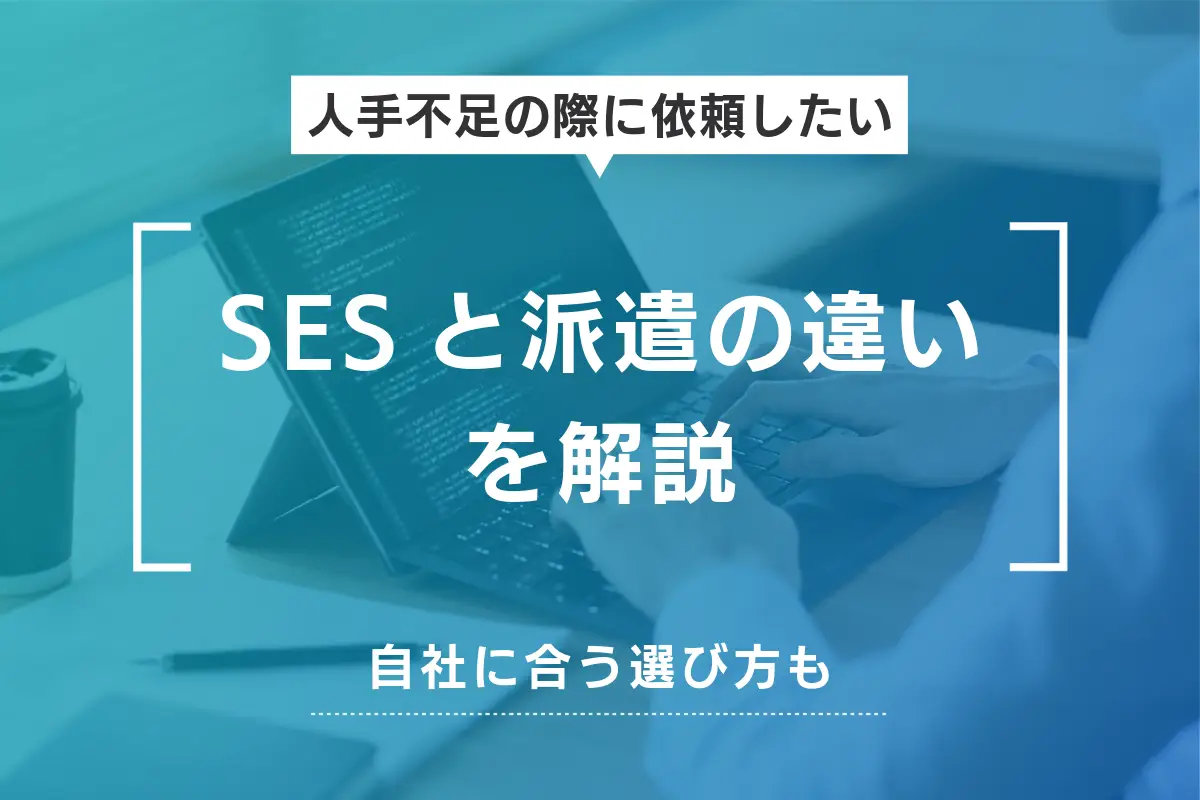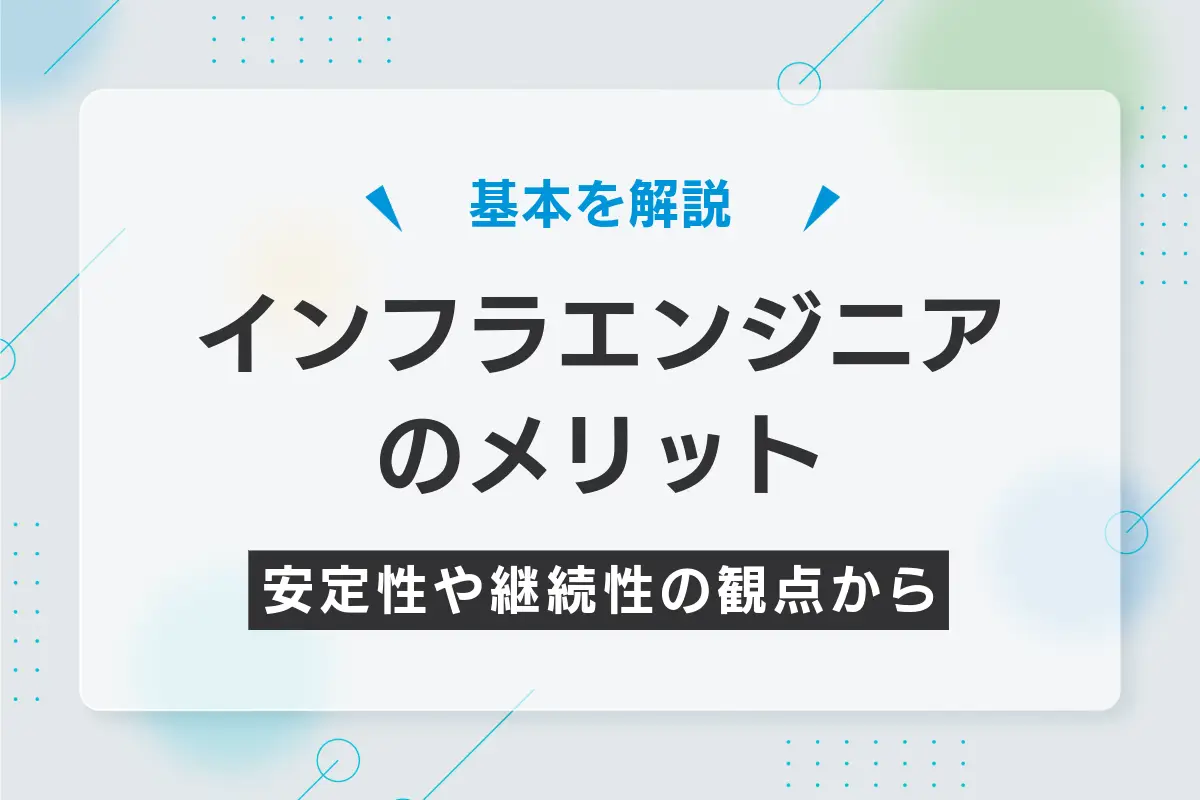事業拡大に伴うインフラ強化にはサーバーエンジニアの存在が欠かせません。しかし、ITインフラの領域はネットワークからクラウドまで幅広く、仕事内容を理解しないと「どのエンジニア職」に依頼すればよいのか迷ってしまいますよね。
そこで今回は、インフラエンジニア経験のある筆者がサーバーエンジニアの仕事内容を紹介します。ネットワークやクラウド領域のエンジニア職と「どのような違いがあるのか」も徹底解説。採用後のミスマッチを防ぐためのポイントも解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
サーバーエンジニアの仕事内容
サーバーエンジニアの仕事内容は、大きく分けて「設計」「構築」「運用・保守」「障害対応」の4フェーズです。サーバーインフラを構築するだけでなく、24時間365日にわたって安定的に動きつづける環境を維持する役割もあります。
以降の見出しでは、各フェーズの仕事内容について具体的に解説します。
サーバーの設計
サーバーの設計フェーズでは、要件定義とサーバー構成の検討を実施します。
要件定義の主な業務は、サービスの責任者や開発エンジニアへのヒアリングです。インフラに搭載するアプリやサービス、想定される利用者数やデータ量などを明確にします。
要件定義の完了後は、具体的なサーバー構成を検討します。以下は、検討すべき構成の一例です。
- サーバーを構築する環境(オンプレミス・クラウド)
- サーバーのOS・設置台数・スペックなど
- システムに適した負荷分散や冗長化の構成
- 構築時の動作検証手順やバックアップ・リストアの計画
サーバーの設定だけでなく、構築後のテスト手順やデータのバックアップ計画なども設定の段階で手順化しておきましょう。
サーバーの構築
サーバーの構築は設計書に基づき、実際にサーバーを動かせる状態につくり上げる工程です。構築作業が完了すると、サーバーがシステムを動かすための基盤として機能します。
以下は、サーバー構築フェーズの主な仕事内容です。
- サーバー機器の設置・ネットワークケーブルの配線(オンプレミス環境のみ)
- OSやミドルウェアのインストール・セットアップ
- サーバーのネットワーク情報やセキュリティ対策の設定
- 動作検証を兼ねたテスト・脆弱性の診断・セキュリティパッチの適用など
設計書に基づく設定が完了したら、動作検証(テスト)を実施します。設計どおりの性能が出るか、システムの弱点(脆弱性)がないかといったチェックが必要です。
動作検証の問題が見つかった場合は修正プログラム(セキュリティパッチ)を適用し、安全な状態で稼働できるサーバーを完成させます。
サーバーの運用・保守
運用・保守の仕事内容は、構築したサーバーを安定稼働させるための日常的な管理・メンテナンスです。監視ツールや目視確認を使い分けながら、以下の項目をチェックします。
- サーバーのCPU使用率やメモリ残量
- ネットワークの通信量
- サーバー機器の稼働状況
- システムログ
システムの正常稼働を確認する目的は、問題が発生する予兆をいち早く検知するためです。監視データから不具合の予兆が見つかった場合は、原因分析と性能を改善する「チューニング」を実施します。
また、万が一のデータ消失に備えて、定期的にデータをバックアップするのも運用・保守の重要な仕事です。バックアップ処理の正常完了を日々確認しながら、いつでもデータを復元できる状態を保ちましょう。
障害対応
サーバーに予期せぬ問題が発生した場合は、サービスへの影響を最小限に抑える障害対応が必要です。運用・保守フェーズで導入した監視ツールが異常を検知すると、以下の流れで障害対応が始まります。
| 対応フロー | 主な仕事内容 |
|---|---|
| 障害を「検知」した |
|
| 障害が「発生」した |
|
| 障害が「復旧」した |
|
サーバーが停止するような障害が発生した場合は、あらかじめ決められた手順に沿って復旧作業を実施します。発生した障害の内容や原因によって、対処すべき手順をマニュアル化しておくのが理想的です。
| 【元インフラエンジニアのひとこと】 障害対応は基本的に「予期せぬ状況への対処」が求められます。過去に私自身が対応した経験では、想定外のタイミングに原因不明の不具合が発生するケースも少なくありませんでした。 そのため、具体的な対応フローや対処方法が手順化されていない状況に陥りがちです。障害が発生すると慌ててしまいますが、まずは実際に対応した流れや発生した事象を必ず記録に残しておきましょう。 障害対応が落ち着いたタイミングで再発防止策を検討しておけば、同様の障害が発生したときのスムーズな復旧につながります。 |
その他エンジニア職種との仕事内容の違い

サーバーエンジニアの採用を検討するときには、ネットワークエンジニアやインフラエンジニアといった役割が似た職種との違いに悩むケースもあります。自社の課題解決に適した人材を見極めるには、それぞれの専門領域の理解が欠かせません。
ここからは、サーバーエンジニアと混同しやすい3つの職種について、それぞれの仕事内容の違いを解説します。
- ネットワークエンジニア
- インフラエンジニア
- クラウドエンジニア
各職種の平均年収を比較したい場合は、以下の関連記事を参考にしてみてください。
関連記事:【企業向け】サーバーエンジニアの平均年収|採用コストの判断基準も解説
ネットワークエンジニアの仕事内容
ネットワークエンジニアは、ITインフラの「ネットワーク領域」に特化した技術者です。各種サーバーや利用者の端末をつなぐ通信環境の設計から構築、運用・保守まで担当します。
具体的な仕事内容は、以下のとおりです。
- ネットワーク機器の選定(ルーターやスイッチなど)
- ネットワークの設計(接続経路・帯域幅など)
- ネットワークの構築(機器の設置・動作検証など)
- 運用・保守・セキュリティ対策など
サーバーが正常に稼働してもネットワークに問題があればサービスを利用できないため、サーバーエンジニアと連携しながらインフラの安定稼働を支える役割です。
関連記事:ネットワークエンジニアの仕事内容とは?年収や資格・将来性などもわかりやすく解説
インフラエンジニアの仕事内容
インフラエンジニアは、サーバーやネットワークを含めたITインフラ全般を幅広く担当する技術者です。サーバーエンジニアは、インフラエンジニアという大きな枠組みに含まれる「サーバー領域」の担当者として位置づけられています。
インフラエンジニアの仕事内容には、サーバーエンジニアとネットワークエンジニアの双方の役割が求められます。そのため、インフラ全体を俯瞰できる人材を求める場合には、インフラエンジニアの確保を検討すべきです。
関連記事:インフラエンジニアとサーバーエンジニアの違い|採用時の観点も解説
クラウドエンジニアの仕事内容
クラウドエンジニアは、クラウドサービスを活用してITインフラを設計・構築する技術者です。インフラを構築する主な役割はインフラエンジニアと同じですが、仮想的な環境にサーバーやネットワークを構築するスキルが問われます。
また、オンプレミス環境からクラウド環境へ移行する業務もあるため、サーバーエンジニアやインフラエンジニアのスキルセットも必要です。多くの企業でクラウド活用が進んでいるため、サーバーエンジニアの経験を活かしてクラウドエンジニアに転身するケースも増えています。
関連記事:クラウドエンジニアとは?仕事内容とスキルからわかる採用ポイントも解説
サーバーエンジニアの仕事に必要なスキル
サーバーエンジニアの仕事に必要なスキルは、主に以下の3つです。
- サーバーの設計・構築スキル
- クラウドサービスの設計・構築スキル
- 構築・運用業務を改善する言語スキル
従来のサーバー設計・構築スキルに加え、最新の技術トレンドへの対応力も問われています。サーバーエンジニアのスキルについては、関連記事で詳しく解説しています。
関連記事:サーバーエンジニアのスキルセットとは?クラウド領域における必要性も解説
サーバーの設計・構築スキル
サーバーエンジニアの土台となるのは、サーバーそのものを設計・構築するスキルです。とくに以下のスキルは欠かせません。
- OS(Linux・Windows Server)のインストールや関連ツールを扱うスキル
- Webサーバー・DBサーバーなどのミドルウェアをセットアップするスキル
- サーバーやネットワークの負荷分散や冗長化を実装するスキル
| 【元インフラエンジニアのひとこと】 重要なアプリやデータを扱うサーバーには、システムエラーや機器の故障に備える対策が欠かせません。とくにエンジニア自身のプレッシャーを和らげるためにも、企業の業務に影響度が高いサーバーには入念に障害対策をしておくべきです。 私自身もサーバーを設計するときには、負荷分散や冗長化の構成を欠かさずに取り入れました。障害発生時の対応は必要ですが「致命傷にはならない」と思えるだけでサーバーを構築する安心感がありました。 |
クラウドサービスの設計・構築スキル
サーバーエンジニアには、クラウドサービスでインフラを設計・構築するスキルも求められています。上図に示すように製造業や小売業などの幅広い分野でDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する流れがあり、既存のインフラをクラウド環境へ移行する需要が高まっているためです。
とくに以下の主要なクラウドサービスに関する知識は、サーバーエンジニアが活用する機会も増えています。
- AWS(Amazon Web Services)
- Microsoft Azure
- GCP(Google Cloud Platform)
また、クラウドサービスは従量課金制を採用しているので、不要なコストを削減するためのリソース最適化スキルも注目すべき観点です。
構築・運用業務を改善する言語スキル
サーバーエンジニアの仕事内容を効率化するなら、言語スキルがあると役立ちます。言語スキルを活用するのは、主にスクリプトやバッチ処理を用いた手作業の自動化です。
- サーバー構築や運用業務をプログラムで自動化できる
- 自動化によって作業時間を短縮できる
- 手作業を減らすことでヒューマンエラーを防げる
たとえば、Shell ScriptやPythonといったスクリプト言語の知識があれば、定型的な作業をコマンドによって自動化できます。また、IaC(Infrastructure as Code)と呼ばれる手法が主流になりつつあるため、コードによる管理に慣れておくのがおすすめです。
関連記事:【企業向け】サーバーエンジニアに言語スキルは必要?採用判断の観点も解説
ミスマッチを防ぐサーバーエンジニアの採用ポイント
サーバーエンジニアの採用におけるミスマッチを防ぐため、以下3つのフェーズに分けてポイントを解説します。
- 採用前:依頼する業務内容を明確化する
- 採用時:具体的な業務経験を確認する
- 採用後:業務のドキュメント化を徹底する
自社にフィットする優秀な人材を確保するためにも、採用プロセス全体をとおして社内の体制づくりを心がけましょう。
採用前:依頼する業務内容を明確化する
サーバーエンジニアの採用活動を始める前に、まずは依頼したい業務内容を明確化しましょう。サーバーエンジニアの仕事内容は設計から運用・保守まで幅広く、求める役割によって必要なスキルセットが異なります。
- ゼロからサーバーインフラを設計・構築できる人材を探しているのか
- 既存システムの安定稼働を支える運用・保守担当者を探しているのか
また、ネットワークの設計やクラウド環境への移行も任せたい場合は、仕事内容を募集要項に明記すべきです。場合によっては、インフラエンジニアやクラウドエンジニアのように、より専門的なエンジニア職の採用も検討しましょう。
採用時:具体的な業務経験を確認する
書類選考や面接といった採用プロセスでは、候補者の具体的な業務経験を確認しましょう。過去の経験や実績を深掘りすると、候補者のスキルレベルや得意領域を正確に見極められます。
たとえば、サーバー構築の経験について質問する場合は、プロジェクトの規模や担当した役割を確認すべきです。小規模な社内システムと大規模なWebサービスでは、求められる技術レベルだけでなく年収相場も異なります。
関連記事:【企業向け】サーバーエンジニアの平均年収|採用コストの判断基準も解説
また、運用・保守の担当者を求めるのであれば、過去に経験した障害対応の事例を確認するのも効果的です。障害対応のフローや再発防止の工夫から、問題解決能力や思考の深さを評価できます。
採用後:業務のドキュメント化を徹底する
サーバーエンジニアの採用後は、チームでインフラを管理できる体制づくりが欠かせません。インフラ関連の業務は専門性が高いため、特定の担当者しか仕事内容を把握していない「属人化」の状況に陥りやすい傾向があります。
不在時にトラブル対応が滞ってしまうリスクもあるため、以下の情報や手順をドキュメント化する取り組みを徹底すべきです。
- サーバーの構成情報
- 各種設定の手順
- 障害発生時の対応フロー
チーム全体で知識やノウハウを共有すれば、新しく加わったメンバーもスムーズに業務を覚えられます。
| 【元インフラエンジニアのひとこと】 私自身がインフラエンジニアとしてサーバー障害に対応したときは、先輩エンジニアが残した過去の障害対応や原因切り分けのドキュメントが役に立ちました。インフラにかかわる基礎知識や障害事例を学んでいましたが、やはり実際に障害が発生すると想定外の状況に陥るケースも少なくありません。 |
【契約形態別】サーバーエンジニアの採用方法
サーバーエンジニアを確保する手段は、正社員採用だけではありません。自社の状況や課題に応じて、フリーランス人材を活用するのも効果的です。
- 正社員採用:長期的な人材育成を視野に
- フリーランス活用:即戦力の人材確保に
ここからは、2種類の契約形態の違いを解説します。業務形態の検討に迷う場合は、無料ダウンロードできる以下の資料も参考にしてみてください。
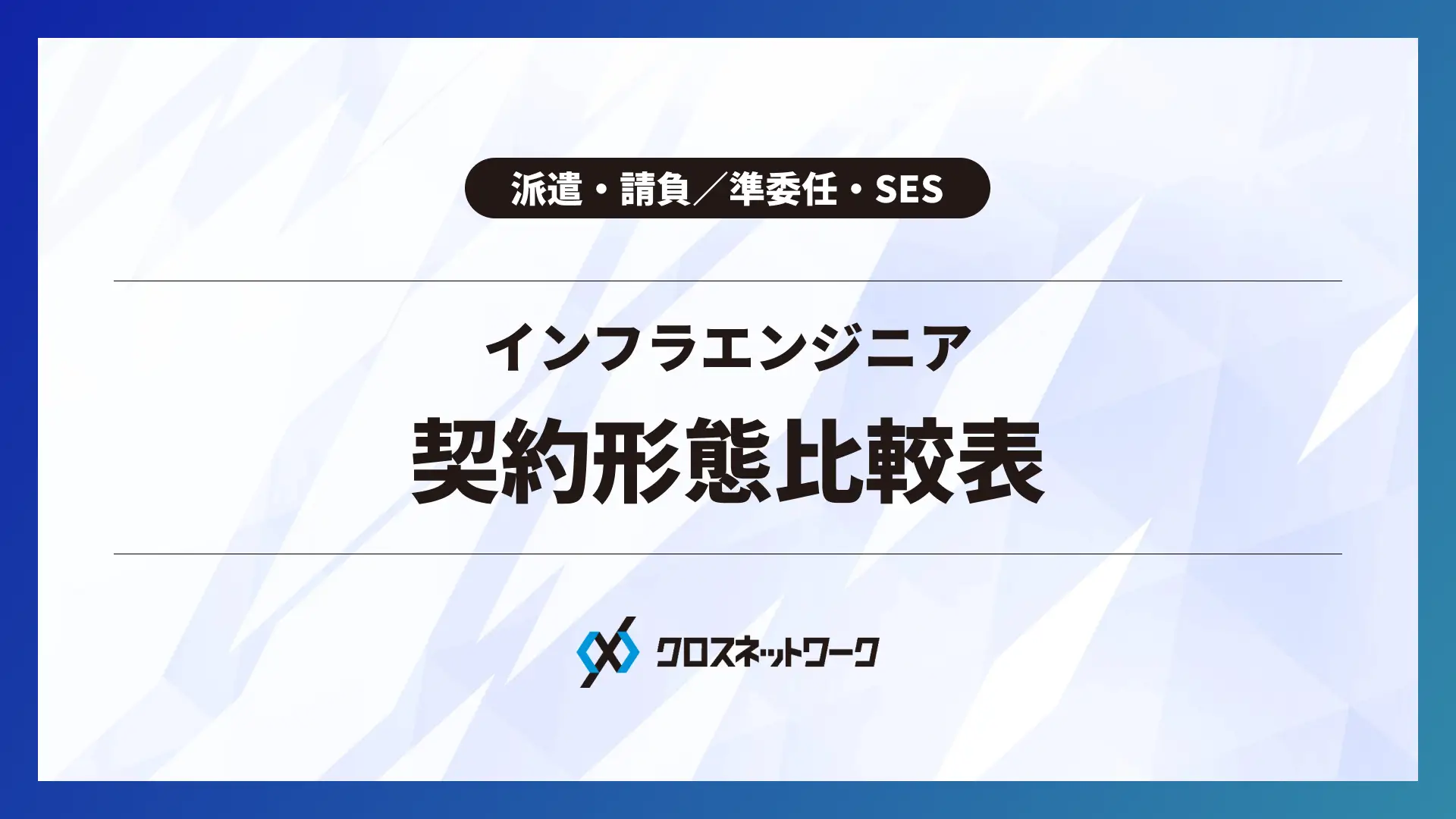
正社員採用:長期的な人材育成を視野に
組織力の強化やノウハウの蓄積など、長期的な人材育成を視野に入れるなら正社員の採用が適しています。サーバーエンジニアの仕事内容は専門性が高いため、業務ノウハウのマニュアル化や内製化に取り組むのが理想的です。
しかし、正社員採用には時間と費用のコストがかかるデメリットもあります。とくに人件費については、月々の給与だけでなく社会保険料や福利厚生費などを含めたトータルコストの考慮が必要です。そのため、プロジェクト単位で人材確保を検討する場合は、フリーランスの活用が適しています。
関連記事:【企業向け】サーバーエンジニアの平均年収|採用コストの判断基準も解説
フリーランス活用:即戦力の人材確保に
即戦力のサーバーエンジニアを確保したい場合は、フリーランス人材の活用が適しています。プロジェクト単位で業務を委託できるため、期間や業務にあわせて柔軟な契約が可能です。
たとえば、数週間から数か月といった短期間のプロジェクトを依頼できます。契約期間のみの人件費を考慮すればよいため、正社員採用に比べてコスト削減につながるケースも少なくありません。
ただし、採用後のミスマッチを防ぐには、企業がサーバーエンジニアに求めるスキルや役割を明確化しておく必要があります。候補者の見極めるに手間を感じる場合は、フリーランス専門のエージェントサービスを活用するのも効果的です。
関連記事:フリーランスのサーバーエンジニアと契約するメリット|正社員との違いも解説
インフラエンジニアを正社員で採用するのか、フリーランス人材を活用するのか、どちらが適しているのか悩むこともあるはずです。あらかじめ違いを知っておくことで、最適な契約形態を選択できます。
以下の資料では、インフラエンジニアの採用と外注について、メリット・デメリットなどを解説しています。インフラエンジニアを求めている企業担当者は、ぜひダウンロードしてみてください。
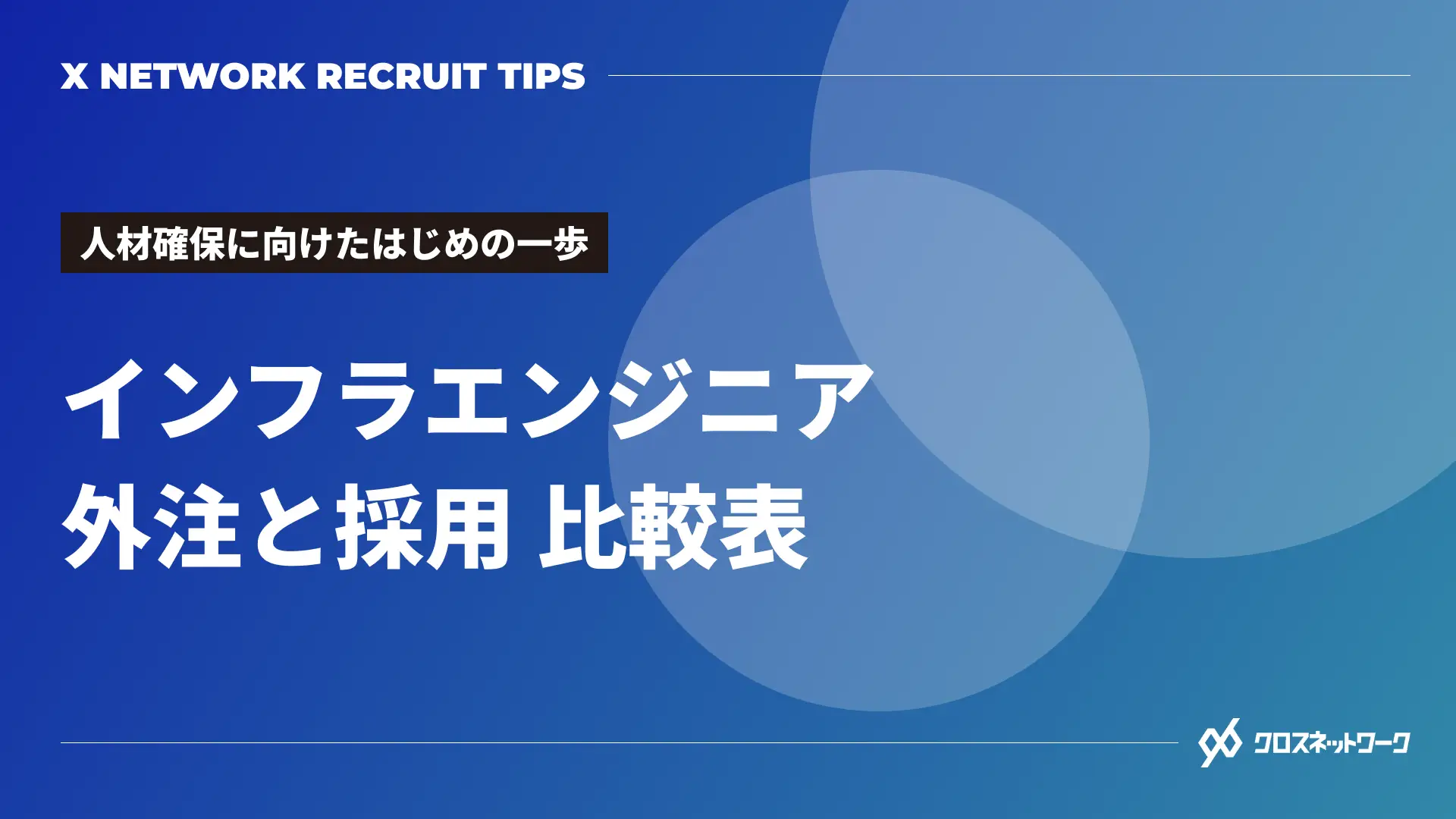
サーバーエンジニア採用のご相談は「クロスネットワーク」におまかせ
自社のインフラ課題を解決するには、サーバーエンジニアの存在が欠かせません。しかし、ITインフラはサーバーからネットワーク、さらにはクラウド領域まで幅広いため、仕事内容を理解しないと適切なエンジニアを採用できません。
とくに採用にかかるコストを考慮すると、プロジェクトの規模や業務範囲に適したエンジニアの採用が求められます。プロジェクトの短期的な課題を解決するなら、即戦力として活躍を期待できる人材の確保を目指すべきです。
そこで効果的な選択肢として、柔軟な条件で契約しやすいフリーランスエンジニアを活用するのがおすすめです。
クロスネットワークでは、インフラ領域の仕事内容を熟知したサーバーエンジニアを迅速にマッチングいたします。プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。
クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の依頼にも対応しているので、ご要望に応じて柔軟な外注をサポートいたします。
サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。即戦力のサーバーエンジニアをお探しの方は、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。