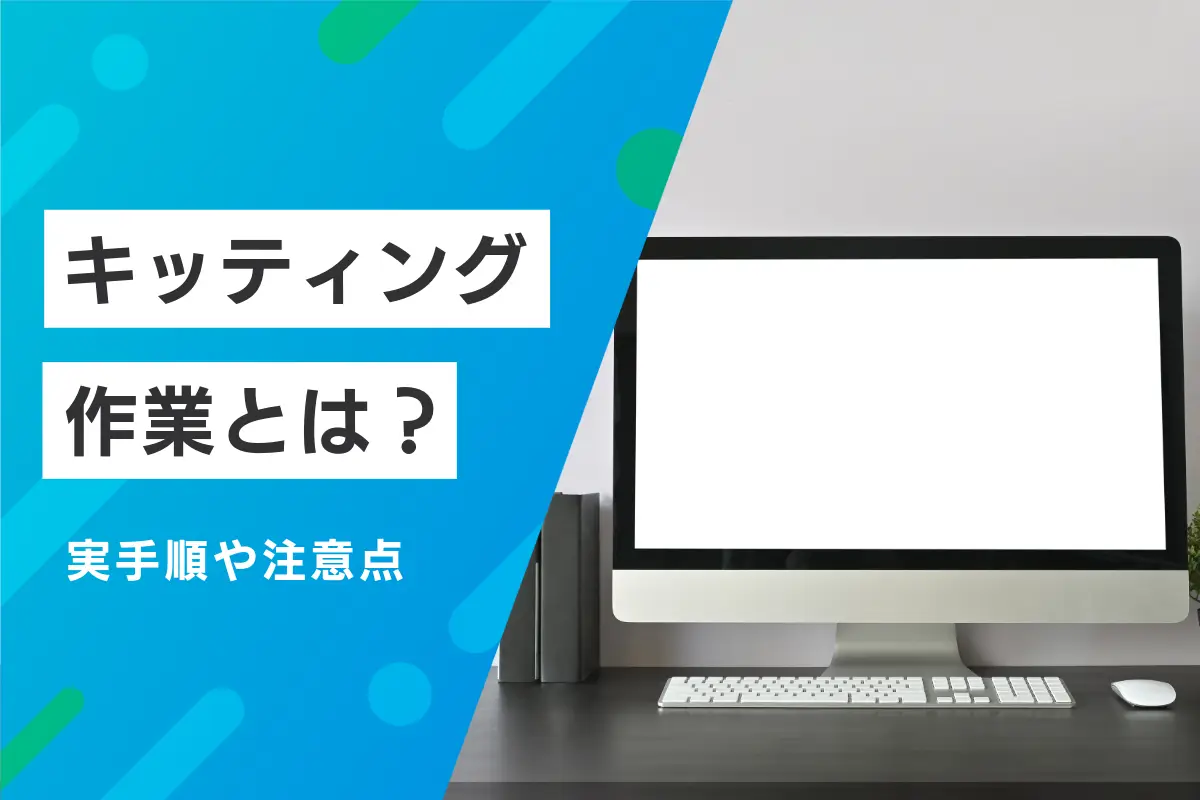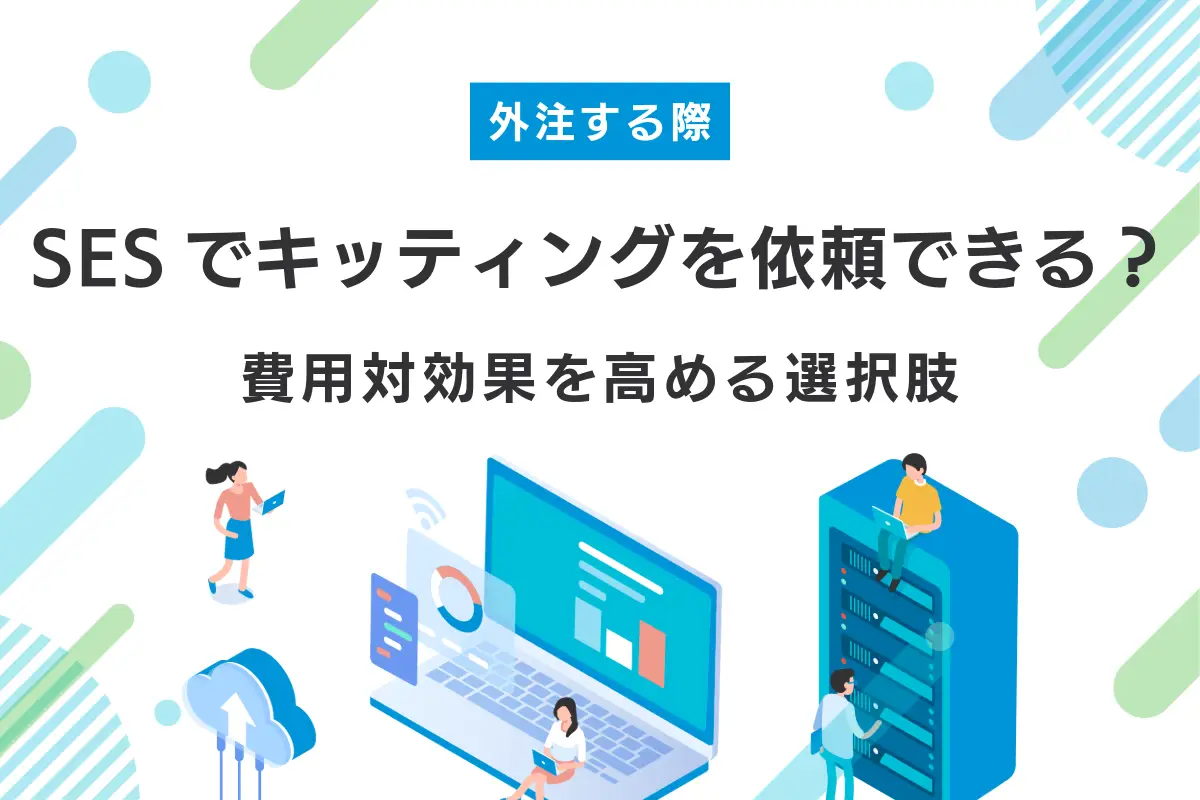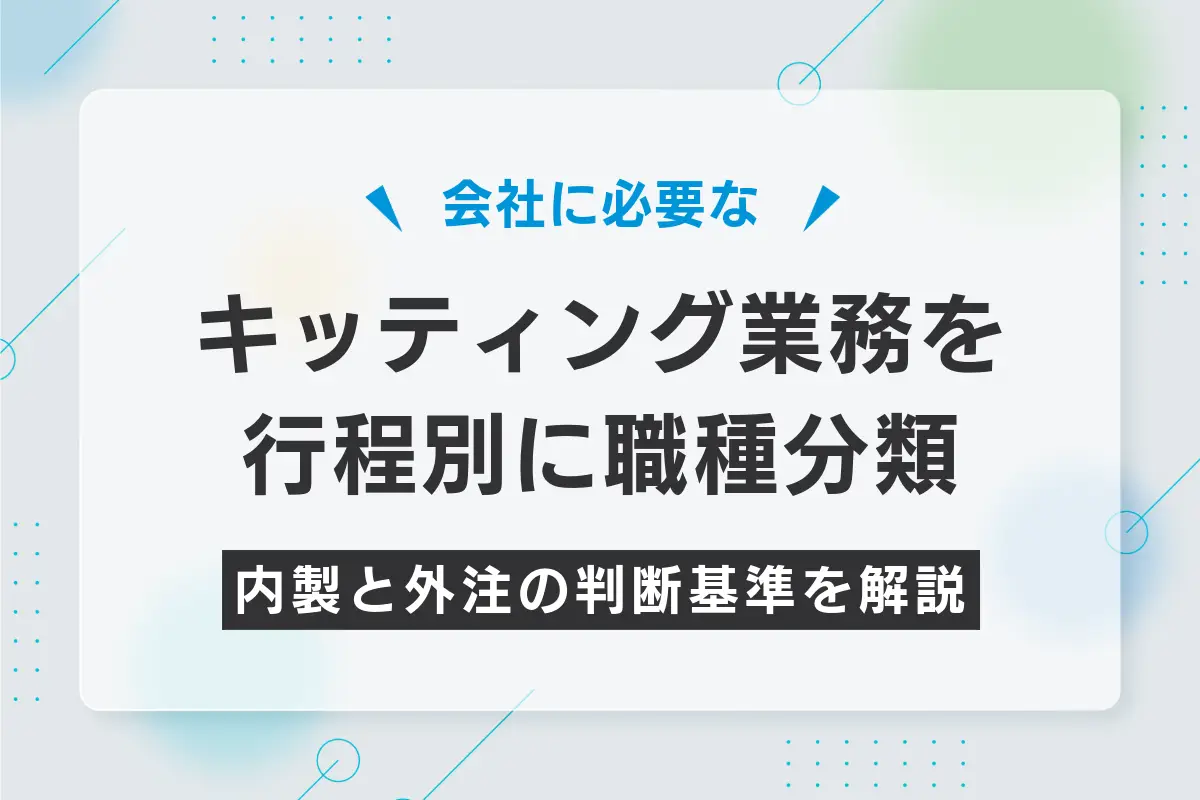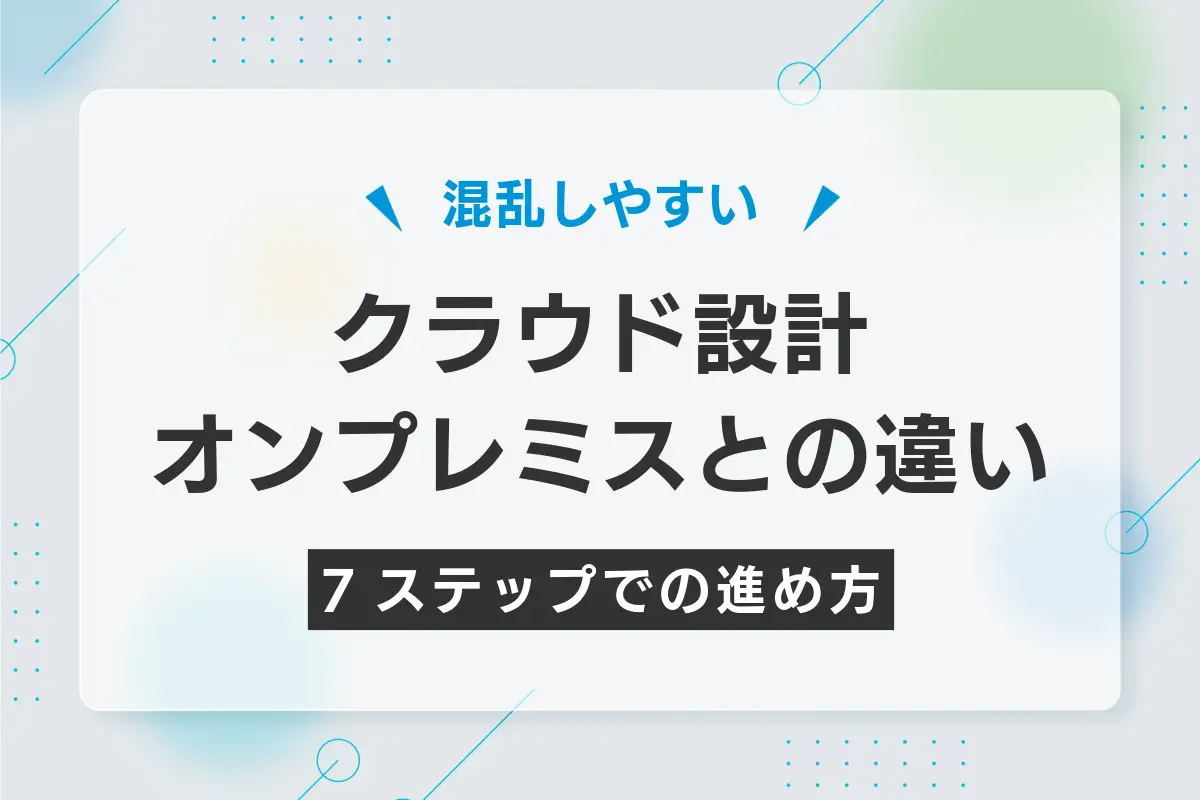
キッティング作業には業務端末の設定を効率化するだけでなく、従業員がスムーズに業務を開始できるメリットもあります。ただし、OSやソフトウェアの複雑な設定を必要とするため、手作業による対応ではヒューマンエラーや業務担当者が偏ってしまう属人化のリスクも見過ごせません。
とくに繁忙期の対応では、本来注力したいコア業務を後回しにしてしまう情報システム部門の担当者も多いのではないでしょうか。そこで今回は、業務端末の「キッティング作業」をテーマに、企業にとって重要な理由や業務負担を軽減するための手法・課題などを解説します。
キッティング作業とは|業務ですぐに使える状態に整えること
キッティング作業とは、PCやサーバーなどのIT機器を業務で「すぐに使える状態」に準備する一連の業務です。新しい端末を受け取った従業員が、設定不要で業務を開始できる状態に整える目的があります。
たとえば、PCのキッティングには、以下のように幅広い作業が含まれています。
- OSやソフトウェアのインストール
- 端末のセキュリティ対策
- 周辺機器やケーブルの設置
キッティングとセットアップの違い
混同されやすいキッティングとセットアップについて、対応する作業範囲に明確な違いがあります。
| セットアップ |
|
| キッティング |
|
OSのインストールやアカウント設定など、セットアップは一般的には初期設定まで対応する意味合いで用いられています。PCを例に挙げると、ログインできる状態まで設定するイメージです。
キッティングは業務用のソフトウェアやデバイスの設定、社内ネットワークへの接続設定などにも対応します。キッティング作業の一部にセットアップが含まれており、業務で使える状態まで設定するイメージです。
関連記事:キッティングとセットアップの違いは?おすすめの外注先も紹介
キッティング作業が企業にとって重要な理由
以下のような業務の効率化やセキュリティ強化の観点から、キッティング作業を導入する企業も少なくありません。
- 従業員がすぐに業務を開始できる
- 端末設定の統一化により業務を効率化できる
- セキュリティリスクの軽減効果を期待できる
従業員がすぐに業務を開始できる
キッティング作業には、従業員がすぐに業務を始められるメリットがあります。OSの初期設定や社内ネットワークの接続など、従業員自身が端末を設定すると本来の業務に着手するまで半日ほどかかるケースも少なくありません。
キッティング作業を代行すれば、従業員は入社初日から業務に必要な端末を利用できます。また、設定方法がわからないといった従業員からの問い合わせが減るため、情シス担当者もサポート業務に費やす工数を削減することが可能です。
端末設定の統一化により業務を効率化できる
キッティング作業を標準化することで、全従業員の端末設定を統一できます。個別に設定を行うと、ソフトウェアの種類やバージョンに差異が発生する状況に陥りがちです。
端末設定がバラバラの環境では、以下のようなトラブルが想定されます。
- 特定のファイルが開けない
- 業務アプリの互換性がない
- データが破損してしまう
キッティング作業では、社内の環境や業務にあわせた共通設定をすべての端末に適用します。全社でOSやソフトウェアのバージョンが統一されるため、部署間でのスムーズなファイル共有や共同作業の実現が可能です。
さらに、全端末の設定が同じであるため、端末トラブルの原因特定もスムーズに対応できます。解決策をマニュアル化しておけば、管理業務の負担も軽減可能です
セキュリティリスクの軽減効果を期待できる
キッティング作業によって、以下のように企業のセキュリティポリシーに準拠した設定を全端末に漏れなく適用できます。
- 共通のウイルス対策ソフトをインストールする
- 全端末でファイアウォールを有効化する
- 共通ルールのパスワードポリシーを設定する
また、従業員による個別の設定変更やインストールを抑制できます。個人の判断でソフトウェアのインストールを許可すると、情報漏洩やマルウェア感染といったセキュリティインシデントの発生リスクが高まるため注意が必要です。
自社でキッティング作業を実施する3つの選択肢
情シスがキッティング作業を実施するときの主な手法は、以下の3パターンです。
- 手作業
- クローニング
- ツールによる自動化
設定する端末の台数や要件によって適切な手法が異なるため、自社の状況にあわせて選択しましょう。
手作業によるキッティング
手作業によるキッティングは、担当者が1台ずつ手動で設定を実施する基本的な手法です。端末台数が少ない場合や端末ごとに特殊な設定が必要な場合など、柔軟に対応できるメリットがあります。
ただし、以下のような手作業によるデメリットもあるため注意が必要です。
- 作業に時間がかかりやすい
- ヒューマンエラーが発生しやすい
- 作業が担当者に依存しやすい(属人化しやすい)
関連記事でPC・サーバーのキッティング作業を詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:PCキッティングとは?主な作業手順やクローニングの注意点を解説
関連記事:サーバーキッティングとは?主な作業内容や失敗しないためのコツを解説
マスターイメージをコピーする「クローニング」
クローニングとは、基盤となる1台の端末環境を別端末に展開(コピー)する手法です。以下の手順で、キッティング作業を効率化できます。
- 基盤となる端末設定(マスターイメージ)の作成
- マスターイメージを別端末に展開(コピー)
クローニングを用いることで、設定が統一化された端末を短時間で複製できます。また、ツールによって実行するため、手作業によるミスや品質のばらつきも抑制可能です。
注意点としては、端末の機種やOSごとにマスターデータを作成・管理する必要があります。OSのアップデートや業務アプリのバージョンアップを適用する場合は、その都度マスターイメージの更新が必要です。
ツールを用いたキッティング作業の自動化
便利なツールを用いることで、キッティング作業の自動化が可能です。たとえば、Microsoft社が提供するWindowsの自動設定・管理ツール「Windows Autopilot」を活用すれば、Windows10以降のOSをクラウド経由でセットアップできます。
ただし、ツールによって特徴やライセンス費用が異なるため、事前に導入・運用方法を把握しておく必要があります。効率化の手法については関連記事で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:キッティングを効率化する方法は?外注時の主な委託先も紹介
キッティング作業で発生しやすい3つの課題
キッティング作業で得られるメリットがある一方で、以下のように情シス担当者が直面しやすい課題もあります。
- 手作業によるヒューマンエラーが起きやすい
- 兼任によるコア業務のリソース不足が発生しやすい
- クローニングや効率化ツールの導入難易度が高い
関連記事:キッティング作業は正社員が担当すべき?外部委託の判断基準も解説
手作業によるヒューマンエラーが起きやすい
手作業でのキッティングには、設定漏れや入力ミスといったヒューマンエラーにつながりやすい課題があります。設定の不備によって、端末を使用する従業員からの問い合わせが増えてしまうケースも少なくありません。
従業員からの問い合わせや再設定に対応するためには、担当者が本来の業務を中断してサポートにあたる必要があります。端末を回収して再設定する手戻り作業が発生するため、従業員と担当者の双方にとって避けたい状況です。
兼任によるコア業務のリソース不足が発生しやすい
情シス担当者が本来の業務と兼任している場合に、キッティング作業がコア業務のリソース不足を引き起こす要因となります。とくに以下の時期はキッティング作業の負荷が高まりやすく、コア業務に割り当てるリソースが減ってしまうケースも少なくありません。
- 新入社員の入社時期
- 業務端末の買い替え時期(5~8年周期が一般的)
- サポート終了によるOSのアップデートが必要な時期
キッティング作業の繁忙期が想定できる場合は、時期にあわせて外部リソースを活用するのも効果的です。
クローニングや効率化ツールの導入難易度が高い
クローニングや専用ツールの導入は、キッティング作業の効率化に効果的です。しかし、マスターイメージを作成する方法やツールの使い方など、効果的に活用するための専門知識が求められます。
たとえば、クローニングでマスターイメージを作成するためには、業務環境に適した設定が必要です。さらに、機種やOSごとに作成したマスターイメージを管理する必要もあります。
また、効率化のためのツールを導入する場合は、目的に応じて選定したり業務に適した初期設定を施したりする必要があります。自社のリソースですべてを対応するには、少なからず手間や負担がかかってしまうことも想定しておくべきです。
高度な作業を社内だけで対応するのは難しい場合もあります。そのような場合は、専門的なスキルをもつインフラエンジニアに支援を依頼することによって、確実かつ効率的な対応が可能です。
キッティング作業の課題解決には外注化が効果的
社内でキッティングするときに直面しやすい課題の解決策として、外注化を検討するのが効果的です。外注化によって豊富な経験をもつ専門家の技術を活用できるため、自社で対応するよりも高品質かつスピーディな対応を期待できます。
高品質かつスピーディな対応を期待できる
専門業者の強みは、キッティング作業を日常的に請け負って確立された作業手順とノウハウです。キッティング作業を外注化することで、経験豊富なプロによる高品質かつ迅速な対応が期待できます。
また、専門業者は専用の作業スペースや人員体制を整えているのが一般的です。新入社員が入社する4月や全社的なPCの入れ替え時期など、繁忙期でも遅延なく対応してもらえます。
関連記事:キッティング代行とは?メリットや活用が適しているケースなどを紹介
社内リソースを本来のコア業務に割り当てられる
キッティング作業を丸ごと外部に委託することで、情シス担当者のリソースを本来注力したいコア業務に集中できます。
また、専門知識が必要なクローニングやツールの導入を、経験豊富なプロに一任できるのも魅力です。自社で学習する時間や費用をかけることなく、専門的な技術や効率的な手法を取り入れられます。
小規模なキッティング作業を依頼したい場合は、人材派遣を活用する選択肢も検討してみましょう。
関連記事:キッティングは派遣会社に依頼すべき?費用相場やメリットなどを解説
専門知識が必要な作業に絞って柔軟に依頼できる
キッティング作業の外注は、すべての工程を丸ごと委託するだけではありません。「マスターイメージの作成」や「自動化ツールの導入」など、専門知識が求められる特定の作業に絞った柔軟な依頼も可能です。
マスターイメージ作成後の展開作業のように、負担の少ない定型業務を社内リソースで対応すれば委託コストを最小限に抑えられます。繁忙期のみ外部委託、通常期は社内で対応といった判断を取り入れるのも効果的です。
なお、専門知識を要するキッティング環境の構築には、サーバー・ネットワーク・セキュリティ設定などの基礎知識をもつインフラエンジニアが対応するケースもあります。とくに、クラウド環境との連携やVPN設定などを伴う場合は、インフラエンジニアのスキルが業務効率化に大きく貢献するでしょう。
キッティング作業の信頼できる外注先を選ぶポイント
キッティング作業の外注で失敗しないためには、自社の目的や状況にあった委託先を選ぶ必要があります。
委託先によってサービス内容や得意分野、料金体系はさまざまです。単純な価格の安さだけでなく、以下のポイントも意識してみましょう。
- 信頼できる実績がある
- 自社の求める費用感とマッチする
- 柔軟な作業範囲で依頼できる
信頼できる実績がある
まずは、外注先の候補にキッティング作業の対応実績があるかどうかを確認しましょう。可能であれば、自社の依頼と同規模・同業界の実績があると理想的です。
具体的な実績が不明確な場合は、問い合わせてみるのが確実です。具体的な導入事例、対応可能な台数・期間など自社の要件を事前に整理しておくとやり取りがスムーズに進められます。
関連記事:キッティングサービスの大手企業5選|依頼先の選び方や注意点も解説
自社の求める費用感とマッチする
外注先候補から相見積もりを取得し、以下のような項目を比較するのも効果的です。
- 料金体系
- 単価
- オプション料金
キッティング作業の料金体系は、業者によってさまざまです。PC1台あたりの単価もあれば、作業時間に応じて費用が発生する場合もあります。また、オプション料金が必要な作業範囲を確認しておくと安心です。
単純な価格の安さではなく、サービス内容との費用対効果で判断しましょう。費用の相場については、関連記事で詳しく解説しています。
関連記事:キッティングの費用相場|コスト削減のコツや業者の選定ポイントも解説
柔軟な作業範囲で依頼できる
自社が依頼したい作業範囲にあわせて、柔軟に対応してもらえるかどうかも確認しておきましょう。たとえば、将来的にキッティング作業の内製化を検討している場合は、ドキュメントの作成や技術的なノウハウの共有までサポートしてくれる委託先が理想的です。
また「マスターイメージの作成のみ」といった部分的な対応を依頼したいケースもあります。作業規模や期間に応じて柔軟な条件を提示するなら、フリーランスエンジニアの活用を検討するのもおすすめです。
関連記事:キッティング作業で求められるエンジニアスキル|人材確保のコツも解説
キッティング作業を外部委託するならクロスネットワークがおすすめ
キッティング作業を導入すれば、業務端末の設定を効率化できるだけでなく、従業員がスムーズに業務を開始できます。しかし、以下のように、自社で対応するキッティングには検討すべき課題も少なくありません。
- 手作業にはヒューマンエラーのリスクがある
- 効率化するためには専門知識が求められる
上記の課題を社内リソースだけで解決しようとすると、情シス担当者の負担が増えてしまいます。
キッティング作業のメリットを最大限に引き出すためには、企業の状況やリソースにあわせて「外部委託」を検討してみましょう。とくにキッティング作業の経験豊富なエンジニアを確保するなら、エージェントサービス「クロスネットワーク」がおすすめです。
クロスネットワークでは、キッティング作業の経験豊富なインフラエンジニアを迅速にマッチングいたします。プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。
クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の依頼にも対応しているので、解決したい課題やご要望に応じて柔軟な外注をサポートいたします。
サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。柔軟な契約条件でインフラエンジニアを確保するなら、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスネットワークの特徴
- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。